久しぶりに横井小楠記念館「四時軒」に寄りました。
2024年12月26日


年末の挨拶回りで、熊本市東部まで来たので、久しぶりに横井小楠記念館「四時軒」に寄りました。
昨年リニューアルして以来、展示は見てなかったので、2階の特別展示をゆっくりと見学しました。熱心に資料を確認されている来館者が居られました。

「国是七条草案」は、以前にも展示してあったのですが、改めて読み直しました。

ちょっと粋な文を見つけました。現代の市民の政治離れにも似た減少が、当時の肥後熊本にもあったことを知る漁師の話です。
(以下、横井小楠の感想の抜粋)
地域を治る長官が新しく代わって来たというが、私はその人の名前すら知らない。私はただ自分の生活をしているだけで政治には何の関心がない。
〜漁師のおやじの言葉 横(井平四郎時)在〜
(以上、写真の話の現代語の解説より)
横井小楠の隠居生活から見えてくる当時の庶民の生活が伺えます。幕末維新の動乱の時期以前は、変わらない平和な時代を、庶民は楽しんでいたのだと思いました。


坂本龍馬と対談した座敷

江戸時代、土佐弁は、江戸者が語ることばと区別かつかなかった。〜司馬遼太郎〜
2024年02月23日

<土佐人の強み「言葉」>・・土佐ことばの最も大きな特色であり、昔から土佐人のお国自慢の一つに数えられてきたことである。〜国学者・土居重俊氏土佐言葉」〜
江戸時代、土佐弁は、江戸者が語ることばと区別かつかなかった。〜司馬遼太郎〜
昨秋に、久しぶりに桂浜の坂本龍馬像を眺めてきました。それも、同じ目線で太平洋を望むこともできました。
先月にリサイクルブック店で見つけた、1978年1月初版の司馬遼太郎さんの旅行記『歴史を紀行する』を見つけ、時折開くのですが、土佐(高知)気質が産んだ偉人坂本龍馬の一端が知れることが書かれていました。
高知は、人口の少ない県に数えられ、瀬戸内から遠いから、江戸時代は"田舎"のイメージと思いきや、土佐弁が江戸言葉と聞き分けができないほど似ていることもあり、江戸の街で語られるそれぞれのお国言葉からすると、かえって江戸者と思われるほどだったと。
(以下、本より抜粋)
江戸期に土佐藩士が江戸へゆき、江戸者はじめ他国の者がこの区別できないことに気づき、江戸弁や上方弁よりも土佐弁のはうが日本語として正しいとおもった。方言による劣等感を持たなかったばかりか、軽い優越感すら持った。これは幕末の土佐人が藩外活動をする上で自信の根拠の一つになったであろう。国学者土居重俊氏によれば「・・土佐ことばの最も大きな特色であり、昔から土佐人のお国自慢の一つに数えられてきたことである」(「土佐言葉」)とある。坂本龍馬は生涯、どの土地のたれに会ったときもまる出しの土佐弁で押し通したという。(中略)
維新後、奥州会津の小学校で発言矯正教育がおこなわれたとき、その教師は東京から招かれず、僻地の土佐からはるばる呼ばれたという。
(以上、司馬遼太郎著『歴史を紀行する』より)
私の姉が鹿児島県の霧島神社の近くに嫁ぎました。結婚して間もないころ、姉の家に遊びに行き留守番をすることになりました。そこへ電話がかかってきて、取ると高齢の女性の声でした。ひとしきり鹿児島弁で話されたが、さっぱりわからない。最後、切られる前に、「すみません、お名前をもう一度教えてください」と言い、メモをしました。姉に、「何の用事かはわからないが、○○さんから電話があった」と。
その後何年かして、奄美大島の方と語る機会があった。どうにか、霧島言葉は、半分くらいは分かるようになったのですが、島言葉は、さっぱり理解できませんでした。(笑)
日本は広い、と思います。
要するに、坂本龍馬の活躍の裏に、土佐弁が、当時のもっとも日本語らしい日本語だったことがあるなぁ、と司馬遼太郎氏の本から知りました。
坂本龍馬は、日本の共通語を話せたのが、活躍の要因にあるように思います。
言葉は大事ですね!
<台湾の英雄は宇土にルーツ>宇土市と台湾の台南市の日台交流の準備が始まっています。
2024年01月10日
<台湾の英雄は宇土にルーツ>宇土市と台湾の台南市の日台交流の準備が始まっています。
そのきっかっけとなった本があります。
『汝、ふたつの故国に殉ずー台湾で「英雄」となったある日本人ー」湯徳章の伝記。
作家の門田隆将氏が、2016年末に発刊したノンフィクション作品です。
今年3月に、宇土市長、教育長などで公式訪問が実現します。これから、宇土市と台湾の台南市との官民の交流が盛んになることを願っています。
出版した後、読ませていただきました。人間の「覚悟」とは何か、生き様、死に様から、リーダーの生き方を学びました。ぜひ、一度読んでみてください。
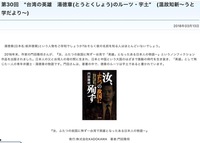

そのきっかっけとなった本があります。
『汝、ふたつの故国に殉ずー台湾で「英雄」となったある日本人ー」湯徳章の伝記。
作家の門田隆将氏が、2016年末に発刊したノンフィクション作品です。
今年3月に、宇土市長、教育長などで公式訪問が実現します。これから、宇土市と台湾の台南市との官民の交流が盛んになることを願っています。
出版した後、読ませていただきました。人間の「覚悟」とは何か、生き様、死に様から、リーダーの生き方を学びました。ぜひ、一度読んでみてください。
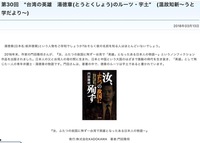

いろんなお話を聴かせていただいた中村青史先生のご逝去を知り、生前の姿を思い出します。
2023年08月23日

いろんなお話を聴かせていただいた中村青史先生のご逝去を知り、生前の姿を思い出します。
私の中村先生との縁は、私がお手伝いしていた九州東海大学の故高宗昭敏教授と中村先生との交流やイベント等でお会いしてきました。高宗先生が病を患い、さらにコロナ禍で、歴史顕彰活動が出来ない状況から、お会いすることが無くなりました。
徳富蘇峰、徳富蘆花に関する研究会で、お話をされる和やかで優しい語り口を懐かしく思い出します。
ここ数日読む、『人間の建設』に、徳富蘆花のことが記されていました。ロシアまで出向き、トルストイに面会した話です。
批評家の小林秀雄と哲学者の岡潔との対談録『人間の建設』から、
岡)トルストイは人としてたいへん偉いですか。
小林)偉いです。
岡)徳富蘆花は会って感心して帰ってきましたね。
小林)私はモスクワへ行って、トルストイの家を見ましたが、感動しました。『アンナ・カレーニナ』を書いた部屋です。岡さんは「コサック」という作品をお読みですか。
岡)ええ、読みました。
小林)あれは青春時代の作ですが、トルストイの方向はあれでもう決まってしまっているのです。(中略)
(以上、『人間の建設』より)
作家や研究者は、作家本人に会い、またかつて住んでいた歴史の現場に出向き、そこで感じたことを糧に、いろんな話を組み立てているのか、と知らされます。
>徳富蘆花は(トルストイに)会って感心して帰ってきましたね。
ジャーナリストである徳富蘆花のとてもリアルな話しですね。
中村青史先生も、徳富蘇峰・蘆花が生まれ育った水俣でのことやジャーナリストとして活躍したこと、熊本での歴史的な役割等にも深く調べて語られていました。ほんと私がまだ30代後半に出会うのですが、何度もお会いし、お話をしたことを思い出します。
しかし、徳富蘆花の言動に、小林秀雄や岡潔も関心を持っていたことを知り、中村先生が、熊本の偉人顕彰をやられたことをまた学びたくなりました。
コロナ禍で一時休止した徳富蘇峰・蘆花の研究、顕彰が再開し、これからも後世に継続されていくことを願いつつ、中村青史先生のご冥福をお祈りいたします。
<社会の転機は4代目?>て開いた本『歴史と人生』(半藤一利著)に、軍事や憲法9条に係る文が
2023年05月09日
<社会の転機は4代目?>朝ウォーキングを終えて、またベッドに横になって開いた本『歴史と人生』(半藤一利著)に、軍事や憲法9条に係る文がありました。
(以下、本より)
憲法9条というハードル
まだまだ、じいさん、ばあさんが生きている限り飛び越せないのですよ。年寄りは戦争体験を経て、戦後に感じたものすごく明るいものをまだ持ち続けていますよ。生身で戦争体験をもつじいさん、ばあさんが生きている間は、なかなか9条はなくならないですよ。なるほど、いまやその御簱(みはた)はぼろぼろになりかけていますが、旗ざおだけは放さない人がいっぱいいます。でもねえ、これが全部死に絶えたら・・・、あっという間かもしれない。
(以上、『いま戦争と平和を語る』より転載)
たとえは違いますが、私の東日本大震災での体験談です。
12年前、東日本大震災後の4月5〜8日に、福島県宮城県岩手県の沿岸被災地へ災害ボランティアに出向いた時、地元の人から聞いた話です。
約200年ほど前にも大きな津波が来て、たくさんの人や家が流された。その時の経験から、「この線(津波到達点)から下に家を建ててはいけない」な、言い伝えがあった。しかし、2代目、3代目までは、どうにか言い伝えが伝わっていたが、4代目ころから線より海寄りに家を建てるようになり、5代目、6代目になると、海岸に家を建てるようになった。しかし、今回の大津波は、言い伝えの"この線から下に家を建てるな"のところまで津波が来て、みんな流された、と話してくれました。
体験者の話が聞けるのは、長くて孫、ひ孫まで、100年を過ぎるころには、言い伝え(体験談)は、聞かなく(効かなく)なることを知りました。
父母は、太平洋戦争の体験者、私は2代目、子どもが3代目。半藤一利氏の言われる戦争体験者がこの世からいなくなった後、4代目たちの変化が気がかりになりました。
(以下、本より)
憲法9条というハードル
まだまだ、じいさん、ばあさんが生きている限り飛び越せないのですよ。年寄りは戦争体験を経て、戦後に感じたものすごく明るいものをまだ持ち続けていますよ。生身で戦争体験をもつじいさん、ばあさんが生きている間は、なかなか9条はなくならないですよ。なるほど、いまやその御簱(みはた)はぼろぼろになりかけていますが、旗ざおだけは放さない人がいっぱいいます。でもねえ、これが全部死に絶えたら・・・、あっという間かもしれない。
(以上、『いま戦争と平和を語る』より転載)
たとえは違いますが、私の東日本大震災での体験談です。
12年前、東日本大震災後の4月5〜8日に、福島県宮城県岩手県の沿岸被災地へ災害ボランティアに出向いた時、地元の人から聞いた話です。
約200年ほど前にも大きな津波が来て、たくさんの人や家が流された。その時の経験から、「この線(津波到達点)から下に家を建ててはいけない」な、言い伝えがあった。しかし、2代目、3代目までは、どうにか言い伝えが伝わっていたが、4代目ころから線より海寄りに家を建てるようになり、5代目、6代目になると、海岸に家を建てるようになった。しかし、今回の大津波は、言い伝えの"この線から下に家を建てるな"のところまで津波が来て、みんな流された、と話してくれました。
体験者の話が聞けるのは、長くて孫、ひ孫まで、100年を過ぎるころには、言い伝え(体験談)は、聞かなく(効かなく)なることを知りました。
父母は、太平洋戦争の体験者、私は2代目、子どもが3代目。半藤一利氏の言われる戦争体験者がこの世からいなくなった後、4代目たちの変化が気がかりになりました。
司馬遼太郎は、「土方歳三の家はどこですか?」と聞くと、「あ、お大尽(だいじん)の家ですか」と言ったとある。
2023年02月17日
<歴史の現場>土方歳三の生家を訪ね、その地域を回った司馬遼太郎は、すれ違った青年に、「土方さんの家はどこですか?」と聞くと、その地域の多くが土方さんばかり、そこで「土方歳三さんの家です」と尋ねたたら、「あ、お大尽(だいじん)の家ですか」と言ったとある。〜『手掘り日本史』〜
3年前の秋、一時コロナ感染が落ち着いたころ、高杉晋作が長州の藩政改革のため決起した「功山寺」を訪ねた。これが、徳川幕府の権威が失墜する第二期長州征伐での大敗につながるのですが、その歴史の現場を訪ねると、若武者・高杉晋作が馬に乗った勇壮な銅像がありました。
冒頭の一文は、司馬遼太郎著『手掘り日本史』の中の、「歴史のなかな日常」の章の初めに書かれている新撰組副隊長の土方歳三の生まれた地域の話です。
「お大尽」とは、大きな百姓のことを、その地域では、物持ちの家を評価した言葉のようです。土方歳三は、その家の末っ子として生まれた。
司馬遼太郎さんは、以下のことを書いています。
(以下、本より)
私はいつも、ほとんど事前に調べていくものですから、現地で調べることがないのです。ただ、現地にゆくと、書斎で考えているのとまったくちがう想像が生まれてきます。土地カンと言いますか、その人が生まれ育ったり、長く住んでいたりしたところを訪ねることで、たとえばその人が植えた庭の矢竹を見たり、庭からのながめた山を自分もながめたりすることで、その人を肌で感じんことが多いのです。
(以上、『手掘り日本史』より)
功山寺を訪ねた時、長門市にも回ったので、金子みすゞ記念館を訪ねた。当時の生活の様子がよく理解できた。捕鯨の町です、とても栄えていて、豊かな地域には新しい情報が集まっていることが理解できた。
私は、議会の視察研修等で他の地域を訪れた時、作家の生家が在ると、時間を少し取れたら、必ず訪ねるようにしています。
長野県飯田市へ産業振興の視察の途中、妻籠宿を訪ねた。そこは島崎藤村の生家が在る。島崎家は大きな商家でした。この山里から、大志を抱き都会へ出て行った。
歴史の現場を訪ねると、そこの空気というか、地形や産業、生業の歴史、地域の人たちの雰囲気等々、それを観るのも楽しみなものです。それを、小説に活かせる人たちは、すごいなと思います。
司馬遼太郎さんの現地訪問の話は、なかなか読み応えがあるので、古本屋に行くと、よく探しています。『手掘り日本史』は、2007年が初版です。
司馬遼太郎講演集があります。歴史の現場を訪ねた話がたくさん出てきて、楽しく読みました。
朝から、話が長くなりました。
3年前の秋、一時コロナ感染が落ち着いたころ、高杉晋作が長州の藩政改革のため決起した「功山寺」を訪ねた。これが、徳川幕府の権威が失墜する第二期長州征伐での大敗につながるのですが、その歴史の現場を訪ねると、若武者・高杉晋作が馬に乗った勇壮な銅像がありました。
冒頭の一文は、司馬遼太郎著『手掘り日本史』の中の、「歴史のなかな日常」の章の初めに書かれている新撰組副隊長の土方歳三の生まれた地域の話です。
「お大尽」とは、大きな百姓のことを、その地域では、物持ちの家を評価した言葉のようです。土方歳三は、その家の末っ子として生まれた。
司馬遼太郎さんは、以下のことを書いています。
(以下、本より)
私はいつも、ほとんど事前に調べていくものですから、現地で調べることがないのです。ただ、現地にゆくと、書斎で考えているのとまったくちがう想像が生まれてきます。土地カンと言いますか、その人が生まれ育ったり、長く住んでいたりしたところを訪ねることで、たとえばその人が植えた庭の矢竹を見たり、庭からのながめた山を自分もながめたりすることで、その人を肌で感じんことが多いのです。
(以上、『手掘り日本史』より)
功山寺を訪ねた時、長門市にも回ったので、金子みすゞ記念館を訪ねた。当時の生活の様子がよく理解できた。捕鯨の町です、とても栄えていて、豊かな地域には新しい情報が集まっていることが理解できた。
私は、議会の視察研修等で他の地域を訪れた時、作家の生家が在ると、時間を少し取れたら、必ず訪ねるようにしています。
長野県飯田市へ産業振興の視察の途中、妻籠宿を訪ねた。そこは島崎藤村の生家が在る。島崎家は大きな商家でした。この山里から、大志を抱き都会へ出て行った。
歴史の現場を訪ねると、そこの空気というか、地形や産業、生業の歴史、地域の人たちの雰囲気等々、それを観るのも楽しみなものです。それを、小説に活かせる人たちは、すごいなと思います。
司馬遼太郎さんの現地訪問の話は、なかなか読み応えがあるので、古本屋に行くと、よく探しています。『手掘り日本史』は、2007年が初版です。
司馬遼太郎講演集があります。歴史の現場を訪ねた話がたくさん出てきて、楽しく読みました。
朝から、話が長くなりました。
低所得者も納税するから政治に関心が高い(スウェーデン)。国民の1/4が所得税を納めないから政治に関心が低い(日本)。
2023年01月24日
<納税義務と権利の行使>低所得者も納税するから政治に関心が高い(スウェーデン)。国民の1/4と法人の65%が所得税を納めないから政治に関心が低い(日本)。〜櫻井よしこさんと瀬戸内寂聴さんの対談録『ニッポンが好きだから』より〜
スウェーデンの国民意識は、納税する権利を持つから国は援助する義務がある。
(以下、本より)
日本の標準家庭(夫婦と子ども2人)の課税限度額は382万1千円、国比較で日本の課税限度額は高く、給与所得者の約4/1が所得税を払っていません。
高福祉で知られるスウェーデンでは、高度の障害を持つ人がハーフタイムで働き、月10万円ほどの収入に28%の所得税を払っていました。税率の高さに私(櫻井)が驚くと、彼は「私にだって税を払う権利があるんです」といいました。
むろん彼は納税した以上に多くの援助を国家から得ていました。どんなに低い所得の人も、税を納めることによって政治に注文をつける権利を手にする、税を納めることは、同時に権利につながる、権利と義務は一体だと彼はいうのです。
(以上、『ニッポンが好きだから』より)
櫻井さんが、日本国憲法の第三章『国民の権利も義務』の章、第10条から40条の中で、権利、自由、責任、義務という言葉が何回出てくるかを紹介しています。
権利 16回
自由 9回
責任 4回
義務 3回
日本の義務の意味とは、
1つ目、義務教育
2つ目、勤労の権利を有し、義務を負ふ
3つ目、納税の義務
本当の「義務」としては納税のみで、他の2つの教育と勤労は、個人の選択の話では、と思いました。また、以下のことも書かれていました。
(本より)
400万円近い収入があっても個人が所得税を払わなくてよいと同時に、法人もまた税を払いません。日本には246万の法人がありますが、そのうち実に65%が国税を払っていないのです。
日本の税制は、利益を出した法人に対しては厳しい税を貸しますが、赤字経営の法人は、税を払わなくて良い仕組みです。こんな税制の下では、経営者マインド何消え去り、無能な経営者ほど、税を払わなくてよいというインセンティブで支えられ、ますます無能に傾いていきます。
(以上、『ニッポンが好きだから』より)
日本人は、権利は主張するが、果たす義務は少ない(無いに等しい)国民なのか!と、櫻井さんの指摘から理解します。
重度の障がいを持つ人のパート収入、月10万円に28%との税金をかけるが、納税以上に援助する国では、国民は政治に関心が高い。
標準家庭(夫婦と子ども2人)は382万1千円まで無税だが、援助も少ないない国では、国民は政治に関心が低い(無関心)。
人間、税金を納めたらその行き先は何処に使われるか、関心を持つのは当たり前の話です。
税金は収めないのに、援助(権利)ばかりを主張する人は少なくと思います。
櫻井さんの指摘から、「日本人の政治への無関心は、納税義務の薄さにあるのでは?」と、読みながら思いました。
朝から、納税意識の国の違いを確認する話になりました。私は、他の国で生活した経験はありませんから、その違いは分かりませんが、お国の違いは、だいぶあるな、と朝から考えました。
みなさんは、日本が良いですか、スウェーデンがよいてすか、考えるきっかけになれば幸いです。
今日から寒波が来るようです。寒さ対策をしっかりして過ごしたいと思います。
スウェーデンの国民意識は、納税する権利を持つから国は援助する義務がある。
(以下、本より)
日本の標準家庭(夫婦と子ども2人)の課税限度額は382万1千円、国比較で日本の課税限度額は高く、給与所得者の約4/1が所得税を払っていません。
高福祉で知られるスウェーデンでは、高度の障害を持つ人がハーフタイムで働き、月10万円ほどの収入に28%の所得税を払っていました。税率の高さに私(櫻井)が驚くと、彼は「私にだって税を払う権利があるんです」といいました。
むろん彼は納税した以上に多くの援助を国家から得ていました。どんなに低い所得の人も、税を納めることによって政治に注文をつける権利を手にする、税を納めることは、同時に権利につながる、権利と義務は一体だと彼はいうのです。
(以上、『ニッポンが好きだから』より)
櫻井さんが、日本国憲法の第三章『国民の権利も義務』の章、第10条から40条の中で、権利、自由、責任、義務という言葉が何回出てくるかを紹介しています。
権利 16回
自由 9回
責任 4回
義務 3回
日本の義務の意味とは、
1つ目、義務教育
2つ目、勤労の権利を有し、義務を負ふ
3つ目、納税の義務
本当の「義務」としては納税のみで、他の2つの教育と勤労は、個人の選択の話では、と思いました。また、以下のことも書かれていました。
(本より)
400万円近い収入があっても個人が所得税を払わなくてよいと同時に、法人もまた税を払いません。日本には246万の法人がありますが、そのうち実に65%が国税を払っていないのです。
日本の税制は、利益を出した法人に対しては厳しい税を貸しますが、赤字経営の法人は、税を払わなくて良い仕組みです。こんな税制の下では、経営者マインド何消え去り、無能な経営者ほど、税を払わなくてよいというインセンティブで支えられ、ますます無能に傾いていきます。
(以上、『ニッポンが好きだから』より)
日本人は、権利は主張するが、果たす義務は少ない(無いに等しい)国民なのか!と、櫻井さんの指摘から理解します。
重度の障がいを持つ人のパート収入、月10万円に28%との税金をかけるが、納税以上に援助する国では、国民は政治に関心が高い。
標準家庭(夫婦と子ども2人)は382万1千円まで無税だが、援助も少ないない国では、国民は政治に関心が低い(無関心)。
人間、税金を納めたらその行き先は何処に使われるか、関心を持つのは当たり前の話です。
税金は収めないのに、援助(権利)ばかりを主張する人は少なくと思います。
櫻井さんの指摘から、「日本人の政治への無関心は、納税義務の薄さにあるのでは?」と、読みながら思いました。
朝から、納税意識の国の違いを確認する話になりました。私は、他の国で生活した経験はありませんから、その違いは分かりませんが、お国の違いは、だいぶあるな、と朝から考えました。
みなさんは、日本が良いですか、スウェーデンがよいてすか、考えるきっかけになれば幸いです。
今日から寒波が来るようです。寒さ対策をしっかりして過ごしたいと思います。
<愛と平和>本日は終戦記念日、地元紙の一面は「日本が戦争をする48% 2年連続増 危機感高まる」
2022年08月15日


<愛と平和>本日は終戦記念日、地元紙の一面は「日本が戦争をする48% 2年連続増 危機感高まる」
非核三原則を堅持すべき 75%
平和主義に基づく専守防衛 60%
相手国のミサイル基地攻撃力を日本が持つ
賛成36%、反対33%、分からない30%
終戦から77年、アメリカ、ロシア(旧ソ連)が絡む紛争や戦争が何度も起きてきた。
1969年、ベトナム戦争反対の野外音楽祭「ウッドストック・フェスティバル」での「愛と平和」の願いは、何処へ行ったのか。会場として農場を提供した農場主は、
「君たちは世界に何かを示した」
と称賛したという。しかし、その後もアメリカは、戦争に深く関わってきた。
『新生面』の最後に、
日本は今日まで77年間、戦争をしていない。けれど分断から深まる世界を見渡すと、この幸福がいつまで続くか不安になる。終戦の日に、いま一度「愛と平和」の尊さを胸に刻む。
(以上、熊日朝刊一面『新生面』より抜粋)
日本は戦争はしていませんが、アメリカの戦争を基地支援や戦費支援はやってきた。今回のウクライナ侵攻に対する西側の一員として、経済制裁を支持することになっている。
世界の「愛と平和」を支持する動きが薄れてきているように感じます。
>「日本が戦争をする」48%(世論調査より)
平和の尊さを真剣に考える終戦記念日であってほしい。

祖父は、スペイン風邪ではやられなかったが、最後の病のきっかけは、風邪(インフルエンザ)だった。
2021年08月31日

祖父は、スペイン風邪ではやられなかったが、最後の病のきっかけは、風邪(インフルエンザ)だった。
100年前の新型コロナウィルス感染症「スペイン風邪」は、3年間猛威をふるったそうだ。
今回のコロナ禍は、どうなるの?
私の祖父は、よく昔の話をしてくれた。でも、スペイン風邪の事は、話してくれた記憶がない。私の田舎では、感染者は出なかったことはないと思うのですが・・・
スペイン風邪は、初めは米国の軍施設から始まったと言われています。日本では、相撲の力士たちが感染し、スポーツ関係から広がったとも?
2学期が始まったが、部活動は休止となった。コロナウィルス感染防止のためという。
100年前のスペイン風邪は?
>当時の人口5500万人に対し約2380万人(人口比:約43%)が感染、約39万人が死亡したとされる。有名人では1918年(大正7年)に島村抱月が、1919年(大正8年)に大山捨松、竹田宮恒久王、辰野金吾がスペインかぜにより死去している。(ウキペディアより)
建築家の辰野金吾も、スペイン風邪で亡くなっていたことを、初めて知った。
しかし、大正時代の我が家は子沢山で、祖父は戦々恐々だったのでは、と思います。
よく感染せずに済んだな、と。
目覚めの読書、田辺聖子さんの『苦味を少々』に、以下がありました。
「我々は、生きていく上で、かなりの復原力を持つものらしい。人生を漕ぎ渡る、我々の舟は、大舟ではないけれど、ひっくり返ってもまたチャンとも通りになって、水を汲み出したら、浮かぶようになっている、そこがおかしい」〜『妾宅・本宅』あとがき〜
当時の日本の人口は、5500万人。スペイン風邪で亡くなったと言われるのが約39万人。たかが風邪と思ってはいけないと思います。
私の祖父の最後、はじめは風邪と思っていたが、その後入院した。そのまま病院で亡くなった。
とにかく、このコロナ禍をどうにか耐えて、生き抜くことが必要と思います。いつか、コロナ禍は終わります。100年前もそうだったように。
祖父は、スペイン風邪ではやられなかったが、最後の病のきっかけは、風邪だった。風邪を舐めたらいけない。
朝から、祖父を思い出し、100年前のスペイン風邪について、再度調べてみました。今日も、感染対策に気をつけて過ごしましょう。


<"時の人"ほど、今はいません>評判ほど、根拠のないものはない。〜良きにつけ、悪しきつけ〜
2021年08月10日
<"時の人"ほど、今はいません>評判ほど、根拠のないものはない。〜良きにつけ、悪しきつけ〜
曽野綾子さん著書『自分の顔、相手の顔』にある文に、
ピン!!
です。
(以下、本より)
根拠のないもの
誰でも自分の評判というものは気になるものだ。(異常に日本人は気にする)
しかし評判ほど、根拠のないものはない。私以外に私のこまかい事情を知っている人はないのに、その知らない他人が私のことを言っているのだから、評判が正しいはずはないのである。それでいてその評判に動かされる人がおお。世間というものが目に見えない力で圧力をかけるのである。
(以上、『引退しない人生』より)
果たして世間の評判とは何か?
作られたもの?
ほんとうこと?
市民活動をしてきて30年、今お付き合いする人は数えるほどの人物。
その時々には、"時の人"がいましたが、残る人は、数名、いや、1人、2人です。
熊本地球市民塾の先輩に言われたこと(私は当時、34歳)があります、それは、
「花火は誰でも上がれるが、継続できる人は少ない」
市民活動を見てきて、"時の人"ほど、今はいません。
先輩の言葉を、今にして学ぶ60代です。
曽野綾子さん著書『自分の顔、相手の顔』にある文に、
ピン!!
です。
(以下、本より)
根拠のないもの
誰でも自分の評判というものは気になるものだ。(異常に日本人は気にする)
しかし評判ほど、根拠のないものはない。私以外に私のこまかい事情を知っている人はないのに、その知らない他人が私のことを言っているのだから、評判が正しいはずはないのである。それでいてその評判に動かされる人がおお。世間というものが目に見えない力で圧力をかけるのである。
(以上、『引退しない人生』より)
果たして世間の評判とは何か?
作られたもの?
ほんとうこと?
市民活動をしてきて30年、今お付き合いする人は数えるほどの人物。
その時々には、"時の人"がいましたが、残る人は、数名、いや、1人、2人です。
熊本地球市民塾の先輩に言われたこと(私は当時、34歳)があります、それは、
「花火は誰でも上がれるが、継続できる人は少ない」
市民活動を見てきて、"時の人"ほど、今はいません。
先輩の言葉を、今にして学ぶ60代です。
日本人にかつてあった「公共の意識」の欠如はいつから?〜災害と義援金、災害とボランティア〜
2021年08月08日
日本人にかつてあった「公共の意識」の欠如はいつから?〜災害と義援金、災害とボランティア〜
阪神淡路大震災の時集まった日本国内の寄付金は、総額1800億円だった。
同じ年のアメリカでの寄付金総額15兆6000億円。アメリカは別に何があったわけではないのに、普通の年として、日本の約100倍集まった。
この原因は何か?
国民を政府が信用しているか、いないか、にあると。〜櫻井よしこ談より〜
原因は何か、アメリカは寄付金は無税。
日本は寄付金に税金をかける。(阪神淡路大震災の時は無税)
1.アメリカは、民間から民間にお金が流れることはほんとうに良いことだと考える。
2.日本は、大蔵省(現、財務省)が寄付金を全部集めて、こっちのNPO(民間非営利団体)に500万円とか、あっちのNGO(非政府団体)に1000万円とかわかる。全部政府が仕切る仕組み。
これからは、寄付金全てを無税にする税制が必要、と指摘する。
それを実現するには、政府と国民の関係を変え直すこと。
日本は、お上意識(依存)が強い。
日本は、問題解決する能力に欠けている。
「日本人には、ここ(災害)に起こったことは自分たち全体のことだという考えがないのですね。それが一番大きな問題だと思う。自分さえよければいいという情けない考えです」〜瀬戸内寂聴〜
災害と義援金、災害とボランティアに、瀬戸内さんは「公共の意識」の欠如を指摘しています。
共に生きる意識
かつての日本にはあった「公共」の意識とは?
コロナ禍を考えると、
100前のスペイン風邪のパンデミック
昨年からの新型コロナウィルスのパンデミック
その時の日本人の対応が、50年後か、100年後か、比較検証される時、果たして1人ひとりの行動は、「公共の意識」があったか?が問われるように思います。
今回のコロナ禍に対する、日本人のワクチン接種、感染防止の行動、政府の対応も含め、歴史が評価する。
話は、阪神淡路大震災の寄付金からでしたが、かつて日本人にあった「公共の意識」がいつから欠落してきたのか、現代の日本人の気質を、少し勉強したくなりました。
*参加資料:瀬戸内寂聴と櫻井よしこ対談集『ニッポンが好きだから』
阪神淡路大震災の時集まった日本国内の寄付金は、総額1800億円だった。
同じ年のアメリカでの寄付金総額15兆6000億円。アメリカは別に何があったわけではないのに、普通の年として、日本の約100倍集まった。
この原因は何か?
国民を政府が信用しているか、いないか、にあると。〜櫻井よしこ談より〜
原因は何か、アメリカは寄付金は無税。
日本は寄付金に税金をかける。(阪神淡路大震災の時は無税)
1.アメリカは、民間から民間にお金が流れることはほんとうに良いことだと考える。
2.日本は、大蔵省(現、財務省)が寄付金を全部集めて、こっちのNPO(民間非営利団体)に500万円とか、あっちのNGO(非政府団体)に1000万円とかわかる。全部政府が仕切る仕組み。
これからは、寄付金全てを無税にする税制が必要、と指摘する。
それを実現するには、政府と国民の関係を変え直すこと。
日本は、お上意識(依存)が強い。
日本は、問題解決する能力に欠けている。
「日本人には、ここ(災害)に起こったことは自分たち全体のことだという考えがないのですね。それが一番大きな問題だと思う。自分さえよければいいという情けない考えです」〜瀬戸内寂聴〜
災害と義援金、災害とボランティアに、瀬戸内さんは「公共の意識」の欠如を指摘しています。
共に生きる意識
かつての日本にはあった「公共」の意識とは?
コロナ禍を考えると、
100前のスペイン風邪のパンデミック
昨年からの新型コロナウィルスのパンデミック
その時の日本人の対応が、50年後か、100年後か、比較検証される時、果たして1人ひとりの行動は、「公共の意識」があったか?が問われるように思います。
今回のコロナ禍に対する、日本人のワクチン接種、感染防止の行動、政府の対応も含め、歴史が評価する。
話は、阪神淡路大震災の寄付金からでしたが、かつて日本人にあった「公共の意識」がいつから欠落してきたのか、現代の日本人の気質を、少し勉強したくなりました。
*参加資料:瀬戸内寂聴と櫻井よしこ対談集『ニッポンが好きだから』
坂本龍馬は、アメリカの大統領制度に憧れていた!〜対談 司馬遼太郎とドナルド・キーン『日本人と日本文化』〜
2021年07月26日
坂本龍馬は、アメリカの大統領制度に憧れていた!〜対談 司馬遼太郎とドナルド・キーン『日本人と日本文化』〜
いやー、この本は面白かった。2日間で読んでしまった。(笑)
本日も、幕末のエピソードを見つけた!
(以下、本より)
勝海舟がアメリカについて「アメリカの大統領は下女の給料の心配もしているんだ」というと、龍馬は飛び上がるほど驚いた。
日本の将軍というのは、そんなことをしたことはないからからね。それでは、徳川幕府を倒さなければいけない、と考えたようです。
(以上、本より抜粋)
坂本龍馬は、無学だったといわれたりしますが、開明的な勉強の仕方をしていたのでは、と思いました。
司馬遼太郎氏とドナルド・キーン氏の対談集『日本人と日本文化』は、太古の時代から戦前まで、歴史、文化、建築、文学、等々・・・
へー!
そうなんだ!
なるほど!
司馬遼太郎氏もドナルド・キーン氏も、すでにこの世に居られないですが、本とは不思議なもので、今も生きて居られるように感じます。
司馬遼太郎氏の本は、小説はほとんど読まないのですが、講演や対談に関したは、古本屋で見つけると必ず買っています。
私は、熊本生まれの熊本育ち、今も同じ場所に住んでいます。歴史は、関西・関東で行われましたが、九州の熊本にも、色々な歴史や人物が有る。地域のことをもっと知らなければ、と本を読み思いました。
いやー、この本は面白かった。2日間で読んでしまった。(笑)
本日も、幕末のエピソードを見つけた!
(以下、本より)
勝海舟がアメリカについて「アメリカの大統領は下女の給料の心配もしているんだ」というと、龍馬は飛び上がるほど驚いた。
日本の将軍というのは、そんなことをしたことはないからからね。それでは、徳川幕府を倒さなければいけない、と考えたようです。
(以上、本より抜粋)
坂本龍馬は、無学だったといわれたりしますが、開明的な勉強の仕方をしていたのでは、と思いました。
司馬遼太郎氏とドナルド・キーン氏の対談集『日本人と日本文化』は、太古の時代から戦前まで、歴史、文化、建築、文学、等々・・・
へー!
そうなんだ!
なるほど!
司馬遼太郎氏もドナルド・キーン氏も、すでにこの世に居られないですが、本とは不思議なもので、今も生きて居られるように感じます。
司馬遼太郎氏の本は、小説はほとんど読まないのですが、講演や対談に関したは、古本屋で見つけると必ず買っています。
私は、熊本生まれの熊本育ち、今も同じ場所に住んでいます。歴史は、関西・関東で行われましたが、九州の熊本にも、色々な歴史や人物が有る。地域のことをもっと知らなければ、と本を読み思いました。
小楠は漢文しか読めない危険な思想家だが、海舟から大統領制を聞き即理解できた。〜司馬遼太郎〜
2021年07月26日
<地方の教育充実を>小楠は漢文しか読めない危険な思想家だが、海舟から大統領制を聞き即理解できた。〜司馬遼太郎〜
昨日は、オリンピックを観戦しつつ、『対談 司馬遼太郎とドナルド・キーン 日本人と日本文化』を読んでいた。
幕末維新のところで、以下のを部分を見つけた。少々引用文が長くなりますが、
(以下、本より)
勝海舟がアメリカから帰ってきて、彼は新知識でおったわけですされど、横井小楠という思想家がいまして、熊本の人ですが、勝海舟とひじように仲が良かった。横井小楠という人は、当時としては相当な危険な思想家なんですけれど、彼は漢文しか読めなくて、オランダ語はもちろん読めない。だから、世界がどうなっているかということを勝に聞きに行くと、海舟はアメリカの大統領制度の説明をするのです。小楠は即座に、「それは堯舜(ぎょうしゅん)の世だな」と言ったそうです。このことで勝海舟は小楠をひじょうにほめているのです。(中略)
ひじょうによくわかった人たちは「聖人は中国にだいるのじゃない」ということだったでしょうね。
(以上、本より抜粋)
なんと司馬遼太郎さんが、勝海舟と横井小楠との関係、さらに、帰国の会談の中で、中国の孔子が求めた「堯舜の政治思想」についても語っていたとは、横井小楠の理念と思想家としての当時の危険視されたことも含め理解していたことに驚きます。
私は、恩師の高宗昭敏先生のお手伝いを33歳から20年近く手伝ってきました。当初は、熊本の幕末の1人の武士でしたが、だんだんと理解が深まり、勝海舟や坂本龍馬との関係、私塾「四時軒」の活動、さまざまな失敗や福井藩、幕府の改革提言等々、とても幅広く活躍をした横井小楠は、漢文しか読めなかったが、世界の情勢を理解できた、ことはやはりすごい思想家だったと思いました。
この本の中で、教育の最先端は当時地方に在り、それを求めて人が動いた。現代の教育は、権限も発想も中央が握っていて自由度が無い。これも、地方が輝かない原因ではないのか?
横井小楠は、熊本から世界を漢文で学んで理解した。蘭学の最先端は、津和野藩と宇和島藩だった。江戸期の日田に在った廣瀬淡窓の咸宜園には、延べ3千人とも言われる若者たちが、学ぶため訪ねた。
地方こそ、教育を充実させてゆかなければいけないように、昨日の読書から思いました。
昨日は、オリンピックを観戦しつつ、『対談 司馬遼太郎とドナルド・キーン 日本人と日本文化』を読んでいた。
幕末維新のところで、以下のを部分を見つけた。少々引用文が長くなりますが、
(以下、本より)
勝海舟がアメリカから帰ってきて、彼は新知識でおったわけですされど、横井小楠という思想家がいまして、熊本の人ですが、勝海舟とひじように仲が良かった。横井小楠という人は、当時としては相当な危険な思想家なんですけれど、彼は漢文しか読めなくて、オランダ語はもちろん読めない。だから、世界がどうなっているかということを勝に聞きに行くと、海舟はアメリカの大統領制度の説明をするのです。小楠は即座に、「それは堯舜(ぎょうしゅん)の世だな」と言ったそうです。このことで勝海舟は小楠をひじょうにほめているのです。(中略)
ひじょうによくわかった人たちは「聖人は中国にだいるのじゃない」ということだったでしょうね。
(以上、本より抜粋)
なんと司馬遼太郎さんが、勝海舟と横井小楠との関係、さらに、帰国の会談の中で、中国の孔子が求めた「堯舜の政治思想」についても語っていたとは、横井小楠の理念と思想家としての当時の危険視されたことも含め理解していたことに驚きます。
私は、恩師の高宗昭敏先生のお手伝いを33歳から20年近く手伝ってきました。当初は、熊本の幕末の1人の武士でしたが、だんだんと理解が深まり、勝海舟や坂本龍馬との関係、私塾「四時軒」の活動、さまざまな失敗や福井藩、幕府の改革提言等々、とても幅広く活躍をした横井小楠は、漢文しか読めなかったが、世界の情勢を理解できた、ことはやはりすごい思想家だったと思いました。
この本の中で、教育の最先端は当時地方に在り、それを求めて人が動いた。現代の教育は、権限も発想も中央が握っていて自由度が無い。これも、地方が輝かない原因ではないのか?
横井小楠は、熊本から世界を漢文で学んで理解した。蘭学の最先端は、津和野藩と宇和島藩だった。江戸期の日田に在った廣瀬淡窓の咸宜園には、延べ3千人とも言われる若者たちが、学ぶため訪ねた。
地方こそ、教育を充実させてゆかなければいけないように、昨日の読書から思いました。
「200年ほど前に大きな津波が来て、生き延びた人たちは被害のなかった高台に移った」〜福島県相馬市の市民活動家〜
2021年03月10日

<10年前の東北視察から>「200年ほど前に大きな津波が来て、みんな流され、生き延びた人たちは被害のなかった高台に移った」〜福島県相馬市の市民活動家〜
今朝の新聞コラム『文化』を読みながら、10年前の東北の被災地訪問のことを思い出しました。
(以下、コラムから抜粋)
政治学者の中島岳志氏は、
>3.11とコロナ危機は、近代をどう反省的に見るのかという意味で密接に絡みます。コロナ危機では人類の行き過ぎた開発が、自然の奥に潜むウィルスとの接点を生んだとも言われます。
民族学者の赤坂憲雄氏は、
>被災地では、津波で流された場所を指して「昔は海だった」と語る人に出会いました。それは開発の所産です。自然と人間を分つ海岸線は自明なものではなかったのに、最大に膨張した人口や経済力が生み出した2011年の境界が前提とされ、巨大な膨張堤で守る必要があるか、というあるべき議論が封じられた。
(以上、熊日『文化』ページより)
私は、10年前、震災直後の4月5〜8日東北の被災地を自らレンタカーを運転して回った。目的は、熊本から送り出したボランティアの活動拠点を見て回ることと、被災地の状況の視察でした。その当時は、まだ自衛隊が入り、どうにか通行できるだけの道を確保される程度で、通行できないところは大きく迂回したり、戻ったりしながら、福島県相馬市〜岩手県陸前高田市まで海岸線を回った。
初日は、福島県相馬市の避難所となっていた中学校体育館の体育倉庫を貸してもらい寝袋で寝た。翌日、相馬市の市民活動家に同行して海岸沿いにあるご自宅まで連れて行ってもらった。車の中で、
「私の住む地域は、200年ほど前は無かった。それは、200年ほど前に大きな津波が来て、みんな流され、生き延びた人たちは被害のなかった高台に移った。(その方向を指差して)あの辺りが、200年ほど前の津波被害の境界です」。
その方向を観て、被害の無い宅地を確認した。そして、
「人間の欲が、その高台から少しずつ、少しづつ海岸へと近づき、ついに私の住む地域に家がたくさん建てられた」
と話されました。この方の自宅は、1階は理髪店の4階建で、4階まで津波が来ていました。
被災地を回って3日目の夜、相馬市の体育館で寝るのですが、寝入って直ぐの深夜11時半過ぎ、震度6弱の余震があり、津波警報も出て、避難所が騒然となった。私の寝た体育倉庫に積まれ支援物資が全部落ち、危うく埋まろうとしました。その余震のひどいところは、震度6強の揺れがありました。
話が長くなりました。その時の市民活動家の話と、今日の新聞の話しが結びつき、「人間の欲望」が、"3.11もコロナも、引き起こしているのではないか?"と、朝から思いました。

<コロナ禍>地球という”神“が、人類に警鐘を鳴らしているのでは?〜500年ぶりの転換〜
2020年04月03日
<コロナ禍>地球という”神“が、人類に警鐘を鳴らしているのでは?〜500年ぶりの転換〜
まず、超高成長の中国から始まり、日本はこれからですが、次に来たのが韓国、さらにイタリア、イラン、スペイン、フランス、そしてアメリカ、と感染者が拡大して行った。
かつての世界を席巻したスペイン、イギリス、フランス、アメリカ、そこが感染者が増えている。
これから途上国に移るのでしょうが、何故中国、韓国、西洋なのか?
日本は、警戒し過ぎて逆に、水際が良かったのか、これからが感染拡大の本番になるのだと思います。
先ほど、中国古典に詳しい日本文学研究者で教授の方から、過去500何規模の世界の天変地異の時期に在る!
と警鐘を語っていました。今回の感染は、島国日本は、とにかく国内を徹底すれば、陸続きのヨーロッパのような感染はなかろう。
が、大航海時代からの流通の世紀から、情報の世紀に変わる転換の事件かもしれないと、考えました。
ものからネット(情報)に変わる事件になりそうな感じを持っています。要は、"主は生活"重視になるのだと思います。
まず、超高成長の中国から始まり、日本はこれからですが、次に来たのが韓国、さらにイタリア、イラン、スペイン、フランス、そしてアメリカ、と感染者が拡大して行った。
かつての世界を席巻したスペイン、イギリス、フランス、アメリカ、そこが感染者が増えている。
これから途上国に移るのでしょうが、何故中国、韓国、西洋なのか?
日本は、警戒し過ぎて逆に、水際が良かったのか、これからが感染拡大の本番になるのだと思います。
先ほど、中国古典に詳しい日本文学研究者で教授の方から、過去500何規模の世界の天変地異の時期に在る!
と警鐘を語っていました。今回の感染は、島国日本は、とにかく国内を徹底すれば、陸続きのヨーロッパのような感染はなかろう。
が、大航海時代からの流通の世紀から、情報の世紀に変わる転換の事件かもしれないと、考えました。
ものからネット(情報)に変わる事件になりそうな感じを持っています。要は、"主は生活"重視になるのだと思います。
<明治維新>戦争を金銭の動きから検証すると、いろんなことが見えてくる?〜勝海舟は凄い!〜
2018年11月04日
<明治維新>戦争を金銭の動きから検証すると、いろんなことが見えてくる?〜勝海舟は凄い!〜
〜少々長文です。お時間ある時にお読みください。〜
おはようございます。11月初めにしては、けっこう冷え込んだ朝です。
昨日今日は、サッカー大会の主催もなく、朝からバタバタしていませんが、同級生のところに不幸があり午後は葬儀に参加します。我が家は両親との別れは3年前、年齢的に同級生たちも親との別れの時期だなと思います。
さて、昨年見つけた面白い本『ようやく日本の世紀がやってきた』(日下公人・馬渕睦夫共著)をたまに開くのですが、
江戸無血開城の真の立役者は、勝海舟だった!
「戦争は金貸しの金儲けのため」の見出しのページには、以下の内容のことが書かれています。
(以下、内容の骨子
)
日下>明治維新の時、西郷隆盛の軍隊が江戸城を前に、動けなくなった、それは金がなくなったらしい。
その金を三井組、小野組とかが出さなかった。それで勝海舟と相談して、とにかく「金をちょっとくれよ」と。それで入城した。(中略)
馬渕>その勝海舟も面白いことを言っている。『氷川清話』『海舟座談』には、何度も「外国から借金してはいけない」と言っている。だから勝海舟こそ、日本の救世主だったと私は思う。(中略)
馬渕>当時、フランスが幕府に金を貸そうとしていた。もし借りていたら代理戦争が起こっていた。ある戦略家は「借金をさせればその国を牛耳ることができる」と。
戦争をするのに莫大な金が必要になる。資金が足りなくなるから、誰が金を貸す。第一次世界大戦も、第二次世界大戦も、要するに金儲けのための戦争なんです。こういうことを、我々は一切教えられない。(中略)
(以上、本より引用)
これを読むと、一昨日に、太平洋戦争で戦死した叔父の命日参拝をしましたが、戦争の意味を「お国のため」と死んで逝った人たちがいる。知らされない、教えないことに怒りを覚えます。
トランプ大統領は、選挙末期に資金が底をついたそうで、それを支援(金を貸)したのがユダヤ資本だった。それから、トランプ氏の発言がユダヤ資本寄りになって行ったそうです。
先進国の選挙は、莫大な費用を要する宣伝合戦、資金が途絶えたら誰かに借金をする。誰に借りるか、とても重要だなと、本読み考えました。
これは余談ですが、私の市議選挙の費用は、全て自前で用意(準備)しました。知恵と工夫で、費用のかからないとも考えました。選挙活動で献身的に協力・応援していただいた方々の意見やアドバイスを参考に、これから4年、正々堂々と議員活動を実践したいと思います。


〜少々長文です。お時間ある時にお読みください。〜
おはようございます。11月初めにしては、けっこう冷え込んだ朝です。
昨日今日は、サッカー大会の主催もなく、朝からバタバタしていませんが、同級生のところに不幸があり午後は葬儀に参加します。我が家は両親との別れは3年前、年齢的に同級生たちも親との別れの時期だなと思います。
さて、昨年見つけた面白い本『ようやく日本の世紀がやってきた』(日下公人・馬渕睦夫共著)をたまに開くのですが、
江戸無血開城の真の立役者は、勝海舟だった!
「戦争は金貸しの金儲けのため」の見出しのページには、以下の内容のことが書かれています。
(以下、内容の骨子
)
日下>明治維新の時、西郷隆盛の軍隊が江戸城を前に、動けなくなった、それは金がなくなったらしい。
その金を三井組、小野組とかが出さなかった。それで勝海舟と相談して、とにかく「金をちょっとくれよ」と。それで入城した。(中略)
馬渕>その勝海舟も面白いことを言っている。『氷川清話』『海舟座談』には、何度も「外国から借金してはいけない」と言っている。だから勝海舟こそ、日本の救世主だったと私は思う。(中略)
馬渕>当時、フランスが幕府に金を貸そうとしていた。もし借りていたら代理戦争が起こっていた。ある戦略家は「借金をさせればその国を牛耳ることができる」と。
戦争をするのに莫大な金が必要になる。資金が足りなくなるから、誰が金を貸す。第一次世界大戦も、第二次世界大戦も、要するに金儲けのための戦争なんです。こういうことを、我々は一切教えられない。(中略)
(以上、本より引用)
これを読むと、一昨日に、太平洋戦争で戦死した叔父の命日参拝をしましたが、戦争の意味を「お国のため」と死んで逝った人たちがいる。知らされない、教えないことに怒りを覚えます。
トランプ大統領は、選挙末期に資金が底をついたそうで、それを支援(金を貸)したのがユダヤ資本だった。それから、トランプ氏の発言がユダヤ資本寄りになって行ったそうです。
先進国の選挙は、莫大な費用を要する宣伝合戦、資金が途絶えたら誰かに借金をする。誰に借りるか、とても重要だなと、本読み考えました。
これは余談ですが、私の市議選挙の費用は、全て自前で用意(準備)しました。知恵と工夫で、費用のかからないとも考えました。選挙活動で献身的に協力・応援していただいた方々の意見やアドバイスを参考に、これから4年、正々堂々と議員活動を実践したいと思います。


人と仕事を共にする時〜人が楽しければ、自分も楽しい〜
2014年08月17日
人と仕事を共にする時〜人が楽しければ、自分も楽しい〜
今日はお盆休みですが、家族は仕事です。午後は、施設にお世話になっている父母を墓参りに連れて来ます。それこそ、私の祖母が元気なころは、親父の兄弟たちが8月14日に家に集まり、祖父の遺影の前で、昔話をよく語っていました。
その親父の兄弟姉妹の子どこたちは、私からすると従兄弟になりますが、年末に従兄弟が集まり、いとこ会なる集まりもやっていました。祖母が百歳で亡くなり12年が過ぎ、盆に訪れる親族も減りました。今年は、16日に叔母叔父たちが集まります。今秋は、私の選挙があるので、その話題が中心になります。
冒頭の言葉ですが、一般の仕事もそうですが、選挙活動(後援会活動)も人が協力しないとできなません。ならば、それぞれが満足する“達成感”をどう実現できるか、にあると思います。江戸時代の儒家・佐藤一斎の訓示録『言志四録』の共同作業の心得がありました。
(現代語訳)
人と仕事を共にするときに、彼が楽しい仕事を担当し、自分が苦しい仕事を担当するとすれば、仕事は苦しくても、心の中は楽しい気分である。ところが、自分が楽しい仕事を担当し、彼が苦しい仕事を担当すれば、仕事は楽しくても、心の中は苦しいものである。
(以上、渡辺五郎三郎編「佐藤一斎一日一言」より)
要は、相手のこと(仕事・財政)を常に頭置き、負担をかけずに楽しい気分になってもらえるか。前回の選挙は、やり方もわからず、時間もなく、アッと言う間に終わった気がします。今回は、しっかり準備をしようと思い、やって来ましたが、告示まで残り44日になりました。前回同様、周りの状況も刻々と変化し、それにどう対応するか、スピード感が必要と思います。
必要なのが、関わる人たちがいかに楽しんでもらえるかです。選挙は武器を持たない心の闘いと言われます。横井小楠の有名な漢詩に出てくる、中国古代の名君の「堯」と「舜」は、次の二つに関心が高かった。
①農業を振興し、農作業のスケジュールを邪魔しない。
〜現代で言えば、経済を振興し、規制の緩和をすること〜
②税の取り立てを少なくし、人民の財産を空っぽにさせない。
〜簡単に言うなら、下の負担を軽減し、元気にさせること〜
①を身近に言うと、できるだけ部下に権限を与え、伸び伸びと働けるようにする。
② 〃 、できるだけ部下の待遇を良くし、プライベートにも配慮する。
その点、前回の選挙は、周りを思いやる配慮が足りなかったように反省します。いかに関わる人々(ステークホルダー)に達成感を感じれるようにできるか。今年の選挙活動は、そこにも力を注ぎ、前回を超える人の和を広げて、絶対に当選を果たすことが目標です。
裏を返せば、選挙事務所を開くまで、どれだけ私が苦しい闘いを乗り越えれるか、にあると思います。候補者状況は、厳しくなり、益々苦しい闘いになっていますが、最後はみんなで笑えるように頑張ります。
<聖徳太子の17条の憲法>いかなる人も、他人を嫉(にく)み妬(ねた)むことがあってはならぬ。
2014年07月15日
<聖徳太子の17条の憲法>いかなる人も、他人を嫉(にく)み妬(ねた)むことがあってはならぬ。
おはようございます。梅雨空の熊本ですが、気温は高くなくすがすがしい朝です。今朝の友人のfacebookのコメントに聖徳太子の17条憲法が、紹介されていました。先月、中国古典輪読会の先輩から「17条の憲法」の解説本をいただきました。今朝開き、条文を読む中で気づかされました。
「人、嫉(にく)まず!」
人の縁は、濃さにより相手を思いやることが深まると思います。薄い人間関係は、相手のことを思いやることもないのではないか、゛思いやること゛関心を持ち続けることが大事だなと思いました。
<第14条>
十四に曰く、群臣百寮、嫉妬有ることなかれ。我れ既に人を嫉(にく)めば、人亦我れを嫉む。嫉妬の患い其の極を知らず。所以に、智己れに勝れば則ち悦ばず、才己れに優れば則ち嫉(にく)み妬む。是を以て、五百(いほ)の乃(いまし)今、賢(さかしきひと)に遭はしむとも、千載にして以て一聖を待つこと難し。其れ賢誠を得ずんば、何を以てか国を治めん。
〔訳〕
第14条。いかなる人も、他人を嫉(にく)み妬(ねた)むことがあってはならぬ。自分が人を嫉めば、人もまた自分を嫉むであろう。このような嫉妬心の弊害は、実は際限のないものであって、他人が自分よりも智が働くようであれば面白くなく、才能が自分より優れていればまた嫉み妬む。このようなことでは(優れた人に嫉妬し、誹謗・中傷などで出る杭を打つようでは)、五百年にして賢者に遭えたとしても、千年にして一人巡りあえるかという聖人の出現を待つことは難しい。しかし、そのような優れた人物を得なければ、どうしても国を治めることができようか。
補足の解説には、つまらぬ嫉妬心から有為の人材を不遇に貶める悪弊を戒め、組織や国家を治める聖賢への待望が述べられています。聖賢は、聖は孔子、賢は孟子を表現したとありました。
人間関係は、相互作用と言います。相手の立場に配慮できるかどうか? 聖賢は、その人間関係を尊重しつつ、「自分の思いをどう伝えるか」に苦心したのだと思います。
関わる人々の対応は、自分の行いの裏返しと肝に銘じて、日々の言動に気を付けることが大事と、1450年の時を越えて、人間の行動の本質を伝えているように思いました。日々反省、今日も反省が大事と思います。
*参考資料:永崎淡泉著「十七条憲法」(中島弘文堂)
おはようございます。梅雨空の熊本ですが、気温は高くなくすがすがしい朝です。今朝の友人のfacebookのコメントに聖徳太子の17条憲法が、紹介されていました。先月、中国古典輪読会の先輩から「17条の憲法」の解説本をいただきました。今朝開き、条文を読む中で気づかされました。
「人、嫉(にく)まず!」
人の縁は、濃さにより相手を思いやることが深まると思います。薄い人間関係は、相手のことを思いやることもないのではないか、゛思いやること゛関心を持ち続けることが大事だなと思いました。
<第14条>
十四に曰く、群臣百寮、嫉妬有ることなかれ。我れ既に人を嫉(にく)めば、人亦我れを嫉む。嫉妬の患い其の極を知らず。所以に、智己れに勝れば則ち悦ばず、才己れに優れば則ち嫉(にく)み妬む。是を以て、五百(いほ)の乃(いまし)今、賢(さかしきひと)に遭はしむとも、千載にして以て一聖を待つこと難し。其れ賢誠を得ずんば、何を以てか国を治めん。
〔訳〕
第14条。いかなる人も、他人を嫉(にく)み妬(ねた)むことがあってはならぬ。自分が人を嫉めば、人もまた自分を嫉むであろう。このような嫉妬心の弊害は、実は際限のないものであって、他人が自分よりも智が働くようであれば面白くなく、才能が自分より優れていればまた嫉み妬む。このようなことでは(優れた人に嫉妬し、誹謗・中傷などで出る杭を打つようでは)、五百年にして賢者に遭えたとしても、千年にして一人巡りあえるかという聖人の出現を待つことは難しい。しかし、そのような優れた人物を得なければ、どうしても国を治めることができようか。
補足の解説には、つまらぬ嫉妬心から有為の人材を不遇に貶める悪弊を戒め、組織や国家を治める聖賢への待望が述べられています。聖賢は、聖は孔子、賢は孟子を表現したとありました。
人間関係は、相互作用と言います。相手の立場に配慮できるかどうか? 聖賢は、その人間関係を尊重しつつ、「自分の思いをどう伝えるか」に苦心したのだと思います。
関わる人々の対応は、自分の行いの裏返しと肝に銘じて、日々の言動に気を付けることが大事と、1450年の時を越えて、人間の行動の本質を伝えているように思いました。日々反省、今日も反省が大事と思います。
*参考資料:永崎淡泉著「十七条憲法」(中島弘文堂)
宮部鼎蔵没後150年記念行事に、よろしければご参加ください。パネリストで出ます。
2014年07月05日

宮部鼎蔵没後150年記念行事に、よろしければご参加ください。パネリストで出ます。
明日、宮部鼎蔵没後150年記念行事が御船町カルチャーセンターで開催されます。そのメイン行事のシンポジウムに、熊本県央の坂本龍馬会として、われわれの不知火龍馬会を参画させていただき、私がパネリストに一人として登壇します。他のパネリストは、吉田松陰顕彰会、宮部鼎蔵顕彰会、高杉晋作研究者、京都の霊山歴史館副館長、等々がスピーカーを勤められます。幕末前期に大きな役割を務めた宮部鼎蔵の功績を顕彰し、現代へ何がしかの思いを伝えることに努めたいと思います。
ぜひ、幕末維新に関心のある方は、御船町カルチャーセンターまで足をお運びいただければ幸いです。よろしくお願い申し上げます。
今日の熊本日日新聞朝刊に告知記事が掲載されています。
「名こそ流れて 今も伝わる」日々前向きに生きることが大事。
2014年06月12日
「名こそ流れて 今も伝わる」日々前向きに生きることが大事。
おはようございます。ゆっくりの朝です。
昨日は、仲間と色々な事を語りました。出会いは、色々な縁が繋がって起こるものですが、その縁がをつなげて行くには、けっこうな気遣いが必要なものです。
日本人は、思惑(世間の評判)を気にする。
はたして、世間とは何か?
地位から退いて時間が経つと、世間の評判になることもあまりなくなる。話題にもならないのもまた寂しいものですが、世界のリーダー中には、シンガポールの元首相のリー・クワンユー氏のように「世界の話題にならないような国にしよう」とやって来た結果、アジア一の一人当たり生産力を持つ国になっていた。一人ひとりの努力こそ、国を富ませるかもしれません。
百人一首に次の歌があります。
「滝の音は たえて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ」
【直訳】滝の音は ずっと前に 消えたけれど その名は流れ 今も伝わる。
[評釈]滝の流れがなくなり、水の落ちる音がしなくなってずいぶん月日が過ぎてしまったけれど、その滝の評判は世間に流れ出て、今でもなお鳴り渡っていることだ。(中略)
百人一首は、恋の歌が多いが、今日はあえて、人の評判としてこの歌を詠むと、地位を退いて長い時間が経っても、その評判は後世まで語り継がれている、と解釈します。よく使う故土光敏夫氏の政治改革への強い思いを語った「出る杭は打たれるが、出過ぎた杭は打てない」の言葉ですが、現代でも政治改革となると、土光敏夫氏の国鉄民営化を含む、政治臨調時代の映像が流れる。
地位を退いた後、どんな話題が世間に残るか、当事者として立場にある時、どんな言動を続けたか、によるように思います。
上記の歌を作った大納言公任(だいなごんきんとう)は、当時とすれば長生きの74才まで生きた方ですが、地位を離れて20年もすると話題のもならないが、亡くなった後、葬儀が始まってから、本人の人柄が語られ始める。人の真の評価は、故人になってからと教えられました。
「名こそ流れて 今も伝わる」
故人になってどんな話題が始まるか、自分の知る由もないないことですが、気になるところです。勝海舟いうに、人の噂など気にもせず、自分の生き方を貫いた人もいます。それぞれの人生、日々前向きに生きることが大事なのかもしれません。
おはようございます。ゆっくりの朝です。
昨日は、仲間と色々な事を語りました。出会いは、色々な縁が繋がって起こるものですが、その縁がをつなげて行くには、けっこうな気遣いが必要なものです。
日本人は、思惑(世間の評判)を気にする。
はたして、世間とは何か?
地位から退いて時間が経つと、世間の評判になることもあまりなくなる。話題にもならないのもまた寂しいものですが、世界のリーダー中には、シンガポールの元首相のリー・クワンユー氏のように「世界の話題にならないような国にしよう」とやって来た結果、アジア一の一人当たり生産力を持つ国になっていた。一人ひとりの努力こそ、国を富ませるかもしれません。
百人一首に次の歌があります。
「滝の音は たえて久しく なりぬれど 名こそ流れて なほ聞こえけれ」
【直訳】滝の音は ずっと前に 消えたけれど その名は流れ 今も伝わる。
[評釈]滝の流れがなくなり、水の落ちる音がしなくなってずいぶん月日が過ぎてしまったけれど、その滝の評判は世間に流れ出て、今でもなお鳴り渡っていることだ。(中略)
百人一首は、恋の歌が多いが、今日はあえて、人の評判としてこの歌を詠むと、地位を退いて長い時間が経っても、その評判は後世まで語り継がれている、と解釈します。よく使う故土光敏夫氏の政治改革への強い思いを語った「出る杭は打たれるが、出過ぎた杭は打てない」の言葉ですが、現代でも政治改革となると、土光敏夫氏の国鉄民営化を含む、政治臨調時代の映像が流れる。
地位を退いた後、どんな話題が世間に残るか、当事者として立場にある時、どんな言動を続けたか、によるように思います。
上記の歌を作った大納言公任(だいなごんきんとう)は、当時とすれば長生きの74才まで生きた方ですが、地位を離れて20年もすると話題のもならないが、亡くなった後、葬儀が始まってから、本人の人柄が語られ始める。人の真の評価は、故人になってからと教えられました。
「名こそ流れて 今も伝わる」
故人になってどんな話題が始まるか、自分の知る由もないないことですが、気になるところです。勝海舟いうに、人の噂など気にもせず、自分の生き方を貫いた人もいます。それぞれの人生、日々前向きに生きることが大事なのかもしれません。




