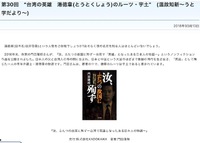江戸時代、土佐弁は、江戸者が語ることばと区別かつかなかった。〜司馬遼太郎〜
2024年02月23日

<土佐人の強み「言葉」>・・土佐ことばの最も大きな特色であり、昔から土佐人のお国自慢の一つに数えられてきたことである。〜国学者・土居重俊氏土佐言葉」〜
江戸時代、土佐弁は、江戸者が語ることばと区別かつかなかった。〜司馬遼太郎〜
昨秋に、久しぶりに桂浜の坂本龍馬像を眺めてきました。それも、同じ目線で太平洋を望むこともできました。
先月にリサイクルブック店で見つけた、1978年1月初版の司馬遼太郎さんの旅行記『歴史を紀行する』を見つけ、時折開くのですが、土佐(高知)気質が産んだ偉人坂本龍馬の一端が知れることが書かれていました。
高知は、人口の少ない県に数えられ、瀬戸内から遠いから、江戸時代は"田舎"のイメージと思いきや、土佐弁が江戸言葉と聞き分けができないほど似ていることもあり、江戸の街で語られるそれぞれのお国言葉からすると、かえって江戸者と思われるほどだったと。
(以下、本より抜粋)
江戸期に土佐藩士が江戸へゆき、江戸者はじめ他国の者がこの区別できないことに気づき、江戸弁や上方弁よりも土佐弁のはうが日本語として正しいとおもった。方言による劣等感を持たなかったばかりか、軽い優越感すら持った。これは幕末の土佐人が藩外活動をする上で自信の根拠の一つになったであろう。国学者土居重俊氏によれば「・・土佐ことばの最も大きな特色であり、昔から土佐人のお国自慢の一つに数えられてきたことである」(「土佐言葉」)とある。坂本龍馬は生涯、どの土地のたれに会ったときもまる出しの土佐弁で押し通したという。(中略)
維新後、奥州会津の小学校で発言矯正教育がおこなわれたとき、その教師は東京から招かれず、僻地の土佐からはるばる呼ばれたという。
(以上、司馬遼太郎著『歴史を紀行する』より)
私の姉が鹿児島県の霧島神社の近くに嫁ぎました。結婚して間もないころ、姉の家に遊びに行き留守番をすることになりました。そこへ電話がかかってきて、取ると高齢の女性の声でした。ひとしきり鹿児島弁で話されたが、さっぱりわからない。最後、切られる前に、「すみません、お名前をもう一度教えてください」と言い、メモをしました。姉に、「何の用事かはわからないが、○○さんから電話があった」と。
その後何年かして、奄美大島の方と語る機会があった。どうにか、霧島言葉は、半分くらいは分かるようになったのですが、島言葉は、さっぱり理解できませんでした。(笑)
日本は広い、と思います。
要するに、坂本龍馬の活躍の裏に、土佐弁が、当時のもっとも日本語らしい日本語だったことがあるなぁ、と司馬遼太郎氏の本から知りました。
坂本龍馬は、日本の共通語を話せたのが、活躍の要因にあるように思います。
言葉は大事ですね!
久しぶりに横井小楠記念館「四時軒」に寄りました。
<台湾の英雄は宇土にルーツ>宇土市と台湾の台南市の日台交流の準備が始まっています。
いろんなお話を聴かせていただいた中村青史先生のご逝去を知り、生前の姿を思い出します。
<社会の転機は4代目?>て開いた本『歴史と人生』(半藤一利著)に、軍事や憲法9条に係る文が
司馬遼太郎は、「土方歳三の家はどこですか?」と聞くと、「あ、お大尽(だいじん)の家ですか」と言ったとある。
低所得者も納税するから政治に関心が高い(スウェーデン)。国民の1/4が所得税を納めないから政治に関心が低い(日本)。
<台湾の英雄は宇土にルーツ>宇土市と台湾の台南市の日台交流の準備が始まっています。
いろんなお話を聴かせていただいた中村青史先生のご逝去を知り、生前の姿を思い出します。
<社会の転機は4代目?>て開いた本『歴史と人生』(半藤一利著)に、軍事や憲法9条に係る文が
司馬遼太郎は、「土方歳三の家はどこですか?」と聞くと、「あ、お大尽(だいじん)の家ですか」と言ったとある。
低所得者も納税するから政治に関心が高い(スウェーデン)。国民の1/4が所得税を納めないから政治に関心が低い(日本)。
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。