コロナ渦中に思う「ふるさと納税」と「地方移住」。〜都市と地方の関係〜
2020年12月26日
コロナ渦中に思う「ふるさと納税」と「地方移住」。〜都市と地方の関係〜
2014年に発売された中公新書の『地方消滅』に、以下のことが書かれていました。
移住とふるさと納税の関係?
(以下、本より)
東京圏から地方へ、中高年層の移住をいっそう進めるためには、「地方移住関心層」に将来的に移住を考える地域を具体的に意識させ、その地域との紐帯(じゅうたい)を強めてもらうことも必要である。そのために推進すべきなのが「ふるさと納税」である。東京圏在住者に特定地域を意識させ、その地域を支える具体的な行動を促すのにこれ以上の仕組みはない。東京圏において「ふるさと納税」のキャンペーンを今まで以上に強力に展開し、「ふるさと納税」を特定の自治体に継続的に行った者には、地域を支えてくれる将来の移住候補者として、きめ細やかな情報提供を行うべきだ。
また、移住に際して住宅が大きな問題となる。東京圏の住宅を売却し、地方圏の住宅を取得した者に対して税制上の優遇措置を講じることも一案だ。
(以上、『地方消滅』(中公新書)より)
長い引用文ですが、この時の提言が、コロナ渦中の状況から、都心から、都市部から、地方移転が始まっている、と思います。
テレワーク、オンライン、三密避ける、等々、
人の住まいと仕事の関係、これから暮らしがどんどん変化しています。
"ふるさと納税→移住候補者の情報提供"
の考え方は、参考になります。来春から取り組む、棚田再生の活動と農産物販売、ふるさと納税も活用するのですが、返礼品に地域の魅力発信も加えるプランを計画したいと思います。
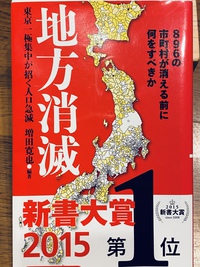
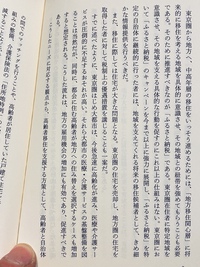
2014年に発売された中公新書の『地方消滅』に、以下のことが書かれていました。
移住とふるさと納税の関係?
(以下、本より)
東京圏から地方へ、中高年層の移住をいっそう進めるためには、「地方移住関心層」に将来的に移住を考える地域を具体的に意識させ、その地域との紐帯(じゅうたい)を強めてもらうことも必要である。そのために推進すべきなのが「ふるさと納税」である。東京圏在住者に特定地域を意識させ、その地域を支える具体的な行動を促すのにこれ以上の仕組みはない。東京圏において「ふるさと納税」のキャンペーンを今まで以上に強力に展開し、「ふるさと納税」を特定の自治体に継続的に行った者には、地域を支えてくれる将来の移住候補者として、きめ細やかな情報提供を行うべきだ。
また、移住に際して住宅が大きな問題となる。東京圏の住宅を売却し、地方圏の住宅を取得した者に対して税制上の優遇措置を講じることも一案だ。
(以上、『地方消滅』(中公新書)より)
長い引用文ですが、この時の提言が、コロナ渦中の状況から、都心から、都市部から、地方移転が始まっている、と思います。
テレワーク、オンライン、三密避ける、等々、
人の住まいと仕事の関係、これから暮らしがどんどん変化しています。
"ふるさと納税→移住候補者の情報提供"
の考え方は、参考になります。来春から取り組む、棚田再生の活動と農産物販売、ふるさと納税も活用するのですが、返礼品に地域の魅力発信も加えるプランを計画したいと思います。
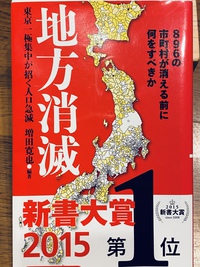
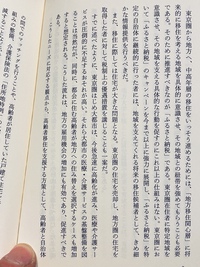
努力をしなかったのだから、それだけの結果しかもらえなかったのだ。日本は公平な国なのである。〜曽野綾子〜
2020年12月23日
<Time is money>努力をしなかったのだから、それだけの結果しかもらえなかったのだ。日本は公平な国なのである。〜曽野綾子〜
(少々長い文、お時間ある時にお読みください)
朝から手厳しい意見ですが、作家の曽野綾子さんの言葉には、これまで出会った人を検証すると納得する場面がいくつも出てくる。冒頭の言葉の前にあるのが、以下の文です。
(以下、『ただ一人の個性を創るために』より)
人並みなことをしていては、人並みかそれ以下にしかならない。もちろんそれでよければ、努力などという野暮なこともしない自由も残されている。しかし、その場合には運命に不平を言わないことだ。(中略)
かつて、"苦労は買ってでもしろ"と言われていた時代がある。ゆとり教育が叫ばれてから、努力などという言葉が薄れて来ているのでは、と感じる風景を見る。
(以下、本は以下の言葉で締められている)
人よりおもしろい人生を送りたければ、徹底して自分の時間と自分の運命の支配になることだろう。その場合、幸運は比較的たやすくその人に微笑みかける。私は今までたくさんの人たちの生涯を見てきた。戦後60年近く続いた平和のおかげでもあるが、少なくとも日本人はそれぞれの才能と努力に対して、実に公平に報われてきたという事実を見てきたと言える。
(以上、本より)
>人よりおもしろい人生を送りたければ、徹底して自分の時間と自分の運命の支配になること
チコちゃんではないですが、
(日々の生活で)"ボーッとしてんじゃないよ!"ということだろう。
何も考えなくても、1日、1時間、1分は過ぎていきます。
昭和の東洋哲学者・安岡正篤氏の日課は、朝の目覚めは未だ暗い未明に一人起き、今日一日に何をするか考えることから始まる、と本で読みました。
夜遅くまで起きて、あるいは夜遅くまで飲んで、夜遅くまでテレビを見て、朝は時間ギリギリに起きて、バタバタと出勤する。
安岡正篤氏の起き方とギリギリ出勤を見て、どちらが自らの時間と運命を支配しているか?
タイムイズマネー(西洋の格言)
人に与えられいる時間は、誰にでも公平です。
>人並みなことをしていては、人並みかそれ以下にしかならない。
熊本出身の政治評論家・故内田健三氏が、80歳を前にして語られた言葉、
「野口さん、身体は衰えていくが、精神はいくらでも成長する。一生勉強です」と。
私は、まだ62歳、内田健三氏の言葉を忘れずに、自分に与えられた時間を有効に使う努力をしなければ、と朝から思いました。
*「時は金なり=Time is money」は、アメリカの政治家ベンジャミン・フランクリンの若い社会人へのアドバイスが語源。
(少々長い文、お時間ある時にお読みください)
朝から手厳しい意見ですが、作家の曽野綾子さんの言葉には、これまで出会った人を検証すると納得する場面がいくつも出てくる。冒頭の言葉の前にあるのが、以下の文です。
(以下、『ただ一人の個性を創るために』より)
人並みなことをしていては、人並みかそれ以下にしかならない。もちろんそれでよければ、努力などという野暮なこともしない自由も残されている。しかし、その場合には運命に不平を言わないことだ。(中略)
かつて、"苦労は買ってでもしろ"と言われていた時代がある。ゆとり教育が叫ばれてから、努力などという言葉が薄れて来ているのでは、と感じる風景を見る。
(以下、本は以下の言葉で締められている)
人よりおもしろい人生を送りたければ、徹底して自分の時間と自分の運命の支配になることだろう。その場合、幸運は比較的たやすくその人に微笑みかける。私は今までたくさんの人たちの生涯を見てきた。戦後60年近く続いた平和のおかげでもあるが、少なくとも日本人はそれぞれの才能と努力に対して、実に公平に報われてきたという事実を見てきたと言える。
(以上、本より)
>人よりおもしろい人生を送りたければ、徹底して自分の時間と自分の運命の支配になること
チコちゃんではないですが、
(日々の生活で)"ボーッとしてんじゃないよ!"ということだろう。
何も考えなくても、1日、1時間、1分は過ぎていきます。
昭和の東洋哲学者・安岡正篤氏の日課は、朝の目覚めは未だ暗い未明に一人起き、今日一日に何をするか考えることから始まる、と本で読みました。
夜遅くまで起きて、あるいは夜遅くまで飲んで、夜遅くまでテレビを見て、朝は時間ギリギリに起きて、バタバタと出勤する。
安岡正篤氏の起き方とギリギリ出勤を見て、どちらが自らの時間と運命を支配しているか?
タイムイズマネー(西洋の格言)
人に与えられいる時間は、誰にでも公平です。
>人並みなことをしていては、人並みかそれ以下にしかならない。
熊本出身の政治評論家・故内田健三氏が、80歳を前にして語られた言葉、
「野口さん、身体は衰えていくが、精神はいくらでも成長する。一生勉強です」と。
私は、まだ62歳、内田健三氏の言葉を忘れずに、自分に与えられた時間を有効に使う努力をしなければ、と朝から思いました。
*「時は金なり=Time is money」は、アメリカの政治家ベンジャミン・フランクリンの若い社会人へのアドバイスが語源。
本日は、今年最後の生活安全パトロール隊網津支部の地域巡回パトロールの日でした。
2020年12月22日

本日は、今年最後の生活安全パトロール隊網津支部の地域巡回パトロールの日でした。たまたま、冬至の夕方で、もう薄暗く回っているうちに暗くなりました。
高田駐在所長から、今年は、校区内では大きな事故もなく、終えて良かったと感想をいただきました。月に2回のパトロール活動ですが、やはり抑止力として意味があるのだな、と思います。
今年のパトロールは、コロナウィルス感染拡大で、一時期運転手のみでパトカー、青パトの3台で回ったこともあり、いろいろなところにコロナ感染防止に気をつけなければならないこともありました。
来年も活動をしますが、早くコロナ感染が収まることを願うばかりです。
<コロナ禍で想う"愛"と"人権">愛についての百十字の定義、『コリントの信徒への手紙 1』の13・4に学ぶ〜曽野綾子〜
2020年12月22日
<コロナ禍で想う"愛"と"人権">愛についての百十字の定義、『コリントの信徒への手紙 1』の13・4に学ぶ〜曽野綾子〜
昨日、小池東京都知事が、コロナウィルス感染拡大を防ぐため"ステイホーム"の年末年始をお願いされていました。身勝手ではなく、国民は「命」のために、耐えることに徹してほしい、と訴えた。
今朝開いた本『ただ一人の個性を創るために』に、愛の定義が紹介されていた。
「愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える」〜『コリントの信徒への手紙 1』の13・4〜
周りの人への愛を持つ、職場、地域、一番は家族、身勝手をしない、させない。
曽野綾子さんは、こんなことにも着目している。
(以下、同じ本より)
今の時代、人権を要求する人は多くなったが、人権などというものは金銭関係を伴う冷たいものだ。しかし愛は純粋に心の問題で、人間と他の動物とは違った、人間そのものにする機能を持つのである。それなのに、人権については、あちこちで討議されるが、愛については現代日本ではほとんど真剣に考えられることがない。(中略)
人権を、仕事と置き換えると生活権とも言える。
職場を保つには、収入が必要となります。政府の訴える経済維持、そこから発想されたGoToキャンペーン、観光を支える活動が感染拡大となって、急遽中止になった。
愛と人権
どちらも大切なこと
家族を大切に思うなら、やはり愛が優先か
生きるためには人権、生活権、支援策
コリントの百十字の「愛の定義」を読み、リーダーたちの発言を聞いて、いろいろ考える機会になっています。
それと、リーダーたちの発言と行動、政府の要望「5人以下の会食」問題。リーダーの表向きの発言と個人としての行動、分からないと思っていても、バレるものです。
中国の故事に「四知」があります。
天知る、地知る、貴方知る、我知る
天も地もしゃべりませんが、自分と相手だけが知っているのに、なぜかどこからか漏れる。秘密のことは、"やらない"が良い教えです。
"愛"か"人権"か、それぞれに考え悩む年末年始になりそうです。
*参考資料:曽野綾子著『ただ一人の個性を創るために』
昨日、小池東京都知事が、コロナウィルス感染拡大を防ぐため"ステイホーム"の年末年始をお願いされていました。身勝手ではなく、国民は「命」のために、耐えることに徹してほしい、と訴えた。
今朝開いた本『ただ一人の個性を創るために』に、愛の定義が紹介されていた。
「愛は忍耐強い。愛は情け深い。ねたまない。愛は自慢せず、高ぶらない。礼を失せず、自分の利益を求めず、いらだたず、恨みを抱かない。不義を喜ばず、真実を喜ぶ。すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える」〜『コリントの信徒への手紙 1』の13・4〜
周りの人への愛を持つ、職場、地域、一番は家族、身勝手をしない、させない。
曽野綾子さんは、こんなことにも着目している。
(以下、同じ本より)
今の時代、人権を要求する人は多くなったが、人権などというものは金銭関係を伴う冷たいものだ。しかし愛は純粋に心の問題で、人間と他の動物とは違った、人間そのものにする機能を持つのである。それなのに、人権については、あちこちで討議されるが、愛については現代日本ではほとんど真剣に考えられることがない。(中略)
人権を、仕事と置き換えると生活権とも言える。
職場を保つには、収入が必要となります。政府の訴える経済維持、そこから発想されたGoToキャンペーン、観光を支える活動が感染拡大となって、急遽中止になった。
愛と人権
どちらも大切なこと
家族を大切に思うなら、やはり愛が優先か
生きるためには人権、生活権、支援策
コリントの百十字の「愛の定義」を読み、リーダーたちの発言を聞いて、いろいろ考える機会になっています。
それと、リーダーたちの発言と行動、政府の要望「5人以下の会食」問題。リーダーの表向きの発言と個人としての行動、分からないと思っていても、バレるものです。
中国の故事に「四知」があります。
天知る、地知る、貴方知る、我知る
天も地もしゃべりませんが、自分と相手だけが知っているのに、なぜかどこからか漏れる。秘密のことは、"やらない"が良い教えです。
"愛"か"人権"か、それぞれに考え悩む年末年始になりそうです。
*参考資料:曽野綾子著『ただ一人の個性を創るために』
<植民地のグアム>グアム島、コロナ禍で見えて来た米国の植民地政策の酷さ。
2020年12月21日
グアム島、コロナ禍で見えて来た米国の植民地政策の酷さ。これは、沖縄米軍の変わらぬ姿勢から、植民地のグアムは、さらにひどいのだろうと思いました。
強国アメリカの裏の姿、実はそれが真の姿なのかもしれない、とグアムの状況から検証が必要と思いました。
(以下、時事通信webより)
>米連邦法上「グアムはアンインコーポレッド・テリトリー(未編入領土)であり米連邦政府の所有物である」と明記されているからだ。未編入領土というと聞こえはよいが、事実上グアムは米国の「植民地」である。(中略)
>米軍基地外に住むグアム島民のコミュニティーは存在していないも同然で、グアム政府は連邦政府の決定には口出しができない一方的な支配関係が21世紀の現在も続いているのだ。(中略)
>島外からの一般の入島者は前述のように14日間ホテルの客室からすら出られない「強制隔離」を強いられている。(中略)
時事通信webにリンク
https://lin.ee/6wffiwv?utm_source=line&utm_medium=share&utm_campaign=none
強国アメリカの裏の姿、実はそれが真の姿なのかもしれない、とグアムの状況から検証が必要と思いました。
(以下、時事通信webより)
>米連邦法上「グアムはアンインコーポレッド・テリトリー(未編入領土)であり米連邦政府の所有物である」と明記されているからだ。未編入領土というと聞こえはよいが、事実上グアムは米国の「植民地」である。(中略)
>米軍基地外に住むグアム島民のコミュニティーは存在していないも同然で、グアム政府は連邦政府の決定には口出しができない一方的な支配関係が21世紀の現在も続いているのだ。(中略)
>島外からの一般の入島者は前述のように14日間ホテルの客室からすら出られない「強制隔離」を強いられている。(中略)
時事通信webにリンク
https://lin.ee/6wffiwv?utm_source=line&utm_medium=share&utm_campaign=none
団体旅行をした時、自分の権威が傷つけられたような気がする人がいるという。〜曽野綾子語録〜
2020年12月20日
<自ら個性(美点・欠点)と同席)団体旅行をした時、いい部屋をもらわないと、自分の権威が傷つけられたような気がする人がいるという。〜曽野綾子語録〜
久しぶりに、寝る前の読書で、作家の曽野綾子著『ただ一人の個性を創るために』を読んでいたら、"あれ!"こんな人、近くにいるなぁ、と思いました。
冒頭の文から、団体旅行なのに、なぜそんな要求をするのだろう。私などは、20歳からの一人旅で、鈍行列車の乗って、乗り継ぎで駅の待合い室で夜明かししたこともあるので、"どこで寝ても良いたい"と思うのですが、御曹司とかはダメなのでしょうね。
この項に以下の文がありました。へーっ!"権威""格式""名家"とは気難しいな、と思います。
(以下、本より)
紹介される順番、住んでいる地域、妻の出身校、そうしたものに、いちいち優劣をつけて、自分を他人と比べている人は決して珍しくないのである。しかしそれらはすべてかなりいい加減な根拠の比較の上になり立っている。
(以上、曽野綾子著『ただ一人の個性を創るために』より)
曽野綾子さんの見識からすると、権威、格式、名家の根拠は、かなりいい加減、とあります。
自らの生きた実感(実績)が、物足りない人ほど、威光を頼りをするのではないか?
宮内庁のある部署の役職は、旧華族の末裔とかで、いまでも「殿」と呼ばれているとか?
国の公的給与をもらっているのに、「殿!」はなかろうと思うのですが。
「それよりも、あなたの人生は、何をしてこられましたか?」
と思います。人について、曽野綾子は以下のように書かれています。
(以下、曽野綾子さんの本より)
人というものは、実は誰とも比べられない。だから静かに自分はただ一人と思っていいのである。美点も欠点もすべて自分のものだ。もちろん社会では、欠点を伸ばされると周囲が困るから、美点と言われる特性のほうを伸ばすほうが無難である。しかしほんとうは美点も欠点も含みですべて個性なのである。
(以上、『ただ一人の個性を創るために』より)
スーパースターのような作られた人間はどこにも存在しません。著名人ほど、不倫、失敗、破産もある。"奢れるものは久しからず"なので、凡人(一般平民)は、謙虚にいきよ!と思います。
>団体旅行の時、いい部屋をもらわないと、自分の権威が傷つけられる人がいる。
私は、そんな人がいるグループとは、旅をしません。そんな輩と一緒のツアーに金を払う気にもならない。
これからは、自ら個性(美点・欠点)を持って楽しめたらいいな、と思います。
久しぶりに、寝る前の読書で、作家の曽野綾子著『ただ一人の個性を創るために』を読んでいたら、"あれ!"こんな人、近くにいるなぁ、と思いました。
冒頭の文から、団体旅行なのに、なぜそんな要求をするのだろう。私などは、20歳からの一人旅で、鈍行列車の乗って、乗り継ぎで駅の待合い室で夜明かししたこともあるので、"どこで寝ても良いたい"と思うのですが、御曹司とかはダメなのでしょうね。
この項に以下の文がありました。へーっ!"権威""格式""名家"とは気難しいな、と思います。
(以下、本より)
紹介される順番、住んでいる地域、妻の出身校、そうしたものに、いちいち優劣をつけて、自分を他人と比べている人は決して珍しくないのである。しかしそれらはすべてかなりいい加減な根拠の比較の上になり立っている。
(以上、曽野綾子著『ただ一人の個性を創るために』より)
曽野綾子さんの見識からすると、権威、格式、名家の根拠は、かなりいい加減、とあります。
自らの生きた実感(実績)が、物足りない人ほど、威光を頼りをするのではないか?
宮内庁のある部署の役職は、旧華族の末裔とかで、いまでも「殿」と呼ばれているとか?
国の公的給与をもらっているのに、「殿!」はなかろうと思うのですが。
「それよりも、あなたの人生は、何をしてこられましたか?」
と思います。人について、曽野綾子は以下のように書かれています。
(以下、曽野綾子さんの本より)
人というものは、実は誰とも比べられない。だから静かに自分はただ一人と思っていいのである。美点も欠点もすべて自分のものだ。もちろん社会では、欠点を伸ばされると周囲が困るから、美点と言われる特性のほうを伸ばすほうが無難である。しかしほんとうは美点も欠点も含みですべて個性なのである。
(以上、『ただ一人の個性を創るために』より)
スーパースターのような作られた人間はどこにも存在しません。著名人ほど、不倫、失敗、破産もある。"奢れるものは久しからず"なので、凡人(一般平民)は、謙虚にいきよ!と思います。
>団体旅行の時、いい部屋をもらわないと、自分の権威が傷つけられる人がいる。
私は、そんな人がいるグループとは、旅をしません。そんな輩と一緒のツアーに金を払う気にもならない。
これからは、自ら個性(美点・欠点)を持って楽しめたらいいな、と思います。
Posted by ノグチ(noguchi) at
22:07
│Comments(0)
<人生は出会いと生き様>日本人が大切にしてきた「権威」とか「格式」とか、みなさんはどう思われますか?
2020年12月20日
<人生は出会いと生き様>日本人が大切にしてきた「権威」とか「格式」とか、みなさんはどう思われますか?
私は、一般平民の家系です。学歴もなく、人の支えもなく、どこかの権威につながりもなく、大会社に所属もせず、地方の個人事業主です。
私は、38歳から仲間づくりを始め、少しづつ縁が広がってきました。人間の価値は、どの時点で、誰が判断するのでしょうか?
私が尊敬する熊本の偉人と思っている故永野光哉氏が、「人の価値(評価)は、棺桶のふたが閉まってから」と語られていました。
と、これを盛り返すと、権威とか、格式とか、名家とか、は関係なく、その人の生き様そのものであるように、教えられた気がします。
死んだら権威も格式も名家もありません。その人の生きた歴史、人との関わり、実績も問われます。
>人の価値(評価)は、棺桶のふたが閉まってから
奢れるものは久しからず、権威に擦り寄る人生は、擦り寄るものがなくなれば、個人の存在そのものが問われます。
夫婦、家族、親族、地域、友人、知人、職場、趣味、社会活動、等々、人とご縁、偶然の同席、も含め出会いをこれからも大切にしていきます。
この歳になれば、見栄(地域、権威、格式)は必要ありません。素敵な人間に出会いたいですね。
私は、一般平民の家系です。学歴もなく、人の支えもなく、どこかの権威につながりもなく、大会社に所属もせず、地方の個人事業主です。
私は、38歳から仲間づくりを始め、少しづつ縁が広がってきました。人間の価値は、どの時点で、誰が判断するのでしょうか?
私が尊敬する熊本の偉人と思っている故永野光哉氏が、「人の価値(評価)は、棺桶のふたが閉まってから」と語られていました。
と、これを盛り返すと、権威とか、格式とか、名家とか、は関係なく、その人の生き様そのものであるように、教えられた気がします。
死んだら権威も格式も名家もありません。その人の生きた歴史、人との関わり、実績も問われます。
>人の価値(評価)は、棺桶のふたが閉まってから
奢れるものは久しからず、権威に擦り寄る人生は、擦り寄るものがなくなれば、個人の存在そのものが問われます。
夫婦、家族、親族、地域、友人、知人、職場、趣味、社会活動、等々、人とご縁、偶然の同席、も含め出会いをこれからも大切にしていきます。
この歳になれば、見栄(地域、権威、格式)は必要ありません。素敵な人間に出会いたいですね。
<コロナ渦後の地方の国際化>ダイバーシティの学校経営から見える社会
2020年12月12日
<コロナ渦後の地方の国際化>ダイバーシティの学校経営から見える社会
今朝4時5分からのNHKのインタビュー番組「明日への言葉」に、京都精華大学学長のウスビ・サコ氏(マリ共和国出身)が、海外留学生を増やしての大学経営と多国籍の多様性について語られました。
労働現場に欠かすことができなくなった技能実習生、農業実習生の海外からの労働者の皆さん、大学の存続に多国籍化が不可欠になっているのだなぁ、と話を聞いていました。
熊本県内にも、宇土市にも、海外からの技能実習生がいるのが普通になっています。一昨年春の日曜日、桜が咲く時期に開催したフットパス・モニターツアーで見た風景は、桜で人気スポットの宇土市の立岡自然公園には、ベトナム、中国、さらに観光ツアーで韓国の若者たちが、桜の花見で、バーベキューやお弁当開き、散策と、まるで海外の桜の公園にいるようでした。
今年は、コロナ渦で全く違う風景になりましたが、感染が収まれば、また国際的な環境が地方にも戻ると思います。国際化の流れは変わらないので、それを想定してコロナ渦後の対応が必要だなぁ、と今朝の放送を聞きながら考えていました。
今朝4時5分からのNHKのインタビュー番組「明日への言葉」に、京都精華大学学長のウスビ・サコ氏(マリ共和国出身)が、海外留学生を増やしての大学経営と多国籍の多様性について語られました。
労働現場に欠かすことができなくなった技能実習生、農業実習生の海外からの労働者の皆さん、大学の存続に多国籍化が不可欠になっているのだなぁ、と話を聞いていました。
熊本県内にも、宇土市にも、海外からの技能実習生がいるのが普通になっています。一昨年春の日曜日、桜が咲く時期に開催したフットパス・モニターツアーで見た風景は、桜で人気スポットの宇土市の立岡自然公園には、ベトナム、中国、さらに観光ツアーで韓国の若者たちが、桜の花見で、バーベキューやお弁当開き、散策と、まるで海外の桜の公園にいるようでした。
今年は、コロナ渦で全く違う風景になりましたが、感染が収まれば、また国際的な環境が地方にも戻ると思います。国際化の流れは変わらないので、それを想定してコロナ渦後の対応が必要だなぁ、と今朝の放送を聞きながら考えていました。
「人間は原子力エネルギーによって生きてはいけず、逆に滅んでいくだけだ。
2020年12月12日
<最新技術は幸福をもたらすのか?>「人間は原子力エネルギーによって生きてはいけず、逆に滅んでいくだけだ。たとえ原子力エネルギーが平和目的にのみ使われたとしても」〜マルティン・ハイデッカー(ドイツの哲学者)〜
原子力の研究者の一人・アインシュタインはドイツ生まれ、原子力の父とも言われる。ハイデッカーは、ドイツの哲学者。だから原子力について語ったのではないのか。
冒頭の言葉は、科学雑誌に書かれたものではなく、ある詩人に捧げたエッセイの中にある一文だそうです。
また、以下のことも書かれている。
「原子力の平和利用が人間の全ての目標設定と使命を規定するようになると、人間は自らの本質を失わねばならぬ」とも言った。
この言葉は、50年以上前に書かれていて、その予言通り、20世紀後半は、原子力発電所の事故が続きました。
日本の最大の原子力事故、東日本大震災の福島第一原発の事故です。町がいくつも避難させられ故郷に帰れない。
ソ連のチェルノブイリ原発事故
アメリカのスリーマイル島原発事故
世界の原子力発電事故の教訓が福島第一原発に活かされなかった。地震国の日本なのに、地震があること、どんな影響を受けるか、忘れていたのでは?
>人間は自らの本質を失わねばならぬ
ハイデッカーの言葉から、日本人は最先端の科学技術を盲信してしまうのではないか?と思いました。
すごい科学技術でも疑うことを忘れてはいけない。そんなことを、ハイデッカーは語ったのかもしれません。
*参考資料:金森誠也監修『世界の名言100選』より
原子力の研究者の一人・アインシュタインはドイツ生まれ、原子力の父とも言われる。ハイデッカーは、ドイツの哲学者。だから原子力について語ったのではないのか。
冒頭の言葉は、科学雑誌に書かれたものではなく、ある詩人に捧げたエッセイの中にある一文だそうです。
また、以下のことも書かれている。
「原子力の平和利用が人間の全ての目標設定と使命を規定するようになると、人間は自らの本質を失わねばならぬ」とも言った。
この言葉は、50年以上前に書かれていて、その予言通り、20世紀後半は、原子力発電所の事故が続きました。
日本の最大の原子力事故、東日本大震災の福島第一原発の事故です。町がいくつも避難させられ故郷に帰れない。
ソ連のチェルノブイリ原発事故
アメリカのスリーマイル島原発事故
世界の原子力発電事故の教訓が福島第一原発に活かされなかった。地震国の日本なのに、地震があること、どんな影響を受けるか、忘れていたのでは?
>人間は自らの本質を失わねばならぬ
ハイデッカーの言葉から、日本人は最先端の科学技術を盲信してしまうのではないか?と思いました。
すごい科学技術でも疑うことを忘れてはいけない。そんなことを、ハイデッカーは語ったのかもしれません。
*参考資料:金森誠也監修『世界の名言100選』より
川辺川ダム建設、これから20年かかるのでは、蒲島知事は存命なのか?
2020年12月02日
川辺川ダム建設、これから20年かかるのでは、蒲島知事は存命なのか?
10年前の白紙撤回の真意はあるのか?
次の選挙睨みの話なら、10年間の治水無策は、政治家として力量が足りないように思います。
くまモンブームでは、人吉球磨の治水は対応できませんね。
川辺川ダム中止からの10年間の知事がやってきたことを語ってから、ダム選択ではないかと、みんな納得しませんし、疑念を持ち続けます。
10年前の白紙撤回の真意はあるのか?
次の選挙睨みの話なら、10年間の治水無策は、政治家として力量が足りないように思います。
くまモンブームでは、人吉球磨の治水は対応できませんね。
川辺川ダム中止からの10年間の知事がやってきたことを語ってから、ダム選択ではないかと、みんな納得しませんし、疑念を持ち続けます。
30分のスピーチより2分の挨拶が難しい。〜15分で11の質問〜
2020年12月01日
30分のスピーチより2分の挨拶が難しい。〜15分で11の質問〜
明日から議会の一般質問、コロナ渦以前は、質問する時間が60分(答弁は、60分以上も可)ありました。コロナ感染が広がり、換気の問題、三密対策から、6・9月議会は、質問と答弁合わせて30分、今回は、質問時間を15分まで(答弁はオーバー可)に変わった。
今の私の質問は、2つのテーマで、11の質問なので、各平均1分〜1分半質問者が語れることになり、時間の使い方に工夫が要る。中には、2分半以上語る場面も出てくるので、とにかく無駄を語らず、主旨をコンパクトですが、質問の意図も語り、後の意見も加えていますので、だいぶ考えて、時間も費やしてきました。
やっとまとまったように思います。
以前読んだスピーチの本で、30分のスピーチよりも、2分の挨拶が難しい!
コロナ禍以前は、60分の質問時間で10〜12の質問で色々語ることもできるが、15分で11の質問は初めての体験です。つくづく、スピーチの本の意味を噛みしめています。
明日から議会の一般質問、コロナ渦以前は、質問する時間が60分(答弁は、60分以上も可)ありました。コロナ感染が広がり、換気の問題、三密対策から、6・9月議会は、質問と答弁合わせて30分、今回は、質問時間を15分まで(答弁はオーバー可)に変わった。
今の私の質問は、2つのテーマで、11の質問なので、各平均1分〜1分半質問者が語れることになり、時間の使い方に工夫が要る。中には、2分半以上語る場面も出てくるので、とにかく無駄を語らず、主旨をコンパクトですが、質問の意図も語り、後の意見も加えていますので、だいぶ考えて、時間も費やしてきました。
やっとまとまったように思います。
以前読んだスピーチの本で、30分のスピーチよりも、2分の挨拶が難しい!
コロナ禍以前は、60分の質問時間で10〜12の質問で色々語ることもできるが、15分で11の質問は初めての体験です。つくづく、スピーチの本の意味を噛みしめています。



