二人の師から台風見舞いの電話、図らずもゆっくり語りました。
2016年09月20日
二人の師から台風見舞いの電話、図らずもゆっくり語りました。
夕方近くに自宅に帰り、明日からの活動の準備をしていると、携帯に電話が入りました。03(東京)から、「ハッ」として、椅子に座り直して電話を受けました。
「台風はどうかね?、テレビでは“うと(宇土)”のことがニュースに流れた」と言葉から台風見舞いの電話が、震災以来の内容、水害被害、静岡合宿、さらには9月議会のことまで、ずっと質問が続きました。
3月ぶりに、ゆっくりと語りました。昭和10年生まれの大企業家で環境活動家の様々に示唆溢れる言葉には、耳を澄ませます。
さらに、夕方には福岡に居られる論語・易経等の教育古典の学びで、過去19年の異業種交流会「四季の会」に助言や参加いただいている年齢もひと回り違う日本文学の研究者とのやり取りは、40分近くになりました。
それぞれ世代での“仲間づくり”の苦労、工夫があるからこそ今がある、と考えています。福岡の先生とは、かれこれ25年。東京の環境活動家とは18年になりました。
明日からの「復興・軽トラ市」に、本日の二人の先輩の言葉や訓示を、私なりに理解し実行していきたいと思います。電話とやり取りですが、なかなかタイミングよくゆっくりと語る機会は少ないと思います。
本日の二人の先輩からの電話は、とても有意義な時間となりました。
夕方近くに自宅に帰り、明日からの活動の準備をしていると、携帯に電話が入りました。03(東京)から、「ハッ」として、椅子に座り直して電話を受けました。
「台風はどうかね?、テレビでは“うと(宇土)”のことがニュースに流れた」と言葉から台風見舞いの電話が、震災以来の内容、水害被害、静岡合宿、さらには9月議会のことまで、ずっと質問が続きました。
3月ぶりに、ゆっくりと語りました。昭和10年生まれの大企業家で環境活動家の様々に示唆溢れる言葉には、耳を澄ませます。
さらに、夕方には福岡に居られる論語・易経等の教育古典の学びで、過去19年の異業種交流会「四季の会」に助言や参加いただいている年齢もひと回り違う日本文学の研究者とのやり取りは、40分近くになりました。
それぞれ世代での“仲間づくり”の苦労、工夫があるからこそ今がある、と考えています。福岡の先生とは、かれこれ25年。東京の環境活動家とは18年になりました。
明日からの「復興・軽トラ市」に、本日の二人の先輩の言葉や訓示を、私なりに理解し実行していきたいと思います。電話とやり取りですが、なかなかタイミングよくゆっくりと語る機会は少ないと思います。
本日の二人の先輩からの電話は、とても有意義な時間となりました。
Posted by ノグチ(noguchi) at
23:28
│Comments(0)
生100年なら道半ば、「脳は何歳になっても育つ」「人は何歳でも始められる」、これからが本番なのかもしれません。
2016年09月19日


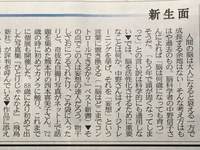
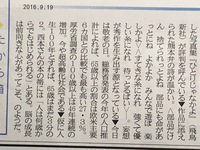
私は58歳、人生100年なら道半ば、「脳は何歳になっても育つ」「人は何歳でも始められる」、これからが本番なのかもしれません。
おはようございます。
本日は、敬老の日ですが、宇土市は熊本地震の影響で、体育館等の施設が被害を受けたり、改修中だったりとで、各地区の敬老会は中止で、金婚式のセレモニーだけが、市全体て開催されるのみです。まだまだ、震災の影響は生活面でも大きいです。
さて、敬老の日に際しての地元新聞の一面コラム「新生面」に、88歳になり初めて写真集『ひとりじゃなかよ』のアマチュアカメラマンの西本喜美子さんのことを取り上げていて、末尾に「人は何歳でも始められる」の言葉で締められ、人間の可能性の素晴らしさを感じ、元気をいただきました。
人は、いつか現役(稼ぐ仕事)から退き、いわゆる余生を過ごす時間になりますが、中には、退職後に輝く人も出てきます。72歳から始めたカメラが、88歳で花開く、素晴らしいと思います。
かつて、退職した熱血サラリーマンが、妻の行くところにくっつき、やることもなく「濡れ落ち葉」と揶揄された記事を読みましたが、「脳は何歳になっても育つ」には、その人自身がどんな老後を過ごすかで、余生も輝きを増すことができることを示しています。
憲政の神様と尊敬された戦前戦後に活躍した政治家の尾崎行雄は、75歳で大病した時、自分の人生を振り返り、人生道半ばと自覚し、
「人生の本舞台は将来にあり」
とさらに成長を誓ったと言われます。
本日の金婚式、どんな方々が出席されるか、とても楽しみな敬老の日の一日です。
Posted by ノグチ(noguchi) at
05:53
│Comments(0)
可愛い子には旅をさせよ(佐藤一斎)
2016年09月13日
可愛い子には旅をさせよ(佐藤一斎)
〜地方の少子化、どうやって回復させるか?〜
おはようございます。
秋雨前線により毎日雨模様ですが、昨夜は熊本地震が北上して、韓国南部を震源とする地震が発生して、大きなニュースになっています。
自然はつながっているなと感じます。
さて、朝から詩を一つ。
<心がほっとする日本の名詩100>
子供たちに
〜小熊秀雄〜
街をあゆむとき
手をふり元気よく
おあるきなさい
夜やすむとき
足をうーんと伸ばして
おやすみなさい
ちぢこまっていてはいけません
日蔭に咲く花のように
みじめに
しなびれてしまいます
(以上、本より転載)
子どもには、元気よくのびのびと生きて欲しい、と思うのは親心と思います。ただ、過保護にはならぬように。
幕末に大きな影響を与えた儒家で教育者の佐藤一斎の子育ての訓示に次の言葉があります。
【現代語訳】
必ず子弟を他国へ出して師について学ばせ、よく鍛錬して初めて学業が成るものである。いつまでも父母のもとでごろごろしていたり、郷里てこせこせしていて、どうして草木が成長するように学業が成就する見込みがあるだろうか。とてもではないが、その望みはない。
(以上、『佐藤一斎一日一言』より)
毎朝、登校指導する中で、雨がひどいと子どもは歩いて来る子が減ります。車通学になる子も増えました。昔のように、長靴履いて傘さして、四季の気候に触れながら、自らの五感を研ぎ澄まして、自然を感じて歩く、それも元気よく!
車通学、時代なのだと思います。
田舎ほど、過保護か?、時代か?
少子化で減り続ける地方の子どもたち、昔のように野山を駆け回ると、イノシシに出くわす時代、どんな地方社会になって行くのか、田舎も未来を描けない時代になっています。
〜地方の少子化、どうやって回復させるか?〜
おはようございます。
秋雨前線により毎日雨模様ですが、昨夜は熊本地震が北上して、韓国南部を震源とする地震が発生して、大きなニュースになっています。
自然はつながっているなと感じます。
さて、朝から詩を一つ。
<心がほっとする日本の名詩100>
子供たちに
〜小熊秀雄〜
街をあゆむとき
手をふり元気よく
おあるきなさい
夜やすむとき
足をうーんと伸ばして
おやすみなさい
ちぢこまっていてはいけません
日蔭に咲く花のように
みじめに
しなびれてしまいます
(以上、本より転載)
子どもには、元気よくのびのびと生きて欲しい、と思うのは親心と思います。ただ、過保護にはならぬように。
幕末に大きな影響を与えた儒家で教育者の佐藤一斎の子育ての訓示に次の言葉があります。
【現代語訳】
必ず子弟を他国へ出して師について学ばせ、よく鍛錬して初めて学業が成るものである。いつまでも父母のもとでごろごろしていたり、郷里てこせこせしていて、どうして草木が成長するように学業が成就する見込みがあるだろうか。とてもではないが、その望みはない。
(以上、『佐藤一斎一日一言』より)
毎朝、登校指導する中で、雨がひどいと子どもは歩いて来る子が減ります。車通学になる子も増えました。昔のように、長靴履いて傘さして、四季の気候に触れながら、自らの五感を研ぎ澄まして、自然を感じて歩く、それも元気よく!
車通学、時代なのだと思います。
田舎ほど、過保護か?、時代か?
少子化で減り続ける地方の子どもたち、昔のように野山を駆け回ると、イノシシに出くわす時代、どんな地方社会になって行くのか、田舎も未来を描けない時代になっています。
Posted by ノグチ(noguchi) at
06:59
│Comments(0)
「アダルトチルドレン」て、どんな症状のこと、???、一度知っていただきたい言葉と意味
2016年09月12日
「アダルトチルドレン」て、どんな症状のこと、???、一度知っていただきたい言葉と意味
あなたのご家庭、スムーズですか?
子どもにストレスはないですか?
子どもは、自分の夢を語りますか?
大人どおしが、わだかまりなく語り合っていますか?
アダルトチルドレン、という精神的な症状について知って欲しいと思います。
〜以下、言葉の説明の抜粋〜
アダルトチルドレンとは、家庭としての正常な機能を果たしていない機能不全家庭で成長したために、大人になってからも心に傷を持っている人のことを言います。
子供は親から精神的な支配を受け続けて成長すると、自分自身では何も決めることが出来なくなり、誰かに支配してもらわないと何も出来なくなってしまうことがあります。また、親も子供が何でも言うことを聞くのが当然の状況になっているため、次第に子供に依存していき共依存の関係に陥ってしまうケースが少なくありません。
共依存になると、親と子供の境界が曖昧になり、子供の頃に育むべき感情を育てることが出来ず、親の気持ちに沿った行動ばかりする子供になってしまいます。これが大人になってからアダルトチルドレンになってしまう、根本的な要因とされています。(中略)
あなたのご家庭、スムーズですか?
子どもにストレスはないですか?
子どもは、自分の夢を語りますか?
大人どおしが、わだかまりなく語り合っていますか?
アダルトチルドレン、という精神的な症状について知って欲しいと思います。
〜以下、言葉の説明の抜粋〜
アダルトチルドレンとは、家庭としての正常な機能を果たしていない機能不全家庭で成長したために、大人になってからも心に傷を持っている人のことを言います。
子供は親から精神的な支配を受け続けて成長すると、自分自身では何も決めることが出来なくなり、誰かに支配してもらわないと何も出来なくなってしまうことがあります。また、親も子供が何でも言うことを聞くのが当然の状況になっているため、次第に子供に依存していき共依存の関係に陥ってしまうケースが少なくありません。
共依存になると、親と子供の境界が曖昧になり、子供の頃に育むべき感情を育てることが出来ず、親の気持ちに沿った行動ばかりする子供になってしまいます。これが大人になってからアダルトチルドレンになってしまう、根本的な要因とされています。(中略)
Posted by ノグチ(noguchi) at
08:49
│Comments(0)
若者の貧困、よく語られる5つの「若者論」の誤りとは?
2016年09月09日
若者の貧困、よく語られる5つの「若者論」の誤りとは?〜長文です〜
おはようございます。今朝は、冷え込んで目覚めました。風呂上がりで、Tシャツ1枚でベットにごろり、そのまま寝てしまい、朝のひんやりで目覚めました。慌ててタオルケットを引っ張りでしました。
さて、寒さで目覚めて、枕元の本を開くと「若者論」について書かれた意見に目が止まりました。藤田孝典著『貧困世代』から、
2014年4月7日の参議院内閣委員会の質疑で、
(山本太郎)
最近では、若者世代の貧困が、深刻な問題となっています。(中略)最近の若者は根性が足りん、とお感じになりますか?
(菅義偉・内閣官房長官)
根性が足りないということではありましたけれども、やはり自分が何をやるのかと、そういうものをやはりしっかりと持って頑張る方が少なくなっていることは、これは事実かなというふうに思っています。たた、やはり親に頼るとかそういう方が増えてきているのかなという思いは、私はしないわけじゃないです。
(以上、藤田孝典著『貧困世代』より)
筆者の藤田孝典氏は、
時代を経ても若者のマインドや性質は大きく変容するものではない。大きく変容するのはいつの時代も若者周辺の環境である。頑張る若者が減っている事実や根拠はどこにもない。(中略)
見出し『大人が貧困をわからない悲劇」の初めの文ですが、
若者たちが置かれている現状は、あまりにも「しんどい」。
の言葉から始まり、
よく語られる5つの「若者論」の誤り
1.働けば収入を得られるという神話[労働万能論)
〜ブラック企業の台頭も若者の困難に拍車をかける。
2.家族が助けてくれるという神話(家族扶養説)
〜(子どもを)搾取の対象とされる。
3.元気で健康であるという神話(青年健康説)
〜日本の若者(15〜34歳)の自殺率。先進国でダントツ1位(人口10万人中、20人)、アメリカの約2倍。
4.昔はもっと大変だったという時代錯誤的神話(時代比較説)
〜「若者はみんないつの時代も大変なものだ」と言い出す人も、特に熟年世代に多い。
*筆者の解説:「貧困」と「貧乏」の違い
昔は貧乏であり、物質的には恵まれない時代だったが、それを補い合う人間関係や連帯感が醸成されていた。
〜(現代の貧困)生まれ持った運で決まってしまう。
5.若いうちは努力すべきで、それは一時的な苦労だという神話[努力至上主義説)
〜非正規雇用でどれだけ努力をしても
正社員になれない若者がいかに多いことだろうか。
「報われる労働」と「報われない労働」の2種類があることを認識し、すべてにおいて「努力すれば報われる」と述べるのは、無責任と考える。
(以上、『貧困世代』から抜粋)
他の言葉は、
・惚れ込めない仕事
・若者支援は必要ないと思っている政府
・社会福祉も若者支援は必要ないと思っている
・支援とともに給付策の充実を
・「特別な存在」に限定されない給付を
等々ご紹介しました。「若者支援に理解のない大人たち」とは、誰のことか、どの世代か、この本を読みながら、考えてみたいと思います。
おはようございます。今朝は、冷え込んで目覚めました。風呂上がりで、Tシャツ1枚でベットにごろり、そのまま寝てしまい、朝のひんやりで目覚めました。慌ててタオルケットを引っ張りでしました。
さて、寒さで目覚めて、枕元の本を開くと「若者論」について書かれた意見に目が止まりました。藤田孝典著『貧困世代』から、
2014年4月7日の参議院内閣委員会の質疑で、
(山本太郎)
最近では、若者世代の貧困が、深刻な問題となっています。(中略)最近の若者は根性が足りん、とお感じになりますか?
(菅義偉・内閣官房長官)
根性が足りないということではありましたけれども、やはり自分が何をやるのかと、そういうものをやはりしっかりと持って頑張る方が少なくなっていることは、これは事実かなというふうに思っています。たた、やはり親に頼るとかそういう方が増えてきているのかなという思いは、私はしないわけじゃないです。
(以上、藤田孝典著『貧困世代』より)
筆者の藤田孝典氏は、
時代を経ても若者のマインドや性質は大きく変容するものではない。大きく変容するのはいつの時代も若者周辺の環境である。頑張る若者が減っている事実や根拠はどこにもない。(中略)
見出し『大人が貧困をわからない悲劇」の初めの文ですが、
若者たちが置かれている現状は、あまりにも「しんどい」。
の言葉から始まり、
よく語られる5つの「若者論」の誤り
1.働けば収入を得られるという神話[労働万能論)
〜ブラック企業の台頭も若者の困難に拍車をかける。
2.家族が助けてくれるという神話(家族扶養説)
〜(子どもを)搾取の対象とされる。
3.元気で健康であるという神話(青年健康説)
〜日本の若者(15〜34歳)の自殺率。先進国でダントツ1位(人口10万人中、20人)、アメリカの約2倍。
4.昔はもっと大変だったという時代錯誤的神話(時代比較説)
〜「若者はみんないつの時代も大変なものだ」と言い出す人も、特に熟年世代に多い。
*筆者の解説:「貧困」と「貧乏」の違い
昔は貧乏であり、物質的には恵まれない時代だったが、それを補い合う人間関係や連帯感が醸成されていた。
〜(現代の貧困)生まれ持った運で決まってしまう。
5.若いうちは努力すべきで、それは一時的な苦労だという神話[努力至上主義説)
〜非正規雇用でどれだけ努力をしても
正社員になれない若者がいかに多いことだろうか。
「報われる労働」と「報われない労働」の2種類があることを認識し、すべてにおいて「努力すれば報われる」と述べるのは、無責任と考える。
(以上、『貧困世代』から抜粋)
他の言葉は、
・惚れ込めない仕事
・若者支援は必要ないと思っている政府
・社会福祉も若者支援は必要ないと思っている
・支援とともに給付策の充実を
・「特別な存在」に限定されない給付を
等々ご紹介しました。「若者支援に理解のない大人たち」とは、誰のことか、どの世代か、この本を読みながら、考えてみたいと思います。
Posted by ノグチ(noguchi) at
07:30
│Comments(0)
<女性の活躍>、欧米は「ガラス天井」、日本は「竹天井」、それから13年
2016年09月05日
<女性の活躍>、欧米は「ガラス天井」、日本は「竹天井」、それから13年
おはようございます。台風は、玄界灘へ抜けたようです。みなさんの地域の被害はいかがでしょうか? 九州は、地震、梅雨の大雨、今回の台風、自然とは怖いなと思います。これから通過する地域の方々は、備えあれば憂いなし、早めの避難が大事と思います。ご用心願います。
さて、話題は違いますが、2003年に日経新聞が出版した『女たちが日本を変えていく』なる本を以前にリサイクルブック店で見つけて購入していたのですが、最近の政府のスローガン「総活躍社会」なる言葉から読み始めました。
私の読書は、初めから全部読むのではなく、気になる言葉やキーワードに目が止まり前後を読み始めるタイプで、パラパラと開き、??から読み始める。
今日は、「昇進拒む竹天井」という言葉に、引っかかりました。この本は、13年前の1月が初版で、その前5年間くらいの日経新聞の話題から集めた内容と思われます。第2章の「会社を撃つ」は物騒な見出しですが、その最後のテーマが昇進問題でした。
(以下、本より抜粋)
「ガラス天井」より不透明
「これまでは実力に大差がなければ女性よりも男性を昇進させる企業が多かった」(日経連の労務法制部)
欧米では、理由が明確でないまま昇進が「ガラス天井」の是正を求める運動が広がった。日本の女性たちには、欧米より物差しが不透明だとして、「竹天井」と呼ぶ声もある。
1998年度の東京都の管理職登用試験(事務系)では26人の合格者のうち女性が14人を占めた。
ある男性の局長は「女性たちは単に筆記試験の成績がいいだけではない。実際に仕事ができ、管理能力も高い」と話す。金子清子前副知事は「20年後は局長の半数が女性になる時代かもしれませんよ」と語る。
(以上、本より)
2003年に出版された本を改めて読み、地方の現状を観察すると惨憺たる状況になっています。金子清子副知事が「20年後」と語った年は、2018年に当たります。やはり地方は、男性優位の状態がまだまだだと感じます。
しかし、自治体のトップに女性が、起業する女性ま増えていること、最近異業種交流に熱心な人たちに女性が目立つようになって来た気がします。
日本は人口減少が確実に進み、地方はさらに加速しています。地方活性化に女性の活躍にが不可欠、「総総活躍社会」なる言葉が広がり、女性が地方で輝き「竹天井」から「ガラス天井」に変わって行くことが必要な気がします。
おはようございます。台風は、玄界灘へ抜けたようです。みなさんの地域の被害はいかがでしょうか? 九州は、地震、梅雨の大雨、今回の台風、自然とは怖いなと思います。これから通過する地域の方々は、備えあれば憂いなし、早めの避難が大事と思います。ご用心願います。
さて、話題は違いますが、2003年に日経新聞が出版した『女たちが日本を変えていく』なる本を以前にリサイクルブック店で見つけて購入していたのですが、最近の政府のスローガン「総活躍社会」なる言葉から読み始めました。
私の読書は、初めから全部読むのではなく、気になる言葉やキーワードに目が止まり前後を読み始めるタイプで、パラパラと開き、??から読み始める。
今日は、「昇進拒む竹天井」という言葉に、引っかかりました。この本は、13年前の1月が初版で、その前5年間くらいの日経新聞の話題から集めた内容と思われます。第2章の「会社を撃つ」は物騒な見出しですが、その最後のテーマが昇進問題でした。
(以下、本より抜粋)
「ガラス天井」より不透明
「これまでは実力に大差がなければ女性よりも男性を昇進させる企業が多かった」(日経連の労務法制部)
欧米では、理由が明確でないまま昇進が「ガラス天井」の是正を求める運動が広がった。日本の女性たちには、欧米より物差しが不透明だとして、「竹天井」と呼ぶ声もある。
1998年度の東京都の管理職登用試験(事務系)では26人の合格者のうち女性が14人を占めた。
ある男性の局長は「女性たちは単に筆記試験の成績がいいだけではない。実際に仕事ができ、管理能力も高い」と話す。金子清子前副知事は「20年後は局長の半数が女性になる時代かもしれませんよ」と語る。
(以上、本より)
2003年に出版された本を改めて読み、地方の現状を観察すると惨憺たる状況になっています。金子清子副知事が「20年後」と語った年は、2018年に当たります。やはり地方は、男性優位の状態がまだまだだと感じます。
しかし、自治体のトップに女性が、起業する女性ま増えていること、最近異業種交流に熱心な人たちに女性が目立つようになって来た気がします。
日本は人口減少が確実に進み、地方はさらに加速しています。地方活性化に女性の活躍にが不可欠、「総総活躍社会」なる言葉が広がり、女性が地方で輝き「竹天井」から「ガラス天井」に変わって行くことが必要な気がします。
Posted by ノグチ(noguchi) at
06:48
│Comments(0)
江戸末期の大地震で命を落とした学者、拾った学者。〜話し合い、忘れ物〜
2016年09月04日
江戸末期の大地震で命を落とした学者、拾った学者。〜話し合い、忘れ物〜
毎週タイミングが合えば見るNHK-BSの「英雄たちの選択」の中心的コメンテーターの国際日本文化研究センター准教授の磯田道史氏の著書『天災から日本史を読み直す、先人に学ぶ』に、幕末の儒家の地震対応で、命を落とした学者、命を拾った学者について書かれていました。
地震発生時の学者家族の対応について
「藤田東湖」
幕末の動乱期に、大きな影響を与えた水戸藩の学者が藤田東湖ですが、あの西郷隆盛が「おそるべき者は東湖一人のみ」と言わしめ、終生敬慕した。
この藤田東湖は、1855年の安政江戸地震で命を落とした。その原因は、家族の“忘れ物”により身代わりとなった。地震が起こり、一旦は家族全員が家から出たが、老母が「火鉢の火を消し忘れた。藤田家から火を出しては主君(忠)に申し訳ない」と思い命がけで家の中へ飛び込んだ。東湖は危ないと母を追った(孝)。そこに家が倒壊し、母はどうにか庭は投げ出したが、本人は崩れてきた鴨居や梁に押しつぶされ亡くなった。
「猪飼敬所」
その前年の1854年に伊賀上野で地震が起こり、その地に住む著名な学者猪飼敬所夫婦の地震対応が紹介されていました。
伊賀上野の地震は、事前に数日前から度々揺れがあったようで、猪飼は妻に有事(大地震)時の対応を話していた。
「小生の家には二人の男子がいる。兄は九歳。弟(小児)は三歳。下男下女のいない家だから、平生から火急の節は、兄の方は小生が抱き、小児は家内(妻)が抱いて逃げる」
この申し合わせが、大地震の時活きた。地震が起きると猪飼夫婦はそれぞれに子どもを抱き、壁の落下、柱か倒れかかる中外へ飛び出た。本人の日記によると、
「今、ひと足、遅れれば死を免れなかったところ天の幸いで逃げられた」
忠孝を貫いて死んだ藤田東湖。
夫婦で備え命を守りぬいた猪飼敬所。
二つの家の歴史が我々に教訓を示していると思います。二つの学者家族の歴史から、
1.事前に家族で地震時(災害時)にどうするか話し合っているか。
2.一度逃げたら、忘れ物は取りに家に戻らない。
藤田東湖の死が、幕末の江戸幕府での水戸藩の進む方向を鈍らせたのではと考えます。著名な学者でもとっさ(有事)の時は、身を危険にさらすことになります。いかに、ふだん(平時)から災害・事件が起きた時にはどうするか? 家族全員が共通意識を持つことが大事だし、事あるごとに確認しておくことも必要です。
三つ子の魂百まで!
海岸近くに住む家族は、三歳になったら「揺れたら(有事)山へ逃げる」の事を常々(平時)子どもに語っておくこと、また何処を目指して走るかも現地確認をさせておくことが大事と思います。江戸時代にも、ちゃんと子どもとともに訓練していた家族がいたから生き延びれたし、教訓を伝承(地震石より下に家を造るな)して東日本大震災の時に被害を受けなかった地区が存在しています。
自然災害はいつ来るかわかりません。備えあれば憂いなし、平時から家族で話し合っておくことの大切さを学んだ気がします。
午後には、台風12号が接近し上陸する予報、早めの避難が大事と思います。ご注意を!
毎週タイミングが合えば見るNHK-BSの「英雄たちの選択」の中心的コメンテーターの国際日本文化研究センター准教授の磯田道史氏の著書『天災から日本史を読み直す、先人に学ぶ』に、幕末の儒家の地震対応で、命を落とした学者、命を拾った学者について書かれていました。
地震発生時の学者家族の対応について
「藤田東湖」
幕末の動乱期に、大きな影響を与えた水戸藩の学者が藤田東湖ですが、あの西郷隆盛が「おそるべき者は東湖一人のみ」と言わしめ、終生敬慕した。
この藤田東湖は、1855年の安政江戸地震で命を落とした。その原因は、家族の“忘れ物”により身代わりとなった。地震が起こり、一旦は家族全員が家から出たが、老母が「火鉢の火を消し忘れた。藤田家から火を出しては主君(忠)に申し訳ない」と思い命がけで家の中へ飛び込んだ。東湖は危ないと母を追った(孝)。そこに家が倒壊し、母はどうにか庭は投げ出したが、本人は崩れてきた鴨居や梁に押しつぶされ亡くなった。
「猪飼敬所」
その前年の1854年に伊賀上野で地震が起こり、その地に住む著名な学者猪飼敬所夫婦の地震対応が紹介されていました。
伊賀上野の地震は、事前に数日前から度々揺れがあったようで、猪飼は妻に有事(大地震)時の対応を話していた。
「小生の家には二人の男子がいる。兄は九歳。弟(小児)は三歳。下男下女のいない家だから、平生から火急の節は、兄の方は小生が抱き、小児は家内(妻)が抱いて逃げる」
この申し合わせが、大地震の時活きた。地震が起きると猪飼夫婦はそれぞれに子どもを抱き、壁の落下、柱か倒れかかる中外へ飛び出た。本人の日記によると、
「今、ひと足、遅れれば死を免れなかったところ天の幸いで逃げられた」
忠孝を貫いて死んだ藤田東湖。
夫婦で備え命を守りぬいた猪飼敬所。
二つの家の歴史が我々に教訓を示していると思います。二つの学者家族の歴史から、
1.事前に家族で地震時(災害時)にどうするか話し合っているか。
2.一度逃げたら、忘れ物は取りに家に戻らない。
藤田東湖の死が、幕末の江戸幕府での水戸藩の進む方向を鈍らせたのではと考えます。著名な学者でもとっさ(有事)の時は、身を危険にさらすことになります。いかに、ふだん(平時)から災害・事件が起きた時にはどうするか? 家族全員が共通意識を持つことが大事だし、事あるごとに確認しておくことも必要です。
三つ子の魂百まで!
海岸近くに住む家族は、三歳になったら「揺れたら(有事)山へ逃げる」の事を常々(平時)子どもに語っておくこと、また何処を目指して走るかも現地確認をさせておくことが大事と思います。江戸時代にも、ちゃんと子どもとともに訓練していた家族がいたから生き延びれたし、教訓を伝承(地震石より下に家を造るな)して東日本大震災の時に被害を受けなかった地区が存在しています。
自然災害はいつ来るかわかりません。備えあれば憂いなし、平時から家族で話し合っておくことの大切さを学んだ気がします。
午後には、台風12号が接近し上陸する予報、早めの避難が大事と思います。ご注意を!
Posted by ノグチ(noguchi) at
08:08
│Comments(0)
復興・うと軽トラ市、復興・宇土マリーナジュニアサッカー大会
2016年09月02日
〜復興・うと軽トラ市、復興・宇土マリーナジュニアサッカー大会〜
<項羽と劉邦>二の矢、三の矢の手を打つ。5年手を打たず現状維持では他に抜き去られる。
ここ数日、中国古典で歴史の英雄たちを追ってみました。『漢書』の中に出てくる英雄たちで代表格は、項羽と劉邦ではないでしょうか。
兵法書と言われる『孫子』には、「先手必勝」の一節があります。「先発すれば人を制し、後発すれば人に制せられる」と。
秦の始皇帝が死去したあと、圧政に不満な豪族たちが反乱を起こした。その一人が項羽で、項羽は用兵巧みさと先発の利を活かして一度は天下を手中に収めたかに見えた。たが、長くはつづかなかった。
やがて、ライバル劉邦の反撃を許し、最後は「四面楚歌」の状態に追い詰められて自滅してしまった。
項羽は、明らかに優勢を過信し一瞬の油断が命取りになった。つまり、先発の利に甘えて、二の矢、三の矢を用意していなかったことが原因と思われる。
本日の朝読書で、作家の守屋洋訳著『人生を面白くする中国古典名言集』に、現代人へ向けたメッセージがありました。
(以下、転載)
「私が長い経験から学んだ教訓は、いかなる大企業といえども、五年間、何ら思いきった手を打たず、現状に満足し続けていれば、あっという間に傾いてしまう現実である。問題は業種にあるのではない」(略)
そうならないためには、先発の利に甘えることなく、二の矢、三の矢の開拓を怠ってはならない。
(以上、『人生を面白くする中国古典名言集』より)
歴史に学べとはよく言ったものです。
9月25日の「復興・うと軽トラ市」は4回目、11月に開催予定の「復興・宇土マリーナジュニアサッカー大会」は15回目、それぞれに工夫をして来たが、さらにアイデアを出して、賑わい創出を考えなければと思います。
うと軽トラ市では、初めて行う「震災復興チャリティーコンサート」に、多くの方にご参集いただけるように告知・広報に頑張ります。
宇土マリーナジュニアサッカー大会では、インターネットを主軸に、告知・広報を行い、さらには、試合の模様をネット配信することを初めて行います。大会2日目の11月13日には、昨年同様に宇土産業祭とコラボして、さらに人が集い楽しむ2日間にできれば準備いたします。
<項羽と劉邦>二の矢、三の矢の手を打つ。5年手を打たず現状維持では他に抜き去られる。
ここ数日、中国古典で歴史の英雄たちを追ってみました。『漢書』の中に出てくる英雄たちで代表格は、項羽と劉邦ではないでしょうか。
兵法書と言われる『孫子』には、「先手必勝」の一節があります。「先発すれば人を制し、後発すれば人に制せられる」と。
秦の始皇帝が死去したあと、圧政に不満な豪族たちが反乱を起こした。その一人が項羽で、項羽は用兵巧みさと先発の利を活かして一度は天下を手中に収めたかに見えた。たが、長くはつづかなかった。
やがて、ライバル劉邦の反撃を許し、最後は「四面楚歌」の状態に追い詰められて自滅してしまった。
項羽は、明らかに優勢を過信し一瞬の油断が命取りになった。つまり、先発の利に甘えて、二の矢、三の矢を用意していなかったことが原因と思われる。
本日の朝読書で、作家の守屋洋訳著『人生を面白くする中国古典名言集』に、現代人へ向けたメッセージがありました。
(以下、転載)
「私が長い経験から学んだ教訓は、いかなる大企業といえども、五年間、何ら思いきった手を打たず、現状に満足し続けていれば、あっという間に傾いてしまう現実である。問題は業種にあるのではない」(略)
そうならないためには、先発の利に甘えることなく、二の矢、三の矢の開拓を怠ってはならない。
(以上、『人生を面白くする中国古典名言集』より)
歴史に学べとはよく言ったものです。
9月25日の「復興・うと軽トラ市」は4回目、11月に開催予定の「復興・宇土マリーナジュニアサッカー大会」は15回目、それぞれに工夫をして来たが、さらにアイデアを出して、賑わい創出を考えなければと思います。
うと軽トラ市では、初めて行う「震災復興チャリティーコンサート」に、多くの方にご参集いただけるように告知・広報に頑張ります。
宇土マリーナジュニアサッカー大会では、インターネットを主軸に、告知・広報を行い、さらには、試合の模様をネット配信することを初めて行います。大会2日目の11月13日には、昨年同様に宇土産業祭とコラボして、さらに人が集い楽しむ2日間にできれば準備いたします。
Posted by ノグチ(noguchi) at
10:39
│Comments(0)
<和して流せず>ジャーナリストで政治家「石橋湛山」の生き方に学ぶ
2016年09月01日
<和して流せず>ジャーナリストで政治家「石橋湛山」の生き方に学ぶ
おはようございます。昨日の東北・北海道の台風被害には、心痛の思いでたまりません。早い復旧を願っています。
昨夜・今朝と、宇土市を震源とする震度5、震度4の地震には、またか、もう余震は嫌だ! とつくづく思いを持ちました。まだまだ、”余震は続くぞ“、と天が伝えているのだろうな、と思いました。
さて今朝は、戦前戦後と日本の言論界をリードした石橋湛山についてコメントします。
自由主義、民主主義、国際協調主義を持論とする戦前はジャーナリスト(東洋新報)、戦後は政治家の石橋湛山という人物に以前から関心を持っていました。
本日のNHK-BSでの番組、英雄たちの選択「石橋湛山」について議論をする出演者の意見を聞き、久しぶりに“リーダーとは何か”を考える機会になりました。
石橋湛山は、戦後政治家に転身した。著名な言論人であっこともあり、72歳の時、首相を務めることになった。精力的に動き、その過密な活動が病を招き、2ヶ月で辞任した。
「東西一家和楽春」(立正大学の掛け軸)
石橋湛山は、首相退任後も世界平和(世界協調主義)のために活動し続けた。日中友好の糸口を開いた石橋湛山の後を引き継いだのが、田中角栄首相だった。
田中角栄首相は、中国に出発する前に、病床の石橋湛山を訪ねて「石橋先生、中国へ行ってきます」と挨拶をし、日中友好条約が結ばれた。
石橋湛山は、自由民主党の中で「和して流せず」(中庸)、周りと協調するけど流されない。人として目指す生き方ではないかと思います。
この『中庸』の目指す“和して流せず”の人物像はどんなものか?
ことばを説明した本に次の説明がありました。
(以下、抜粋)
つまり、一人ひとりが、まず個性に富んだ士であって、そのうえに成り立つ“和”であることが望ましい。
こういう社員を一人でも多く育て、彼らの能力を引き出し、それを組織力としてうまく結集していくことが、これからのリーダーの課題である。
(以上、守屋洋訳編『人生を面白くする中国古典名言集』より)
石橋湛山は、戦前の東洋新報時代のジャーナリストとしての生き方、戦後の政治家としての生き様、戦後日本の進む方向を戦中時期から考えていたのだと思います。
戦後の日本は、石橋湛山が提唱した人材を経済発展に集中し、日本は再生を果たした。「和して流せず」の組織とは、
・明確な目標を提示する
・率先垂範でことに当たる
・部下の意見に耳を傾ける
簡単なようでできないのが現実です。今日は、昭和の偉人の一人「石橋湛山」を取り上げた番組を見て、“和して流せず”の生き方について考えてみたいと思います。
おはようございます。昨日の東北・北海道の台風被害には、心痛の思いでたまりません。早い復旧を願っています。
昨夜・今朝と、宇土市を震源とする震度5、震度4の地震には、またか、もう余震は嫌だ! とつくづく思いを持ちました。まだまだ、”余震は続くぞ“、と天が伝えているのだろうな、と思いました。
さて今朝は、戦前戦後と日本の言論界をリードした石橋湛山についてコメントします。
自由主義、民主主義、国際協調主義を持論とする戦前はジャーナリスト(東洋新報)、戦後は政治家の石橋湛山という人物に以前から関心を持っていました。
本日のNHK-BSでの番組、英雄たちの選択「石橋湛山」について議論をする出演者の意見を聞き、久しぶりに“リーダーとは何か”を考える機会になりました。
石橋湛山は、戦後政治家に転身した。著名な言論人であっこともあり、72歳の時、首相を務めることになった。精力的に動き、その過密な活動が病を招き、2ヶ月で辞任した。
「東西一家和楽春」(立正大学の掛け軸)
石橋湛山は、首相退任後も世界平和(世界協調主義)のために活動し続けた。日中友好の糸口を開いた石橋湛山の後を引き継いだのが、田中角栄首相だった。
田中角栄首相は、中国に出発する前に、病床の石橋湛山を訪ねて「石橋先生、中国へ行ってきます」と挨拶をし、日中友好条約が結ばれた。
石橋湛山は、自由民主党の中で「和して流せず」(中庸)、周りと協調するけど流されない。人として目指す生き方ではないかと思います。
この『中庸』の目指す“和して流せず”の人物像はどんなものか?
ことばを説明した本に次の説明がありました。
(以下、抜粋)
つまり、一人ひとりが、まず個性に富んだ士であって、そのうえに成り立つ“和”であることが望ましい。
こういう社員を一人でも多く育て、彼らの能力を引き出し、それを組織力としてうまく結集していくことが、これからのリーダーの課題である。
(以上、守屋洋訳編『人生を面白くする中国古典名言集』より)
石橋湛山は、戦前の東洋新報時代のジャーナリストとしての生き方、戦後の政治家としての生き様、戦後日本の進む方向を戦中時期から考えていたのだと思います。
戦後の日本は、石橋湛山が提唱した人材を経済発展に集中し、日本は再生を果たした。「和して流せず」の組織とは、
・明確な目標を提示する
・率先垂範でことに当たる
・部下の意見に耳を傾ける
簡単なようでできないのが現実です。今日は、昭和の偉人の一人「石橋湛山」を取り上げた番組を見て、“和して流せず”の生き方について考えてみたいと思います。
Posted by ノグチ(noguchi) at
09:23
│Comments(0)



