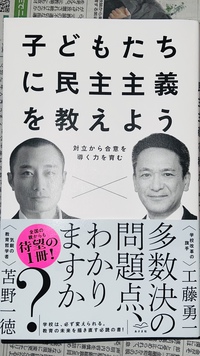<公立高校定員割れ>県庁所在地の県立の進学校のクラスを減らす要求が出ないのが不思議でならない。
2025年05月18日

人口減少する県も含む地方自治体の現状があるのに、県庁所在地の県立の進学校のクラスを減らす要求が出ないのが不思議でならない。
今年の宇土高校の入学式前に、定員割れの
話から、そんな話となった。
51年前、私も宇土高校の門をくぐり入学しました。(笑)変わらない母校の姿。
2025年04月08日


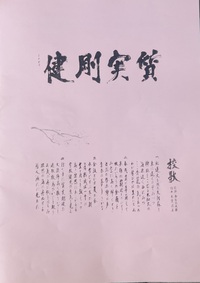
51年前、私も宇土高校の門をくぐり入学しました。(笑)
本日51年前、私も宇土高校の門をくぐり入学しました。(笑)
本日は、県立宇土中学校・高等学校の入学に参列しました。宇土市長とともに宇土市議会からもたくさん参列し、入学をお祝いしました。
会場に入る前に、グランドを見ると高校のサッカー部が練習をしていました。私たちの時代からある大きな木と傾いているコンクリートのベンチもそのままでした。懐かしいですね。
県立中学校ができて15年が過ぎ、中高一貫校ですが、中学校卒業生が高校を、熊本市内の県立高校や私立高校の進学校を受験するようになり、今年も定員割れの高校の生徒数でした。今後の課題として、入学式前の意見交換で、話題となりました。は、県立宇土中学校・高等学校の入学に参列しました。宇土市長とともに宇土市議会からもたくさん参列し、入学をお祝いしました。
会場に入る前に、グランドを見ると高校のサッカー部が練習をしていました。私たちの時代からある大きな木と傾いているコンクリートのベンチもそのままでした。懐かしいですね。
県立中学校ができて15年が過ぎ、中高一貫校ですが、中学校卒業生が高校を、熊本市内の県立高校や私立高校の進学校を受験するようになり、今年も定員割れの高校の生徒数でした。今後の課題として、入学式前の意見交換で、話題となりました。


東日本大震災から14年、その被害のすごさを改めて確認します。
2025年03月11日

東日本大震災から14年、その被害のすごさを改めて確認します。
先月に訪れた、日本都市センター会館内に在る「防災専門図書館」には、日本の歴史上に起こった大災害、特に地震にまつわる被害が詳しく整理展示してありました。
東日本大震災を起こしたマグニチュード9.0のプレート型巨大地震は、大きな津波が何度も海岸を襲いました。あれから14年、改めて地震の怖さと、備え、避難を考える1日にしなければと思います。
本日は、議会の総務市民常任委員会が開催されます。特に防災を担当する部署が含まれる委員会なので、国の目指す防災のあり方が変わってくる中、将来を見据えた議論ができると良いなと考えています。
最後に、東日本大震災、中越地震、北海道地震、熊本地震、能登半島地震等、自然災害によりお亡くなりになった方々のご冥福をお祈りいたします。




<豊かさの条件>いつの時代にも人間社会は共同体的な部分を残さなければ、社会基盤の安定を欠く。
2025年01月06日


<豊かさの条件>いつの時代にも人間社会は共同体的な部分を残さなければ、社会基盤の安定を欠く。また個人が共同体の中に埋没してしまうと、社会の活力を失う。〜暉峻淑子著『豊かさの条件』〜
年始から矛盾する提言の言葉を紹介します。
(長い論文?です。お時間ある時にお読みください。)
本日は、私が住む集落で毎年に新年に開催される住民会議「初寄り合い」に、市議会議員として、新年の挨拶をして回る大切な日でした。4ヶ所の自治区の寄り合いの会場に出向き、活動報告と今年の方針をお話しさせていただきました。終わって15時過ぎ帰宅して、未明のウォーキングもあり、疲れて少し仮眠を取りました。この正月行事も今年で15年目、なかなか緊張する一日です。
さて冒頭の言葉からも、田舎の集落運営と個人生活の充実を、本日の挨拶回りと寄り合いでのみなさんの意見を拝聴して、いつも感じるのですが、いにしえ(古)の時代から営々と続けられてきたのだろうと、本日も振り返りました。
集落運営は、共同体の活動。
日々の暮らしを作る活動は、個人の生活。
娘が年末年始に帰郷していて、本日の寄り合いを回る活動を見て、話をする中で感じたのが、地域を支えるには古くから共同体活動で支えられていることを、都市生活をする若者たちは知らない人が多いように感じました。
例を上げると、昨年の地域課題一つ、防犯対策の要望で、
・街灯の増設
・防犯カメラの設置
がありました。地方は、人口減少から人口密度が減り、広い地域の安心安全の対策が不充分になっています。
しかしその対策で、街灯の設置には、市(国・県)の補助金があっても、日常の電気代は地域(自治区)で負担することになります。
このことを、どれだけの住民が知っているのか?と思います。
過疎地ほど、住民が共同体(集落運営)に拠出する費用(個人負担)が膨らむ現状があります。
私は若い頃、日本政府は人を都市に集めのは、地方に交付する税金を減らすためにやっているのでは、と思ったことがありますした。そんなことから、
冒頭の言葉を紹介した意味は、以下のエピソードからです。
社会学者の暉峻淑子(てるおか いつこ)著『豊かの条件』の最後の方に、
19世紀のロシアの政治思想家・クロポトキン(注1)著『相互扶助論』の序論で、ある逸話(エピソード)が紹介されていました。
(以下、『豊かの条件』より)
1827年のある日、ゲーテを秘書のエッカーマンがたずねて、彼が直接に経験したある助け合いの実例を話したところ、ゲーテはその話に感激して「もし縁もゆかりもない他人をこうして養うということが、自然のどこにでも行われていて、その一般的法則だということにならば、今まで解くことのできなかった多くの謎はたちどころに解けてしまう」と言い、翌日もそのことを話題にして、その問題についての特別な研究をエッカーマンに熱心にすすめた、というのである。
クロポトキンは、労働者達の住む長屋のいたるところで、もし産婦がお産をすれば近所の女達が手伝いにきて、生まれた子どもの世話や産婦が起きられるようになるまでの家事や、そのために入用なものを持ち寄って助け合っている事実を知っていた。親が死んだあとの孤児をだれかが必ずひきとって育てていることも、そしてそれがごくつうのことで、珍しいことでもなんでもないことを知っていた。
(以上、本より)
引用文が、長くなりましたが、日本もかつては"村社会"である共同体の暮らしが、長く続いていました。
明治からの産業革命、戦争の時代、戦後の高度経済成長、バブル経済時代、デフレの失われた日本、そして令和の時代になりました。
本日の古(いにしえ)から続いている、新年の初寄り合いの行事から、
共同体の運営と、個人生活の成長からも、
明治に導入された西洋の"資本主義"について、クロポトキンの理論から、振り返りました。
暉峻淑子さんの『豊かさの条件』の一節にありました。
(以下、本より)
だが、資本主義は共同体を徹底的に解体し、社会をバラバラの私的所有に分解してしまう。そうすれば、社会的な生産力は、飛躍的に発展するが、やがてその生産力は競争の中で敵対的にぶつかりあい、資本相互の間で弱肉強食が進む。資本と労働者の間にも衝突が起こり、不況と失業による社会的な危機がおとすれる。
(以上、『豊かさの条件』より)
この引用文の続きが、冒頭の言葉です。
>は共同体的な部分を残さなければ、社会基盤の安定を欠く。
>個人が共同体の中に埋没してしまう
過疎化する地方衰退の原因に、資本主義化した日本社会の変化と都市集中があるのだろうとは思っていましたが、暉峻淑子さん本を読み、益々の確信を持ちました。
これからの政府に望むのは、地方で今も維持されている共同体活動の支援を、地方創生のメニューに加えるべきではと思いました。
熊本選出の衆議院議員・金子恭之氏が常々に語られている、「地方の繁栄なくして、国の繁栄なし」の言葉を、思い出しました。
人口減少地域を支えることが、次なる日本の繁栄を生み出すようになってほしいですね。
長々と書きました。最後までお読みいただき感謝いたします。
*注1:ピョートル・アレクセイヴィチ・クロポトキン(1842年12月9日〜1921年2月8日)。ロシアの革命家、政治思想家であり、地理学者、社会学者、生物学者。
#地方の繁栄なくして国の繁栄なし
#クロポトキン『相互扶助論』
#地方創生
#日本の地方
#人口減少
#少子高齢化
#資本主義
#共同体
#暉峻淑子
#豊かさの条件
#相互扶助論
久しぶりに横井小楠記念館「四時軒」に寄りました。
2024年12月26日


年末の挨拶回りで、熊本市東部まで来たので、久しぶりに横井小楠記念館「四時軒」に寄りました。
昨年リニューアルして以来、展示は見てなかったので、2階の特別展示をゆっくりと見学しました。熱心に資料を確認されている来館者が居られました。

「国是七条草案」は、以前にも展示してあったのですが、改めて読み直しました。

ちょっと粋な文を見つけました。現代の市民の政治離れにも似た減少が、当時の肥後熊本にもあったことを知る漁師の話です。
(以下、横井小楠の感想の抜粋)
地域を治る長官が新しく代わって来たというが、私はその人の名前すら知らない。私はただ自分の生活をしているだけで政治には何の関心がない。
〜漁師のおやじの言葉 横(井平四郎時)在〜
(以上、写真の話の現代語の解説より)
横井小楠の隠居生活から見えてくる当時の庶民の生活が伺えます。幕末維新の動乱の時期以前は、変わらない平和な時代を、庶民は楽しんでいたのだと思いました。


坂本龍馬と対談した座敷

高宗昭敏先生の活動を振り返る。熊本地球市民塾から「横井小楠と維新群像」建立まで
2024年07月26日
「こよなく酒を愛し、この熊本から日本の未来を、熱っぽく語り合った小楠・海舟・龍馬」
〜高宗昭敏先生の活動を振り返る。熊本地球市民塾から「横井小楠と維新群像」建立まで〜
私が、熊本地球市民塾に参加したのは32年前、その時に、高宗昭敏先生との出会いでもありました。
高宗先生は、大学教授でありながら、社会的・政治的な目的を持ち、セミナー、講演会、フォーラム、歴史検証、偉人顕彰の様々な活動を主催されました。私は、その事務的な補佐をさせていただきながら、社会活動の経験を積ませてもらっていたように思います。
地球市民ウォーラムは、3日連続のセミナー、講演、パネルディスカッション開催されました。
九州初の「太陽光発電推進九州ブロック研究集会」には、予想を遥かに超える417人が集まり、来賓で出席された福島譲二熊本県知事も驚かれました。
そして横井小楠顕彰活動は、生誕190年記念事業から始まり、生誕195年では、催し・イベント・講演会、さらには5体の銅像建立まで発展していきます。
銅像建立の5年後に開催された、銅像前での花見の宴に参加して思ったのは、高宗昭敏先生自身が、現代の坂本龍馬のように思えたことです。経済学の教授でありながら、社会変化の気づきを、周りに与える提案を常に続けておられた気がします。
坂本龍馬の活躍した時期は、約5年間と言われています。高宗昭敏先生の60代から始まった、熊本県だけでなく、東京ともつながり、再生可能エネルギー政策への提言、熊本の幕末・明治維新で活躍した偉人の再評価を懸命に続けられました。
特に、「太陽光発電推進九州ブロック研究集会」後に始まった、横井小楠生誕190年(1994年)〜生誕195年(1999年)までの約6年間の活動は、横で見ていて飛び回る忙しさがあった。すごい方だったと、今になりつくづく感じます。
高宗先生が、
「これからは、頭の強い人間にならないといけない」
と、よく話されていました。私が、
「先生、頭の強い人間とは、どんな人ですか?」
と尋ねたことがあります。すると、
「頭の良い人間は、成績優秀で頭の回転が速いのだろうが、"頭の強い人間"とは、何か事をやろうとした時、完了させるまで、終わるまで、諦めず考え続けられる頭を持つ人のことだ」
と話されました。ちょうど銅像建立へ向けた、人・モノ・金を巻き込む最中で、5年間の到達目標を持ち、多様なイベントと銅像建立(1億円)という事業をやり終えるために、思考を最大限に駆使されやり遂げられたなぁ、と振り返りました。
>これからは、頭の強い人間にならないといけない
ここ3日、季刊誌「KUMAMOTO」に、熊本地球市民塾からの活動をまとめた文を投稿するので、32年前からの出来事を思い起こしていました。
頭の強い人間とは?から、目的達成まで諦めない意志の強さを教えられた経験でした。
高宗昭敏先生は、新型コロナウィルス感染拡大前の年末、12月28日にお亡くなりになりました。年の瀬の押し迫った時期でしたから、葬儀はご家族だけで執り行い、少し経ってから「偲ぶ会」を計画されましたが、コロナ感染拡大で、人の集まることが制限されたために、出来ず仕舞いになりました。私自身も、同日に叔母が亡くなり、高宗先生の葬儀も知らず、ご家族からご連絡を受けて、仏壇にお参りしたのは年が明けしばらくしてからでした。
社会活動の先生として、長く指導を受けた方でした。心よりご冥福をお祈りいたします。合掌。






〜高宗昭敏先生の活動を振り返る。熊本地球市民塾から「横井小楠と維新群像」建立まで〜
私が、熊本地球市民塾に参加したのは32年前、その時に、高宗昭敏先生との出会いでもありました。
高宗先生は、大学教授でありながら、社会的・政治的な目的を持ち、セミナー、講演会、フォーラム、歴史検証、偉人顕彰の様々な活動を主催されました。私は、その事務的な補佐をさせていただきながら、社会活動の経験を積ませてもらっていたように思います。
地球市民ウォーラムは、3日連続のセミナー、講演、パネルディスカッション開催されました。
九州初の「太陽光発電推進九州ブロック研究集会」には、予想を遥かに超える417人が集まり、来賓で出席された福島譲二熊本県知事も驚かれました。
そして横井小楠顕彰活動は、生誕190年記念事業から始まり、生誕195年では、催し・イベント・講演会、さらには5体の銅像建立まで発展していきます。
銅像建立の5年後に開催された、銅像前での花見の宴に参加して思ったのは、高宗昭敏先生自身が、現代の坂本龍馬のように思えたことです。経済学の教授でありながら、社会変化の気づきを、周りに与える提案を常に続けておられた気がします。
坂本龍馬の活躍した時期は、約5年間と言われています。高宗昭敏先生の60代から始まった、熊本県だけでなく、東京ともつながり、再生可能エネルギー政策への提言、熊本の幕末・明治維新で活躍した偉人の再評価を懸命に続けられました。
特に、「太陽光発電推進九州ブロック研究集会」後に始まった、横井小楠生誕190年(1994年)〜生誕195年(1999年)までの約6年間の活動は、横で見ていて飛び回る忙しさがあった。すごい方だったと、今になりつくづく感じます。
高宗先生が、
「これからは、頭の強い人間にならないといけない」
と、よく話されていました。私が、
「先生、頭の強い人間とは、どんな人ですか?」
と尋ねたことがあります。すると、
「頭の良い人間は、成績優秀で頭の回転が速いのだろうが、"頭の強い人間"とは、何か事をやろうとした時、完了させるまで、終わるまで、諦めず考え続けられる頭を持つ人のことだ」
と話されました。ちょうど銅像建立へ向けた、人・モノ・金を巻き込む最中で、5年間の到達目標を持ち、多様なイベントと銅像建立(1億円)という事業をやり終えるために、思考を最大限に駆使されやり遂げられたなぁ、と振り返りました。
>これからは、頭の強い人間にならないといけない
ここ3日、季刊誌「KUMAMOTO」に、熊本地球市民塾からの活動をまとめた文を投稿するので、32年前からの出来事を思い起こしていました。
頭の強い人間とは?から、目的達成まで諦めない意志の強さを教えられた経験でした。
高宗昭敏先生は、新型コロナウィルス感染拡大前の年末、12月28日にお亡くなりになりました。年の瀬の押し迫った時期でしたから、葬儀はご家族だけで執り行い、少し経ってから「偲ぶ会」を計画されましたが、コロナ感染拡大で、人の集まることが制限されたために、出来ず仕舞いになりました。私自身も、同日に叔母が亡くなり、高宗先生の葬儀も知らず、ご家族からご連絡を受けて、仏壇にお参りしたのは年が明けしばらくしてからでした。
社会活動の先生として、長く指導を受けた方でした。心よりご冥福をお祈りいたします。合掌。






熊日宇土市局長の古東竜之介さんの選挙についての記事に、23歳の記者として、若者としての意見。
2024年02月10日

熊本日日新聞社・宇土市局長の古東竜之介さんの選挙についての記事に、23歳の記者として、若者としての意見に、いい内容だなぁと思いました。
戦禍のイスラエルの投票率は70%を超える。
台湾総統選挙は71.86%。
日本の衆議院選挙は55.93%。
〃 参議院選挙は52.05%。
来月に控える県知事選挙については、前回の投票率は45.03%だったことを指摘している。
>どんな熊本を望むのか、自ら学び、考える良い機会にしたい。私たちの手には、国や自治体の在り方をきめる一票がある。
関心のあるかたは、『取材前線』の記事に目を通してください。
<能登半島地震>熊本の災害ボランティア団体「一般社団法人熊本支援チーム」
2024年01月11日
<能登半島地震>熊本の災害ボランティア団体「一般社団法人熊本支援チーム」のFacebookページの掲載をシェアしました。
一昨日までの活動報告がアップされていました。寒い中、できる範囲ですが、若い人たちが頑張っています。応援をよろしくお願いいたします。
・熊本支援チームの現地活動拠点
送り先
石川県七尾市大津町東小谷内11の乙
佐川急便能登営業所止
宛名
株式会社創生ななお内
熊本支援チーム
電話
08017833580
*熊本支援チーム(旧東日本大震災・熊本支援チーム)は、13年前に発生した東日本大震災の被災地支援活動をしたメンバーが、熊本地震ときも、熊本豪雨でも活動しました。大きな自然災害が発生したとき、災害ボランティア活動をする熊本のネットワーク(一般社団法人)です。
*一般社団法人熊本支援チームのホームページ
https://kumamoto-team.net/
(以下、Facebookページ「熊本支援チーム」より転載)
【能登町支援状況報告】
熊本支援チームは、能登町からの要請により、炊き出し及び支援物資をご提供させていただきました。
能登町と関係のある島田由香さんのご助力もあり、今回の支援へとつながりました。
1月4日
能登町能都中学校に宮城県東松島市の自治会及び地域の方々から預かった物資をご提供すると共に、300人の炊き出しを当日夕方、翌朝実施。
1月5日
能登町大森町長へ東松島市渥美市長からの親書をお渡しすると共に毛布100枚をお届けした。
その後、350人分の炊き出しを実施。
能登町では、未だ断水中。
地域の要望を聞きながら、能登役場と連携をとりながら、しっかりと継続して支援にあたっていきます
1月7日
能登町小木中学校にて、再度要望により、炊き出しを実施致しました。
被災地の方々は、まだ支援が行き届いていない場所も現段階では存在しています。
しっかりと地域行政との共有を行いながら、熊本支援チーム一丸となって支援を続けて参ります。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。
#災害支援 #能登半島地震 #復旧 #物資支援 #熊本支援チーム #現状 #支援金 #寄付 #寄り添い #石川県 #七尾市 #感謝 #笑顔 #拡散希望
活動報告や最新の動きはInstagramでチェックしてください!
https://www.instagram.com/kumamoto_team?igsh=eGgzMnVkdjFjancy&utm_source=qr
=====
◆活動支援金の寄付
~熊本支援チーム「能登半島地震」への支援寄付(1回100円から簡単クレカ決済!)
https://square.link/u/rLmu2yl1
◆熊本支援チームサポーターズ
~サブスクで支える熊本支援チームの災害支援体制への寄付(毎月500円から)
https://community.camp-fire.jp/projects/view/325816
======


一昨日までの活動報告がアップされていました。寒い中、できる範囲ですが、若い人たちが頑張っています。応援をよろしくお願いいたします。
・熊本支援チームの現地活動拠点
送り先
石川県七尾市大津町東小谷内11の乙
佐川急便能登営業所止
宛名
株式会社創生ななお内
熊本支援チーム
電話
08017833580
*熊本支援チーム(旧東日本大震災・熊本支援チーム)は、13年前に発生した東日本大震災の被災地支援活動をしたメンバーが、熊本地震ときも、熊本豪雨でも活動しました。大きな自然災害が発生したとき、災害ボランティア活動をする熊本のネットワーク(一般社団法人)です。
*一般社団法人熊本支援チームのホームページ
https://kumamoto-team.net/
(以下、Facebookページ「熊本支援チーム」より転載)
【能登町支援状況報告】
熊本支援チームは、能登町からの要請により、炊き出し及び支援物資をご提供させていただきました。
能登町と関係のある島田由香さんのご助力もあり、今回の支援へとつながりました。
1月4日
能登町能都中学校に宮城県東松島市の自治会及び地域の方々から預かった物資をご提供すると共に、300人の炊き出しを当日夕方、翌朝実施。
1月5日
能登町大森町長へ東松島市渥美市長からの親書をお渡しすると共に毛布100枚をお届けした。
その後、350人分の炊き出しを実施。
能登町では、未だ断水中。
地域の要望を聞きながら、能登役場と連携をとりながら、しっかりと継続して支援にあたっていきます
1月7日
能登町小木中学校にて、再度要望により、炊き出しを実施致しました。
被災地の方々は、まだ支援が行き届いていない場所も現段階では存在しています。
しっかりと地域行政との共有を行いながら、熊本支援チーム一丸となって支援を続けて参ります。
引き続き、よろしくお願い申し上げます。
#災害支援 #能登半島地震 #復旧 #物資支援 #熊本支援チーム #現状 #支援金 #寄付 #寄り添い #石川県 #七尾市 #感謝 #笑顔 #拡散希望
活動報告や最新の動きはInstagramでチェックしてください!
https://www.instagram.com/kumamoto_team?igsh=eGgzMnVkdjFjancy&utm_source=qr
=====
◆活動支援金の寄付
~熊本支援チーム「能登半島地震」への支援寄付(1回100円から簡単クレカ決済!)
https://square.link/u/rLmu2yl1
◆熊本支援チームサポーターズ
~サブスクで支える熊本支援チームの災害支援体制への寄付(毎月500円から)
https://community.camp-fire.jp/projects/view/325816
======


<熊本城再建>宇土櫓の解体修理に関心を持っています。現場見学会に参加したい。
2024年01月11日

<熊本城再建>宇土櫓の解体修理に関心を持っています。本日の熊日『一筆』で、熊本城総合事務所の津曲俊博氏の記事に、「途中の段階を見ていただくことも考えています」とあり、期待するところです。宇土櫓は、天守閣のコンクリート構造でなく、往時のままの木造5階建構造で、国内で同規模の天守閣があるほど大きな櫓と思っています。もし、現場見学会が開催されれば、ぜひ行きたいと思います。
八代亜紀さんがお亡くなりになりました。安らかにお休みください。ご冥福をお祈りいたします。
2024年01月10日

八代亜紀さんがお亡くなりになりました。大ショックです。今の時代、73歳の死は残念でなりません。機会があれば、歌謡ショーを見たいと思っていたので、悔やまれますが、熊本のため、さまざまに活動をしていただきました。特に熊本地震では、良く顔を見ていました。安らかにお休みください。ご冥福をお祈りいたします。
<異業種交流会「秋の会」>「世界平和へ旅しよう。女性の視点で世界を見聞し伝えるセミナー
2023年11月07日
<異業種交流会「秋の会」>「世界平和へ旅しよう。女性の視点で世界を見聞し伝えるセミナー。講師は、高木あゆみさん(一般社団法人teemはちどり代表〜
高木あゆみさんは、5年前、5歳の子どもを連れて、アフガン難民について調査のために、ヨーロッパに渡ります。特に、ドイツとスウェーデンでは、子どもの難民と面談し、戦火から逃れた話し、難民テントの生活、さらにドイツの難民への対応、またスウェーデンの難民支援のこと、等々、てとも詳しく聞くことができました。
5歳の子どもを連れて14ヵ国、110日間の旅もすごいのですが、現在活動されている、「海外を知ろう、難民に関心を持って」の地道な活動には、とても興味が湧きました。
記
日時 11月24日19時〜
会場 熊本市国際交流会館第一会議室
定員 20名
参加費 5000円(セミナー+懇親会)
主催は、環境共生施設研究所
問合せは、09036667682、野口修一まで。
Eメール noguchi.shuichiutokumamoto@gmailcom
ぜひ、興味ある方は、日程に加えていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
#異業種交流会
#異業種交流会四季の会
#四季の会
#一般社団法人teemはちどり
#カフェハチドリ
#国際貢献
#難民支援
#多様性社会
高木あゆみさんは、5年前、5歳の子どもを連れて、アフガン難民について調査のために、ヨーロッパに渡ります。特に、ドイツとスウェーデンでは、子どもの難民と面談し、戦火から逃れた話し、難民テントの生活、さらにドイツの難民への対応、またスウェーデンの難民支援のこと、等々、てとも詳しく聞くことができました。
5歳の子どもを連れて14ヵ国、110日間の旅もすごいのですが、現在活動されている、「海外を知ろう、難民に関心を持って」の地道な活動には、とても興味が湧きました。
記
日時 11月24日19時〜
会場 熊本市国際交流会館第一会議室
定員 20名
参加費 5000円(セミナー+懇親会)
主催は、環境共生施設研究所
問合せは、09036667682、野口修一まで。
Eメール noguchi.shuichiutokumamoto@gmailcom
ぜひ、興味ある方は、日程に加えていただければありがたいです。よろしくお願いいたします。
#異業種交流会
#異業種交流会四季の会
#四季の会
#一般社団法人teemはちどり
#カフェハチドリ
#国際貢献
#難民支援
#多様性社会
いろんなお話を聴かせていただいた中村青史先生のご逝去を知り、生前の姿を思い出します。
2023年08月23日

いろんなお話を聴かせていただいた中村青史先生のご逝去を知り、生前の姿を思い出します。
私の中村先生との縁は、私がお手伝いしていた九州東海大学の故高宗昭敏教授と中村先生との交流やイベント等でお会いしてきました。高宗先生が病を患い、さらにコロナ禍で、歴史顕彰活動が出来ない状況から、お会いすることが無くなりました。
徳富蘇峰、徳富蘆花に関する研究会で、お話をされる和やかで優しい語り口を懐かしく思い出します。
ここ数日読む、『人間の建設』に、徳富蘆花のことが記されていました。ロシアまで出向き、トルストイに面会した話です。
批評家の小林秀雄と哲学者の岡潔との対談録『人間の建設』から、
岡)トルストイは人としてたいへん偉いですか。
小林)偉いです。
岡)徳富蘆花は会って感心して帰ってきましたね。
小林)私はモスクワへ行って、トルストイの家を見ましたが、感動しました。『アンナ・カレーニナ』を書いた部屋です。岡さんは「コサック」という作品をお読みですか。
岡)ええ、読みました。
小林)あれは青春時代の作ですが、トルストイの方向はあれでもう決まってしまっているのです。(中略)
(以上、『人間の建設』より)
作家や研究者は、作家本人に会い、またかつて住んでいた歴史の現場に出向き、そこで感じたことを糧に、いろんな話を組み立てているのか、と知らされます。
>徳富蘆花は(トルストイに)会って感心して帰ってきましたね。
ジャーナリストである徳富蘆花のとてもリアルな話しですね。
中村青史先生も、徳富蘇峰・蘆花が生まれ育った水俣でのことやジャーナリストとして活躍したこと、熊本での歴史的な役割等にも深く調べて語られていました。ほんと私がまだ30代後半に出会うのですが、何度もお会いし、お話をしたことを思い出します。
しかし、徳富蘆花の言動に、小林秀雄や岡潔も関心を持っていたことを知り、中村先生が、熊本の偉人顕彰をやられたことをまた学びたくなりました。
コロナ禍で一時休止した徳富蘇峰・蘆花の研究、顕彰が再開し、これからも後世に継続されていくことを願いつつ、中村青史先生のご冥福をお祈りいたします。
甲佐町・美里町の図書館スタッフの知恵にエールです!"本好きの市民を中心に据えた図書館づくり"
2023年06月09日

甲佐町・美里町の図書館スタッフの知恵にエールです!
人が多いことばかりが強調される公共施設利用の話題ですが、施設の意味を理解している図書館スタッフは素晴らしい!と思う記事を読み嬉しくなりました。
図書館は、何のためにあるのか分かっているのか、です。
本好きの人は、静かな場所で、好きなスタイルで本を読みたい。私は、たくさんの図書館を見てきました。大きな県立図書館や小さな民間の図書館、それぞれに特徴を出しいます。ならば、市町村の図書館は、何の役割りがあるのか、常に考える中で、"本好きの市民を中心に据えた図書館づくり"だと思います。
1カ月に何万人来た、開館以来何十万人来たの話題を新聞で見るに、"本好きの市民を置き去りにしている"と悲しくなります。
図書館には、蔵書の多さも必要です。町村の図書館は予算も少ないので、そうそう毎年本を増やせません。町連携の図書館ネットワークの発想は素晴らしいです。近々、甲佐町図書館と美里町図書館を訪問したいと思いました。
1年ぶりの再会>災害ボランティア団体「一般社団法人熊本支援チーム」の理事会が1年ぶりにあり、久しぶりに仲間に会います。
2023年05月10日
<1年ぶりの再会>本日の午後は、災害ボランティア団体「一般社団法人熊本支援チーム」の理事会が1年ぶりにあり、久しぶりに仲間に会います。コロナ禍で、なかなか会いづらい時間が続きましたが、これからは、コミュニケーションも上手くいくのでは、と期待しています。
熊本支援チームは、大きな災害の時に、"この指とまれ"と集まる。きっかけは12年前の東日本大震災後に活動した熊本県内の若者が中心の災害ボランティア団体で、これまで熊本地震、熊本豪雨災害の時に活動しました。
平時(大災害のない時)は、それぞれの仕事を懸命にやり社会貢献を果たしていく。有事(地域を一変する大災害)には、呼びかけることなく駆けつけて活動する。震災や豪雨のような自然災害は起こってほしくないが、いざ発生したら"この指とまれ"と直ぐに活動が始まる。
本日は、平時の集まりなので、日頃の活動の情報交換が主ですが、とても楽しみな仲間たちとの再会てす。
#熊本支援チーム
#東日本大震災熊本支援チーム
#災害ボランティア団体
#有事と平時
#東日本大震災
#熊本地震
#熊本豪雨
#一般社団法人熊本支援チーム
熊本支援チームは、大きな災害の時に、"この指とまれ"と集まる。きっかけは12年前の東日本大震災後に活動した熊本県内の若者が中心の災害ボランティア団体で、これまで熊本地震、熊本豪雨災害の時に活動しました。
平時(大災害のない時)は、それぞれの仕事を懸命にやり社会貢献を果たしていく。有事(地域を一変する大災害)には、呼びかけることなく駆けつけて活動する。震災や豪雨のような自然災害は起こってほしくないが、いざ発生したら"この指とまれ"と直ぐに活動が始まる。
本日は、平時の集まりなので、日頃の活動の情報交換が主ですが、とても楽しみな仲間たちとの再会てす。
#熊本支援チーム
#東日本大震災熊本支援チーム
#災害ボランティア団体
#有事と平時
#東日本大震災
#熊本地震
#熊本豪雨
#一般社団法人熊本支援チーム
<郡築争議100年>田中正造研究会(熊本市)の塾生仲間の内田敬介氏の素晴らしい提言に読み入りました。
2023年04月24日

<郡築争議100年>田中正造研究会(熊本市)の塾生仲間の内田敬介氏の素晴らしい提言に読み入りました。まさに日本の農業は正念場、世論も含め真剣な議論と政策実現の時と思います。
<新聞購読が減少続く?>市民投稿『読者ひろば』の何処にあるのか?・・・あれ!、ここか。
2023年04月22日
<新聞購読が減少続く・・10年後は?>市民投稿『読者ひろば』の何処にあるのか?・・・あれ!、ここか。
投稿者は2人だけ?
えらく少ないなから、ふと思い、最近の新聞購読者の減少を危惧していたので、ネットで、「新聞購読数の減少?」のキーワードで検索したら、なんと
全国で、昨年190万部近く新聞購読数が減少していた。
さらに驚くべきは、熊日新聞の購読数は23万部台まで下がっていました。以前は、多い時は40万部を超えていたように記憶していますので、半分近くまで減っていました。
組織も変化があり、前宇土支局長の記者は事業部へ移り、宇土支局は無くなり、熊本県央を管轄する宇城総局の中に、宇土支局長ポストを設けて活動が、今年から始まった。
最近、テレビを持たない若者たちが増えていると聞きますが、テレビを生み出した母体の新聞本体が、さらに危うくなっています。このまま190〜200万部づつ減り続くと、10年もすれば、新聞という仕事が無くなる?ような意見もあります。
私は、ある意味新聞を活用して来た世代なので、新聞の斜陽化はとても悲しくてなりません。活字世代、特に地方紙の存続を願っています。


投稿者は2人だけ?
えらく少ないなから、ふと思い、最近の新聞購読者の減少を危惧していたので、ネットで、「新聞購読数の減少?」のキーワードで検索したら、なんと
全国で、昨年190万部近く新聞購読数が減少していた。
さらに驚くべきは、熊日新聞の購読数は23万部台まで下がっていました。以前は、多い時は40万部を超えていたように記憶していますので、半分近くまで減っていました。
組織も変化があり、前宇土支局長の記者は事業部へ移り、宇土支局は無くなり、熊本県央を管轄する宇城総局の中に、宇土支局長ポストを設けて活動が、今年から始まった。
最近、テレビを持たない若者たちが増えていると聞きますが、テレビを生み出した母体の新聞本体が、さらに危うくなっています。このまま190〜200万部づつ減り続くと、10年もすれば、新聞という仕事が無くなる?ような意見もあります。
私は、ある意味新聞を活用して来た世代なので、新聞の斜陽化はとても悲しくてなりません。活字世代、特に地方紙の存続を願っています。


あと23日となりました。手づくり作家作品展示交流会「第4回オリジナルinうと」の開催が近づきました。
2023年03月16日

あと23日となりました。手づくり作家作品展示交流会「第4回オリジナルinうと」の開催が近づきました。
出展者も15人が決まり、チラシもやっと届きました。3年休みましたから、4年ぶりの開催です。ロボットプログラミング教室のチラシも来週届きます。学童クラブに、案内をを出したいと考えています。
嘉島町在住の皆さんは、ぜひぜひ穴井さんに投票をお願い致します。頑張れ、穴井さん!
2023年01月31日


本日告示の嘉島町議会議員選挙に、30年来家族ぐるみのお付き合いの穴井智子さんが出馬されました。嘉島町在住の皆さんは、ぜひぜひ穴井さんに投票をお願い致します。頑張れ、穴井さん!
本日は臨時議会でした。子育て支援の事業を実施するための予算審議でした。海苔漁場被害支援について要望。
2023年01月27日
本日は、今年最初の臨時議会が開催されました。国県のコロナ対策と子育て支援の事業を実施するための予算審議でした。18歳以下の1人1万円の支援、新入学への生活支援等々の議決でした。もちろん賛成多数の議決で、私も賛成しました。
また、1月24・25日の寒波による海苔養殖の漁場が、冬とは思えない台風並みの強風で大荒れとなり、手のつけられないような被害を受けました。これは、行政も支援しなければと、宇土市西部の網津・網田地区の「網津網田地区活性化議員連盟」で、海苔漁場被害支援の提言(要望書)を、臨時議会後に市長へ提出しました。
提言に対して、意見交換をする中で"即対応が大事"となり、本日夕方には支援内容を発表することになりました。


また、1月24・25日の寒波による海苔養殖の漁場が、冬とは思えない台風並みの強風で大荒れとなり、手のつけられないような被害を受けました。これは、行政も支援しなければと、宇土市西部の網津・網田地区の「網津網田地区活性化議員連盟」で、海苔漁場被害支援の提言(要望書)を、臨時議会後に市長へ提出しました。
提言に対して、意見交換をする中で"即対応が大事"となり、本日夕方には支援内容を発表することになりました。


<学校運営、教室運営を民主主義の学びの場に>優秀な指導者?の恐怖支配、体罰暴言、
2022年12月18日
<学校運営、教室運営を民主主義の学びの場に>優秀な指導者?の恐怖支配、体罰暴言、元教師「俺も若かったけん、本当に悪かった」・・・
最近、学校内ルール「校則」の見直し論が始まっているが、なかなか進展はないように見えます。
今日の熊日一面に「恐怖支配」で、子どもを指導した元教師のことが取り上げられていました。
先週から読んでいる、哲学者の苫野一徳氏と教育者の工藤勇一氏の対談録『子どもたちに民主主義を教えよう』に、以下のことば紹介されていました。
(以下、本より転載)
苫野)とても重要なポイントてす。「自由の相互承認」は、この社会の基本ルールなんです。工藤さん流に家ば、誰もがきっと合意できるはずの、この社会の最上位ルールなんですね。
工藤)ですよね。たとえば麹町中では一斉授業をできるだけやめる方向で動いていて、子どもたちが自分であった学習スタイルを選べるようにしています。だから授業がはじまると友だち同士で教え合う子もいるし、教員から教わる子もいるし、黙々とタブレットと向き合う子もいるし、家から問題集を持ってくる子もいます。そこには確実に自由があるんですけど、ルールもある。「どうやって勉強するかは君たちの自由だけど、他の人の勉強の邪魔をする権利はないからな」って。これってまさに自由の相互承認ですよね。
苫野)まさにですね。この言い方だと、中学生も「自由の相互承認」を十分に理解してくれそうですね。
(以上、『子どもたちに民主主義を教えよう』より)
新聞記事によると、
>数秒以内の星列や大きな声での返事、5分前行動などを強要する厳しい指導。「外からは統率の取れたクラスに見えたと思う」としつつ、「恐怖支配だった。返事の声が小さいと、壁に向かって「はい」と何十回も言わされた」と証言する。
(以上、熊日新聞より)
大人から強制される、7〜12歳の子どもたちには、そのトラウマは後々まで続くように思います。自由のない教室は、ある意味「檻の中」にいるようなものです。
苫野氏の説明にある「自由の相互承認」とは何か?
「みんな自由に生きたいと願っている。でも、自由をめぐって戦争したり、一部の人が大多数の人の自由を奪ったいたら、誰も自由に生きられない。だったら、誰もが自由な存在であることを、お互いに認め合うことを、お互いに認め合うことをルールにした社会をつくるしかない」そうヘーゲルは言ったのです。
すへての人が、対等に自由な存在であることをお互いに認めあう。そのことをルールにした社会的。これが民主主義の根本原理です。
(以上、本より)
苫野氏、工藤氏の意見を読んだ後に、本日の朝刊をたまたま読み、教師になるための教育に、民主主義の理解が足りていないように思いました。
「自由の相互承認」という、民主主義の根本を、小中学校での実習や初任教師の研修の中で、理解するカリキュラムを、加えることが大事と思います。
熊日記事とお二人の対談録から、指導力とは何か、保護者の価値観が多様化する中、民主主義の本質を保護者も学ぶ機会を毎年設ける必要があると、痛感しました。
子どもだけでなく、教師も保護者も、学校運営、教室運営を民主主義の学びの場にしなければと思います。

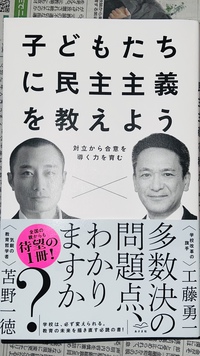
最近、学校内ルール「校則」の見直し論が始まっているが、なかなか進展はないように見えます。
今日の熊日一面に「恐怖支配」で、子どもを指導した元教師のことが取り上げられていました。
先週から読んでいる、哲学者の苫野一徳氏と教育者の工藤勇一氏の対談録『子どもたちに民主主義を教えよう』に、以下のことば紹介されていました。
(以下、本より転載)
苫野)とても重要なポイントてす。「自由の相互承認」は、この社会の基本ルールなんです。工藤さん流に家ば、誰もがきっと合意できるはずの、この社会の最上位ルールなんですね。
工藤)ですよね。たとえば麹町中では一斉授業をできるだけやめる方向で動いていて、子どもたちが自分であった学習スタイルを選べるようにしています。だから授業がはじまると友だち同士で教え合う子もいるし、教員から教わる子もいるし、黙々とタブレットと向き合う子もいるし、家から問題集を持ってくる子もいます。そこには確実に自由があるんですけど、ルールもある。「どうやって勉強するかは君たちの自由だけど、他の人の勉強の邪魔をする権利はないからな」って。これってまさに自由の相互承認ですよね。
苫野)まさにですね。この言い方だと、中学生も「自由の相互承認」を十分に理解してくれそうですね。
(以上、『子どもたちに民主主義を教えよう』より)
新聞記事によると、
>数秒以内の星列や大きな声での返事、5分前行動などを強要する厳しい指導。「外からは統率の取れたクラスに見えたと思う」としつつ、「恐怖支配だった。返事の声が小さいと、壁に向かって「はい」と何十回も言わされた」と証言する。
(以上、熊日新聞より)
大人から強制される、7〜12歳の子どもたちには、そのトラウマは後々まで続くように思います。自由のない教室は、ある意味「檻の中」にいるようなものです。
苫野氏の説明にある「自由の相互承認」とは何か?
「みんな自由に生きたいと願っている。でも、自由をめぐって戦争したり、一部の人が大多数の人の自由を奪ったいたら、誰も自由に生きられない。だったら、誰もが自由な存在であることを、お互いに認め合うことを、お互いに認め合うことをルールにした社会をつくるしかない」そうヘーゲルは言ったのです。
すへての人が、対等に自由な存在であることをお互いに認めあう。そのことをルールにした社会的。これが民主主義の根本原理です。
(以上、本より)
苫野氏、工藤氏の意見を読んだ後に、本日の朝刊をたまたま読み、教師になるための教育に、民主主義の理解が足りていないように思いました。
「自由の相互承認」という、民主主義の根本を、小中学校での実習や初任教師の研修の中で、理解するカリキュラムを、加えることが大事と思います。
熊日記事とお二人の対談録から、指導力とは何か、保護者の価値観が多様化する中、民主主義の本質を保護者も学ぶ機会を毎年設ける必要があると、痛感しました。
子どもだけでなく、教師も保護者も、学校運営、教室運営を民主主義の学びの場にしなければと思います。