「いつまでもあると思うな、親と金。ないと思うな、運と災難」〜田中角栄語録〜
2019年10月26日
「いつまでもあると思うな、親と金。ないと思うな、運と災難」〜田中角栄語録〜
田中角栄の秘書の朝賀昭氏が、田中角栄から訓示され大事にした言葉は、
「希望の朝、法悦の夕/努めて誠実を持って/働け、働け、精一杯/人のことを言うなかれ/まず自分でやれ」
だそうです。短い言葉ですが、なかなか実行にできないのが凡人です。
人の心を動かすのは、美辞麗句、学識歴史をたくさん語るよりも、短く心を動かす自らの言葉が、心に残るように思います。
昭和の苦労人たちの言葉が、心に響く歳になったのかもしれません。
田中角栄の秘書の朝賀昭氏が、田中角栄から訓示され大事にした言葉は、
「希望の朝、法悦の夕/努めて誠実を持って/働け、働け、精一杯/人のことを言うなかれ/まず自分でやれ」
だそうです。短い言葉ですが、なかなか実行にできないのが凡人です。
人の心を動かすのは、美辞麗句、学識歴史をたくさん語るよりも、短く心を動かす自らの言葉が、心に残るように思います。
昭和の苦労人たちの言葉が、心に響く歳になったのかもしれません。
<「農泊」研修>政治とは何か、生活である。吹き過ぎてゆく風、政治はそれでよい。〜田中角栄語録より〜
2019年10月26日


<「農泊」研修>政治とは何か、生活である。吹き過ぎてゆく風、政治はそれでよい。〜田中角栄語録より〜
おはようございます。今朝は、宇佐市の中山間地域の宿に泊まっています。いつもより長く寝れて、気分も良いです。
さて、朝食までの時間、庭先やかまどの前で朝読書ですが、山登りの話から、元首相の田中角栄の語録から、
(以下、『人間を動かす天才 田中角栄の人間力』より)
山に登って道に迷ったら二つの方法がある。川に沿って下る。これは行政た。もう一歩登って霧の晴れるのを待つ。これが政治だよ。困難な時ほど前に出て視野をひろげることだ。(中略)
政治とは何か。生活である。
政治の仕事は、国民の邪魔になる小石をたんねんに拾って捨てる。国の力でなければ崩さない岩を砕いて、道をあける。それだけでよい。いい政治というものは、国民生活の片隅にあるものだ。目立たずつつましく、国民の後ろに控えている。吹き過ぎて行く風、政治はそれで良い。(中略)
(以上、本より抜粋)
小沢一郎が率いた民主党が掲げた「国民生活第一」を唱え、子ども手当、高速道路無償化、高校無償化など政策を目指したが、財源ができずに頓挫した。財政悪化は進み、安倍政権が消費税を上げることで、全世帯型福祉の財源が確保されたように見えるが、それはこれから・・・
田中角栄語録を読むと、なるほどと思うことが、しばしばある。地方独自の小さな事業にもそれを動かす、金と人(財源と人材)が必要です。
議員立法をもっとも多く成立させた田中角栄は、金(財源)を確保して地味に仕事を進めて来た意味で「政治とは生活。吹きゆく風」と語ったのだと思いました。
1980年代から、大分県安心院町で起こったグリーンツーリズムの活動は、時を経て、国に提言して政策にも反映され、地方創生の風に乗り、全国へ広がる「農泊」の基となり、未だにその輝きを失っていない。
2010年の年末にきて以来の安心院町の民泊ですが、やはり政治は実行することだな、と。今日と安心院町グリーンツーリズム、特に中学生の農業体験修学旅行の受け入れについて勉強したいと思います。

<夜郎自大>大人物は決して尊大ぶらない。逆に、小人物ほどつまらぬ実力を誇示したがる。
2019年10月25日
<夜郎自大>大人物は決して尊大ぶらない。逆に、小人物ほどつまらぬ実力を誇示したがる。〜「自」と「大」を重ねると臭(くさい)の文字になる。〜
朝から意味不明な諺の話しですが、説明を詳しくしている本から、
(以下、『中国人の発想80の知恵』から)
「自大」というのは、自分で自分をえらい人間だと思って尊大ぶること、そうなると「臭」つまり臭気プンプンとして鼻もちならないというのが、この諺の意味である。中国人ならずとも、そんな人のお相手はごめんこうむりたいものだ。(中略)
そうですね、こんな輩とはお付き合いはしたくない。また、次のエピソードも紹介されています。後漢の光武帝と地方国家の蜀(しょく)の公孫述(こうそんじゅ)の人物比較の話です。
(以下、本より抜粋)
ある地方豪族の将軍は、蜀の王である公孫述の昔馴染が、どんな人物になったか確認しに行った。ところが、護衛兵が厳然と威儀を正し、実によそよそしい迎え方だった。随行の部下に「外面ばかり飾りたてて、ごたいそうなものだな」と感想を述べた。
その後に、豪族の王の親書を携え、後漢の光武帝を訪ねた。控えの間で待つほどもなく、光武帝は自ら回廊をつたって迎えに出てきた。ニコニコ笑いながら声をかけてくるではないか。
「やあ、貴公の噂はかねてから聞いておるぞ」
それを聞き深々と頭を垂れた。
「陛下は、刺客とも知れぬ初対面のこのわたくしに、かくも気軽にお会いくださいました。なぜでしょうか」
「いや、いや、貴公は刺客などではあるまい」
そういって、光武帝はカラカラ笑ったという。(中略)
公孫述と光武帝の対応の違い、小物ほど尊大な態度を取るのは、昔も今も同じようです。この将軍は、すぐさまわが子を後漢の都やり光武帝に支えさせた。蜀の公孫述は、ほどなく光武帝に滅ぼされた。
冒頭の「夜郎自大」の諺は、『史記』にある話。漢王朝が中国全土を治めたころ、人もすまないような山奥の地域の豪族「夜郎」に、漢の使者が訪ねた。夜郎の王は使者に向かって、
「漢、我が大なるはいずれぞ」
と訪ねたという。(中略)
これを聞いた使者は、何も答えなかたようで、要は、呆れて言葉が出なかったのでは。
自と大を重ねると「臭(くさい)」となる。日本では、うさんくさい、の言葉も。狭い世界で誇示ばかりやっていると、うさんくさい、と煙たがれることを知らなければならない。
トップは常に動ける人、また社会変化を感じることのできる人を選びたいものです。
今朝は、雨で朝のウォーキングがお休み、長々と書きました。最後までお読みいただきありがとうございます。
今日は、大分県の安心院町の熊本県の「むらづくり人材育成」の研修に参加します。あいにくの雨ですが、有意義な研修にしたいと思います。
*参考資料:守谷洋著『中国人の発想80の知恵』
朝から意味不明な諺の話しですが、説明を詳しくしている本から、
(以下、『中国人の発想80の知恵』から)
「自大」というのは、自分で自分をえらい人間だと思って尊大ぶること、そうなると「臭」つまり臭気プンプンとして鼻もちならないというのが、この諺の意味である。中国人ならずとも、そんな人のお相手はごめんこうむりたいものだ。(中略)
そうですね、こんな輩とはお付き合いはしたくない。また、次のエピソードも紹介されています。後漢の光武帝と地方国家の蜀(しょく)の公孫述(こうそんじゅ)の人物比較の話です。
(以下、本より抜粋)
ある地方豪族の将軍は、蜀の王である公孫述の昔馴染が、どんな人物になったか確認しに行った。ところが、護衛兵が厳然と威儀を正し、実によそよそしい迎え方だった。随行の部下に「外面ばかり飾りたてて、ごたいそうなものだな」と感想を述べた。
その後に、豪族の王の親書を携え、後漢の光武帝を訪ねた。控えの間で待つほどもなく、光武帝は自ら回廊をつたって迎えに出てきた。ニコニコ笑いながら声をかけてくるではないか。
「やあ、貴公の噂はかねてから聞いておるぞ」
それを聞き深々と頭を垂れた。
「陛下は、刺客とも知れぬ初対面のこのわたくしに、かくも気軽にお会いくださいました。なぜでしょうか」
「いや、いや、貴公は刺客などではあるまい」
そういって、光武帝はカラカラ笑ったという。(中略)
公孫述と光武帝の対応の違い、小物ほど尊大な態度を取るのは、昔も今も同じようです。この将軍は、すぐさまわが子を後漢の都やり光武帝に支えさせた。蜀の公孫述は、ほどなく光武帝に滅ぼされた。
冒頭の「夜郎自大」の諺は、『史記』にある話。漢王朝が中国全土を治めたころ、人もすまないような山奥の地域の豪族「夜郎」に、漢の使者が訪ねた。夜郎の王は使者に向かって、
「漢、我が大なるはいずれぞ」
と訪ねたという。(中略)
これを聞いた使者は、何も答えなかたようで、要は、呆れて言葉が出なかったのでは。
自と大を重ねると「臭(くさい)」となる。日本では、うさんくさい、の言葉も。狭い世界で誇示ばかりやっていると、うさんくさい、と煙たがれることを知らなければならない。
トップは常に動ける人、また社会変化を感じることのできる人を選びたいものです。
今朝は、雨で朝のウォーキングがお休み、長々と書きました。最後までお読みいただきありがとうございます。
今日は、大分県の安心院町の熊本県の「むらづくり人材育成」の研修に参加します。あいにくの雨ですが、有意義な研修にしたいと思います。
*参考資料:守谷洋著『中国人の発想80の知恵』
私は“くまモンよりも天草エアライン”と考えています。
2019年10月18日
天草エアラインが素晴らしい!
私は“くまモンよりも天草エアライン”と考えています。
飛行機が1機しかありません。飛行機のトラブルがあれば、欠航です。熊本県は、天草のことを考えて欲しいです。
私は“くまモンよりも天草エアライン”と考えています。
飛行機が1機しかありません。飛行機のトラブルがあれば、欠航です。熊本県は、天草のことを考えて欲しいです。
一強のアメリカから多様な世界へ、若い経済学者はインド文化に感化された。者
2019年10月16日
<一強のアメリカから多様な世界へ>アメリカン・ウェイ・オブ・ライフを広めようとインドへ行った若い経済学者は、インディアン・ウェイ・オブ・ライフに染まって帰る?〜宇沢弘文の回想から〜
1960年代は、ケネディ大統領が取った途上国支援により、開発経済の考え方が起こった。戦後の苦しい時代に学び、1960年代からアメリカで活躍した経済学者の宇沢弘文氏は、ある意味、途上国からアメリカへ移り成功した経済学者である。
ケネディ大統領の途上国支援のプログラムで、スタンフォード大学等からインドへ経済学者が派遣される際、必ずと行って良いほど、宇沢弘文氏を訪ねて、途上国の生活や考え方について語って現地へ向かったそうです。
2〜3年インドで過ごすと、冒頭の話になっていたそうです。アメリカの経済の普及をしに行ったのに、インドのカルチャーに染まっていた、と。
人間は、経済ばかりではない、歴史文化に大きく影響を受けて生きています。若い経済学者は、若者でありますから、文化の違いはショックを受けたことでしょう。確か、ビートルズもインドの文化を学びに出かけていたことを思い出します。
1960年代は、パックスアメリカーナの時代で、一強の経済大国であり軍事大国でした。現在、中国の経済成長により一強のアメリカから多様な国々による経済発展に変わりつつあ流のでは。
英語圏であるインドの存在、人口が増え続けている国であり、理数に強い教育から、米中印の経済関係が、これからの世界経済関係に影響を与えていくのだろうと思います。
若い経済学者は、アメリカン・ウェイ・オブ・ライフのはずが、インディアンアメリカン・ウェイ・オブ・ライフ感化された。(宇沢弘文)
*参考資料:佐々木実著『資本主義と闘った男』
1960年代は、ケネディ大統領が取った途上国支援により、開発経済の考え方が起こった。戦後の苦しい時代に学び、1960年代からアメリカで活躍した経済学者の宇沢弘文氏は、ある意味、途上国からアメリカへ移り成功した経済学者である。
ケネディ大統領の途上国支援のプログラムで、スタンフォード大学等からインドへ経済学者が派遣される際、必ずと行って良いほど、宇沢弘文氏を訪ねて、途上国の生活や考え方について語って現地へ向かったそうです。
2〜3年インドで過ごすと、冒頭の話になっていたそうです。アメリカの経済の普及をしに行ったのに、インドのカルチャーに染まっていた、と。
人間は、経済ばかりではない、歴史文化に大きく影響を受けて生きています。若い経済学者は、若者でありますから、文化の違いはショックを受けたことでしょう。確か、ビートルズもインドの文化を学びに出かけていたことを思い出します。
1960年代は、パックスアメリカーナの時代で、一強の経済大国であり軍事大国でした。現在、中国の経済成長により一強のアメリカから多様な国々による経済発展に変わりつつあ流のでは。
英語圏であるインドの存在、人口が増え続けている国であり、理数に強い教育から、米中印の経済関係が、これからの世界経済関係に影響を与えていくのだろうと思います。
若い経済学者は、アメリカン・ウェイ・オブ・ライフのはずが、インディアンアメリカン・ウェイ・オブ・ライフ感化された。(宇沢弘文)
*参考資料:佐々木実著『資本主義と闘った男』
Posted by ノグチ(noguchi) at
10:34
│Comments(0)
<森林集約化の調査>午前中は、山林の集約化のための現地調査に同行しました。
2019年10月08日
<森林集約化の調査>午前中は、山林の集約化のための現地調査に同行しました。
人が山に入らないと、こんなに荒れるのか!と思いました。
ナタで、倒れた竹や雑木を切って登ります。そんな荒れた山の所用林の境をどうやって調べるかと言いますと、GPSを使い、20年ほど前に地籍調査を地図に落としてあり、数十センチ単位で位置が確認できます。優れものの位置確認の機械があるから、荒れた林でもわかるのです。
杉檜が植林してある場所を確認し、材の大きさ(直径、高さ)直径5mの円内に何本在るかを調べます。杉檜の植林してある範囲は、現地確認かどうしても必要なので、道なき道を歩いて山を登り、下り、大変な調査です。
赤い手袋の横の四角の杭が、20年前の地籍調査の跡です。
そもそも、今回の調査は、山林を集約化(山林団地)にして、地域で林業維持団体を作り、間伐、伐採、植林、等々を行うと作業費用を国が支援する制度のための前準備です。
初めて同行しましたが、地域の林研グループの献身的なご協力おかげで、着実に進んでいます。調査が終わると、山林団地の維持管理計画を国に提出して、事業が始まります。
移動の途中、イノシシが子育てをした巣の跡見つけました。巣は、こんもりした草木を集めた形で、大きさを理解してもらうために赤い手袋と写真を撮りました。
全部調べるのは、あと1年近くかかりますが、地域の山林の状況がわかり、私も時々同行しようと思いました。













人が山に入らないと、こんなに荒れるのか!と思いました。
ナタで、倒れた竹や雑木を切って登ります。そんな荒れた山の所用林の境をどうやって調べるかと言いますと、GPSを使い、20年ほど前に地籍調査を地図に落としてあり、数十センチ単位で位置が確認できます。優れものの位置確認の機械があるから、荒れた林でもわかるのです。
杉檜が植林してある場所を確認し、材の大きさ(直径、高さ)直径5mの円内に何本在るかを調べます。杉檜の植林してある範囲は、現地確認かどうしても必要なので、道なき道を歩いて山を登り、下り、大変な調査です。
赤い手袋の横の四角の杭が、20年前の地籍調査の跡です。
そもそも、今回の調査は、山林を集約化(山林団地)にして、地域で林業維持団体を作り、間伐、伐採、植林、等々を行うと作業費用を国が支援する制度のための前準備です。
初めて同行しましたが、地域の林研グループの献身的なご協力おかげで、着実に進んでいます。調査が終わると、山林団地の維持管理計画を国に提出して、事業が始まります。
移動の途中、イノシシが子育てをした巣の跡見つけました。巣は、こんもりした草木を集めた形で、大きさを理解してもらうために赤い手袋と写真を撮りました。
全部調べるのは、あと1年近くかかりますが、地域の山林の状況がわかり、私も時々同行しようと思いました。













今夕は、月2回の地域を巡回する防犯パトロールの日でした。
2019年10月07日


今夕は、月2回の地域を巡回する防犯パトロールの日でした。有明海の夕陽と長部田海床路の海に立つ街灯の電柱が並びいい写真が撮れました。10人ほどの観光客が、夕陽と電柱の並ぶ風景をカメラに収めていました。だんだん、長部田海床路も観光客が増えていいそうな気配があります。
<香港の混乱>中国4千年の闘争・政治の知恵を思いだして民衆の心掴め。〜法を厳しくすればするほど、民衆は反発する〜
2019年10月07日
<香港の混乱>中国4千年の闘争・政治の知恵を思いだして民衆の心掴め。〜法を厳しくすればするほど、民衆は反発する〜
香港政府の対話の中途半端な対応が、対立をエスカレートさせたと思います。さらに、将来のある若者たちが、怒る方法で取り締まれば、さらに反発はエスカレートするのは必至。
インドのガンジーは、イギリスの強権、暴力的な圧政を、無抵抗に徹して世界へ訴え続けた。香港政府(=中国政府)は、今のような対応を続け、対立がエスカレートしていけば、民主国家どころか、強権、独裁国家に成り下がることになる。世界経済のけん引役が、圧政国家とみなされるようだと、世界のリーダーどころか、三流国にも見られないことになる。
そろそろ、香港政府の対応も考えを変える時期に来ているように思います。
闘争・闘いの大陸政治を治めてきた中国4千年の知恵を働かせて、民衆の怒りを治めないと、中国自体が揺るぎかねないと危惧します。
しかし日本も、つい50年前くらいは、安保闘争をやっていた時代がありますから、よそ事ではありませんね。民衆の意見に耳を傾けてほしいですね。

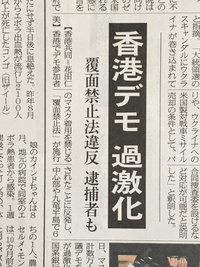

香港政府の対話の中途半端な対応が、対立をエスカレートさせたと思います。さらに、将来のある若者たちが、怒る方法で取り締まれば、さらに反発はエスカレートするのは必至。
インドのガンジーは、イギリスの強権、暴力的な圧政を、無抵抗に徹して世界へ訴え続けた。香港政府(=中国政府)は、今のような対応を続け、対立がエスカレートしていけば、民主国家どころか、強権、独裁国家に成り下がることになる。世界経済のけん引役が、圧政国家とみなされるようだと、世界のリーダーどころか、三流国にも見られないことになる。
そろそろ、香港政府の対応も考えを変える時期に来ているように思います。
闘争・闘いの大陸政治を治めてきた中国4千年の知恵を働かせて、民衆の怒りを治めないと、中国自体が揺るぎかねないと危惧します。
しかし日本も、つい50年前くらいは、安保闘争をやっていた時代がありますから、よそ事ではありませんね。民衆の意見に耳を傾けてほしいですね。

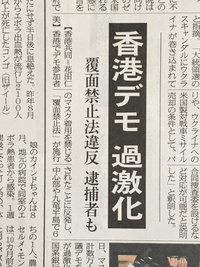

<新交通システム検証中>今日は、一日中バスに揺られていました。
2019年10月03日
<新交通システム検証中>今日は、一日中バスに揺られていました。
新ダイヤの宇土市街地を循環するコミュニティバス「行長しゃん号」の新ルートを検証と、利用状況を確認のため、すべての時間に乗っています。よく考えられたコースと時間ですが、まだ改善の余地はあるなと思います。
加えて、ミニバス「のんなっせ」との連携も考えることが必要だと思います。最後の便に乗っています。宇土市街地を、8周回りました。もうすぐ終点ですが、まだ途中のミニバスの検証と合わせて整理したいと思います。
震災から3年半、市街地もだいぶ復興が進んでいるように思いました。でも、空き地には雑草が繁ったところも、まだまだ課題も多いです。
もう一月後くらいに、再度乗ってみたいと思います。ドライバーの方とも面識ができ、次は色々アドバイスを頂けると思います。


新ダイヤの宇土市街地を循環するコミュニティバス「行長しゃん号」の新ルートを検証と、利用状況を確認のため、すべての時間に乗っています。よく考えられたコースと時間ですが、まだ改善の余地はあるなと思います。
加えて、ミニバス「のんなっせ」との連携も考えることが必要だと思います。最後の便に乗っています。宇土市街地を、8周回りました。もうすぐ終点ですが、まだ途中のミニバスの検証と合わせて整理したいと思います。
震災から3年半、市街地もだいぶ復興が進んでいるように思いました。でも、空き地には雑草が繁ったところも、まだまだ課題も多いです。
もう一月後くらいに、再度乗ってみたいと思います。ドライバーの方とも面識ができ、次は色々アドバイスを頂けると思います。





