<豊かさの条件>いつの時代にも人間社会は共同体的な部分を残さなければ、社会基盤の安定を欠く。
2025年01月06日


<豊かさの条件>いつの時代にも人間社会は共同体的な部分を残さなければ、社会基盤の安定を欠く。また個人が共同体の中に埋没してしまうと、社会の活力を失う。〜暉峻淑子著『豊かさの条件』〜
年始から矛盾する提言の言葉を紹介します。
(長い論文?です。お時間ある時にお読みください。)
本日は、私が住む集落で毎年に新年に開催される住民会議「初寄り合い」に、市議会議員として、新年の挨拶をして回る大切な日でした。4ヶ所の自治区の寄り合いの会場に出向き、活動報告と今年の方針をお話しさせていただきました。終わって15時過ぎ帰宅して、未明のウォーキングもあり、疲れて少し仮眠を取りました。この正月行事も今年で15年目、なかなか緊張する一日です。
さて冒頭の言葉からも、田舎の集落運営と個人生活の充実を、本日の挨拶回りと寄り合いでのみなさんの意見を拝聴して、いつも感じるのですが、いにしえ(古)の時代から営々と続けられてきたのだろうと、本日も振り返りました。
集落運営は、共同体の活動。
日々の暮らしを作る活動は、個人の生活。
娘が年末年始に帰郷していて、本日の寄り合いを回る活動を見て、話をする中で感じたのが、地域を支えるには古くから共同体活動で支えられていることを、都市生活をする若者たちは知らない人が多いように感じました。
例を上げると、昨年の地域課題一つ、防犯対策の要望で、
・街灯の増設
・防犯カメラの設置
がありました。地方は、人口減少から人口密度が減り、広い地域の安心安全の対策が不充分になっています。
しかしその対策で、街灯の設置には、市(国・県)の補助金があっても、日常の電気代は地域(自治区)で負担することになります。
このことを、どれだけの住民が知っているのか?と思います。
過疎地ほど、住民が共同体(集落運営)に拠出する費用(個人負担)が膨らむ現状があります。
私は若い頃、日本政府は人を都市に集めのは、地方に交付する税金を減らすためにやっているのでは、と思ったことがありますした。そんなことから、
冒頭の言葉を紹介した意味は、以下のエピソードからです。
社会学者の暉峻淑子(てるおか いつこ)著『豊かの条件』の最後の方に、
19世紀のロシアの政治思想家・クロポトキン(注1)著『相互扶助論』の序論で、ある逸話(エピソード)が紹介されていました。
(以下、『豊かの条件』より)
1827年のある日、ゲーテを秘書のエッカーマンがたずねて、彼が直接に経験したある助け合いの実例を話したところ、ゲーテはその話に感激して「もし縁もゆかりもない他人をこうして養うということが、自然のどこにでも行われていて、その一般的法則だということにならば、今まで解くことのできなかった多くの謎はたちどころに解けてしまう」と言い、翌日もそのことを話題にして、その問題についての特別な研究をエッカーマンに熱心にすすめた、というのである。
クロポトキンは、労働者達の住む長屋のいたるところで、もし産婦がお産をすれば近所の女達が手伝いにきて、生まれた子どもの世話や産婦が起きられるようになるまでの家事や、そのために入用なものを持ち寄って助け合っている事実を知っていた。親が死んだあとの孤児をだれかが必ずひきとって育てていることも、そしてそれがごくつうのことで、珍しいことでもなんでもないことを知っていた。
(以上、本より)
引用文が、長くなりましたが、日本もかつては"村社会"である共同体の暮らしが、長く続いていました。
明治からの産業革命、戦争の時代、戦後の高度経済成長、バブル経済時代、デフレの失われた日本、そして令和の時代になりました。
本日の古(いにしえ)から続いている、新年の初寄り合いの行事から、
共同体の運営と、個人生活の成長からも、
明治に導入された西洋の"資本主義"について、クロポトキンの理論から、振り返りました。
暉峻淑子さんの『豊かさの条件』の一節にありました。
(以下、本より)
だが、資本主義は共同体を徹底的に解体し、社会をバラバラの私的所有に分解してしまう。そうすれば、社会的な生産力は、飛躍的に発展するが、やがてその生産力は競争の中で敵対的にぶつかりあい、資本相互の間で弱肉強食が進む。資本と労働者の間にも衝突が起こり、不況と失業による社会的な危機がおとすれる。
(以上、『豊かさの条件』より)
この引用文の続きが、冒頭の言葉です。
>は共同体的な部分を残さなければ、社会基盤の安定を欠く。
>個人が共同体の中に埋没してしまう
過疎化する地方衰退の原因に、資本主義化した日本社会の変化と都市集中があるのだろうとは思っていましたが、暉峻淑子さん本を読み、益々の確信を持ちました。
これからの政府に望むのは、地方で今も維持されている共同体活動の支援を、地方創生のメニューに加えるべきではと思いました。
熊本選出の衆議院議員・金子恭之氏が常々に語られている、「地方の繁栄なくして、国の繁栄なし」の言葉を、思い出しました。
人口減少地域を支えることが、次なる日本の繁栄を生み出すようになってほしいですね。
長々と書きました。最後までお読みいただき感謝いたします。
*注1:ピョートル・アレクセイヴィチ・クロポトキン(1842年12月9日〜1921年2月8日)。ロシアの革命家、政治思想家であり、地理学者、社会学者、生物学者。
#地方の繁栄なくして国の繁栄なし
#クロポトキン『相互扶助論』
#地方創生
#日本の地方
#人口減少
#少子高齢化
#資本主義
#共同体
#暉峻淑子
#豊かさの条件
#相互扶助論
藩主が自ら思い切った贅肉落しを行う。鍋釜(官僚)を頑強に鋳る(育成する)ことが最も肝要である。〜上杉鷹山〜
2024年01月09日
<政治改革とは>藩主が自ら思い切った贅肉落しを行う。鍋釜(官僚)を頑強に鋳る(育成する)ことが最も肝要である。〜上杉鷹山〜
一昨日、昨日は、20歳の集い(成人式)が各地で開催され、若人たちの輝く姿を見ることができました。これからの活躍が楽しみです。
さて朝の読書は、元都庁職員で作家の童門冬二著『上杉鷹山と細井平洲』を開きました。
江戸期の名藩主と言われる米沢藩の上杉鷹山を若いときから指導をしたのは儒家の細井平洲です。
藩主となり鷹山が初めて江戸から米沢藩に帰郷した時の方から・・・
(以下、童門冬二著『上杉鷹山と細井平洲』より抜粋)
財政も行政も最悪で、泊まるはずの宿(本陣)は潰れ、食事も用意されない状況だった。つまり、都市基盤整備が全く行われず、税ばかり高く、働き場もないなら若者はどんどん大都会に行ってしまった。
寒い中、部下たちと一緒に囲む火鉢を見ながら、「火種の誓い」なる発言が生まれる。
「責任はすべて藩主の自分にある。私が灰の中のこの小さな火種になろう。おまえたちはこの火種を受ける黒い灰になってほしい。そして、明日から米沢城内で火種運動を起せ。いつかその火が城中に漲(みなぎ)れば、やがて飛び火をして、町に住む人や村に住む人の胸に飛んでいく。そうすれば、住民もこの改革に協力してくれる」
>改革の究極的な目的は、下々が暮らし易く幸福感を感ずることにある。そのためには、藩主が入用を省き、恵み深く下々に接しなければならない。具体的には節倹な術を自身の奥向きから実行することである。
>藩主が自ら思い切った贅肉落しを行うことである。
>だからといって、藩主が自ら贅肉を落す行為を、これ見よがしに他にPRするような邪な心があってはならない。
(以上、本より)
等々、細井平洲の指導を受けた鷹山の気構えの話が続くのですが、リーダーの在り方、実践行動、部下として役割、殖産興業の政策と実施、詳しく具体的に書かれています。さすが、行政マンの視点で鋭く、『嚶鳴舘遺草』を分析されていて面白い。
また、以下の部分は特に例えが生活感があって感心しました。
>藩主は米である。士農工商は薪である。地方役人は鍋釜である。最も大切なのは鍋釜である。たとえどんなに米がよく、薪がよく燃えても、鍋釜が壊れていては米はよく炊けない。鍋釜を頑強に鋳ることが最も肝要である。〜細井平洲『嚶鳴舘遺草』〜
上杉家は、様々な事情から、多くの家臣を抱えたまま、広く豊かな領地から、東北の狭い米沢藩に移されます。元々厳しい財政に加え、領地替えで大変な苦労があったと思います。
戦国時代の武士とは違い、平和な社会になり武士は地方役人となった。民から税を吸い上げるのでなく、自ら金を稼ぐことを推奨し、それを後押しする基盤整備に熱心に取り組み、財政を立て直して行ったのが上杉鷹山公でした。
現代も、政治の役割の一つに、産業の育成がありますし、基盤(インフラ)整備ももちろん重要です。
ご存知かとは思いますが、熊本藩の『時習館』の設立に尽力した儒家の秋山玉山と細井平洲は、親交があったことから、同時期に『嚶鳴舘』と『時習館』が創設されています。人のつながりを不思議に思います。
これから数日、この『上杉鷹山と細井平洲』をまた読み返そうかと考えています。
今日から3学期が始まるので、日常が戻ることになります。寒いですが、ぼちぼち朝活の準備です。
一昨日、昨日は、20歳の集い(成人式)が各地で開催され、若人たちの輝く姿を見ることができました。これからの活躍が楽しみです。
さて朝の読書は、元都庁職員で作家の童門冬二著『上杉鷹山と細井平洲』を開きました。
江戸期の名藩主と言われる米沢藩の上杉鷹山を若いときから指導をしたのは儒家の細井平洲です。
藩主となり鷹山が初めて江戸から米沢藩に帰郷した時の方から・・・
(以下、童門冬二著『上杉鷹山と細井平洲』より抜粋)
財政も行政も最悪で、泊まるはずの宿(本陣)は潰れ、食事も用意されない状況だった。つまり、都市基盤整備が全く行われず、税ばかり高く、働き場もないなら若者はどんどん大都会に行ってしまった。
寒い中、部下たちと一緒に囲む火鉢を見ながら、「火種の誓い」なる発言が生まれる。
「責任はすべて藩主の自分にある。私が灰の中のこの小さな火種になろう。おまえたちはこの火種を受ける黒い灰になってほしい。そして、明日から米沢城内で火種運動を起せ。いつかその火が城中に漲(みなぎ)れば、やがて飛び火をして、町に住む人や村に住む人の胸に飛んでいく。そうすれば、住民もこの改革に協力してくれる」
>改革の究極的な目的は、下々が暮らし易く幸福感を感ずることにある。そのためには、藩主が入用を省き、恵み深く下々に接しなければならない。具体的には節倹な術を自身の奥向きから実行することである。
>藩主が自ら思い切った贅肉落しを行うことである。
>だからといって、藩主が自ら贅肉を落す行為を、これ見よがしに他にPRするような邪な心があってはならない。
(以上、本より)
等々、細井平洲の指導を受けた鷹山の気構えの話が続くのですが、リーダーの在り方、実践行動、部下として役割、殖産興業の政策と実施、詳しく具体的に書かれています。さすが、行政マンの視点で鋭く、『嚶鳴舘遺草』を分析されていて面白い。
また、以下の部分は特に例えが生活感があって感心しました。
>藩主は米である。士農工商は薪である。地方役人は鍋釜である。最も大切なのは鍋釜である。たとえどんなに米がよく、薪がよく燃えても、鍋釜が壊れていては米はよく炊けない。鍋釜を頑強に鋳ることが最も肝要である。〜細井平洲『嚶鳴舘遺草』〜
上杉家は、様々な事情から、多くの家臣を抱えたまま、広く豊かな領地から、東北の狭い米沢藩に移されます。元々厳しい財政に加え、領地替えで大変な苦労があったと思います。
戦国時代の武士とは違い、平和な社会になり武士は地方役人となった。民から税を吸い上げるのでなく、自ら金を稼ぐことを推奨し、それを後押しする基盤整備に熱心に取り組み、財政を立て直して行ったのが上杉鷹山公でした。
現代も、政治の役割の一つに、産業の育成がありますし、基盤(インフラ)整備ももちろん重要です。
ご存知かとは思いますが、熊本藩の『時習館』の設立に尽力した儒家の秋山玉山と細井平洲は、親交があったことから、同時期に『嚶鳴舘』と『時習館』が創設されています。人のつながりを不思議に思います。
これから数日、この『上杉鷹山と細井平洲』をまた読み返そうかと考えています。
今日から3学期が始まるので、日常が戻ることになります。寒いですが、ぼちぼち朝活の準備です。
世界のデジタル競争力は、日本は世界32位、しかし韓国は6位だった。日本のデジタル化の取り組みを前へ。
2023年12月09日

世界のデジタル競争力は、日本は世界32位、しかし韓国は6位だそうです。
10月に、日韓交流で忠清南道とソウルを訪問して、現金をいっさい使わずに帰りました。5年前は、田舎のレストランで、ツアーコンダクターが払っていたような、気がします。デジタル競争力は、特にここ5年に、日本と世界の格差が開いたように感じます。
半導体工場の誘致に浮かれるのでなく、生活のデジタル化の取り組みを進めないと、ますます世界との格差は開いていくように、危惧します。
7年前、大きな水害を私の住む地域が受けました。西山県議とともに、県の担当者と現地の状況を見てもらいました。
2023年05月12日
7年前、大きな水害を私の住む地域が受けました。被害状況は、山の沢などから流れてきた土石流が支流の川を埋めて、川から溢れ水が、家の敷地や田畑に流れ込みました。何をすれば対策になるのか、山の保全はもちろんが、やはり土砂の流出を防ぐことが必要だと、球磨川豪雨災害の被災地へボランティアに行って、支流の被害を確認する中で、必要と思うようになりました。
そこで、西山県議とともに、県の担当者と現地の状況を見てもらおうと、ご案内しました。いろいろ、対策をあることも含め、とても参考になりました。
さっそく、県議の事務所へ土砂流出防止の砂防ダムや土砂止め対策の拠点を地図に示したものと届け、来週の県の担当との打ち合わせに取り上げてもらえることになりました。計画もこれからですが、現地確認だけでもしてもらうと、今後の対応がスムーズになると考えています。
写真の砂防ダムは、私の住む地域の支流に在る、昭和時代に計画されたものです。こんなのが必要と考えています。
そこで、西山県議とともに、県の担当者と現地の状況を見てもらおうと、ご案内しました。いろいろ、対策をあることも含め、とても参考になりました。
さっそく、県議の事務所へ土砂流出防止の砂防ダムや土砂止め対策の拠点を地図に示したものと届け、来週の県の担当との打ち合わせに取り上げてもらえることになりました。計画もこれからですが、現地確認だけでもしてもらうと、今後の対応がスムーズになると考えています。
写真の砂防ダムは、私の住む地域の支流に在る、昭和時代に計画されたものです。こんなのが必要と考えています。
「輝け‼︎ 地方議会」〜対話による地方議会活性化フォーラムin春日に参加しました。
2023年02月15日


ローカルマニフェスト推進ネットワークが主催する
「輝け‼︎ 地方議会」
対話による地方議会活性化フォーラムin春日
最初に、北川正恭氏(早稲田大学教授)による基調講演から始まりました。
1995年からの地方へ権限を渡して行く、地方分権一括法からの地方自治、地方議会の役割は何か、改革の意味も含め、約1時間の講義ありました。
宇土市議会、6月定例議会は、6月3日開会です。会期は6月3日〜20日まで。私の代表質問は、6月7日10時からです。
2022年05月27日
宇土市議会、6月定例議会は、6月3日開会です。会期は6月3日〜20日まで。
6月7日〜9日 代表質問・一般質問
私は、6月7日10時から、会派・宇土市政研「志」を代表して、代表質問を行います。市長の4期目のマニフェストと今年の施政方針について、5分野19項目について質問します。今度の議会は、傍聴の制限はありませんので、興味ある方は聞きに来てみてください。
市議会は、宇土市役所仮設庁舎2回会議室が開催されます。

6月7日〜9日 代表質問・一般質問
私は、6月7日10時から、会派・宇土市政研「志」を代表して、代表質問を行います。市長の4期目のマニフェストと今年の施政方針について、5分野19項目について質問します。今度の議会は、傍聴の制限はありませんので、興味ある方は聞きに来てみてください。
市議会は、宇土市役所仮設庁舎2回会議室が開催されます。

<過疎地の教育支援>「教育の三大原則」(『民主主義と教育』ジョン・デューイ著)から、現代教育を考える。
2022年02月22日
<過疎地の教育支援>「教育の三大原則」(『民主主義と教育』ジョン・デューイ著)から、現代教育を考える。
枕元にある本の中から、経済学者の宇沢弘文著『人間の経済』を開くと、教育についての考え方を語っていました。
以下、ジョン・デューイの「教育の三大原則」について書かれていました。
(以下、本より)
第一は、社会的統合。
子どもたちが学校の教室と言う場で、他の子どもたちと一緒に学び、あそぶことで一人前のなんかに成長したするのを助ける。〜アメリカは、特に十九世紀は典型的な移民社会でしたから〜
第二は、平等に関わる原則。
どんな僻地に生まれても、どれほど貧しい過程に育ったとしても、その時々の社会が提供できる最高の教育を、すべての子どもたちが受けられるようにする。
第三は、一人ひとりの子どもの知的、精神的、道徳的な側面の発達を助ける。
子どもたちはみなinnate(生来的)に、あるいは後天的に独特の能力と性向を持っている。それらの良い面をできるだけ生かしながら、同時に社会的な存在としてバランスのとれた人間に育てる。
(以上、宇沢弘文著『人間の経済』より)
この三原則は、日本の教育の基本的な考え方になっている、とあります。
さて、現代教育の現状はどうでしょう?
毎日、イジメの話が新聞に出ないことは無い。
教育現場に任せっきりの家庭教育の現状。さらに食育も。
デューイの「教育の三大原則」を、今の親世代は理解して学校と向き合う必要性か改めて思っています。
しかし、私自身は子育てを終わったものですが、子育て時期に、三大原則を知ってやっていたか?問われると、返事に困るのです。
個性の違う二人の娘たち、手探りでやっていたなぁ、と振り返ります。
子育ては、親も初めての体験であります。
ただ、三つの三大原則を知っていることは必要です。特に、過疎地に住む我々家族は、
>第二は、平等に関わる原則。
「どんな僻地に生まれても、どれほど貧しい家庭に育ったとしても、」
教育基本法の根幹にある考え方で、地方在住の家庭は、国へ県へ要求することができることを知るべきですし、もっと意見を出すべきと思います。
日本の人口は、都市部と地方は、確実に偏在し、年々偏りが強くなっています。ジョン・デューイの「教育の三大原則」から、過疎地の教育に、国は支援をもっとすべきと思いました。
枕元にある本の中から、経済学者の宇沢弘文著『人間の経済』を開くと、教育についての考え方を語っていました。
以下、ジョン・デューイの「教育の三大原則」について書かれていました。
(以下、本より)
第一は、社会的統合。
子どもたちが学校の教室と言う場で、他の子どもたちと一緒に学び、あそぶことで一人前のなんかに成長したするのを助ける。〜アメリカは、特に十九世紀は典型的な移民社会でしたから〜
第二は、平等に関わる原則。
どんな僻地に生まれても、どれほど貧しい過程に育ったとしても、その時々の社会が提供できる最高の教育を、すべての子どもたちが受けられるようにする。
第三は、一人ひとりの子どもの知的、精神的、道徳的な側面の発達を助ける。
子どもたちはみなinnate(生来的)に、あるいは後天的に独特の能力と性向を持っている。それらの良い面をできるだけ生かしながら、同時に社会的な存在としてバランスのとれた人間に育てる。
(以上、宇沢弘文著『人間の経済』より)
この三原則は、日本の教育の基本的な考え方になっている、とあります。
さて、現代教育の現状はどうでしょう?
毎日、イジメの話が新聞に出ないことは無い。
教育現場に任せっきりの家庭教育の現状。さらに食育も。
デューイの「教育の三大原則」を、今の親世代は理解して学校と向き合う必要性か改めて思っています。
しかし、私自身は子育てを終わったものですが、子育て時期に、三大原則を知ってやっていたか?問われると、返事に困るのです。
個性の違う二人の娘たち、手探りでやっていたなぁ、と振り返ります。
子育ては、親も初めての体験であります。
ただ、三つの三大原則を知っていることは必要です。特に、過疎地に住む我々家族は、
>第二は、平等に関わる原則。
「どんな僻地に生まれても、どれほど貧しい家庭に育ったとしても、」
教育基本法の根幹にある考え方で、地方在住の家庭は、国へ県へ要求することができることを知るべきですし、もっと意見を出すべきと思います。
日本の人口は、都市部と地方は、確実に偏在し、年々偏りが強くなっています。ジョン・デューイの「教育の三大原則」から、過疎地の教育に、国は支援をもっとすべきと思いました。
定期的に視察する八代港のコンテナヤードには、けっこうコンテナが3段積みの列が増えたように思います。
2022年01月26日
定期的に視察する八代港のコンテナヤードには、けっこうコンテナが3段積みの列が増えたように思います。
海運の需要高から、海外での港では、コンテナの積み残しも増えていると聞くので、九州内の各地のコンテナ積出港へ、トラック輸送が増えているのではと想像します。益々、八代港のコンテナ船の利用が増えると、宇土市街地を経由して、九州を北上する大型車両が増えると思います。


海運の需要高から、海外での港では、コンテナの積み残しも増えていると聞くので、九州内の各地のコンテナ積出港へ、トラック輸送が増えているのではと想像します。益々、八代港のコンテナ船の利用が増えると、宇土市街地を経由して、九州を北上する大型車両が増えると思います。


オミクロン株の国内感染拡大と米軍基地の存在。〜感染対策で考え方にズレ〜
2022年01月07日


オミクロン株の国内感染拡大と米軍基地の存在。〜感染対策で考え方にズレ〜
「欧米諸国は、オミクロン株をインフルエンザ並みの感染症と思っているのでは?」
政府は、これまで水際対策を徹底すると、空港での検疫を重点的にやっていたが、沖縄県の米軍基地、山口県の岩国米軍基地から、じわり広がったオミクロン株の感染拡大が、国内の市中感染源になっていることから、もう水際どころではないと判断した。
100年前のスペイン風邪の発生源は、米国内の米軍基地から始まったことを、思い出した。
集団生活、施設内の緩い規律から、一気に広がった可能性が大きい。オミクロン株に対する米軍の対応が、そのまま市中感染まで広げてしまった。
オミクロン株の感染が、急速に拡大する中、大阪府の吉村知事は、
オミクロン株は重症化しにくいとして「その状況なら、人の生活に制約をかけるのは違う」と市役所で記者団に述べ、経済活動を維持する必要性を強調した。
(以上、熊日の共同通信配信記事から)
>全国の感染者 オミクロン株の疑い46%
デルタ株は沈静化し、すでに市中感染のほとんどはオミクロン株に変わっているのだろう、と推測します。
米軍基地は、重症化しにくいオミクロン株の対応は、米国政府の意向と同じく、"緩かった"ことから、基地外へ感染が染み出したことは間違いない。
国内の米軍基地周辺では、すでに市中感染が始まっていて、それが国内感染拡大の要因の一つになっていると思われる。
〜沖縄県、山口県、広島県が、蔓延防止等重点措置の適用へ〜
今後は、爆発的に感染拡大するのに、各自治体の対応はどうなるか。今回、米軍基地周辺では蔓延防止等重点措置が適用されるが、他の地域では必要か、経済活動の規制について悩むところだろう。
あびき棚田米(宇土市・ふるさと納税返礼品)炊き立てはもちろん、冷えても美味しい、お弁当には最高です。
2021年12月12日
あびき棚田米(宇土市・ふるさと納税返礼品)
宇土市の中山間地の棚田で、丁寧に育てました。炊き立てはもちろん、冷えても美味しい、お弁当には最高です。ぜひ、チョイスしてください。5kg 8000円、10kg(5kg×2)15000円。
#ふるさと納税、#宇土市、#お米、#棚田米、
#ふるさとチョイスあびき棚田米
https://www.furusato-tax.jp/search?display_company_name_row1=%E6%A3%9A%E7%94%B0%E7%B1%B3%E6%B4%BB%E7%94%A8%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A&city_code%5B%5D=43211&is_target_companies=1
宇土市の中山間地の棚田で、丁寧に育てました。炊き立てはもちろん、冷えても美味しい、お弁当には最高です。ぜひ、チョイスしてください。5kg 8000円、10kg(5kg×2)15000円。
#ふるさと納税、#宇土市、#お米、#棚田米、
#ふるさとチョイスあびき棚田米
https://www.furusato-tax.jp/search?display_company_name_row1=%E6%A3%9A%E7%94%B0%E7%B1%B3%E6%B4%BB%E7%94%A8%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A&city_code%5B%5D=43211&is_target_companies=1
自然が素晴らしい、いい国に生まれたなという思いを、子供たちに残す。(司馬遼太郎)〜自然保護と経済格差〜
2021年11月01日
<自然保護と経済格差>司馬遼太郎の最後の言葉は「空を見ても、川を見ても、山を見ても、ああ美しい、いい国に生まれたなという思いを、子供たちに残す、それが私たちの義務だというものじゃないか」〜半藤一利『歴史と人生』より〜
昨日の午後、久しぶりに休日のイオンモール・クレアに出かけた。その人の多さに、田舎暮らしの私は、やはりイオンモールは、平日に行くところと思って、書店で妻の用事が済む間に、選書していると見つかるもので、作家の半藤一利氏の文を集めた『歴史と人生』の新書版を見つけ購入した。モール内は、かかる場所も無く、駐車場の車で読書しながら待っているの間に、パラパラと・・・、冒頭の司馬遼太郎さんと半藤氏との会話て語られた言葉に目が止まった。
半藤氏が司馬氏に「国民のうち80%、90%が合意できることがありますか?」と聞いた。その返事は、以下です。
(以下、本より)
「それは君ね、自然をこれ以上壊さないということだよ。もとに戻せたいったって無理だから、ここまで許すことにしよう。しかしこれ以上はもう壊さないことを、日本国民が全部で合意しようじゃないか。そうしなければ、われわれは子孫に顔向けができないじゃないか」
(以上、『歴史と人生』より転載)
その後に語った言葉が、冒頭の一文です。この会話は、司馬遼太郎氏が亡くなる1年前のことだそうで、ほんとに最後まで元気に人と語っておられたこと学校伝わってきます。
日本の自然、これから北海道から始まる紅葉は、だんだんと南下して、日本列島を"秋色"に染めていきます。九州は、11月下旬から、高地から平地へと下がってきます。晩秋の日本の美しさは、格別と思います。
司馬遼太郎氏は、日本の自然保護を最後に語っていたことを知り、荒れる中山間地域は、過疎と高齢化、人口減少学校原因ですが、今回の衆議院選挙ても、地方再生、創生が訴えられたが、今のままでは、人生減少の流れは変わらない。
都市部と地方の情報格差を平準化して、テレワークを活用して地方は人が移動できるように、5Gの普及を加速化してほしいですね。私の地域にもやっと光ファイバー網が敷かれましたが、やはり維持するには、固定経費となる月額料金が必要であります。年金生活者には、ちょっとハードルが高いですが、仕事する若い世代は高くても使わなけばならないので、もっと使いやすく(都市並の低料金に)する必要があります。都市部と地方の情報格差解消は、まだまだ課題があります。
話は戻りますが、自然保護をするにも若い世代が必要です。豊か自然は、地方にあります。若者たちが、地方(中山間地域に)でも暮らしやすい環境を整えていき、情報格差を無くし、地方経済を活性化することが、これから政府に望むことです。
昨日の午後、久しぶりに休日のイオンモール・クレアに出かけた。その人の多さに、田舎暮らしの私は、やはりイオンモールは、平日に行くところと思って、書店で妻の用事が済む間に、選書していると見つかるもので、作家の半藤一利氏の文を集めた『歴史と人生』の新書版を見つけ購入した。モール内は、かかる場所も無く、駐車場の車で読書しながら待っているの間に、パラパラと・・・、冒頭の司馬遼太郎さんと半藤氏との会話て語られた言葉に目が止まった。
半藤氏が司馬氏に「国民のうち80%、90%が合意できることがありますか?」と聞いた。その返事は、以下です。
(以下、本より)
「それは君ね、自然をこれ以上壊さないということだよ。もとに戻せたいったって無理だから、ここまで許すことにしよう。しかしこれ以上はもう壊さないことを、日本国民が全部で合意しようじゃないか。そうしなければ、われわれは子孫に顔向けができないじゃないか」
(以上、『歴史と人生』より転載)
その後に語った言葉が、冒頭の一文です。この会話は、司馬遼太郎氏が亡くなる1年前のことだそうで、ほんとに最後まで元気に人と語っておられたこと学校伝わってきます。
日本の自然、これから北海道から始まる紅葉は、だんだんと南下して、日本列島を"秋色"に染めていきます。九州は、11月下旬から、高地から平地へと下がってきます。晩秋の日本の美しさは、格別と思います。
司馬遼太郎氏は、日本の自然保護を最後に語っていたことを知り、荒れる中山間地域は、過疎と高齢化、人口減少学校原因ですが、今回の衆議院選挙ても、地方再生、創生が訴えられたが、今のままでは、人生減少の流れは変わらない。
都市部と地方の情報格差を平準化して、テレワークを活用して地方は人が移動できるように、5Gの普及を加速化してほしいですね。私の地域にもやっと光ファイバー網が敷かれましたが、やはり維持するには、固定経費となる月額料金が必要であります。年金生活者には、ちょっとハードルが高いですが、仕事する若い世代は高くても使わなけばならないので、もっと使いやすく(都市並の低料金に)する必要があります。都市部と地方の情報格差解消は、まだまだ課題があります。
話は戻りますが、自然保護をするにも若い世代が必要です。豊か自然は、地方にあります。若者たちが、地方(中山間地域に)でも暮らしやすい環境を整えていき、情報格差を無くし、地方経済を活性化することが、これから政府に望むことです。
<画策は短期決戦>地域の出来事から学ぶ。「相手の「善意」に期待をかけるな!」(韓非子)
2021年09月18日
<画策は短期決戦>地域の出来事から学ぶ。「相手の「善意」に期待をかけるな!」(韓非子)
地域の出来事を考えていて中国古典の『韓非子』思い出し、久しぶりにの解説書『韓非子を見よ!』を読み始めた。
パラパラと開くと、?、このエピソードはすごい!
で紹介されていた、ある夫婦のエピソードは、
(以下、本より)
衛の国の夫婦が神様にお祈りをした。妻が祈るのには、
「どうか神様、わたしに百束の布をお恵みください」
「ばかに少ないな」夫が聞くと、妻は、こう答えた。
「これより多いと、あなたが妾を持つようになるからですわ」
同じ家に住む夫婦でさえ、それぞれの立場によってこれだけ利益が違うのである。
(以上、『韓非子を見よ!』より)
人それぞれ求める利益は、違っている事を、夫婦の神頼みのエピソードが表している。『韓非子』は、人は悪意(我欲)を持って生きていると説いているそうだ。
これを逆手に取った韓非子の教えが、以下です。
「相手が背かないことに期待をかけるのではなく、背こうにも背けないような態勢をつくりあげる。相手がペテンを使わないことに期待をかけるのではなく、使おうにも使えないような態勢をつくりあげる。これが名君というものだ」
(以上、本より)
ここ最近の地域の出来事から考えるに、
短期決戦の場合は、策略は効果を生むが、少し時間が経つと、画策者の本意が、だんだん言動から周りに伝わり、さらに時間が経つと、どんな利益を求めているのかも知れ渡るもの。
策略は、誰がやったか分からないような短期間で決着に持ち込まないと、ボロが出て、失敗に終わるどころか、信用まで落としてしまう。
策略は、短期の収束予定が、じわじわと手続きに時間がかかったり、社会情勢(コロナ禍)で、人を集める場を逸したりすると、ボロが出てしまう。
私の地域であった出来事を、この韓非子の視点で分析すると、「時間を要したことで、周りが理解し態勢(周知)が整った、大義ある号令(策略)が、萎んで我欲になり下がった」と判明し、会議に集まった役職は、とても冷静に対応して、権力者の画策は失敗した。
策略は、誰が首謀者分からないよう徹底し、実行は短期決戦でなければならない。また慌てる(言い訳、威圧)と、さらに時間を要することになり、ボロが傍からこぼれ落ちる。
我欲の結末は、みんな同じような結末になってしまう。人間の能力の限界は、そんなものなのかもしれません。
地域の出来事を考えていて中国古典の『韓非子』思い出し、久しぶりにの解説書『韓非子を見よ!』を読み始めた。
パラパラと開くと、?、このエピソードはすごい!
で紹介されていた、ある夫婦のエピソードは、
(以下、本より)
衛の国の夫婦が神様にお祈りをした。妻が祈るのには、
「どうか神様、わたしに百束の布をお恵みください」
「ばかに少ないな」夫が聞くと、妻は、こう答えた。
「これより多いと、あなたが妾を持つようになるからですわ」
同じ家に住む夫婦でさえ、それぞれの立場によってこれだけ利益が違うのである。
(以上、『韓非子を見よ!』より)
人それぞれ求める利益は、違っている事を、夫婦の神頼みのエピソードが表している。『韓非子』は、人は悪意(我欲)を持って生きていると説いているそうだ。
これを逆手に取った韓非子の教えが、以下です。
「相手が背かないことに期待をかけるのではなく、背こうにも背けないような態勢をつくりあげる。相手がペテンを使わないことに期待をかけるのではなく、使おうにも使えないような態勢をつくりあげる。これが名君というものだ」
(以上、本より)
ここ最近の地域の出来事から考えるに、
短期決戦の場合は、策略は効果を生むが、少し時間が経つと、画策者の本意が、だんだん言動から周りに伝わり、さらに時間が経つと、どんな利益を求めているのかも知れ渡るもの。
策略は、誰がやったか分からないような短期間で決着に持ち込まないと、ボロが出て、失敗に終わるどころか、信用まで落としてしまう。
策略は、短期の収束予定が、じわじわと手続きに時間がかかったり、社会情勢(コロナ禍)で、人を集める場を逸したりすると、ボロが出てしまう。
私の地域であった出来事を、この韓非子の視点で分析すると、「時間を要したことで、周りが理解し態勢(周知)が整った、大義ある号令(策略)が、萎んで我欲になり下がった」と判明し、会議に集まった役職は、とても冷静に対応して、権力者の画策は失敗した。
策略は、誰が首謀者分からないよう徹底し、実行は短期決戦でなければならない。また慌てる(言い訳、威圧)と、さらに時間を要することになり、ボロが傍からこぼれ落ちる。
我欲の結末は、みんな同じような結末になってしまう。人間の能力の限界は、そんなものなのかもしれません。
「時に赴く」と「四時軒」:易経と横井小楠。<地域の人の頭の中にある生きる季節の知恵に学ぶ>
2021年04月06日
「時に赴く」と「四時軒」:易経と横井小楠。<地域の人の頭の中にある生きる季節の知恵に学ぶ>
今朝のウォーキングは12kmほどを歩きました。早足ではなく、時速5km/hくらいでしょうか。ぼちぼちと歩くと、けっこう距離も延びるものです。
さて、昨日に初めて語る人がいて、語ってみると同級生の従兄弟の方で、私の地元にも縁が深く、「応援してますよ」と励まされた。地域を時折回ると意外な出会いがあるものです。
こんな出会いもタイミング(間)があるように思います。
今日は4月5日、『易経一日一言』に書かれたことは、
(以下、本より)
時に赴(おもむ)く
変通とは時に赴くものなり。
【訳文】
変化に通じていくとは、冬が春になって種を蒔き、順調に暖かくなり、種が芽生え、成長することである。
「時に赴く」とは、時に背かず、適した行いをすること。種蒔きでいえば、春を待って蒔くということである。
時に趣くならば、物事はより良く変化して、目的を達することができるだろう。
(以上、『易経一日一言』より)
私は種蒔きはしていませんが、毎年同じ時期に同じ行いを繰り返す。地道に、コツコツとやり続けていけば、目的に近づくことが可能となる。
春夏秋冬、毎年の季節は変わらずに来る。春に種蒔き、夏に成長して、秋に実りを得る。冬は我慢、特に今年の冬は寒かったですから、春の息吹は待ち遠しい。
横井小楠の私塾は「四時軒」と称していました。四時は、季節の意味があります。毎年変わらずに農家の人は稲作取り組む。人は、季節の変化に合わせて作業する。政治もまた、季節に合わせて役割を果たす。
行政は、地域社会の季節に合わせて政策を進めることが大事。昨日の出会いでの会話から、地域を時期に合わせて回る意味はあると思いました。
「時に赴く」と「四時軒」
地域の季節を知ることは大事ですし、人と語ることが必要と思いました。
今は、コロナで人が集うことが難しい時代、ならば出向き語る機会を自ら創るのが必要なことと思います。
今朝のウォーキングは12kmほどを歩きました。早足ではなく、時速5km/hくらいでしょうか。ぼちぼちと歩くと、けっこう距離も延びるものです。
さて、昨日に初めて語る人がいて、語ってみると同級生の従兄弟の方で、私の地元にも縁が深く、「応援してますよ」と励まされた。地域を時折回ると意外な出会いがあるものです。
こんな出会いもタイミング(間)があるように思います。
今日は4月5日、『易経一日一言』に書かれたことは、
(以下、本より)
時に赴(おもむ)く
変通とは時に赴くものなり。
【訳文】
変化に通じていくとは、冬が春になって種を蒔き、順調に暖かくなり、種が芽生え、成長することである。
「時に赴く」とは、時に背かず、適した行いをすること。種蒔きでいえば、春を待って蒔くということである。
時に趣くならば、物事はより良く変化して、目的を達することができるだろう。
(以上、『易経一日一言』より)
私は種蒔きはしていませんが、毎年同じ時期に同じ行いを繰り返す。地道に、コツコツとやり続けていけば、目的に近づくことが可能となる。
春夏秋冬、毎年の季節は変わらずに来る。春に種蒔き、夏に成長して、秋に実りを得る。冬は我慢、特に今年の冬は寒かったですから、春の息吹は待ち遠しい。
横井小楠の私塾は「四時軒」と称していました。四時は、季節の意味があります。毎年変わらずに農家の人は稲作取り組む。人は、季節の変化に合わせて作業する。政治もまた、季節に合わせて役割を果たす。
行政は、地域社会の季節に合わせて政策を進めることが大事。昨日の出会いでの会話から、地域を時期に合わせて回る意味はあると思いました。
「時に赴く」と「四時軒」
地域の季節を知ることは大事ですし、人と語ることが必要と思いました。
今は、コロナで人が集うことが難しい時代、ならば出向き語る機会を自ら創るのが必要なことと思います。
<夫婦別姓・官僚高額接待>選挙のためなら"主義主張"も隠す。それで良いのでしょうか?〜みんなお地蔵さになってきた〜
2021年03月14日
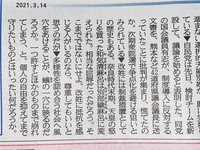
<夫婦別姓・官僚高額接待>選挙のためなら"主義主張"も隠す。それで良いのでしょうか?〜みんなお地蔵さになってきた〜
自民党は、夫婦別姓を反対する有志議員が、熊本系を含む42都道府県議会議長へ、制度導入に反対する分書を送ったことに批判が集まり、慌てた。そこで、先日検討チームを新設して、議論を始めるという・・・
(以上、熊日『人生面』より抜粋)
今年は、必ず選挙があるので、総務省官僚接待問題、オリンピック組織委員会の会長交代劇、さらに夫婦別姓導入に物議を醸した各県議会議長への導入反対文書、等々。
選挙を見据えて、トゲ抜き地蔵のように、大人しくなってきた。
それだけ、選挙前のモードになりつつあるのでしょう。ワクチンの接種も始まり、任期4年末になるであろう衆議院解散、熊本でも動きが活発になっています。
私は、夫婦別姓導入論議含め、さまざまな主義主張をどしどし出して、国民の審判を受けてほしいですね。

40年前の"ギャフン!"という体験を、今日の網津小学校の戦争講話の準備で思い出しました。(人間は、世のチリのようです)
2021年02月25日
40年前の"ギャフン!"という体験を、今日の網津小学校の戦争講話の準備で思い出しました。(人間は、世のチリのようです)
私は、建築の専門学校「専修学校熊本YMCA学院建築科」に通いました。そのおかげで、一級建築士事務所を30年やってこれました。
私が、熊本YMCA学園建築科を選んだ条件の一つに、日本YMCAとフィリピンYMCAの交流で、日本から学生が春休みに「ワークキャンプ」体験(45日間)ができることがありました。
私は、とにかく一回海外からに出たかった!
熊本弁なら"わさもん"でしょうか!
退学受験の失敗から、いったん社会人になりますが・・・んー!
浪人、社会人、浪人、から専門学校へ
決めたキーワードは、フィリピンYMCAとの交流でした。
40年前、オイルショック後の厳しい時、父(元海軍)を説得して日本YMCA代表の20人(熊本は、変わり者3人)で、マニラへ。
フィリピンYMCAと日本YMCAとのセレモニーを終えて、ミンダナオ島のダバオ市に行き、ダウンタウンの小学校がボランティア活動の拠点なので、連れて行かれました。
初日の歓迎と罵倒する言葉に、唖然とします。
フィリピンYMCAのお偉方から帰った後始末、小学校周りの人が集まり、明日からのボランティア活動(現地1ヶ月間で、公民館建設、水道管敷設、バスケットゴール製作)をするのですが、"宴もたけなわ!"なり70歳を超える古老が壇上に上がり(主催者の予定外)語った言葉は、
「俺の娘は、戦争で日本軍に殺された、お前ら何しに来た、日本へ帰れ!」
でした。会場が、騒然となるかと思うと、会場にいる大人たちの視線が、全部我々を見ていることを知りました。
ダバオ市は、太平洋戦争の時、フィリピンへ日本軍が最初に上陸し、当時の統治国のアメリカ軍と、凄まじい戦闘を行なったのが、ダバオのでした。それを知らされずに、ただ日本YMCAとフィリピンYMCAの交流をする学生の集まり、すごい!ショックでした。
>俺の娘は日本軍に殺された!
本日の網津小学校の戦争のお話は、父と兄2人は、海軍に志願して行きました。父は数え16歳、満15歳の現代なら高校1年生でした。兄の戦死を知らずに志願しました。父が志願した頃、日本の敗戦のきっかけとなったソロモン諸島の海戦で叔父は亡くなりました。24歳でした。
今回の小学校の戦争講話で「私が生きて来て聞きたい"戦争"の話を思いだしました。みなさんの参考になるかわかりませんが、お読みいただけるとありがたいです。
今日の講話で、
終戦の直前、8月12・13日の熊本大空襲では、試作的に作られた、ベトナムの森林を焼くために開発されたナパーム弾が使われています。ナパーム弾は、実はベトナム戦争のためでなく、日本の家屋を焼き払うために開発されたと聞き、驚愕しました。
私は、建築の専門学校「専修学校熊本YMCA学院建築科」に通いました。そのおかげで、一級建築士事務所を30年やってこれました。
私が、熊本YMCA学園建築科を選んだ条件の一つに、日本YMCAとフィリピンYMCAの交流で、日本から学生が春休みに「ワークキャンプ」体験(45日間)ができることがありました。
私は、とにかく一回海外からに出たかった!
熊本弁なら"わさもん"でしょうか!
退学受験の失敗から、いったん社会人になりますが・・・んー!
浪人、社会人、浪人、から専門学校へ
決めたキーワードは、フィリピンYMCAとの交流でした。
40年前、オイルショック後の厳しい時、父(元海軍)を説得して日本YMCA代表の20人(熊本は、変わり者3人)で、マニラへ。
フィリピンYMCAと日本YMCAとのセレモニーを終えて、ミンダナオ島のダバオ市に行き、ダウンタウンの小学校がボランティア活動の拠点なので、連れて行かれました。
初日の歓迎と罵倒する言葉に、唖然とします。
フィリピンYMCAのお偉方から帰った後始末、小学校周りの人が集まり、明日からのボランティア活動(現地1ヶ月間で、公民館建設、水道管敷設、バスケットゴール製作)をするのですが、"宴もたけなわ!"なり70歳を超える古老が壇上に上がり(主催者の予定外)語った言葉は、
「俺の娘は、戦争で日本軍に殺された、お前ら何しに来た、日本へ帰れ!」
でした。会場が、騒然となるかと思うと、会場にいる大人たちの視線が、全部我々を見ていることを知りました。
ダバオ市は、太平洋戦争の時、フィリピンへ日本軍が最初に上陸し、当時の統治国のアメリカ軍と、凄まじい戦闘を行なったのが、ダバオのでした。それを知らされずに、ただ日本YMCAとフィリピンYMCAの交流をする学生の集まり、すごい!ショックでした。
>俺の娘は日本軍に殺された!
本日の網津小学校の戦争のお話は、父と兄2人は、海軍に志願して行きました。父は数え16歳、満15歳の現代なら高校1年生でした。兄の戦死を知らずに志願しました。父が志願した頃、日本の敗戦のきっかけとなったソロモン諸島の海戦で叔父は亡くなりました。24歳でした。
今回の小学校の戦争講話で「私が生きて来て聞きたい"戦争"の話を思いだしました。みなさんの参考になるかわかりませんが、お読みいただけるとありがたいです。
今日の講話で、
終戦の直前、8月12・13日の熊本大空襲では、試作的に作られた、ベトナムの森林を焼くために開発されたナパーム弾が使われています。ナパーム弾は、実はベトナム戦争のためでなく、日本の家屋を焼き払うために開発されたと聞き、驚愕しました。
川辺川ダム中止から10年、治水議論(空欄)はありましたが、球磨川水害対策は何もされなかった!
2020年07月07日
河辺川ダム中止から10年、治水議論(空欄)はありましたが、球磨川水害対策は何もされなかった!
河辺川ダムを討論した潮谷県政が終わり次期県政を担う知事選から12年、環境保護論議から河辺川ダム中止を、蒲島知事は決断されました。今春の熊本県知事選挙では、コロナ、コロナで、選挙線も、政策提言もなく、終わりました。
熊本は、水俣病と河辺川ダム(球磨川治水・利水)が、過去40年の政治課題なのに、両候補の議論がありませんでした。
荒瀬ダムは解体されました。
ならば、球磨川治水と河辺川ダム中止、熊本県知事が常に緊張感を持ってやられてきたのか?
疑問に思っています。
人吉の市民活動仲間たちの家々は、1階が水没、ひどいところは2階窓まで泥水が来た!と。
政治は危機管理、何を首長が目指しているのか、今後の検証から、リーダーの政治理念が問われると思います。
河辺川ダムを討論した潮谷県政が終わり次期県政を担う知事選から12年、環境保護論議から河辺川ダム中止を、蒲島知事は決断されました。今春の熊本県知事選挙では、コロナ、コロナで、選挙線も、政策提言もなく、終わりました。
熊本は、水俣病と河辺川ダム(球磨川治水・利水)が、過去40年の政治課題なのに、両候補の議論がありませんでした。
荒瀬ダムは解体されました。
ならば、球磨川治水と河辺川ダム中止、熊本県知事が常に緊張感を持ってやられてきたのか?
疑問に思っています。
人吉の市民活動仲間たちの家々は、1階が水没、ひどいところは2階窓まで泥水が来た!と。
政治は危機管理、何を首長が目指しているのか、今後の検証から、リーダーの政治理念が問われると思います。
<熊本県知事選挙>益々集中する県庁機能が心配。防災対応拠点は本庁舎(熊本市)から離すべきでは?
2020年03月18日
<熊本県知事選挙>益々集中する県庁機能が心配。防災対応拠点は本庁舎(熊本市)から離すべきでは?
今朝の朝刊に、熊本県知事選の候補者緊急討論会が開催され、その内容が整理され、掲載された。ぜひ、県民の皆さんは読んで、投票の判断材料にして欲しい。
一つ疑問が、ある。
100億円もかかる県防災センター等の建設に、二人の候補が言及しなかった。
県市連携と施設分散が必要と思うが、議論になっていない。
7年前、日韓交流で、忠清南道と熊本県の交流30周年で、韓国へ行って驚いたことがあります。
忠清南道の道都・大田(テジョン)市が、政令市になったのを機に、忠清南道は、道庁を太田市から、移転させた。それは、太田市は、政令市になり、権限等々が、道並になったのので、それ以外の忠清南道の自治に担う新庁舎が建設中だった。忠清南道の新庁舎周りは、原野を新たに開発した地域にあった。
それを見てきた、知事や県議会、当時訪問団には、現熊本市長の大西一史氏も県議として参加されていました。
今回の熊本県の庁舎が、未だに熊本都市圏の東部には位置していますが、人口の分布状況の重心に位置する点は県庁近くになるという。
すぐに、忠清南道のように県庁を、太田(テジョン)市外移転することは無理かもしれないが、20年計画くらいで、県央か、県南でも庁舎を移すと言う発想がなければ、現在の都市集中は変わらずに、なってしまうように思います。
インターネットは、もともと冷戦時代、軍機能を分散させるためにかいはいさた。それは、攻撃対象を集中させないことが目的だった。そのインターネットは、G7の首脳がテレビ会議をでき、通訳・翻訳まで担うICT技術となって、現代社会に浸透している。
本庁機能を分散させることは、現代のICT技術を使えば、遠隔地とのテレビ会議話出来る。危機管理対応にも、必要ような問集中回避は、これからの自治体経営必要な発想ではないのか。100億円かける防災センター等の建設は、インターチェンジに隣接する場所とか、あるいは空港の敷地とか、もっと考える必要があると思う。
今回の熊本県知事選挙の論争に、県庁移転の発想が議論に起こることを期待している。


今朝の朝刊に、熊本県知事選の候補者緊急討論会が開催され、その内容が整理され、掲載された。ぜひ、県民の皆さんは読んで、投票の判断材料にして欲しい。
一つ疑問が、ある。
100億円もかかる県防災センター等の建設に、二人の候補が言及しなかった。
県市連携と施設分散が必要と思うが、議論になっていない。
7年前、日韓交流で、忠清南道と熊本県の交流30周年で、韓国へ行って驚いたことがあります。
忠清南道の道都・大田(テジョン)市が、政令市になったのを機に、忠清南道は、道庁を太田市から、移転させた。それは、太田市は、政令市になり、権限等々が、道並になったのので、それ以外の忠清南道の自治に担う新庁舎が建設中だった。忠清南道の新庁舎周りは、原野を新たに開発した地域にあった。
それを見てきた、知事や県議会、当時訪問団には、現熊本市長の大西一史氏も県議として参加されていました。
今回の熊本県の庁舎が、未だに熊本都市圏の東部には位置していますが、人口の分布状況の重心に位置する点は県庁近くになるという。
すぐに、忠清南道のように県庁を、太田(テジョン)市外移転することは無理かもしれないが、20年計画くらいで、県央か、県南でも庁舎を移すと言う発想がなければ、現在の都市集中は変わらずに、なってしまうように思います。
インターネットは、もともと冷戦時代、軍機能を分散させるためにかいはいさた。それは、攻撃対象を集中させないことが目的だった。そのインターネットは、G7の首脳がテレビ会議をでき、通訳・翻訳まで担うICT技術となって、現代社会に浸透している。
本庁機能を分散させることは、現代のICT技術を使えば、遠隔地とのテレビ会議話出来る。危機管理対応にも、必要ような問集中回避は、これからの自治体経営必要な発想ではないのか。100億円かける防災センター等の建設は、インターチェンジに隣接する場所とか、あるいは空港の敷地とか、もっと考える必要があると思う。
今回の熊本県知事選挙の論争に、県庁移転の発想が議論に起こることを期待している。


<熊本県知事選挙>けじめの問題ですね。つまり、男らしい男は、けじめをつける。〜城山三郎〜
2020年03月15日
<熊本県知事選挙>けじめの問題ですね。つまり、男らしい男は、けじめをつける。〜城山三郎〜
逃げる男は、後々、評価はガクッと下がる。リーダーとは、30年後、50年後に評価されるものです。
城山三郎の著書の名文を集めた本『人生の流儀』にある一文、
(以下、本より)
男にとって大切なことは愚直さですよね。もう明らかにそういうことをしたら損だということがわかってても、そういうことをしなくちゃいけないという使命感なり理想があって、愚直に生きていく。その愚直さということを、もう少し言いかえると、けじめの問題ですね。つまり、男らしい男は、けじめをつけるっていうことです。
(以上、『失われた志』)
要は、逃げる男は、後々評価はガクッと下がるのです。志が問われるのが、勝負の世界ですね。
ケネディ大統領は、政治の評価は、50年後、100年後に後世の人たちがするものです、と語っています。
現代のりーの孫か、ひ孫の世代に、「あなたの祖父は、どうだった」、「あなたの曽祖父は、選挙で討論会にも出ずに、逃げた?」と言われることもあります。
要は、男とは何か?
子孫から、疎まれない生き方も必要ではないか?
勝てば官軍、それで良いのでしょうか?
ほんと孤軍奮闘の幸山政史さんば愚直に、真面目に、県下を回り、政策を訴えておられます。あと残り1週間、縁ある方に、直接お願いをしただけでいます。ほんと、投票箱の蓋が閉まるまで、応援要請をし続けます。
逃げる男は、後々、評価はガクッと下がる。リーダーとは、30年後、50年後に評価されるものです。
城山三郎の著書の名文を集めた本『人生の流儀』にある一文、
(以下、本より)
男にとって大切なことは愚直さですよね。もう明らかにそういうことをしたら損だということがわかってても、そういうことをしなくちゃいけないという使命感なり理想があって、愚直に生きていく。その愚直さということを、もう少し言いかえると、けじめの問題ですね。つまり、男らしい男は、けじめをつけるっていうことです。
(以上、『失われた志』)
要は、逃げる男は、後々評価はガクッと下がるのです。志が問われるのが、勝負の世界ですね。
ケネディ大統領は、政治の評価は、50年後、100年後に後世の人たちがするものです、と語っています。
現代のりーの孫か、ひ孫の世代に、「あなたの祖父は、どうだった」、「あなたの曽祖父は、選挙で討論会にも出ずに、逃げた?」と言われることもあります。
要は、男とは何か?
子孫から、疎まれない生き方も必要ではないか?
勝てば官軍、それで良いのでしょうか?
ほんと孤軍奮闘の幸山政史さんば愚直に、真面目に、県下を回り、政策を訴えておられます。あと残り1週間、縁ある方に、直接お願いをしただけでいます。ほんと、投票箱の蓋が閉まるまで、応援要請をし続けます。
<森林集約化の調査>午前中は、山林の集約化のための現地調査に同行しました。
2019年10月08日
<森林集約化の調査>午前中は、山林の集約化のための現地調査に同行しました。
人が山に入らないと、こんなに荒れるのか!と思いました。
ナタで、倒れた竹や雑木を切って登ります。そんな荒れた山の所用林の境をどうやって調べるかと言いますと、GPSを使い、20年ほど前に地籍調査を地図に落としてあり、数十センチ単位で位置が確認できます。優れものの位置確認の機械があるから、荒れた林でもわかるのです。
杉檜が植林してある場所を確認し、材の大きさ(直径、高さ)直径5mの円内に何本在るかを調べます。杉檜の植林してある範囲は、現地確認かどうしても必要なので、道なき道を歩いて山を登り、下り、大変な調査です。
赤い手袋の横の四角の杭が、20年前の地籍調査の跡です。
そもそも、今回の調査は、山林を集約化(山林団地)にして、地域で林業維持団体を作り、間伐、伐採、植林、等々を行うと作業費用を国が支援する制度のための前準備です。
初めて同行しましたが、地域の林研グループの献身的なご協力おかげで、着実に進んでいます。調査が終わると、山林団地の維持管理計画を国に提出して、事業が始まります。
移動の途中、イノシシが子育てをした巣の跡見つけました。巣は、こんもりした草木を集めた形で、大きさを理解してもらうために赤い手袋と写真を撮りました。
全部調べるのは、あと1年近くかかりますが、地域の山林の状況がわかり、私も時々同行しようと思いました。













人が山に入らないと、こんなに荒れるのか!と思いました。
ナタで、倒れた竹や雑木を切って登ります。そんな荒れた山の所用林の境をどうやって調べるかと言いますと、GPSを使い、20年ほど前に地籍調査を地図に落としてあり、数十センチ単位で位置が確認できます。優れものの位置確認の機械があるから、荒れた林でもわかるのです。
杉檜が植林してある場所を確認し、材の大きさ(直径、高さ)直径5mの円内に何本在るかを調べます。杉檜の植林してある範囲は、現地確認かどうしても必要なので、道なき道を歩いて山を登り、下り、大変な調査です。
赤い手袋の横の四角の杭が、20年前の地籍調査の跡です。
そもそも、今回の調査は、山林を集約化(山林団地)にして、地域で林業維持団体を作り、間伐、伐採、植林、等々を行うと作業費用を国が支援する制度のための前準備です。
初めて同行しましたが、地域の林研グループの献身的なご協力おかげで、着実に進んでいます。調査が終わると、山林団地の維持管理計画を国に提出して、事業が始まります。
移動の途中、イノシシが子育てをした巣の跡見つけました。巣は、こんもりした草木を集めた形で、大きさを理解してもらうために赤い手袋と写真を撮りました。
全部調べるのは、あと1年近くかかりますが、地域の山林の状況がわかり、私も時々同行しようと思いました。













<空港民営化>熊本空港利用者の調査研究がもっと必要と感じます。
2019年07月14日
<空港民営化>熊本空港利用者の調査研究がもっと必要と感じます。
熊日に熊本空港民営化の代表企業・三井不動産の久一洋康氏が、空港経営について、「熊本空港は、九州各県の観光地にアクセスしやすく魅力的な場所だ。2051年までに国際線の旅客数を10倍以上の175万人まで増やしたい」とあった。
国際線は、東アジアの経済発展で増えると思いますが、県民の利用状況は、県北は福岡空港、人吉球磨は鹿児島空港が多いと聞きます。以前、宮崎県の椎葉、五ヶ瀬、高千穂を訪れたとき「空港は何処を使われますか?」と尋ねると「熊本空港。お歳暮も熊本です」との返事だった。
熊本空港経営の久一氏は、「熊本市街地からのバスルート拡充と駐車場の立体化を目指す」とも語っていました。別の話題だが、大西一史熊本市長が「福岡の都市高速のような空間を利用した道路が必要。高架下にバス専用道路を走らせるなど大胆な発想を具体的に検討する」からも地方都市はバス活用が重要と考えます。
八代からの熊本空港直行バス「ばんぺいゆ号」はいつも満席の状況、天草からの空港リムジンも利用者が多い。現況と人口変化を踏まえ、九州中央部の空港利用者の調査研究がもっと必要と思っています。
上記のような私の意見です。感想等々あれば、ありがたいです。
熊日に熊本空港民営化の代表企業・三井不動産の久一洋康氏が、空港経営について、「熊本空港は、九州各県の観光地にアクセスしやすく魅力的な場所だ。2051年までに国際線の旅客数を10倍以上の175万人まで増やしたい」とあった。
国際線は、東アジアの経済発展で増えると思いますが、県民の利用状況は、県北は福岡空港、人吉球磨は鹿児島空港が多いと聞きます。以前、宮崎県の椎葉、五ヶ瀬、高千穂を訪れたとき「空港は何処を使われますか?」と尋ねると「熊本空港。お歳暮も熊本です」との返事だった。
熊本空港経営の久一氏は、「熊本市街地からのバスルート拡充と駐車場の立体化を目指す」とも語っていました。別の話題だが、大西一史熊本市長が「福岡の都市高速のような空間を利用した道路が必要。高架下にバス専用道路を走らせるなど大胆な発想を具体的に検討する」からも地方都市はバス活用が重要と考えます。
八代からの熊本空港直行バス「ばんぺいゆ号」はいつも満席の状況、天草からの空港リムジンも利用者が多い。現況と人口変化を踏まえ、九州中央部の空港利用者の調査研究がもっと必要と思っています。
上記のような私の意見です。感想等々あれば、ありがたいです。


 メンバー登録はこちら
メンバー登録はこちら



