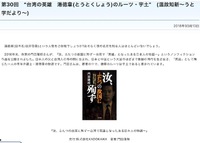<聖徳太子の17条の憲法>いかなる人も、他人を嫉(にく)み妬(ねた)むことがあってはならぬ。
2014年07月15日
<聖徳太子の17条の憲法>いかなる人も、他人を嫉(にく)み妬(ねた)むことがあってはならぬ。
おはようございます。梅雨空の熊本ですが、気温は高くなくすがすがしい朝です。今朝の友人のfacebookのコメントに聖徳太子の17条憲法が、紹介されていました。先月、中国古典輪読会の先輩から「17条の憲法」の解説本をいただきました。今朝開き、条文を読む中で気づかされました。
「人、嫉(にく)まず!」
人の縁は、濃さにより相手を思いやることが深まると思います。薄い人間関係は、相手のことを思いやることもないのではないか、゛思いやること゛関心を持ち続けることが大事だなと思いました。
<第14条>
十四に曰く、群臣百寮、嫉妬有ることなかれ。我れ既に人を嫉(にく)めば、人亦我れを嫉む。嫉妬の患い其の極を知らず。所以に、智己れに勝れば則ち悦ばず、才己れに優れば則ち嫉(にく)み妬む。是を以て、五百(いほ)の乃(いまし)今、賢(さかしきひと)に遭はしむとも、千載にして以て一聖を待つこと難し。其れ賢誠を得ずんば、何を以てか国を治めん。
〔訳〕
第14条。いかなる人も、他人を嫉(にく)み妬(ねた)むことがあってはならぬ。自分が人を嫉めば、人もまた自分を嫉むであろう。このような嫉妬心の弊害は、実は際限のないものであって、他人が自分よりも智が働くようであれば面白くなく、才能が自分より優れていればまた嫉み妬む。このようなことでは(優れた人に嫉妬し、誹謗・中傷などで出る杭を打つようでは)、五百年にして賢者に遭えたとしても、千年にして一人巡りあえるかという聖人の出現を待つことは難しい。しかし、そのような優れた人物を得なければ、どうしても国を治めることができようか。
補足の解説には、つまらぬ嫉妬心から有為の人材を不遇に貶める悪弊を戒め、組織や国家を治める聖賢への待望が述べられています。聖賢は、聖は孔子、賢は孟子を表現したとありました。
人間関係は、相互作用と言います。相手の立場に配慮できるかどうか? 聖賢は、その人間関係を尊重しつつ、「自分の思いをどう伝えるか」に苦心したのだと思います。
関わる人々の対応は、自分の行いの裏返しと肝に銘じて、日々の言動に気を付けることが大事と、1450年の時を越えて、人間の行動の本質を伝えているように思いました。日々反省、今日も反省が大事と思います。
*参考資料:永崎淡泉著「十七条憲法」(中島弘文堂)
おはようございます。梅雨空の熊本ですが、気温は高くなくすがすがしい朝です。今朝の友人のfacebookのコメントに聖徳太子の17条憲法が、紹介されていました。先月、中国古典輪読会の先輩から「17条の憲法」の解説本をいただきました。今朝開き、条文を読む中で気づかされました。
「人、嫉(にく)まず!」
人の縁は、濃さにより相手を思いやることが深まると思います。薄い人間関係は、相手のことを思いやることもないのではないか、゛思いやること゛関心を持ち続けることが大事だなと思いました。
<第14条>
十四に曰く、群臣百寮、嫉妬有ることなかれ。我れ既に人を嫉(にく)めば、人亦我れを嫉む。嫉妬の患い其の極を知らず。所以に、智己れに勝れば則ち悦ばず、才己れに優れば則ち嫉(にく)み妬む。是を以て、五百(いほ)の乃(いまし)今、賢(さかしきひと)に遭はしむとも、千載にして以て一聖を待つこと難し。其れ賢誠を得ずんば、何を以てか国を治めん。
〔訳〕
第14条。いかなる人も、他人を嫉(にく)み妬(ねた)むことがあってはならぬ。自分が人を嫉めば、人もまた自分を嫉むであろう。このような嫉妬心の弊害は、実は際限のないものであって、他人が自分よりも智が働くようであれば面白くなく、才能が自分より優れていればまた嫉み妬む。このようなことでは(優れた人に嫉妬し、誹謗・中傷などで出る杭を打つようでは)、五百年にして賢者に遭えたとしても、千年にして一人巡りあえるかという聖人の出現を待つことは難しい。しかし、そのような優れた人物を得なければ、どうしても国を治めることができようか。
補足の解説には、つまらぬ嫉妬心から有為の人材を不遇に貶める悪弊を戒め、組織や国家を治める聖賢への待望が述べられています。聖賢は、聖は孔子、賢は孟子を表現したとありました。
人間関係は、相互作用と言います。相手の立場に配慮できるかどうか? 聖賢は、その人間関係を尊重しつつ、「自分の思いをどう伝えるか」に苦心したのだと思います。
関わる人々の対応は、自分の行いの裏返しと肝に銘じて、日々の言動に気を付けることが大事と、1450年の時を越えて、人間の行動の本質を伝えているように思いました。日々反省、今日も反省が大事と思います。
*参考資料:永崎淡泉著「十七条憲法」(中島弘文堂)
久しぶりに横井小楠記念館「四時軒」に寄りました。
江戸時代、土佐弁は、江戸者が語ることばと区別かつかなかった。〜司馬遼太郎〜
<台湾の英雄は宇土にルーツ>宇土市と台湾の台南市の日台交流の準備が始まっています。
いろんなお話を聴かせていただいた中村青史先生のご逝去を知り、生前の姿を思い出します。
<社会の転機は4代目?>て開いた本『歴史と人生』(半藤一利著)に、軍事や憲法9条に係る文が
司馬遼太郎は、「土方歳三の家はどこですか?」と聞くと、「あ、お大尽(だいじん)の家ですか」と言ったとある。
江戸時代、土佐弁は、江戸者が語ることばと区別かつかなかった。〜司馬遼太郎〜
<台湾の英雄は宇土にルーツ>宇土市と台湾の台南市の日台交流の準備が始まっています。
いろんなお話を聴かせていただいた中村青史先生のご逝去を知り、生前の姿を思い出します。
<社会の転機は4代目?>て開いた本『歴史と人生』(半藤一利著)に、軍事や憲法9条に係る文が
司馬遼太郎は、「土方歳三の家はどこですか?」と聞くと、「あ、お大尽(だいじん)の家ですか」と言ったとある。
Posted by ノグチ(noguchi) at 09:19│Comments(0)
│日本の歴史、世界の歴史
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。