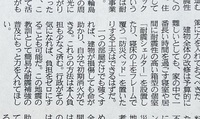<コロナ渦後の地方の国際化>ダイバーシティの学校経営から見える社会
2020年12月12日
<コロナ渦後の地方の国際化>ダイバーシティの学校経営から見える社会
今朝4時5分からのNHKのインタビュー番組「明日への言葉」に、京都精華大学学長のウスビ・サコ氏(マリ共和国出身)が、海外留学生を増やしての大学経営と多国籍の多様性について語られました。
労働現場に欠かすことができなくなった技能実習生、農業実習生の海外からの労働者の皆さん、大学の存続に多国籍化が不可欠になっているのだなぁ、と話を聞いていました。
熊本県内にも、宇土市にも、海外からの技能実習生がいるのが普通になっています。一昨年春の日曜日、桜が咲く時期に開催したフットパス・モニターツアーで見た風景は、桜で人気スポットの宇土市の立岡自然公園には、ベトナム、中国、さらに観光ツアーで韓国の若者たちが、桜の花見で、バーベキューやお弁当開き、散策と、まるで海外の桜の公園にいるようでした。
今年は、コロナ渦で全く違う風景になりましたが、感染が収まれば、また国際的な環境が地方にも戻ると思います。国際化の流れは変わらないので、それを想定してコロナ渦後の対応が必要だなぁ、と今朝の放送を聞きながら考えていました。
今朝4時5分からのNHKのインタビュー番組「明日への言葉」に、京都精華大学学長のウスビ・サコ氏(マリ共和国出身)が、海外留学生を増やしての大学経営と多国籍の多様性について語られました。
労働現場に欠かすことができなくなった技能実習生、農業実習生の海外からの労働者の皆さん、大学の存続に多国籍化が不可欠になっているのだなぁ、と話を聞いていました。
熊本県内にも、宇土市にも、海外からの技能実習生がいるのが普通になっています。一昨年春の日曜日、桜が咲く時期に開催したフットパス・モニターツアーで見た風景は、桜で人気スポットの宇土市の立岡自然公園には、ベトナム、中国、さらに観光ツアーで韓国の若者たちが、桜の花見で、バーベキューやお弁当開き、散策と、まるで海外の桜の公園にいるようでした。
今年は、コロナ渦で全く違う風景になりましたが、感染が収まれば、また国際的な環境が地方にも戻ると思います。国際化の流れは変わらないので、それを想定してコロナ渦後の対応が必要だなぁ、と今朝の放送を聞きながら考えていました。
<第二次世界大戦の検証>一度は行きたかった「大刀洗平和記念館」に行ってきました。
能登半島地震、「倒壊死9割」に愕然となる。何か耐震の工夫が必要。
<熊本城再建>宇土櫓の解体修理に関心を持っています。現場見学会に参加したい。
「耐震シェルター」、「防災ベッド」、一つの部屋だけ強化する。〜福和伸夫名誉教授(名古屋大学)〜
世界のデジタル競争力は、日本は世界32位、しかし韓国は6位だった。日本のデジタル化の取り組みを前へ。
>たとえ100年続いてきた仕組みであったとしても、変えようとする柔軟性を、校長をはじめとする教育関係者は持つべき
能登半島地震、「倒壊死9割」に愕然となる。何か耐震の工夫が必要。
<熊本城再建>宇土櫓の解体修理に関心を持っています。現場見学会に参加したい。
「耐震シェルター」、「防災ベッド」、一つの部屋だけ強化する。〜福和伸夫名誉教授(名古屋大学)〜
世界のデジタル競争力は、日本は世界32位、しかし韓国は6位だった。日本のデジタル化の取り組みを前へ。
>たとえ100年続いてきた仕組みであったとしても、変えようとする柔軟性を、校長をはじめとする教育関係者は持つべき
Posted by ノグチ(noguchi) at 06:40│Comments(0)
│新技術、新潮流
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。