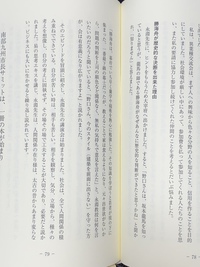文明社会には、青年には青年の、老人には老人の、貢献するべき余地がある。〜渋澤栄一〜
2025年03月07日
<老いてますます学問を>文明社会には、青年には青年の、老人には老人の、貢献するべき余地がある。〜渋澤栄一〜
(昨日の出来事からコメントしました)
文明開花の明治が始まって160年、馬車から汽車さらに自動車から飛行機の時代になって、ますます世界が狭くなったように、科学や技術の発展により、人間の邪魔やは延び、ますます人生は長くなっています。
それこそ、幕末維新で活躍した熊本の政治思想家の横井小楠が暗殺されたのは61才、坂本龍馬は32才でした。私は、龍馬の歳の倍、小楠の歳も越えてしまいました。
人生は短いとは言いますが、戦前からすると、長生きになっています。
渋澤栄一は、以下のように書いています。
>そんな中で、30歳までが勉強の時間であるならば、少なくとも70歳ぐらいまでは働かないと、もったいないではありませんか?
>もし50や55で老いて衰えてしまえば、20年、25年しか働いていないことになります。
>それだけの期間で、何を成し遂げられるでしょう。そして、何かを成すには、学び続けるしかないのです。
(以上、『渋澤栄一100の訓言』より)
男女を問わず、大学進学が当たり前になりました。しかし、日本の大学は、難関大学がいくつも存在しているように、入るは難し、出るは優しの狭き門がいまだにあります。
昨日の防犯パトロール中に、高校無償化の話から、北欧の大学の学費無料の話になった。現役教師から、
「大学は、出るのを難しくしないから、人材が育たない」
と話していました。確かにそうかとは思いますが、社会人でも最初は学ばないと、仕事はできません。
共同通信の論説委員長で、久米宏さんのニュースステーションにも出られた政治評論家の故内田健三氏が80歳を前にして語られた、
「身体は老いるが、精神は成長する。まだまだ勉強です」
を忘れられません。当時私は40代前半でした。
内田健三氏が語られたことと同じ内容が、本日読んだページにありました。
(以下、『渋澤栄一100の訓言』より転載)
しかして文明の老人たるには、
身体はたとい衰弱するとしても、
精神が衰弱せぬようにしたい、
精神を衰弱せぬようにするには学問によるほかない。
(以上、【『論語と算盤』立志と学問】より)
内田健三氏は、東京大学在学中に、学徒動員で戦地に向かい戦った後、戦後すぐは肺病(結核)を患い床に伏された。病気を乗り越えて大学に復帰されたのは6年後だったと聞きました。なので、30歳まで大学で学ばれました。
>文明社会には、青年には青年の、老人には老人の、貢献するべき余地がある。
老いても益々学ぶ意欲を持たなければ、と朝から考えました。
私の40代前半ころの、昼は社会活動に参加して、夜に設計の仕事をした体力は流石に今はなくなりましたが、学ぶ意欲がなくならないようしなければと思います。
話が長くなりました。明日からの宇土半島一周ウォークの準備を、午後からやります。さて、完歩できるか、足を状態を労わりつつ頑張ります。
(昨日の出来事からコメントしました)
文明開花の明治が始まって160年、馬車から汽車さらに自動車から飛行機の時代になって、ますます世界が狭くなったように、科学や技術の発展により、人間の邪魔やは延び、ますます人生は長くなっています。
それこそ、幕末維新で活躍した熊本の政治思想家の横井小楠が暗殺されたのは61才、坂本龍馬は32才でした。私は、龍馬の歳の倍、小楠の歳も越えてしまいました。
人生は短いとは言いますが、戦前からすると、長生きになっています。
渋澤栄一は、以下のように書いています。
>そんな中で、30歳までが勉強の時間であるならば、少なくとも70歳ぐらいまでは働かないと、もったいないではありませんか?
>もし50や55で老いて衰えてしまえば、20年、25年しか働いていないことになります。
>それだけの期間で、何を成し遂げられるでしょう。そして、何かを成すには、学び続けるしかないのです。
(以上、『渋澤栄一100の訓言』より)
男女を問わず、大学進学が当たり前になりました。しかし、日本の大学は、難関大学がいくつも存在しているように、入るは難し、出るは優しの狭き門がいまだにあります。
昨日の防犯パトロール中に、高校無償化の話から、北欧の大学の学費無料の話になった。現役教師から、
「大学は、出るのを難しくしないから、人材が育たない」
と話していました。確かにそうかとは思いますが、社会人でも最初は学ばないと、仕事はできません。
共同通信の論説委員長で、久米宏さんのニュースステーションにも出られた政治評論家の故内田健三氏が80歳を前にして語られた、
「身体は老いるが、精神は成長する。まだまだ勉強です」
を忘れられません。当時私は40代前半でした。
内田健三氏が語られたことと同じ内容が、本日読んだページにありました。
(以下、『渋澤栄一100の訓言』より転載)
しかして文明の老人たるには、
身体はたとい衰弱するとしても、
精神が衰弱せぬようにしたい、
精神を衰弱せぬようにするには学問によるほかない。
(以上、【『論語と算盤』立志と学問】より)
内田健三氏は、東京大学在学中に、学徒動員で戦地に向かい戦った後、戦後すぐは肺病(結核)を患い床に伏された。病気を乗り越えて大学に復帰されたのは6年後だったと聞きました。なので、30歳まで大学で学ばれました。
>文明社会には、青年には青年の、老人には老人の、貢献するべき余地がある。
老いても益々学ぶ意欲を持たなければ、と朝から考えました。
私の40代前半ころの、昼は社会活動に参加して、夜に設計の仕事をした体力は流石に今はなくなりましたが、学ぶ意欲がなくならないようしなければと思います。
話が長くなりました。明日からの宇土半島一周ウォークの準備を、午後からやります。さて、完歩できるか、足を状態を労わりつつ頑張ります。
<遊び上手>飽かないから遊びなのであって、飽くのは単なるヒマ(暇)つぶしである。〜田辺聖子著『ダンスと空想』〜
<消費税3%→5%直前の激務>乗り越えれない試練を天は与えない。
<前途多難、日々新たに>算数(計算)通りにならない人生。〜曽野綾子著『中年以後』〜
<人の時のアセス>愚直に生きた夏目漱石、その思考は『老子』を参考にしていた。〜半藤一利〜
<生活習慣と学力>規則正しい生活習慣と本のある家、本を読む習慣。〜岸本裕史〜
老いを楽しむ3人の女性と評論家・樋口恵子さんの「7つのご機嫌のヒント」
<消費税3%→5%直前の激務>乗り越えれない試練を天は与えない。
<前途多難、日々新たに>算数(計算)通りにならない人生。〜曽野綾子著『中年以後』〜
<人の時のアセス>愚直に生きた夏目漱石、その思考は『老子』を参考にしていた。〜半藤一利〜
<生活習慣と学力>規則正しい生活習慣と本のある家、本を読む習慣。〜岸本裕史〜
老いを楽しむ3人の女性と評論家・樋口恵子さんの「7つのご機嫌のヒント」
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。