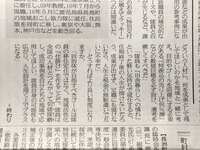鹿児島県長島町の「地域おこし協力隊」の実践は、当初の発想が、他の自治体と全く違っていた。
2017年11月14日


長島町の「地域おこし協力隊」の実践は、当初の発想が、他の自治体と全く違っていた。
長島町に赴任した総務省官僚が、自らの人脈をベースにした町おこしブランと国の制度を活用した地域おこし協力隊スタイルを確立していました。
・楽天の開発とマーケティングスキルを持った若者
・現役大学生(一橋大、東大、慶応大、等々)が中心に主催する塾(松下村塾的発想)の取り組み
・空き家プロジェクトは、官民共同から民間主導へ+空き家保全ビジネス
・過疎地の高校教育支援+ネット高校の取り組み
・関東関西の有名シェフに旬の食材を届けるビジネスの仕組みづくり
・健康増進のスポーツジムを展開するグループ
これが、長島町の地域おこし協力隊のスタイルです。学歴と都市部との人脈は、すこぶる豊富な人材が集まっていました。
田舎で、三年後に活性化の人材になるのではなく、そもそも、都市と田舎でできるビジネスモデルを持った人材を求めて来たから、明石照久さんが熊日新聞に書いた「ビション(ビジネスモデル)を、3年後に実現するために、長島町に移り住んできている感がある」と、全員に感じられました。
1時間ほど、事務所「地方創生室」にいたのですが、とにかく行動か早い。空き家の情報があると、電話が来てすぐ動く。まだまだ、語りつくせないほどありますが、12議会の質問ネタなので、語りません。隊員のその行動力こそ、長島町の地域おこし協力隊の真髄だなと思いました。
とにかく、行って良かったし、何度か通いたいと思います。熊本県立大学名誉教授が、住み込むほど中身のある活動が、テキパキと行われいます。