大学で地域課題の解決策を見いだす力を身に付けてもらう〜地域公共人材クラス(熊本大学法学部)〜
2021年03月06日

「将来、古里に貢献したい」という意欲ある高校生を推薦入試です迎え入れ、大学で地域課題の解決策を見いだす力を身に付けてもらう〜地域公共人材クラス(熊本大学法学部)〜
私は、熊本大学で12年間、学際科で非常勤講師をした経験と、熊大学医学部から熊本学園大学へ移られ「水俣学」を開設された原田正純教授との意見交換から、熊本大学の学生は、東京志向、大企業志向がほとんどのイメージがあったが、大日方教授の意見からすると、少し地域志向に変わってきたのか?と思いました。
この「地域公共人材クラス」には、自治体や企業へのインターンシップもあるようで、少し期待できるか、と思えています。
地方自治体は、人材確保が少子化から、集まらない状況はここ数年続いている。知人の息子さんは熊本大学でしたが、国土交通省、熊本県庁、熊本市役所の採用試験に全て合格し、選んだのは国土交通省だった。
自治体の人材確保策は、役所側のPRも今後は取り組む必要があるように思います。特に技術職は、収入の高い所へ行く者がほとんどなので、公務員の魅力づくりも必要な気がしています。
今後は、地元大学との関係を、自治体も積極的に取り組んで、人材確保に努める時期に来ているのかもしれません。
<温室効果ガスゼロと大牟田市石炭産業科学館>私は「三池争議」について丸一日かけ大牟田市図書館の関連資料を調べた。
2021年01月20日

私は「三池争議」について丸一日かけ大牟田市図書館の関連資料を調べたことがあります。〜温室効果ガスゼロと大牟田市石炭産業科学館〜
かつて、日本は石炭産業が栄えた時代があります、明治からの産業革命、高度成長を支えたのが、日本の石炭です。
数年前訪れた「大牟田市石炭産業科学館」で、40数年前まで続けられた石炭掘削の歴史、当時の最新式の掘削機が展示されています。
私の社会活動で指導を受けた先生(マクロ経済学者)から、「野口君、日本エネルギー政策が変わる転換点時期に起きた"三池争議"は一度勉強しておきなさい」と以前に何度か聞いたので、10年ほど前に、朝から大牟田市へ向かい、大牟田市図書館に半日近くいて、三池争議に関する資料や後に出された本よりを読みました。
先生は、エネルギーが石炭から石油に変化する時どうなったか、のちに変わる化石資源を使うエネルギーから再生可能エネルギー(当時の先生は、自然エネルギーと発言されていた)へ転換するヒントを、三井争議のころの日本社会の変化に注目しておきなさい、だったのかとふりかえります。
日本社会のインフラは大きく変わりますし、世界の化石資源大国と言われるオーストラリアや中東などは、今後の社会変化、特にエネルギー転換について取り組む必要が出てきているのだと思いました。



高校生たちのコロナ感染の影響とはどんなことがあるのか?〜『女性展望』より〜
2021年01月14日
高校生たちのコロナ感染の影響とはどんなことがあるのか?〜『女性展望』より〜
コロナ禍中、高校生たちをどんな思いなのか?
〜アンケートから、
<心配なこと>
・外へ出かけられない
・卒業後の進路が心配
・自分の家族がコロナ感染者なること
・友達とあえない
<気持ちや生活の変化>
・ほとんど家にいる
・寝てることが多くなった
・何もやる気がない
・ゲームやスマホ時間が増えた
・理由もなくイライラする
また有権者としての政治への関心について、
<投票するか、しないか>投票するが、前回のアンケートより14%減ったのはなぜか。
・私たちは現実の政治をあまり学んでいないからだと思います。
・(野党が)多党化していて、各政党の主張がわかりにくいです。
・学校で教えてもらえるのは政治制度までで、政治の具体的な内容までは教えてもらっていないし、分かりません。
等々、が報告されている。
今週末は、新しくなった大学一斉テストだが、コロナ感染した生徒や濃厚接触の生徒たちの思いを考えると、たまらなくなる。今のコロナ禍が、高校生たちの後の人生に大きく禍根を残さないことを願う幕臣のばかりです。





コロナ禍中、高校生たちをどんな思いなのか?
〜アンケートから、
<心配なこと>
・外へ出かけられない
・卒業後の進路が心配
・自分の家族がコロナ感染者なること
・友達とあえない
<気持ちや生活の変化>
・ほとんど家にいる
・寝てることが多くなった
・何もやる気がない
・ゲームやスマホ時間が増えた
・理由もなくイライラする
また有権者としての政治への関心について、
<投票するか、しないか>投票するが、前回のアンケートより14%減ったのはなぜか。
・私たちは現実の政治をあまり学んでいないからだと思います。
・(野党が)多党化していて、各政党の主張がわかりにくいです。
・学校で教えてもらえるのは政治制度までで、政治の具体的な内容までは教えてもらっていないし、分かりません。
等々、が報告されている。
今週末は、新しくなった大学一斉テストだが、コロナ感染した生徒や濃厚接触の生徒たちの思いを考えると、たまらなくなる。今のコロナ禍が、高校生たちの後の人生に大きく禍根を残さないことを願う幕臣のばかりです。





<コロナ渦後の地方の国際化>ダイバーシティの学校経営から見える社会
2020年12月12日
<コロナ渦後の地方の国際化>ダイバーシティの学校経営から見える社会
今朝4時5分からのNHKのインタビュー番組「明日への言葉」に、京都精華大学学長のウスビ・サコ氏(マリ共和国出身)が、海外留学生を増やしての大学経営と多国籍の多様性について語られました。
労働現場に欠かすことができなくなった技能実習生、農業実習生の海外からの労働者の皆さん、大学の存続に多国籍化が不可欠になっているのだなぁ、と話を聞いていました。
熊本県内にも、宇土市にも、海外からの技能実習生がいるのが普通になっています。一昨年春の日曜日、桜が咲く時期に開催したフットパス・モニターツアーで見た風景は、桜で人気スポットの宇土市の立岡自然公園には、ベトナム、中国、さらに観光ツアーで韓国の若者たちが、桜の花見で、バーベキューやお弁当開き、散策と、まるで海外の桜の公園にいるようでした。
今年は、コロナ渦で全く違う風景になりましたが、感染が収まれば、また国際的な環境が地方にも戻ると思います。国際化の流れは変わらないので、それを想定してコロナ渦後の対応が必要だなぁ、と今朝の放送を聞きながら考えていました。
今朝4時5分からのNHKのインタビュー番組「明日への言葉」に、京都精華大学学長のウスビ・サコ氏(マリ共和国出身)が、海外留学生を増やしての大学経営と多国籍の多様性について語られました。
労働現場に欠かすことができなくなった技能実習生、農業実習生の海外からの労働者の皆さん、大学の存続に多国籍化が不可欠になっているのだなぁ、と話を聞いていました。
熊本県内にも、宇土市にも、海外からの技能実習生がいるのが普通になっています。一昨年春の日曜日、桜が咲く時期に開催したフットパス・モニターツアーで見た風景は、桜で人気スポットの宇土市の立岡自然公園には、ベトナム、中国、さらに観光ツアーで韓国の若者たちが、桜の花見で、バーベキューやお弁当開き、散策と、まるで海外の桜の公園にいるようでした。
今年は、コロナ渦で全く違う風景になりましたが、感染が収まれば、また国際的な環境が地方にも戻ると思います。国際化の流れは変わらないので、それを想定してコロナ渦後の対応が必要だなぁ、と今朝の放送を聞きながら考えていました。
『22世紀の文明のあり方』は、「循環」と「共生」〜国の中央環境審議会の議論より〜
2017年08月03日
『22世紀の文明のあり方』は、「循環」と「共生」〜国の中央環境審議会の議論より〜
おはようございます。毎日猛暑日を記録。昨日は熊本は37℃を超えた場所が広がった。いつもの夏とは、違うレベルの猛暑の夏のように思います。
加えて、迷走台風の5号の動きは、九州地方に接近する予想となって来て、3号台風の準備不足から反省し、しっかり強風対策が必要と思います。
さて、今朝は冒頭の言葉から、人類が拡大し続けてきたが地球には限界があり、枯渇する資源に加えて、人類の活動が地球環境に変化を与え、異常気象の原因となり、巨大ハリケーンや台風の被害拡大させています。
(以下、『里海資本論』より)
・・・.かつて、地球がいっぱいになったら、月に行けばいい。月を使い切ったら火星に行けばいい。そんな時代か確かにあった。
「無限」を追い求めていた時代から数十年。
里海研究の先頭を走るひとり、広島大学名誉教授の松田治さんが教えてくれた。国の中央環境審議会では、「22世紀の文明のあり方」を議論しているそうだ。最大の課題として、人口減少と超高齢化社会の到来をあげ、日本という国の経済社会のあり方自体を変えていく必要を説く。(中略)
・・・.長きにわたって続いてきた、現在の貨幣的価値に基づく市場経済の偏重と地球の容量が無限であると思い込みが課題解決のネックとなっていることを指摘し、あらゆる意味で「有限」を認識すべきだとしている。
(以上、『里海資本論』より抜粋)
『里海資本論』の一説に、日本の縄文時代の知恵を尊重して未来を考える、意味の言葉があります。自然=地球は、有限であること、拡大し続けてきた人類は限界にきていること、自然から搾取してきた経済から自然を再生させる経済に変わらなければ行けないこと、『循環」と「共生」がこれからの課題ではないこと思います。
この話題が出たからではないですが、十数年前から使っている私の建築事務所の名前は「環境共生施設研究所」というものです。数年ほど前に名刺交換した他分野の先輩から、「これからの時代に先駆けた名前だね」という言葉をいただきました。
事務所の名前に恥じない活動を心がけたいと思います。
*参考資料:井上恭介・NHK「里海」取材班共著『里海資本論』〜日本社会は「共生の原理」で動く〜
おはようございます。毎日猛暑日を記録。昨日は熊本は37℃を超えた場所が広がった。いつもの夏とは、違うレベルの猛暑の夏のように思います。
加えて、迷走台風の5号の動きは、九州地方に接近する予想となって来て、3号台風の準備不足から反省し、しっかり強風対策が必要と思います。
さて、今朝は冒頭の言葉から、人類が拡大し続けてきたが地球には限界があり、枯渇する資源に加えて、人類の活動が地球環境に変化を与え、異常気象の原因となり、巨大ハリケーンや台風の被害拡大させています。
(以下、『里海資本論』より)
・・・.かつて、地球がいっぱいになったら、月に行けばいい。月を使い切ったら火星に行けばいい。そんな時代か確かにあった。
「無限」を追い求めていた時代から数十年。
里海研究の先頭を走るひとり、広島大学名誉教授の松田治さんが教えてくれた。国の中央環境審議会では、「22世紀の文明のあり方」を議論しているそうだ。最大の課題として、人口減少と超高齢化社会の到来をあげ、日本という国の経済社会のあり方自体を変えていく必要を説く。(中略)
・・・.長きにわたって続いてきた、現在の貨幣的価値に基づく市場経済の偏重と地球の容量が無限であると思い込みが課題解決のネックとなっていることを指摘し、あらゆる意味で「有限」を認識すべきだとしている。
(以上、『里海資本論』より抜粋)
『里海資本論』の一説に、日本の縄文時代の知恵を尊重して未来を考える、意味の言葉があります。自然=地球は、有限であること、拡大し続けてきた人類は限界にきていること、自然から搾取してきた経済から自然を再生させる経済に変わらなければ行けないこと、『循環」と「共生」がこれからの課題ではないこと思います。
この話題が出たからではないですが、十数年前から使っている私の建築事務所の名前は「環境共生施設研究所」というものです。数年ほど前に名刺交換した他分野の先輩から、「これからの時代に先駆けた名前だね」という言葉をいただきました。
事務所の名前に恥じない活動を心がけたいと思います。
*参考資料:井上恭介・NHK「里海」取材班共著『里海資本論』〜日本社会は「共生の原理」で動く〜
資源の無い国「日本」は、日本の縄文の知恵を学ぶべきではないか?〜“核のゴミをどう廃棄するか?“から日本の進む道を考える〜
2017年07月29日
資源の無い国「日本」は、日本の縄文の知恵を学ぶべきではないか?〜“核のゴミをどう廃棄するか?“から日本の進む道を考える〜
おはようございます。今朝は、朝ウオーキングはおやすみです。週休2日、週休3日のさぼりウォーカーなので、今朝はゆっくりです。
LINEニュースを見ていて、核のゴミを地下に埋めるニュースを思い出しました。
ふと「自然を破壊し続ける人類、すでに自然界の限界に達しているのではないか?」と考え、もう9年前になりますが、アメリカにオバマ大統領が誕生し、政策の中に「グリーンエネルギー」が取り上げられ、再生可能エネルギーの開発発展につながり、偶然に日本にも旧体制から、寄せ集め政権ではあるが、民主党政権が登場してグリーンエネルギーの推進を打ち出した。
私も、グリーンエネルギーに取り組む仲間から、再生可能エネルギーへの対応を迫られ、いくつも太陽光発電設備を設置していました。
6年前、東日本大震災が起き、大津波が福島第一原子力発電所を襲った。昨年は、熊本を大地震が襲った。地震国日本に、原子力発電所が数え切れないくらい存在する。
原子力発電所は、地上では処理できない核のゴミを出し続けている。このゴミをどうするのか?
東日本大震災から、稼働中の原子力発電所のゴミに加え、福島第一原子力発電所の廃炉作業から出る核のゴミと汚染水は膨大な量になっています。
これを何処にどう廃棄するのか?
本日の時事通信のwebニュースに、核のゴミをどう廃棄するのか、方法と場所の話が初めて示されています。
〜以下、時事通信のwebニュースより〜
>>昨年4月に町長が処分場受け入れを「選択肢の一つ」と発言した佐賀県玄海町の大部分のほか、東京都心や大阪府中心部は、地下資源の存在などから「好ましくない」と位置付けた。
(以上、時事通信より)
読み進んでも、何処に埋めるのか決めかねています。・・・、本当に廃棄場所を受け入れるところは出るのだろうか。
2か月ほど前に紹介した『里海資本論』のあとがき部分に次の一節がありました。
「現代文明は危機に瀕している。私たちの世代はなんとかもつだろう。しかしもう20年もすれば、持続はあやしくなる。ありとあらゆる意味で、自然が大変な状況になっている。健全な自然がなければ、人類は存在できない。自然を破壊することは、人類を破壊することと同義だ。今こそ人類は、日本の縄文の知恵を学ぶべきではないか」
「海藻がなくなると、魚もいなくなる。日本では持続可能な自然との付き合い方をしているそうですね。そのやり方を、世界中に広めたいものです」
(以上、『里海資本論』より)
これは、『銃・病原菌・鉄 1万3000年にわたる人類史の謎(上)(下)』の著者、ジャレット・ダイアモンド博士の言葉です。
瀬戸内の漁師は、工業化されて荒れた海の再生に取り組んでいる。広島の中山間地域は、里山の再生に取り組み新たな経済システムを生み出した。どちらも自然との付き合い方を、強制的から共生的な再生型に変えて成功しています。
枯渇する天然資源を使う経済から、再生型に変える取り組みに変えないと、資源の無い国の日本に、未来はないように思います。
おはようございます。今朝は、朝ウオーキングはおやすみです。週休2日、週休3日のさぼりウォーカーなので、今朝はゆっくりです。
LINEニュースを見ていて、核のゴミを地下に埋めるニュースを思い出しました。
ふと「自然を破壊し続ける人類、すでに自然界の限界に達しているのではないか?」と考え、もう9年前になりますが、アメリカにオバマ大統領が誕生し、政策の中に「グリーンエネルギー」が取り上げられ、再生可能エネルギーの開発発展につながり、偶然に日本にも旧体制から、寄せ集め政権ではあるが、民主党政権が登場してグリーンエネルギーの推進を打ち出した。
私も、グリーンエネルギーに取り組む仲間から、再生可能エネルギーへの対応を迫られ、いくつも太陽光発電設備を設置していました。
6年前、東日本大震災が起き、大津波が福島第一原子力発電所を襲った。昨年は、熊本を大地震が襲った。地震国日本に、原子力発電所が数え切れないくらい存在する。
原子力発電所は、地上では処理できない核のゴミを出し続けている。このゴミをどうするのか?
東日本大震災から、稼働中の原子力発電所のゴミに加え、福島第一原子力発電所の廃炉作業から出る核のゴミと汚染水は膨大な量になっています。
これを何処にどう廃棄するのか?
本日の時事通信のwebニュースに、核のゴミをどう廃棄するのか、方法と場所の話が初めて示されています。
〜以下、時事通信のwebニュースより〜
>>昨年4月に町長が処分場受け入れを「選択肢の一つ」と発言した佐賀県玄海町の大部分のほか、東京都心や大阪府中心部は、地下資源の存在などから「好ましくない」と位置付けた。
(以上、時事通信より)
読み進んでも、何処に埋めるのか決めかねています。・・・、本当に廃棄場所を受け入れるところは出るのだろうか。
2か月ほど前に紹介した『里海資本論』のあとがき部分に次の一節がありました。
「現代文明は危機に瀕している。私たちの世代はなんとかもつだろう。しかしもう20年もすれば、持続はあやしくなる。ありとあらゆる意味で、自然が大変な状況になっている。健全な自然がなければ、人類は存在できない。自然を破壊することは、人類を破壊することと同義だ。今こそ人類は、日本の縄文の知恵を学ぶべきではないか」
「海藻がなくなると、魚もいなくなる。日本では持続可能な自然との付き合い方をしているそうですね。そのやり方を、世界中に広めたいものです」
(以上、『里海資本論』より)
これは、『銃・病原菌・鉄 1万3000年にわたる人類史の謎(上)(下)』の著者、ジャレット・ダイアモンド博士の言葉です。
瀬戸内の漁師は、工業化されて荒れた海の再生に取り組んでいる。広島の中山間地域は、里山の再生に取り組み新たな経済システムを生み出した。どちらも自然との付き合い方を、強制的から共生的な再生型に変えて成功しています。
枯渇する天然資源を使う経済から、再生型に変える取り組みに変えないと、資源の無い国の日本に、未来はないように思います。
里山資本主義、里海資本論は、アベノミクスに対するアンチテーゼか。
2017年07月04日




里山資本主義、里海資本論は、アベノミクスに対するアンチテーゼか。
〜藻谷浩介+広島取材班、井上恭介+NHK「里海」取材班より〜
(長文です、時間ある時にお読みください)
おはようございます。外は、雨が強くなっています。まだ、風の影響はこれからと思いますが、被害が最小限になることを願うばかりです。
大自然のなせるパワーが台風(サイクロン)ですが、その台風は、年々強さを増しているように感じる事例増えているように思います。
自然に立ち向かう人間の準備は、どこまで準備すればいいのかわかりませんが、“危ない!”と思ったらとにかく、早く安全な場所に避難することが大事と思います。
人間の営みは、自然を制御する方向が目指してきたことを歴史から学びますが、自然災害の猛威はその上を行きます。経済も同じで、でかくなるばかり、成長ばかりを目指すと、資源がない国の日本は、限界があることも知らなければならない。
その成長経済に、小さなメッセージを送ったのが『里山資本主義』なる本で、徐々に広がり再版を重ねて40万部を売っています。本日注目したのが、同じNHK取材班が中心となった『里海資本論』で、宅地化、工業化で汚れた瀬戸内の海をカキ筏(いかだ)が、再生していく話です。
西日本でカキ(牡蠣)の産地は、広島のイメージか広がり、最近の熊本で人気の牡蠣小屋の牡蠣は広島産が多いことはみなさん周知のことですが、その牡蠣が瀬戸内の海の再生に一役かっていることを、『里海資本論』で知りました。
カキ筏による牡蠣の養殖が盛んになり、それまで富栄養化した瀬戸内では、赤潮の大量発生から広がっていました。ところが、カキ筏養殖か広がり、先ず広島近海から赤潮発生が減り、瀬戸内でのカキ筏養殖が盛んになり、赤潮の大量発生が少なつくなった、とありました。貝の浄化能力の凄さを示した調査結果でした。
私の住む有明海は、二枚貝の純国産ハマグリ「ヤマトハマグリ」が生まれ育つ地域で、かつてはアサリ貝の大産地でした。その頃の干潟は、里山と自然農法の田畑農業による栄養の流入が海まで届き、二枚貝の浄化能力により、サラサラの砂浜が広がっていました。
しかし、高度成長期の終わりころから砂浜がヘドロ化して、二枚貝も減りました。しかし、若い漁師たちは、搾取する漁協から、保護育成する有明海の干潟漁協を数年前から試みるようになり、二枚貝の収量が増えてきています。
富栄養化を二枚貝が浄化能力のを発揮させることで、赤潮の発揮を抑え、干潟の再生に貢献できる「里海漁業」の考え方が、これから広がることに期待します。
また、後日紹介したい瀬戸内と綿花の歴史から、瀬戸内の地域活性化の話は、『里海資本論』で検証すると興味を持つ事例となると、これから研究してみたいと思います。瀬戸内地域の海の歴史は、これからの漁業活性化のヒントが、あるように思います。
*参考資料:『里海資本論』、『里山資本主義』
東日本の電力の発送電分離構想が新聞紙面に発表された。
2015年02月06日
東日本の電力の発送電分離構想が新聞紙面に発表された。
電力の発送電分離は、西日本の電力会社はしないのでしょうか?
これからの市民の声が大事と思います。

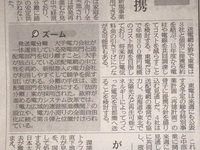
電力の発送電分離は、西日本の電力会社はしないのでしょうか?
これからの市民の声が大事と思います。

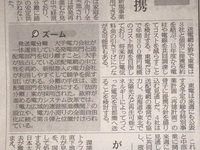
日本人の長所を「親切」が71%(国民性調査)、「自分の人生もそれなりに意味があったのだ」と安らかな死期に。
2014年10月31日

日本人の長所を「親切」が71%(国民性調査)、「自分の人生もそれなりに意味があったのだ」と安らかな死期に。
おはようございます。今朝は、朝のウォーキングはお休みで、普通の朝になりました。
今朝の新聞に、「国民性調査3013」で、日本人の長所を「親切」が71%で5年前より19ポイント増えたそうです。また、「勤勉」「礼儀正しい」は共に77%で過去最高となった。今回の評価は、「東日本大震災で東北の人たちが実直な対応をしているのを見聞きしたことが結果に表れているのではないか」とありました。
また、生まれ変われるなら日本と外国のどちらがよいかとの質問には、83%が日本と回答。同質問の20代の回答は、5年前は60%未満だったが、今回は上昇し73%と日本人であることを肯定的にとらえる若者が増えている。
昨日寝る前に開いた、守屋洋著『四書五経の名言録』の一節に、次のみだで書かれた解説文がありました。
「善行にはそれなりの見返りがある」
皆さんがよく見る文は、「積善の家には必ず余慶あり」だと思います。これは、先祖の善行によって子孫が手にする幸せのことです。
この項に次の出来事が紹介されていました。
(以下、抜粋)
死期を迎えた患者をみとるホスピスに勤めている方の話を聞いたことがあります。安らかに死んでもらうためには、その人の人生を振り返ってもらって、何か人様のお役に立ったことを思いしてもらうのだいいます。どんな些細なことでもいいのです。ふつうの人なら、たぶん幾つもあるに違いありません。
(そして命が尽きる前)「あなたこういういいことをしたんですよ」「そういうことしてあげたんですよ」と言って聞かせますと、患者は「自分の人生もそれなりに意味があったのだ」と安らかに息ひきとっていくというのです。
(以上、本より転載)
人に親切にしておくことが、自分の人生にも、後世の子孫にも幸福感をもたらすの教えと思います。
私は、今度の選挙で、親世代、祖父世代も含め、大きな恩恵を受けていると、つくづくと体験を何度もしました。これは、私自身の言動が後世の子孫たちにも影響を与えるということだと気づかされます。
日本人の意識に「親切」を重要視する方々が増えていること、生まれ変わったらまた日本人に83%の国民意識を嬉しく思います。私も、死期を迎えた時、ホスピスの看護師さんに、「こんないいことをしましたよ」言ってもらえるような後半生を生きたいものです。
今日は金曜日、午後は詰まった日程ですが、より良き一日となり、人のお役に立てるような日であればと思います。
未来の乗り物「燃料電池車」年内に量産化する計画(トヨタ)、他社も追随。
2014年06月05日
未来の乗り物「燃料電池車」年内に量産化する計画(トヨタ)、他社も追随。
おはようございます。どんよりした空の熊本です。雨が心配なので、朝ウォーキングは中止です。
さて、昨日ガソリンスタンドへ行き、料金が上がっていました。今朝の新聞に「ガソリン値上がり166円」の見出しで、記事があります。都市の景気は良いと言いますが地方は仕事は増えているようですが、競争も激しく、いっこうに給与は上がらないと、ぼやく声が聞こえてきます。
同じ経済紙面に、「トヨタ 燃料電池車12月にも量産」の記事がありました。1台800万円とか? 庶民からすると高嶺の花、まだ水素ガスステーションのインフラができておらず、自治体などへのレンタルから始まるのだろうと推測します。
九州はカーアイランドと言われるくらい自動車産業が集積している中、九州大学や佐賀県が、燃料電池車の推進に積極的で、2015年度を目処に、水素ガスの商用開始を目指し、準備を進めています。一昨年2月に、佐賀県の鳥栖に在る、木屑から水素ガスを取り出す装置を見学に行きましたが、そこには、佐賀県が使用する燃料電池車が頻繁に、給水素に訪れるそうです。
燃料電池車は、一度の給水素で約500km走るそうなので、まずは九州に20ヶ所程度の水素ガスステーションを設置して、商用開始が始まる計画のようです。
また一昨年2月に、佐賀県が主催する燃料電池の社会を検証する研修会に参加した時、最新の燃料電池車に試乗させてもらいました。静かで、排気は水(水蒸気)のみ、開発費は1台1億円以上とも聞く試乗車でした。流石に、自分では運転させてもらえませんでしたが、未来の乗り物に乗った気分は、最高でした。その未来の乗り物「燃料電池車」が市場へ出回ることになりました。
トヨタは年内、ホンダは来年、日産は2017年を目処に市販される計画とありました。電気自動車の普及も進んでいますが、次世代の乗り物「燃料電池車」の動向は、自動車業界を大きく変えるように思えて来ました。
*燃料電池車
水素と酸素の化学反応で発電する燃料電池を搭載し、電気自動車と同様にモーターを動かして走行する。排出するには水だけで環境に優しい。
・6月6日から定例議会
昨夜から、6月の議会で一般質問する内容をし執行部とやり取りを終え、質問原稿を書き始めました。秋改選なので、実質最後の中身の詰まった質疑が行われると思います。3年半の経験を活かした質問にしたいと思っています。私の一般質問は、6月10日午後最初の質問者の予定です。お近くの方で、興味ある方は聴きに来ていただければ幸いです。
おはようございます。どんよりした空の熊本です。雨が心配なので、朝ウォーキングは中止です。
さて、昨日ガソリンスタンドへ行き、料金が上がっていました。今朝の新聞に「ガソリン値上がり166円」の見出しで、記事があります。都市の景気は良いと言いますが地方は仕事は増えているようですが、競争も激しく、いっこうに給与は上がらないと、ぼやく声が聞こえてきます。
同じ経済紙面に、「トヨタ 燃料電池車12月にも量産」の記事がありました。1台800万円とか? 庶民からすると高嶺の花、まだ水素ガスステーションのインフラができておらず、自治体などへのレンタルから始まるのだろうと推測します。
九州はカーアイランドと言われるくらい自動車産業が集積している中、九州大学や佐賀県が、燃料電池車の推進に積極的で、2015年度を目処に、水素ガスの商用開始を目指し、準備を進めています。一昨年2月に、佐賀県の鳥栖に在る、木屑から水素ガスを取り出す装置を見学に行きましたが、そこには、佐賀県が使用する燃料電池車が頻繁に、給水素に訪れるそうです。
燃料電池車は、一度の給水素で約500km走るそうなので、まずは九州に20ヶ所程度の水素ガスステーションを設置して、商用開始が始まる計画のようです。
また一昨年2月に、佐賀県が主催する燃料電池の社会を検証する研修会に参加した時、最新の燃料電池車に試乗させてもらいました。静かで、排気は水(水蒸気)のみ、開発費は1台1億円以上とも聞く試乗車でした。流石に、自分では運転させてもらえませんでしたが、未来の乗り物に乗った気分は、最高でした。その未来の乗り物「燃料電池車」が市場へ出回ることになりました。
トヨタは年内、ホンダは来年、日産は2017年を目処に市販される計画とありました。電気自動車の普及も進んでいますが、次世代の乗り物「燃料電池車」の動向は、自動車業界を大きく変えるように思えて来ました。
*燃料電池車
水素と酸素の化学反応で発電する燃料電池を搭載し、電気自動車と同様にモーターを動かして走行する。排出するには水だけで環境に優しい。
・6月6日から定例議会
昨夜から、6月の議会で一般質問する内容をし執行部とやり取りを終え、質問原稿を書き始めました。秋改選なので、実質最後の中身の詰まった質疑が行われると思います。3年半の経験を活かした質問にしたいと思っています。私の一般質問は、6月10日午後最初の質問者の予定です。お近くの方で、興味ある方は聴きに来ていただければ幸いです。
日本人は素晴らしい。でも当たり前のことでは? 恐るべき日本人…中国ネットで賞賛の声。
2014年04月22日
日本人は素晴らしい。でも当たり前のことでは? 恐るべき日本人…中国ネットで賞賛の声。
昨日の布巾を洗濯中に、ネット検索していたら下記のことを見つけました。日本では、当たり前のことが、中国では驚かれている。民族の違い、家庭教育の違いだろうか。日本人は、神戸震災以来、良識の民族として高く評価されてきているような気がします。
~以下、ネットニュース転載~
恐るべき日本人…様々なエピソードに驚愕、中国ネットで賞賛の声
世界の旅行市場の中で、中国の存在感が増している。中国国家統計局によると、2013年に海外旅行者した中国人は延べ9819万人。対前年比で18.0%の高い伸びとなっており、2014年には1億1000万人を突破すると見られている。人民網などが報じた。
海外旅行者が増えるのにともなって、ネット上に発表される中国人の日本旅行記も増えている。実際に訪日した中国人たちの旅行記は好意的なものがほとんどだ。例として最近発表された「恐るべき日本人」と題した文章を紹介しよう。
筆者は日本旅行を経験した中国人で、自身の体験や人から聞いた日本人の礼儀正しさに関する以下のようなエピソードを列挙している。
「阪神淡路大震災の時、ある貸金業者が多くの被災者に無利子・無担保で融資を実施したが、“恐ろしいことに”3年後にはすべて返済された」
「1994年の広島アジア大会の閉会式後、6万人を収容した競技場に紙屑一つ落ちていなかった」
「日本の若者は痰を吐いたり、ゴミをポイ捨てしない。エスカレーターに乗る時には、急ぐ人のために片側を空けている。交差点では必ず青信号になるまで待つ」
「1人でツインルームに泊まった際、日本の友人から『使うベッドは一つだけにすればホテルの手間が省ける』と忠告された」
「ガソリンスタンドでは従業員が車の誘導から給油、会計まですべてやってくれるため、車を降りる必要がない」
「誰もいない道端に無人の販売所があって、ミカンが1カゴ100円で売られている。誰かが盗んでも分からないのに、常に商品が補充され、しかも盗む人がいない」
「レストランやバー、喫茶店、商店、路上などで大声で話している人がいない」
文章は、こうした日本人の礼儀正しさを「恐るべき高度な文明だ!」などと称賛する一方で、「5000年の文明を誇る中国人は、文化大革命後に文明を失った」と中国の現状を嘆いている。(編集 都築)
(以上、ネットニュースより)
昨日の布巾を洗濯中に、ネット検索していたら下記のことを見つけました。日本では、当たり前のことが、中国では驚かれている。民族の違い、家庭教育の違いだろうか。日本人は、神戸震災以来、良識の民族として高く評価されてきているような気がします。
~以下、ネットニュース転載~
恐るべき日本人…様々なエピソードに驚愕、中国ネットで賞賛の声
世界の旅行市場の中で、中国の存在感が増している。中国国家統計局によると、2013年に海外旅行者した中国人は延べ9819万人。対前年比で18.0%の高い伸びとなっており、2014年には1億1000万人を突破すると見られている。人民網などが報じた。
海外旅行者が増えるのにともなって、ネット上に発表される中国人の日本旅行記も増えている。実際に訪日した中国人たちの旅行記は好意的なものがほとんどだ。例として最近発表された「恐るべき日本人」と題した文章を紹介しよう。
筆者は日本旅行を経験した中国人で、自身の体験や人から聞いた日本人の礼儀正しさに関する以下のようなエピソードを列挙している。
「阪神淡路大震災の時、ある貸金業者が多くの被災者に無利子・無担保で融資を実施したが、“恐ろしいことに”3年後にはすべて返済された」
「1994年の広島アジア大会の閉会式後、6万人を収容した競技場に紙屑一つ落ちていなかった」
「日本の若者は痰を吐いたり、ゴミをポイ捨てしない。エスカレーターに乗る時には、急ぐ人のために片側を空けている。交差点では必ず青信号になるまで待つ」
「1人でツインルームに泊まった際、日本の友人から『使うベッドは一つだけにすればホテルの手間が省ける』と忠告された」
「ガソリンスタンドでは従業員が車の誘導から給油、会計まですべてやってくれるため、車を降りる必要がない」
「誰もいない道端に無人の販売所があって、ミカンが1カゴ100円で売られている。誰かが盗んでも分からないのに、常に商品が補充され、しかも盗む人がいない」
「レストランやバー、喫茶店、商店、路上などで大声で話している人がいない」
文章は、こうした日本人の礼儀正しさを「恐るべき高度な文明だ!」などと称賛する一方で、「5000年の文明を誇る中国人は、文化大革命後に文明を失った」と中国の現状を嘆いている。(編集 都築)
(以上、ネットニュースより)
大都会の大気汚染の防止対策、パリもナンバーの奇数・偶数で日分け通行に?
2014年03月17日
大都会の大気汚染の防止対策、パリもナンバーの奇数・偶数で日分け通行に?
中国の大気汚染がニュース流れる度に、「よくあそこで住めるな」と疑問に思うが、生活をするとなかなか自分の地域から離れられないものです。都会の大気汚染は、どこでもあり得ることです。
熊本でも、冬の晴れた日に、朝8時半頃に熊本市へ向かうと、市街地の空がある高さを境に、快晴の空と淀んだ空気の層の境がくっきり見えることがある。熊本市でも大気汚染は悪化しているのでないかと思います。
実は、どこの地方都市もそうですが、熊本市の市街地にも100円パーキングが増えたこともあり、1990年代よりも大気汚染が進んだと、市民団体の報告で知りました。その証拠に、市街地中心部に暮らす小学生や幼稚園児に気管支炎が増加し、全国平均の2倍以上になったことも知りました。
中国の大都市ほどはないですが、ヨーロッパの都会でも同様で、今日のニュースでのパリの車規制ですが、ロンドンでは既に市街地へ入るには、ナンバーの奇数・偶数で日分けして入る制限をかけ、もし間違って入ったら料金がかかる(1回日本円で1000円程度)、主要な路線にカメラがありチェックされている。
ハイブリッド車、電気自動車は規制外になっていることを考えると、電力の再生可能エネルギー利用を促進し、大気汚染、廃棄物を出さない発電所と電気自動車への切り替えを急ぐ必要があるように思います。
また一昨年、燃料電池車に試乗したのですが、日本が最先端を行く燃料電池車開発も急ピッチで進め、世界の都市の空気がきれいなり、子供たちの気管支炎が減ることを願うばかりです。
~(時事通信 3月16日(日)9時13分)~
パリで車の運転制限=大気汚染対策の第2弾
>【パリ時事】フランス政府は15日、ここ数日深刻化している大気汚染を軽減するため、17日早朝から2日間、パリやその近郊で車の運転を制限すると決めた。
>AFP通信によると、新たな対策は、車両のナンバープレートが奇数なら奇数の日付、偶数なら偶数の日付だけ運転を認める内容。自家用車と2輪車が対象で、順守されれば車両の運行を半分程度に抑える効果が期待される。電気自動車やハイブリッド車は例外とする。・・・・
(以上、ネットニュースより)
中国の大気汚染がニュース流れる度に、「よくあそこで住めるな」と疑問に思うが、生活をするとなかなか自分の地域から離れられないものです。都会の大気汚染は、どこでもあり得ることです。
熊本でも、冬の晴れた日に、朝8時半頃に熊本市へ向かうと、市街地の空がある高さを境に、快晴の空と淀んだ空気の層の境がくっきり見えることがある。熊本市でも大気汚染は悪化しているのでないかと思います。
実は、どこの地方都市もそうですが、熊本市の市街地にも100円パーキングが増えたこともあり、1990年代よりも大気汚染が進んだと、市民団体の報告で知りました。その証拠に、市街地中心部に暮らす小学生や幼稚園児に気管支炎が増加し、全国平均の2倍以上になったことも知りました。
中国の大都市ほどはないですが、ヨーロッパの都会でも同様で、今日のニュースでのパリの車規制ですが、ロンドンでは既に市街地へ入るには、ナンバーの奇数・偶数で日分けして入る制限をかけ、もし間違って入ったら料金がかかる(1回日本円で1000円程度)、主要な路線にカメラがありチェックされている。
ハイブリッド車、電気自動車は規制外になっていることを考えると、電力の再生可能エネルギー利用を促進し、大気汚染、廃棄物を出さない発電所と電気自動車への切り替えを急ぐ必要があるように思います。
また一昨年、燃料電池車に試乗したのですが、日本が最先端を行く燃料電池車開発も急ピッチで進め、世界の都市の空気がきれいなり、子供たちの気管支炎が減ることを願うばかりです。
~(時事通信 3月16日(日)9時13分)~
パリで車の運転制限=大気汚染対策の第2弾
>【パリ時事】フランス政府は15日、ここ数日深刻化している大気汚染を軽減するため、17日早朝から2日間、パリやその近郊で車の運転を制限すると決めた。
>AFP通信によると、新たな対策は、車両のナンバープレートが奇数なら奇数の日付、偶数なら偶数の日付だけ運転を認める内容。自家用車と2輪車が対象で、順守されれば車両の運行を半分程度に抑える効果が期待される。電気自動車やハイブリッド車は例外とする。・・・・
(以上、ネットニュースより)
【10倍の注意力】これからの選挙は、ネットを活用できないと取り残される。
2014年01月30日
【10倍の注意力】これからの選挙は、ネットを活用できないと取り残される。
首長選挙も様変わりした。公開討論会もネット中継が当たり前になった。
~朝日新聞デジタル 1月26日(日)7時8分配信~
スマホ中継、政策募集…都知事選、ネット選挙で発信競う。
>2月9日投開票の東京都知事選で、主な候補者が「ネット選挙」に力を入れている。有権者が約1千万人にのぼる東京都。少しでも多くの人に政策を訴えようという狙いがある。
>25日、JR有楽町駅前で演説する宇都宮健児氏(67)を、陣営の担当者がスマートフォンでネット中継した。専属スタッフが連日、演説に同行している。
>「もっとはきはき話した方がいい」「公約の財源は?」。メールやツイッターで、これまで百数十件の声が寄せられた。ネット担当スタッフを70人置く陣営は「ネット活動で10万票の上積みが目標」と意気込む。
(以上、朝日新聞webより)
地方選挙もここ1年で大きく変わった。情報発信力に加えて、有権者の反応をいかにキャッチできるか。後援会チラシの配布は、これまで同様に必要。加えてホームページ、公式ブログ、活動日記(写真、動画、他)、等々。候補者自身の発信力が、今後は問われる。さらに、ネットの反応にいかに答えれるかも問われる。
以前、社会活動の指導を受ける方から、「いろいろな会議で発言するのは、約1割の人たち。社会も同様で、ネットツール上の発言も同じ比率と考えると、発言者の10倍の人が、発言(コメント)に注目している」と指摘を受けた。なるほどと思った。Facebookで反応する「いいね」の約10倍の人たちが、日々書く意見に目を通している、と思って注意して書いたが良いと思っています。
首長選挙も様変わりした。公開討論会もネット中継が当たり前になった。
~朝日新聞デジタル 1月26日(日)7時8分配信~
スマホ中継、政策募集…都知事選、ネット選挙で発信競う。
>2月9日投開票の東京都知事選で、主な候補者が「ネット選挙」に力を入れている。有権者が約1千万人にのぼる東京都。少しでも多くの人に政策を訴えようという狙いがある。
>25日、JR有楽町駅前で演説する宇都宮健児氏(67)を、陣営の担当者がスマートフォンでネット中継した。専属スタッフが連日、演説に同行している。
>「もっとはきはき話した方がいい」「公約の財源は?」。メールやツイッターで、これまで百数十件の声が寄せられた。ネット担当スタッフを70人置く陣営は「ネット活動で10万票の上積みが目標」と意気込む。
(以上、朝日新聞webより)
地方選挙もここ1年で大きく変わった。情報発信力に加えて、有権者の反応をいかにキャッチできるか。後援会チラシの配布は、これまで同様に必要。加えてホームページ、公式ブログ、活動日記(写真、動画、他)、等々。候補者自身の発信力が、今後は問われる。さらに、ネットの反応にいかに答えれるかも問われる。
以前、社会活動の指導を受ける方から、「いろいろな会議で発言するのは、約1割の人たち。社会も同様で、ネットツール上の発言も同じ比率と考えると、発言者の10倍の人が、発言(コメント)に注目している」と指摘を受けた。なるほどと思った。Facebookで反応する「いいね」の約10倍の人たちが、日々書く意見に目を通している、と思って注意して書いたが良いと思っています。
ネットでスポーツイベントと地域の店舗・会社の連携の試み。
2014年01月30日
ネットでスポーツイベントと地域の店舗・会社の連携の試み。
おはようございます。今朝は、炬燵にうたた寝して、変な時間に目が覚めた。
一昨年から、私が役を受けたスポーツ協会会長の課題は、ある大会の運営経費の問題。地方社会の厳しい経済の中、広告協賛を集めるのが難しくなっている。何か新しい試みができないか考える中で、既存のメディアに情報発信を固定せず、時代変化のスピードに追随できる広報活動にしたいと、いろいろ考えてきた。
これを後押しするような、web情報を見つけた。
<環境・サイエンス・IT >
~2013年12月20日 15:11 発信地:サンフランシスコ/米国 ~
「今後5年の5大技術革新」、米IBMが予測
>【12月20日 AFP】米IBMは17日、今後5年間に人々の生活を大きく変えると考えられる5つの大きなイノベーション(技術革新)を示す毎年恒例の未来予測を発表した。
>今回の予測は「機械が学習して論理的に思考し、個人に合わせた形でより自然に人間と交流する認知システムの新時代」を色濃く反映したものだという。
>人間の脳と似た方法で「思考」するよう進化したソフトウエア、処理能力が向上したコンピューター、そしてインターネットの「クラウド」上に保存された大量のデータによって、教室や店舗、病院、街中などでコンピューターによる技術革新が起きると同社は予想している。
>■地元のお店も変わる
>小売業界では、IBMが開発し、人気クイズテレビ番組「ジョパディ!(Jeopardy!)」で優勝した人工知能「ワトソン(Watson)」のような技術と拡張現実(AR)技術によって店舗の規模にかかわらずオンラインと現実世界の店頭が融合するようになるという。
>医療分野では患者の遺伝情報を活用してその人に最適な治療法を選択し、「がんを治療するのに患者の全身をじゅうたん爆撃するのではなく、健康な細胞には触らずにがん細胞への攻撃の精度を上げることができる」(マイヤーソン氏)という。
>また都市部では、ソーシャルネットワーク、スマートフォン(多機能携帯電話)、センサー、機械学習(コンピューターなどの機械に自動的に学習させる研究分野)を公共サービスの改善に活用するようになるという。「技術に非常に明るく、技術をよく活用できる新しい世代のリーダーが登場しつつある」(同氏)
(以上、webニュースより)
上記のIBMの示唆「5大技術革新」で、
>技術と拡張現実(AR)技術によって店舗の規模にかかわらずオンラインと現実世界の店頭が融合するようになる・・
今年は、地域のスポーツイベントと地域の店舗・会社を、ネットを使い融合的にwebと現実の店をつなげる広報活動の試みをしみたいと考えています。そのねらいは、経費節減と情報受発信の拡大(エリアを県内から九州へ)、この矛盾したテーマにチャレンジしてみたいと思っています。
色々アイデアのある方は、ご意見、ご指導いただければ幸いです。
おはようございます。今朝は、炬燵にうたた寝して、変な時間に目が覚めた。
一昨年から、私が役を受けたスポーツ協会会長の課題は、ある大会の運営経費の問題。地方社会の厳しい経済の中、広告協賛を集めるのが難しくなっている。何か新しい試みができないか考える中で、既存のメディアに情報発信を固定せず、時代変化のスピードに追随できる広報活動にしたいと、いろいろ考えてきた。
これを後押しするような、web情報を見つけた。
<環境・サイエンス・IT >
~2013年12月20日 15:11 発信地:サンフランシスコ/米国 ~
「今後5年の5大技術革新」、米IBMが予測
>【12月20日 AFP】米IBMは17日、今後5年間に人々の生活を大きく変えると考えられる5つの大きなイノベーション(技術革新)を示す毎年恒例の未来予測を発表した。
>今回の予測は「機械が学習して論理的に思考し、個人に合わせた形でより自然に人間と交流する認知システムの新時代」を色濃く反映したものだという。
>人間の脳と似た方法で「思考」するよう進化したソフトウエア、処理能力が向上したコンピューター、そしてインターネットの「クラウド」上に保存された大量のデータによって、教室や店舗、病院、街中などでコンピューターによる技術革新が起きると同社は予想している。
>■地元のお店も変わる
>小売業界では、IBMが開発し、人気クイズテレビ番組「ジョパディ!(Jeopardy!)」で優勝した人工知能「ワトソン(Watson)」のような技術と拡張現実(AR)技術によって店舗の規模にかかわらずオンラインと現実世界の店頭が融合するようになるという。
>医療分野では患者の遺伝情報を活用してその人に最適な治療法を選択し、「がんを治療するのに患者の全身をじゅうたん爆撃するのではなく、健康な細胞には触らずにがん細胞への攻撃の精度を上げることができる」(マイヤーソン氏)という。
>また都市部では、ソーシャルネットワーク、スマートフォン(多機能携帯電話)、センサー、機械学習(コンピューターなどの機械に自動的に学習させる研究分野)を公共サービスの改善に活用するようになるという。「技術に非常に明るく、技術をよく活用できる新しい世代のリーダーが登場しつつある」(同氏)
(以上、webニュースより)
上記のIBMの示唆「5大技術革新」で、
>技術と拡張現実(AR)技術によって店舗の規模にかかわらずオンラインと現実世界の店頭が融合するようになる・・
今年は、地域のスポーツイベントと地域の店舗・会社を、ネットを使い融合的にwebと現実の店をつなげる広報活動の試みをしみたいと考えています。そのねらいは、経費節減と情報受発信の拡大(エリアを県内から九州へ)、この矛盾したテーマにチャレンジしてみたいと思っています。
色々アイデアのある方は、ご意見、ご指導いただければ幸いです。
【金相場の25%下落】金暴落、世界の金山に打撃-南アでは大量解雇
2013年12月31日
【金相場の25%下落】金暴落、世界の金山に打撃-南アでは大量解雇
おはようございます。2013年大晦日ですね。
丸一年がすぎるには早いもにです。さて、ネットをパラパラと検索していると、「金相場1年で25%下落」の文字、世界はそうなっているか、と思った。
数年前から、貴金属の買い取りが店が地方の熊本でも目立ち、チラシも入っていたが、最近見ないなと思いっていたら、金相場の大幅下落だった。1981年以来の下落だそうです。1981年といえば、日本がバブルへ突き進んでいた時期、経済の膨張はどこまで行くのか?
やはり、膨張し、縮小しを繰り返しながら、人々はそのブームに翻弄されながら、自分の欲を満たすために、奔走するにだろう。金相場の崩落は、我が家には関係ない世界だが、金本位制だった時代、金の相場は経済の相場に沿っていたように思います。
市場経済の変化は、ローカル経済を翻弄する。南アの経済成長に引きずられた地下資源開発、加えてアメリカの量的緩和もあり、アフリカ経済は上昇し続けてきたのだろう。来春、日本は消費税が上がる。経済対策が大きく打ち出されると思うが、東アジアの緊張から、投資先がインドなど南アジアに移っているとも言われる。
2014年日本は、どこへ向かうか。年末・年始のリーダーたちの発言に注目したいと思います。
~web・ブルームバーグ~
金暴落、世界の金山に打撃-南アでは大量解雇で終末に似た光景
>年初来の金相場の25%下落が、金に依存する世界各地の鉱山町に及ぼす影響を象徴する極端な一例だ。年間ベースの金相場が13年ぶりの下落に向かう中、産金各社は米ネバダ州やペルー、パプアニューギニアなどにある金山の閉鎖や操業縮小計画を発表している。
我が家の大晦日は、地域の方の葬儀があり、その後は残りの大掃除して、年越しの地区の催しに参加します。今年は、ゆっくり紅白見れるようです。今日も一日元気に過ごしたいものです。
おはようございます。2013年大晦日ですね。
丸一年がすぎるには早いもにです。さて、ネットをパラパラと検索していると、「金相場1年で25%下落」の文字、世界はそうなっているか、と思った。
数年前から、貴金属の買い取りが店が地方の熊本でも目立ち、チラシも入っていたが、最近見ないなと思いっていたら、金相場の大幅下落だった。1981年以来の下落だそうです。1981年といえば、日本がバブルへ突き進んでいた時期、経済の膨張はどこまで行くのか?
やはり、膨張し、縮小しを繰り返しながら、人々はそのブームに翻弄されながら、自分の欲を満たすために、奔走するにだろう。金相場の崩落は、我が家には関係ない世界だが、金本位制だった時代、金の相場は経済の相場に沿っていたように思います。
市場経済の変化は、ローカル経済を翻弄する。南アの経済成長に引きずられた地下資源開発、加えてアメリカの量的緩和もあり、アフリカ経済は上昇し続けてきたのだろう。来春、日本は消費税が上がる。経済対策が大きく打ち出されると思うが、東アジアの緊張から、投資先がインドなど南アジアに移っているとも言われる。
2014年日本は、どこへ向かうか。年末・年始のリーダーたちの発言に注目したいと思います。
~web・ブルームバーグ~
金暴落、世界の金山に打撃-南アでは大量解雇で終末に似た光景
>年初来の金相場の25%下落が、金に依存する世界各地の鉱山町に及ぼす影響を象徴する極端な一例だ。年間ベースの金相場が13年ぶりの下落に向かう中、産金各社は米ネバダ州やペルー、パプアニューギニアなどにある金山の閉鎖や操業縮小計画を発表している。
我が家の大晦日は、地域の方の葬儀があり、その後は残りの大掃除して、年越しの地区の催しに参加します。今年は、ゆっくり紅白見れるようです。今日も一日元気に過ごしたいものです。
ブータンの国民総幸福量(GNH)、熊本の県民総幸福量(AKH)とは何か?
2013年11月22日
ブータンの国民総幸福量(GNH)、熊本の県民総幸福量(AKH)とは何か?
おはようございます。今朝のウォーキングは、月夜の綺麗な夜空を見ながら歩きました。気分爽快、今日も頑張れそうです。
さて、今日のテーマは、総幸福量の話です。ブータンの政策が、世界の注目を集めて、経済成長ばかりでは幸福感は満たせない。違った発想の幸福を目指すべきと、アジアの小国が、世界へメッセージを出したのが、国民総幸福量(GNH)です。
実は、熊本県知事が2期目になり、独自目標の「県民総幸福量(AKH)」の算出に取り組んでいる。なかなか理解できない分野、学者知事らしい発想と思いますが、ブータンの「心の幸せ重要視」の政策GNH(国民総幸福量)が元のようですが、一人ひとり求める幸福感はそれぞれに違う、GNHがどんな内容か?以前から関心があった。
ここ数日、熊本にそのブータンのGNH政策に深く関わった研究者が来熊し、知事と会見したり、講演会あったりと、熊本の話題になっている。GNHに関しても、色々な研究が広がり、日本国内の自治体も取り入れるところも増えている。本家のブータンの総幸福量は、次の4つの柱と9分野にわたる領域をベースに、249の質問で、幸福量を測るようです。
GNH 国民総幸福(4つの柱)
・持続可能で公平な社会経済的開発
・環境保護
・文化の推進
・良き統治
GNHは4つの柱と、さらに9つの領域に分けられている。
・心理的な幸福
・国民の健康
・教育
・文化の多様性
・地域の活力
・環境の多様性の活力
・時間の使い方とバランス(ワーク・ライフ・バランス
・生活水準
・良き統治(ガバナンス)
ブータンを訪問したジャーナリストの池上彰氏のブログに、こんなブータンの感想がありました。
「ブータンは国土の60%以上は森でなければいけない、という基準が設けられている。経済が発展していくと、どんどん木を切って、開発します。それにストップをかけようということ。緑を大事にしながら、発展しましょうということです」
「ブータンのGNHも、国民に幸福を押しつけるわけではないんです。それぞれの人が幸福を追求できるような状況をつくっていくと考えれば、日本でもそれぞれの人が幸福を追求できるような環境をつくっていく。あるいは、そのために政治が頑張らないといけない。探し求めていた『青い鳥』は実は近くにいるのかもしれない。日本が新たに考える。そのきっかけをブータン、あるいはチベット仏教が与えてくれているのかなと思います」
(以上、池上彰氏のブログより)
日本文化に足るを知る「知足」という生活観があります。意外に、知足的な発想がGNHにあるように感じました。池上氏の「探し求めていた『青い鳥』は実は近くにいるのかもしれない」の言葉ではないですが、遠い国や国内の先進地を羨望し、新しい取り組みをするよりも、身近にある生活を充実させることが、総幸福量の向上を増やすことにつながるのかもしれないと思いました。
そろそろ、12月議会の一般質問の準備のため、色々資料集めをする時期になりました。今回の質問から、ブータンの総幸福量ではないですが、身近な生活の視点からの質問をいくつか準備しています。12月9日の午前11時前後に、私の質問時間が予定されています。関心のある方は、傍聴いただけるとありがたいです。
おはようございます。今朝のウォーキングは、月夜の綺麗な夜空を見ながら歩きました。気分爽快、今日も頑張れそうです。
さて、今日のテーマは、総幸福量の話です。ブータンの政策が、世界の注目を集めて、経済成長ばかりでは幸福感は満たせない。違った発想の幸福を目指すべきと、アジアの小国が、世界へメッセージを出したのが、国民総幸福量(GNH)です。
実は、熊本県知事が2期目になり、独自目標の「県民総幸福量(AKH)」の算出に取り組んでいる。なかなか理解できない分野、学者知事らしい発想と思いますが、ブータンの「心の幸せ重要視」の政策GNH(国民総幸福量)が元のようですが、一人ひとり求める幸福感はそれぞれに違う、GNHがどんな内容か?以前から関心があった。
ここ数日、熊本にそのブータンのGNH政策に深く関わった研究者が来熊し、知事と会見したり、講演会あったりと、熊本の話題になっている。GNHに関しても、色々な研究が広がり、日本国内の自治体も取り入れるところも増えている。本家のブータンの総幸福量は、次の4つの柱と9分野にわたる領域をベースに、249の質問で、幸福量を測るようです。
GNH 国民総幸福(4つの柱)
・持続可能で公平な社会経済的開発
・環境保護
・文化の推進
・良き統治
GNHは4つの柱と、さらに9つの領域に分けられている。
・心理的な幸福
・国民の健康
・教育
・文化の多様性
・地域の活力
・環境の多様性の活力
・時間の使い方とバランス(ワーク・ライフ・バランス
・生活水準
・良き統治(ガバナンス)
ブータンを訪問したジャーナリストの池上彰氏のブログに、こんなブータンの感想がありました。
「ブータンは国土の60%以上は森でなければいけない、という基準が設けられている。経済が発展していくと、どんどん木を切って、開発します。それにストップをかけようということ。緑を大事にしながら、発展しましょうということです」
「ブータンのGNHも、国民に幸福を押しつけるわけではないんです。それぞれの人が幸福を追求できるような状況をつくっていくと考えれば、日本でもそれぞれの人が幸福を追求できるような環境をつくっていく。あるいは、そのために政治が頑張らないといけない。探し求めていた『青い鳥』は実は近くにいるのかもしれない。日本が新たに考える。そのきっかけをブータン、あるいはチベット仏教が与えてくれているのかなと思います」
(以上、池上彰氏のブログより)
日本文化に足るを知る「知足」という生活観があります。意外に、知足的な発想がGNHにあるように感じました。池上氏の「探し求めていた『青い鳥』は実は近くにいるのかもしれない」の言葉ではないですが、遠い国や国内の先進地を羨望し、新しい取り組みをするよりも、身近にある生活を充実させることが、総幸福量の向上を増やすことにつながるのかもしれないと思いました。
そろそろ、12月議会の一般質問の準備のため、色々資料集めをする時期になりました。今回の質問から、ブータンの総幸福量ではないですが、身近な生活の視点からの質問をいくつか準備しています。12月9日の午前11時前後に、私の質問時間が予定されています。関心のある方は、傍聴いただけるとありがたいです。
再生可能エネルギー業界は、国際競争の時代に。ホンダソルテック撤退へ。
2013年10月31日
再生可能エネルギー業界は、国際競争の時代に。ホンダソルテック撤退へ。
今朝の地元紙に、ホンダの子会社「ホンダソルテック」の業績悪化の記事があり、さっき見たネットニュースに来年度で製造販売を終了するとあった。価格競争で、アモルファス型の太陽光発電は、国内生産は低価格競争に参画できず、さらに中国製の太陽光発電の参入で、シェアを奪われていった。
太陽光発電システムの販売を手がける友人の企業が、熊本県の要請もありホンダソルテックの太陽電池設置講習会に参加したおり、私も同行させてもらった経験から、熊本の企業としても応援してきたが、国際競争になってきたために、撤退を余儀無くされたようだ。
車のホンダ、やはり車で勝負して来た技術がある。特に先端を走る燃料電池車は、どんどん先へ進んで欲しいと思っています。ホンダ頑張れ、応援しています。
~以下、webニュースより転載~
ホンダ、太陽電池製・販から撤退 子会社解散(産経新聞 10月31日(木)8時0分配信)
ホンダは30日、太陽電池事業を手がける全額出資子会社「ホンダソルテック」(熊本県)を解散し、太陽電池の製造・販売から撤退すると発表した。2014年春に事業を終了、従業員91人(今年9月末時点)には自主退職を求める。
ソルテックは06年12月に設立。ホンダが独自に開発した天候や熱の影響を受けにくいCIGS薄膜太陽電池を製造、販売していた。累計投資金額は約70億円。
再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度を背景に国内の太陽電池市場は拡大しているが、シリコン価格の下落に伴うシリコン結晶系太陽電池パネルの値下げに加え、中国など新興国メーカーとの価格競争が激しい。ホンダは「市場環境が事業計画と異なり、競争力を失った」(幹部)と判断し、撤退を決断した。
(以上、産経新聞webより)
今朝の地元紙に、ホンダの子会社「ホンダソルテック」の業績悪化の記事があり、さっき見たネットニュースに来年度で製造販売を終了するとあった。価格競争で、アモルファス型の太陽光発電は、国内生産は低価格競争に参画できず、さらに中国製の太陽光発電の参入で、シェアを奪われていった。
太陽光発電システムの販売を手がける友人の企業が、熊本県の要請もありホンダソルテックの太陽電池設置講習会に参加したおり、私も同行させてもらった経験から、熊本の企業としても応援してきたが、国際競争になってきたために、撤退を余儀無くされたようだ。
車のホンダ、やはり車で勝負して来た技術がある。特に先端を走る燃料電池車は、どんどん先へ進んで欲しいと思っています。ホンダ頑張れ、応援しています。
~以下、webニュースより転載~
ホンダ、太陽電池製・販から撤退 子会社解散(産経新聞 10月31日(木)8時0分配信)
ホンダは30日、太陽電池事業を手がける全額出資子会社「ホンダソルテック」(熊本県)を解散し、太陽電池の製造・販売から撤退すると発表した。2014年春に事業を終了、従業員91人(今年9月末時点)には自主退職を求める。
ソルテックは06年12月に設立。ホンダが独自に開発した天候や熱の影響を受けにくいCIGS薄膜太陽電池を製造、販売していた。累計投資金額は約70億円。
再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度を背景に国内の太陽電池市場は拡大しているが、シリコン価格の下落に伴うシリコン結晶系太陽電池パネルの値下げに加え、中国など新興国メーカーとの価格競争が激しい。ホンダは「市場環境が事業計画と異なり、競争力を失った」(幹部)と判断し、撤退を決断した。
(以上、産経新聞webより)
スマホ、タブレットの普及で、電車内の使用が目立ってきた、利用の中止も必要
2013年09月29日
スマホ、タブレットの普及で、電車内の使用が目立ってきた、利用の中止も必要
おはようございます。今朝は、ゆっくりの朝活動です。
さて、スマホが年内に7割に近づくとの話、便利なものは普及すのが早いなと思います。私もスマホに替えて2年が過ぎ、春からタブレットも使いはじめた。文明の道具は確かに便利なものだと思います。
しかし、そのおかげで影響を受けている方々がいることも忘れてはならない。たまにしか電車には乗らないが、スマホの画面を多くの方々が見ている。微弱だが、電波を発している。ペースメーカーを利用している人は、必ず優先席に座っているわけではない。やはり、電車内での携帯電話、タブレットの利用は、控えるにが良いように最近感じている。
今日は、運動会のところも多いと思います。熊本は、少し曇り空ですが、思い出に残る運動会が行われるのを願っています。
そろそろ、老人ホームの落成式へ行く準備をします。今日も一日、元気に過ごしましょう。
Yahooニュース
> 指針に関し、約30年間、ペースメーカー治療に携わっている板橋中央総合病院循環器科不整脈・心不全診療部長の中島博医師は「胸ポケットに携帯電話を入れて抱き合うなどの特殊な状態が続く場合を除き、電波に干渉される可能性は極めて低い。電車内の放送は装着者に過大な恐怖を与え、普通の生活を送るために装着したはずの患者が、不安で電車に乗れないなど生活が制限される事態が起きている」と指摘する。
>一方、ペースメーカー使用者らでつくる日本ペースメーカー友の会の日高進副会長は「影響はないと会員に周知をしているが、周知は行き届いていないし、古くからの装着者の不安を拭いきれない。電源オフは継続してほしい」と慎重な意見だ。・・・・
おはようございます。今朝は、ゆっくりの朝活動です。
さて、スマホが年内に7割に近づくとの話、便利なものは普及すのが早いなと思います。私もスマホに替えて2年が過ぎ、春からタブレットも使いはじめた。文明の道具は確かに便利なものだと思います。
しかし、そのおかげで影響を受けている方々がいることも忘れてはならない。たまにしか電車には乗らないが、スマホの画面を多くの方々が見ている。微弱だが、電波を発している。ペースメーカーを利用している人は、必ず優先席に座っているわけではない。やはり、電車内での携帯電話、タブレットの利用は、控えるにが良いように最近感じている。
今日は、運動会のところも多いと思います。熊本は、少し曇り空ですが、思い出に残る運動会が行われるのを願っています。
そろそろ、老人ホームの落成式へ行く準備をします。今日も一日、元気に過ごしましょう。
Yahooニュース
> 指針に関し、約30年間、ペースメーカー治療に携わっている板橋中央総合病院循環器科不整脈・心不全診療部長の中島博医師は「胸ポケットに携帯電話を入れて抱き合うなどの特殊な状態が続く場合を除き、電波に干渉される可能性は極めて低い。電車内の放送は装着者に過大な恐怖を与え、普通の生活を送るために装着したはずの患者が、不安で電車に乗れないなど生活が制限される事態が起きている」と指摘する。
>一方、ペースメーカー使用者らでつくる日本ペースメーカー友の会の日高進副会長は「影響はないと会員に周知をしているが、周知は行き届いていないし、古くからの装着者の不安を拭いきれない。電源オフは継続してほしい」と慎重な意見だ。・・・・
オフィスや会議室を共有「コワーキング」の広がりの理解と支援を
2013年08月27日
オフィスや会議室を共有「コワーキング」の広がりの理解と支援を
おはようございます。今朝は、肌寒いような朝です。昨日までの雨が嘘のような晴天で、秋の気配が嬉しいですね。今日のテーマは「コワーキング」、何だそれは? いわゆる、共同オフィスのことで、フリー(個人)事業者が、事務所や会議室をシェアして使う、公的にはインキュベーション(ふ化)施設があるが、そういう杓子定規のようなオフィスではなく、安い使用料で共有するスペース。
これを可能にしているにが、ネット環境と携帯端末の発達。携帯電話とノートPCさえあれば、どこでもできるが、出来ないにが資料作成作業と情報交換。それを、互いに使い合う(シェア)ことで、ビジネスを逆に広げる。私は、異業種交流会を14年続けて来ました。コワーキングの場は、異業種交流の場にもなる。
今朝の地元紙に、友人の若い人たちが、子育てをしながら仕事できるコワーキングを活用してたくましく働く姿をきじで読み、ワクワクしてきた。全国のコワーキング協同組合(神戸市)の伊藤代表理事は、「個人で働く人たちが連帯することで、地域経済を活性化させることもできる。人とのつながりを前提にしたコワーキングの可能性は大きい。各地にあるインキュベーション施設のように、社会インフラとして必要とされる時期に来ている」と語っている。
コワーキングとは、
フリーランス(個人事業者)や小規模法人の労働者がオフィスを共通し、各自それぞれの仕事をしながら、他の利用者とも情報交換し、交流する働き方。国内では3年前から広がり始め、全国に280ヶ所ほどあるそうだ。利用料は、それぞれで、熊本の「キャンパス・ラボ」は個人3000円~、法人12000円~。「クロッカス」は12000円で、1日1000円の設定もある。共に会員制。
都市部は、オフィス賃料が高いので共有の発想と思うが、地方では情報交換と交流を目的に、既存の組合や会の高い年会費や参加費を避け、場の共有と異業種交流を目的に、地方都市の中心部に、オフィスを共有することはとても有効と思う。熊本市では、男女共同参画センター「はあもにい」には、コワーキングを無料で体験スペースもある。
一時期「ノマド」という働き方があったが、やはり人は交流を持つことが必要ということもあり、コワーキングの場が広がって来たのだろう。今後、地方都市でネット環境が充実して行けば、情報交換と交流の場として、コワーキング的な場所が必要になって来るように思う。
おはようございます。今朝は、肌寒いような朝です。昨日までの雨が嘘のような晴天で、秋の気配が嬉しいですね。今日のテーマは「コワーキング」、何だそれは? いわゆる、共同オフィスのことで、フリー(個人)事業者が、事務所や会議室をシェアして使う、公的にはインキュベーション(ふ化)施設があるが、そういう杓子定規のようなオフィスではなく、安い使用料で共有するスペース。
これを可能にしているにが、ネット環境と携帯端末の発達。携帯電話とノートPCさえあれば、どこでもできるが、出来ないにが資料作成作業と情報交換。それを、互いに使い合う(シェア)ことで、ビジネスを逆に広げる。私は、異業種交流会を14年続けて来ました。コワーキングの場は、異業種交流の場にもなる。
今朝の地元紙に、友人の若い人たちが、子育てをしながら仕事できるコワーキングを活用してたくましく働く姿をきじで読み、ワクワクしてきた。全国のコワーキング協同組合(神戸市)の伊藤代表理事は、「個人で働く人たちが連帯することで、地域経済を活性化させることもできる。人とのつながりを前提にしたコワーキングの可能性は大きい。各地にあるインキュベーション施設のように、社会インフラとして必要とされる時期に来ている」と語っている。
コワーキングとは、
フリーランス(個人事業者)や小規模法人の労働者がオフィスを共通し、各自それぞれの仕事をしながら、他の利用者とも情報交換し、交流する働き方。国内では3年前から広がり始め、全国に280ヶ所ほどあるそうだ。利用料は、それぞれで、熊本の「キャンパス・ラボ」は個人3000円~、法人12000円~。「クロッカス」は12000円で、1日1000円の設定もある。共に会員制。
都市部は、オフィス賃料が高いので共有の発想と思うが、地方では情報交換と交流を目的に、既存の組合や会の高い年会費や参加費を避け、場の共有と異業種交流を目的に、地方都市の中心部に、オフィスを共有することはとても有効と思う。熊本市では、男女共同参画センター「はあもにい」には、コワーキングを無料で体験スペースもある。
一時期「ノマド」という働き方があったが、やはり人は交流を持つことが必要ということもあり、コワーキングの場が広がって来たのだろう。今後、地方都市でネット環境が充実して行けば、情報交換と交流の場として、コワーキング的な場所が必要になって来るように思う。
「道化のリーダーシップ」闘う人を笑うより、闘って笑われることを潔く選ぶ
2013年07月26日
「道化のリーダーシップ」闘う人を笑うより、闘って笑われることを潔く選ぶ
朝から、雨がひどく降っています。おはようございます。3日連続の朝ウォーキングのお休みです。これだけ降れば、草刈りも無理です。
さて、昨夜の日韓交流30周年の企画会議の会場に、早く着いたのでショッピングモールの本屋で、時間つぶしをしている時に、目に止まった本「バカと笑われるリーダーが最後に勝つ~トリックスター・リーダーシップ~」(松山淳著)、??初めて聞く言葉に、つい買い求めてしまった。
実は、第4章に、笑われながら時代を切り拓いたリーダーたち、に書かれた日本人は、織田信長、坂本龍馬、本田宗一郎、稲盛和夫。海外ではスティーブ・ジョブズ、ニッコロ・マキャベリ。等々、何か面白そうな本かなと立ち読みして、はじめの文章の冒頭は、
「新しい考えはまず『バカバカしい』と非難され、次に『つまらないことだ』と退けられ、そしてさいごはに『そんなことは誰でも知っている』と言われる」(略)
とあった。これは、19世紀を代表するアメリカの心理学者で哲学者のウィリアム・ジェームズの名言です。組織で新しいことを始めると、「バカバカしい」「つまらない」「キャリアを棒にふるよ」と否定的な言葉が来る。しかし、そんなことは物ともせず、やり遂げる人は、しなやかに人をつなぎ、嘲笑されることも厭わずに、仲間をまとめて行く。
著者は、リーダーシップの研究から「リーダーのつまづき」には、3つの性格・要因があると指摘している。
1.自己認識のズレ
2.行動範囲の狭さ
3.思考の硬直化(白黒思考・真面目さへの過度の執着)
これをの聞こえるには、心理学でいう「トリックスター性」の言動とあった。トリックスターは、「道化」「いたずら者」の意味があり、神話などでは、愚か者と笑われながらも英雄的な偉業を成し遂げる。
本の一節から、
社員が犯罪に手を染めぬように管理したいが、神経質になり過ぎて逆に社員の力を奪っていないか。「あれもだめ、これもだめ」制度(マニュアル)規制で、創造性を高めるリーダーが肩身の狭い思いをする。(略)
はじめの紹介文の締めの言葉は、「闘う人を笑うより、闘って笑われることを潔く選ぶリーダーたちへ」どうそお楽しみください。
これからは、多様な価値観の中で、仲間と新分野へ挑戦し続けることが要求される。しなやかな思考で、広く仲間と交流し、目的に向かって遂行し続けることが必要なのかもしれません。
外の雨も小休止、しかし一日雨模様のようで、久々に気温も猛暑日でない日になりそうです。
朝から、雨がひどく降っています。おはようございます。3日連続の朝ウォーキングのお休みです。これだけ降れば、草刈りも無理です。
さて、昨夜の日韓交流30周年の企画会議の会場に、早く着いたのでショッピングモールの本屋で、時間つぶしをしている時に、目に止まった本「バカと笑われるリーダーが最後に勝つ~トリックスター・リーダーシップ~」(松山淳著)、??初めて聞く言葉に、つい買い求めてしまった。
実は、第4章に、笑われながら時代を切り拓いたリーダーたち、に書かれた日本人は、織田信長、坂本龍馬、本田宗一郎、稲盛和夫。海外ではスティーブ・ジョブズ、ニッコロ・マキャベリ。等々、何か面白そうな本かなと立ち読みして、はじめの文章の冒頭は、
「新しい考えはまず『バカバカしい』と非難され、次に『つまらないことだ』と退けられ、そしてさいごはに『そんなことは誰でも知っている』と言われる」(略)
とあった。これは、19世紀を代表するアメリカの心理学者で哲学者のウィリアム・ジェームズの名言です。組織で新しいことを始めると、「バカバカしい」「つまらない」「キャリアを棒にふるよ」と否定的な言葉が来る。しかし、そんなことは物ともせず、やり遂げる人は、しなやかに人をつなぎ、嘲笑されることも厭わずに、仲間をまとめて行く。
著者は、リーダーシップの研究から「リーダーのつまづき」には、3つの性格・要因があると指摘している。
1.自己認識のズレ
2.行動範囲の狭さ
3.思考の硬直化(白黒思考・真面目さへの過度の執着)
これをの聞こえるには、心理学でいう「トリックスター性」の言動とあった。トリックスターは、「道化」「いたずら者」の意味があり、神話などでは、愚か者と笑われながらも英雄的な偉業を成し遂げる。
本の一節から、
社員が犯罪に手を染めぬように管理したいが、神経質になり過ぎて逆に社員の力を奪っていないか。「あれもだめ、これもだめ」制度(マニュアル)規制で、創造性を高めるリーダーが肩身の狭い思いをする。(略)
はじめの紹介文の締めの言葉は、「闘う人を笑うより、闘って笑われることを潔く選ぶリーダーたちへ」どうそお楽しみください。
これからは、多様な価値観の中で、仲間と新分野へ挑戦し続けることが要求される。しなやかな思考で、広く仲間と交流し、目的に向かって遂行し続けることが必要なのかもしれません。
外の雨も小休止、しかし一日雨模様のようで、久々に気温も猛暑日でない日になりそうです。





