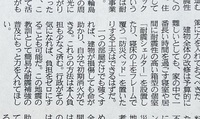ブータンの国民総幸福量(GNH)、熊本の県民総幸福量(AKH)とは何か?
2013年11月22日
ブータンの国民総幸福量(GNH)、熊本の県民総幸福量(AKH)とは何か?
おはようございます。今朝のウォーキングは、月夜の綺麗な夜空を見ながら歩きました。気分爽快、今日も頑張れそうです。
さて、今日のテーマは、総幸福量の話です。ブータンの政策が、世界の注目を集めて、経済成長ばかりでは幸福感は満たせない。違った発想の幸福を目指すべきと、アジアの小国が、世界へメッセージを出したのが、国民総幸福量(GNH)です。
実は、熊本県知事が2期目になり、独自目標の「県民総幸福量(AKH)」の算出に取り組んでいる。なかなか理解できない分野、学者知事らしい発想と思いますが、ブータンの「心の幸せ重要視」の政策GNH(国民総幸福量)が元のようですが、一人ひとり求める幸福感はそれぞれに違う、GNHがどんな内容か?以前から関心があった。
ここ数日、熊本にそのブータンのGNH政策に深く関わった研究者が来熊し、知事と会見したり、講演会あったりと、熊本の話題になっている。GNHに関しても、色々な研究が広がり、日本国内の自治体も取り入れるところも増えている。本家のブータンの総幸福量は、次の4つの柱と9分野にわたる領域をベースに、249の質問で、幸福量を測るようです。
GNH 国民総幸福(4つの柱)
・持続可能で公平な社会経済的開発
・環境保護
・文化の推進
・良き統治
GNHは4つの柱と、さらに9つの領域に分けられている。
・心理的な幸福
・国民の健康
・教育
・文化の多様性
・地域の活力
・環境の多様性の活力
・時間の使い方とバランス(ワーク・ライフ・バランス
・生活水準
・良き統治(ガバナンス)
ブータンを訪問したジャーナリストの池上彰氏のブログに、こんなブータンの感想がありました。
「ブータンは国土の60%以上は森でなければいけない、という基準が設けられている。経済が発展していくと、どんどん木を切って、開発します。それにストップをかけようということ。緑を大事にしながら、発展しましょうということです」
「ブータンのGNHも、国民に幸福を押しつけるわけではないんです。それぞれの人が幸福を追求できるような状況をつくっていくと考えれば、日本でもそれぞれの人が幸福を追求できるような環境をつくっていく。あるいは、そのために政治が頑張らないといけない。探し求めていた『青い鳥』は実は近くにいるのかもしれない。日本が新たに考える。そのきっかけをブータン、あるいはチベット仏教が与えてくれているのかなと思います」
(以上、池上彰氏のブログより)
日本文化に足るを知る「知足」という生活観があります。意外に、知足的な発想がGNHにあるように感じました。池上氏の「探し求めていた『青い鳥』は実は近くにいるのかもしれない」の言葉ではないですが、遠い国や国内の先進地を羨望し、新しい取り組みをするよりも、身近にある生活を充実させることが、総幸福量の向上を増やすことにつながるのかもしれないと思いました。
そろそろ、12月議会の一般質問の準備のため、色々資料集めをする時期になりました。今回の質問から、ブータンの総幸福量ではないですが、身近な生活の視点からの質問をいくつか準備しています。12月9日の午前11時前後に、私の質問時間が予定されています。関心のある方は、傍聴いただけるとありがたいです。
おはようございます。今朝のウォーキングは、月夜の綺麗な夜空を見ながら歩きました。気分爽快、今日も頑張れそうです。
さて、今日のテーマは、総幸福量の話です。ブータンの政策が、世界の注目を集めて、経済成長ばかりでは幸福感は満たせない。違った発想の幸福を目指すべきと、アジアの小国が、世界へメッセージを出したのが、国民総幸福量(GNH)です。
実は、熊本県知事が2期目になり、独自目標の「県民総幸福量(AKH)」の算出に取り組んでいる。なかなか理解できない分野、学者知事らしい発想と思いますが、ブータンの「心の幸せ重要視」の政策GNH(国民総幸福量)が元のようですが、一人ひとり求める幸福感はそれぞれに違う、GNHがどんな内容か?以前から関心があった。
ここ数日、熊本にそのブータンのGNH政策に深く関わった研究者が来熊し、知事と会見したり、講演会あったりと、熊本の話題になっている。GNHに関しても、色々な研究が広がり、日本国内の自治体も取り入れるところも増えている。本家のブータンの総幸福量は、次の4つの柱と9分野にわたる領域をベースに、249の質問で、幸福量を測るようです。
GNH 国民総幸福(4つの柱)
・持続可能で公平な社会経済的開発
・環境保護
・文化の推進
・良き統治
GNHは4つの柱と、さらに9つの領域に分けられている。
・心理的な幸福
・国民の健康
・教育
・文化の多様性
・地域の活力
・環境の多様性の活力
・時間の使い方とバランス(ワーク・ライフ・バランス
・生活水準
・良き統治(ガバナンス)
ブータンを訪問したジャーナリストの池上彰氏のブログに、こんなブータンの感想がありました。
「ブータンは国土の60%以上は森でなければいけない、という基準が設けられている。経済が発展していくと、どんどん木を切って、開発します。それにストップをかけようということ。緑を大事にしながら、発展しましょうということです」
「ブータンのGNHも、国民に幸福を押しつけるわけではないんです。それぞれの人が幸福を追求できるような状況をつくっていくと考えれば、日本でもそれぞれの人が幸福を追求できるような環境をつくっていく。あるいは、そのために政治が頑張らないといけない。探し求めていた『青い鳥』は実は近くにいるのかもしれない。日本が新たに考える。そのきっかけをブータン、あるいはチベット仏教が与えてくれているのかなと思います」
(以上、池上彰氏のブログより)
日本文化に足るを知る「知足」という生活観があります。意外に、知足的な発想がGNHにあるように感じました。池上氏の「探し求めていた『青い鳥』は実は近くにいるのかもしれない」の言葉ではないですが、遠い国や国内の先進地を羨望し、新しい取り組みをするよりも、身近にある生活を充実させることが、総幸福量の向上を増やすことにつながるのかもしれないと思いました。
そろそろ、12月議会の一般質問の準備のため、色々資料集めをする時期になりました。今回の質問から、ブータンの総幸福量ではないですが、身近な生活の視点からの質問をいくつか準備しています。12月9日の午前11時前後に、私の質問時間が予定されています。関心のある方は、傍聴いただけるとありがたいです。
<第二次世界大戦の検証>一度は行きたかった「大刀洗平和記念館」に行ってきました。
能登半島地震、「倒壊死9割」に愕然となる。何か耐震の工夫が必要。
<熊本城再建>宇土櫓の解体修理に関心を持っています。現場見学会に参加したい。
「耐震シェルター」、「防災ベッド」、一つの部屋だけ強化する。〜福和伸夫名誉教授(名古屋大学)〜
世界のデジタル競争力は、日本は世界32位、しかし韓国は6位だった。日本のデジタル化の取り組みを前へ。
>たとえ100年続いてきた仕組みであったとしても、変えようとする柔軟性を、校長をはじめとする教育関係者は持つべき
能登半島地震、「倒壊死9割」に愕然となる。何か耐震の工夫が必要。
<熊本城再建>宇土櫓の解体修理に関心を持っています。現場見学会に参加したい。
「耐震シェルター」、「防災ベッド」、一つの部屋だけ強化する。〜福和伸夫名誉教授(名古屋大学)〜
世界のデジタル競争力は、日本は世界32位、しかし韓国は6位だった。日本のデジタル化の取り組みを前へ。
>たとえ100年続いてきた仕組みであったとしても、変えようとする柔軟性を、校長をはじめとする教育関係者は持つべき
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。