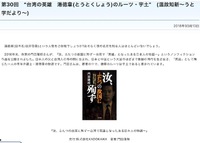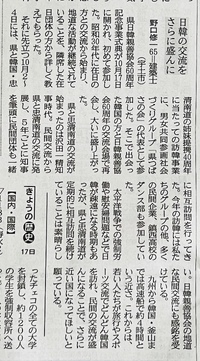<エジプト危機>オイルマネー食料市場に流入、物価上昇招く恐れ
2011年02月02日
<エジプト危機>オイルマネーが食料市場に流入、物価上昇招く恐れ
エジプト危機、中東の物価高騰、石油高騰、食料高騰
→ 日本のTPP受け入れと農業自給率50%の行方は
■焦点:オイルマネーが食料市場に流入、一段の物価上昇招く恐れも(ロイター)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1489895&media_id=52
>2月1日、食料インフレによる社会不安を警戒する中東の産油国が、食料の買い付けを急いでいる。写真は昨年9月、ロシアのアルタイ地方で撮影された小麦(2011年 ロイター/Andrei Kasprishin)
>食料インフレによる社会不安を警戒する中東の産油国が、食料の買い付けを急いでいる。在庫の積み増しで価格高騰を防ぐことが狙いだが、大量のオイルマネーが食料市場に流入すれば、広範な物価上昇をもたらす恐れもある。
>食料インフレは各地で暴動や反政府デモの一因となっており、チュニジアやエジプトの混乱が自国に飛び火することを警戒する中東湾岸諸国は、海外からの食料輸入加速に加え、海外農地への投資にも乗り出している。
・サウジは小麦備蓄を拡大
>サウジアラビアは先週、世界的な食料インフレを懸念していると表明。サウジには、大量の外国人労働者が流入、約1900万人の自国民は高失業率に悩まされている。
>昨年のサウジの小麦輸入は200万トン。今年の輸入は260万トンに達する可能性があり、2015年までに年間300万トンの輸入が必要になる見通しという。
>サウジは政府は、2015年までに大麦380万トン、コメ125万トン、砂糖7800万トンが必要になるとの見通しも示している。
・アルジェリアも大量の買い付け
>他の石油輸出国機構(OPEC)加盟国も食料確保を急いでいる。
>アルジェリアは1月、100万トン近い小麦を買い付けたことを確認。穀物輸入を緊急に増やすよう指示を出したことも明らかにした。
>リビア国営石油のガーネム代表は、商品価格全般が値上がりしており、原油高は正当化できるとの考えを繰り返し示している。
>同代表はロイターに「食品価格の高騰分を補うには、1バレル100ドル前後の原油価格が必要だ。食品価格の上昇は、所得が大きく減ることを意味する」と述べた。
・途上国の農地を買収
>湾岸諸国は、食料安全保障のため、途上国の農地買収にも乗り出している。
>特に、外国人労働者の流入を背景に自国民の失業率が昨年10%に達したサウジでは、国民の不満が高まりつつある。
・ドル安に伴う原油収入の目減りを回避
>米原油先物は昨年5月に付けた安値から40%以上上昇。
>米小麦先物は昨年6月の2倍以上に急騰している。
>商品価格の上昇は、米金融緩和でドル安が進んだことも一因だ。今後、産油国がドル安に伴う輸出収入の目減りを防ぐため、一段の原油高を求める可能性もある。
>原油高が進めば、石油系肥料が値上がりし、農産物価格の上昇を促す恐れもある。
・農地買収、食料インフレを促す恐れも
>湾岸諸国の海外農地買収も、食料インフレの原因となり得る。
>サウジは2009年、企業の農地投資を支援する組織を8億ドルを投じて設立。投資先は20カ国以上にのぼる。
・途上国が恩恵を受けない
>「これまでのところ、GCC諸国の主な目的は自国の食料確保のようだ。余った分は利益を上乗せして国際市場で売却する。途上国が恩恵を受けるとは思えない」との認識を示した。
チュニジアの政変から、数週間の経たないうちに、エジプト危機が起こった。
中東の石油産油国は、同じような火種を抱えた国は多い。
各国の若者が、物価高騰、経済不安から、現政権の打破に国民が動けば、中東の安定が崩れ、日本にも多大な影響が起こり始めると思います。
しかし、エジプトの若者たちに生活の厳しさを報じる報道、特別警察に言論の自由を抑えられて来た30年の不満が今回のデモに現れていると思います。ただ、政権奪取だけの革命的な運動なく、良識ある市民が中心となり、整然と街を自主的管理しながら、デモが続いているように思います。
一部に略奪の事件もあるが、交通整理など市民の印象がすこぶる良いと感じる。政権側の対応次第では、9月までムバラク政権が持つとは思えない印象を受けます。エジプトの動向を、世界の人々がかたずを飲んで見ています。中東のバランサーとして機能して来たエジプトの誇りを持って、民主的にリーダーが選ばれることを望みます。
長引けは、長引くほど、世界の不安が嵩み、物価高騰、食料の高騰から、オイルマネーが食料に集中せれば大変な状況を生み出します。
今、日本はTPPの問題が議論されている。国会議員の頭に中に、世界に食料事情を踏まえて、現国会で討論がなされているか不安になる。状況は、常に変化している。
リーダーとは、支援者(国民)の要望に耳を傾け、社会変化(状況)を的確に把握し、瞬時に判断し、梶を切り替えることも必要なことがある。
金曜礼拝後のエジプトに、注目をしたいと思います。
キューバではないですが、食料危機から食料輸入が少なくなれば、日本の休耕地を元に戻すことが求められる状況が来るかもしれません。TPPの準備も必要ですが、中山間地の休耕田(畑)が山林に戻る前に、将来の日本の食料確保を考えることも必要かもしれません。
民主党は、次年度に大きく中山間地保全の助成を、大ナタを振るって減額しました。後継者の意欲を更に削ぐことになっています。
中東危機、中国の隆盛、インドの成長、アフリカの経済勃興を見るに、日本国民の命をどう守るか、真剣な議論が国会でなされることが必要と思います。
エジプト危機、中東の物価高騰、石油高騰、食料高騰
→ 日本のTPP受け入れと農業自給率50%の行方は
■焦点:オイルマネーが食料市場に流入、一段の物価上昇招く恐れも(ロイター)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1489895&media_id=52
>2月1日、食料インフレによる社会不安を警戒する中東の産油国が、食料の買い付けを急いでいる。写真は昨年9月、ロシアのアルタイ地方で撮影された小麦(2011年 ロイター/Andrei Kasprishin)
>食料インフレによる社会不安を警戒する中東の産油国が、食料の買い付けを急いでいる。在庫の積み増しで価格高騰を防ぐことが狙いだが、大量のオイルマネーが食料市場に流入すれば、広範な物価上昇をもたらす恐れもある。
>食料インフレは各地で暴動や反政府デモの一因となっており、チュニジアやエジプトの混乱が自国に飛び火することを警戒する中東湾岸諸国は、海外からの食料輸入加速に加え、海外農地への投資にも乗り出している。
・サウジは小麦備蓄を拡大
>サウジアラビアは先週、世界的な食料インフレを懸念していると表明。サウジには、大量の外国人労働者が流入、約1900万人の自国民は高失業率に悩まされている。
>昨年のサウジの小麦輸入は200万トン。今年の輸入は260万トンに達する可能性があり、2015年までに年間300万トンの輸入が必要になる見通しという。
>サウジは政府は、2015年までに大麦380万トン、コメ125万トン、砂糖7800万トンが必要になるとの見通しも示している。
・アルジェリアも大量の買い付け
>他の石油輸出国機構(OPEC)加盟国も食料確保を急いでいる。
>アルジェリアは1月、100万トン近い小麦を買い付けたことを確認。穀物輸入を緊急に増やすよう指示を出したことも明らかにした。
>リビア国営石油のガーネム代表は、商品価格全般が値上がりしており、原油高は正当化できるとの考えを繰り返し示している。
>同代表はロイターに「食品価格の高騰分を補うには、1バレル100ドル前後の原油価格が必要だ。食品価格の上昇は、所得が大きく減ることを意味する」と述べた。
・途上国の農地を買収
>湾岸諸国は、食料安全保障のため、途上国の農地買収にも乗り出している。
>特に、外国人労働者の流入を背景に自国民の失業率が昨年10%に達したサウジでは、国民の不満が高まりつつある。
・ドル安に伴う原油収入の目減りを回避
>米原油先物は昨年5月に付けた安値から40%以上上昇。
>米小麦先物は昨年6月の2倍以上に急騰している。
>商品価格の上昇は、米金融緩和でドル安が進んだことも一因だ。今後、産油国がドル安に伴う輸出収入の目減りを防ぐため、一段の原油高を求める可能性もある。
>原油高が進めば、石油系肥料が値上がりし、農産物価格の上昇を促す恐れもある。
・農地買収、食料インフレを促す恐れも
>湾岸諸国の海外農地買収も、食料インフレの原因となり得る。
>サウジは2009年、企業の農地投資を支援する組織を8億ドルを投じて設立。投資先は20カ国以上にのぼる。
・途上国が恩恵を受けない
>「これまでのところ、GCC諸国の主な目的は自国の食料確保のようだ。余った分は利益を上乗せして国際市場で売却する。途上国が恩恵を受けるとは思えない」との認識を示した。
チュニジアの政変から、数週間の経たないうちに、エジプト危機が起こった。
中東の石油産油国は、同じような火種を抱えた国は多い。
各国の若者が、物価高騰、経済不安から、現政権の打破に国民が動けば、中東の安定が崩れ、日本にも多大な影響が起こり始めると思います。
しかし、エジプトの若者たちに生活の厳しさを報じる報道、特別警察に言論の自由を抑えられて来た30年の不満が今回のデモに現れていると思います。ただ、政権奪取だけの革命的な運動なく、良識ある市民が中心となり、整然と街を自主的管理しながら、デモが続いているように思います。
一部に略奪の事件もあるが、交通整理など市民の印象がすこぶる良いと感じる。政権側の対応次第では、9月までムバラク政権が持つとは思えない印象を受けます。エジプトの動向を、世界の人々がかたずを飲んで見ています。中東のバランサーとして機能して来たエジプトの誇りを持って、民主的にリーダーが選ばれることを望みます。
長引けは、長引くほど、世界の不安が嵩み、物価高騰、食料の高騰から、オイルマネーが食料に集中せれば大変な状況を生み出します。
今、日本はTPPの問題が議論されている。国会議員の頭に中に、世界に食料事情を踏まえて、現国会で討論がなされているか不安になる。状況は、常に変化している。
リーダーとは、支援者(国民)の要望に耳を傾け、社会変化(状況)を的確に把握し、瞬時に判断し、梶を切り替えることも必要なことがある。
金曜礼拝後のエジプトに、注目をしたいと思います。
キューバではないですが、食料危機から食料輸入が少なくなれば、日本の休耕地を元に戻すことが求められる状況が来るかもしれません。TPPの準備も必要ですが、中山間地の休耕田(畑)が山林に戻る前に、将来の日本の食料確保を考えることも必要かもしれません。
民主党は、次年度に大きく中山間地保全の助成を、大ナタを振るって減額しました。後継者の意欲を更に削ぐことになっています。
中東危機、中国の隆盛、インドの成長、アフリカの経済勃興を見るに、日本国民の命をどう守るか、真剣な議論が国会でなされることが必要と思います。
地元小学6年生に、太平洋戦争末期に宇土市で起こった戦闘の話した。
環境と経済の両立を目指す「2005.フューチャー500国際シンポジウムin北京」に参加
<台湾の英雄は宇土にルーツ>宇土市と台湾の台南市の日台交流の準備が始まっています。
世界のデジタル競争力は、日本は世界32位、しかし韓国は6位だった。日本のデジタル化の取り組みを前へ。
11月17日の記事
国家意識を現すユーモアとは?〜江沢民(中国・元国家主席)のハワイでのスピーチ〜
環境と経済の両立を目指す「2005.フューチャー500国際シンポジウムin北京」に参加
<台湾の英雄は宇土にルーツ>宇土市と台湾の台南市の日台交流の準備が始まっています。
世界のデジタル競争力は、日本は世界32位、しかし韓国は6位だった。日本のデジタル化の取り組みを前へ。
11月17日の記事
国家意識を現すユーモアとは?〜江沢民(中国・元国家主席)のハワイでのスピーチ〜
Posted by ノグチ(noguchi) at 17:41│Comments(0)
│国際関係
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。