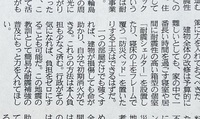「健康と昼食」平日の昼食、予算はいくら?(アンケート)
2011年03月04日
「健康と昼食」平日の昼食、予算はいくら?(アンケート)
■平日の昼食、予算はいくら?
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1523253&media_id=40
>昼食の平均的な予算
>平日の昼食は誰と食べることが多いのだろうか。この質問に対し、「自分ひとり」(51.3%)と答えた人が半数を超えた。次いで「職場の同僚」(22.8%)、「家族」(17.0%)、「職場の上司・先輩や部下」(4.7%)と続いた。
私は、一人が多いですね。
議会がある時は、先輩議員と食事をしながら、色々ノーハウを聞くことが多いです。
自宅で昼食は、決まった時間ではなく、昼前後が多いですね。
>また昼食の平均的な予算を聞いたところ「100円以上~300円未満」(34.7%)と答えた人がトップ。以下「300円以上~500円未満」(33.4%)、「100円未満」(12.6%)、「500円以上~700円未満」(12.5%)だった。平日の昼食は300円未満で済ませる人が、半数近くいるようだ。
「100円未満」(12.6%)、
どんな食べものを食べてるか、少々心配になります。
わが家も、大学生が県外で一人暮らしをしているで、何を食べているかとても気なります。
>インターネットによる調査で、10代以上の男女1万3246人が回答した。調査期間は2月1日から5日まで。【Business Media 誠】
けっこうな数なので、日本の昼食の現状が分かるように思います。
今日、日本ダイエット市場は、1兆円3千億円なることを聞きました。
飽食の時代と、切り詰める昼食、なにか矛盾を感じますが、これが現代日本の食事事情なのだと思います。
私も人生の後半になり、肉類から魚に、油ものから野菜中心の食事なって行くのだと思います。健康、自分自身の養生しか、方法は無いのかもしれません。
■平日の昼食、予算はいくら?
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1523253&media_id=40
>昼食の平均的な予算
>平日の昼食は誰と食べることが多いのだろうか。この質問に対し、「自分ひとり」(51.3%)と答えた人が半数を超えた。次いで「職場の同僚」(22.8%)、「家族」(17.0%)、「職場の上司・先輩や部下」(4.7%)と続いた。
私は、一人が多いですね。
議会がある時は、先輩議員と食事をしながら、色々ノーハウを聞くことが多いです。
自宅で昼食は、決まった時間ではなく、昼前後が多いですね。
>また昼食の平均的な予算を聞いたところ「100円以上~300円未満」(34.7%)と答えた人がトップ。以下「300円以上~500円未満」(33.4%)、「100円未満」(12.6%)、「500円以上~700円未満」(12.5%)だった。平日の昼食は300円未満で済ませる人が、半数近くいるようだ。
「100円未満」(12.6%)、
どんな食べものを食べてるか、少々心配になります。
わが家も、大学生が県外で一人暮らしをしているで、何を食べているかとても気なります。
>インターネットによる調査で、10代以上の男女1万3246人が回答した。調査期間は2月1日から5日まで。【Business Media 誠】
けっこうな数なので、日本の昼食の現状が分かるように思います。
今日、日本ダイエット市場は、1兆円3千億円なることを聞きました。
飽食の時代と、切り詰める昼食、なにか矛盾を感じますが、これが現代日本の食事事情なのだと思います。
私も人生の後半になり、肉類から魚に、油ものから野菜中心の食事なって行くのだと思います。健康、自分自身の養生しか、方法は無いのかもしれません。
<第二次世界大戦の検証>一度は行きたかった「大刀洗平和記念館」に行ってきました。
能登半島地震、「倒壊死9割」に愕然となる。何か耐震の工夫が必要。
<熊本城再建>宇土櫓の解体修理に関心を持っています。現場見学会に参加したい。
「耐震シェルター」、「防災ベッド」、一つの部屋だけ強化する。〜福和伸夫名誉教授(名古屋大学)〜
世界のデジタル競争力は、日本は世界32位、しかし韓国は6位だった。日本のデジタル化の取り組みを前へ。
>たとえ100年続いてきた仕組みであったとしても、変えようとする柔軟性を、校長をはじめとする教育関係者は持つべき
能登半島地震、「倒壊死9割」に愕然となる。何か耐震の工夫が必要。
<熊本城再建>宇土櫓の解体修理に関心を持っています。現場見学会に参加したい。
「耐震シェルター」、「防災ベッド」、一つの部屋だけ強化する。〜福和伸夫名誉教授(名古屋大学)〜
世界のデジタル競争力は、日本は世界32位、しかし韓国は6位だった。日本のデジタル化の取り組みを前へ。
>たとえ100年続いてきた仕組みであったとしても、変えようとする柔軟性を、校長をはじめとする教育関係者は持つべき
Posted by ノグチ(noguchi) at 21:25│Comments(0)
│新技術、新潮流
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。