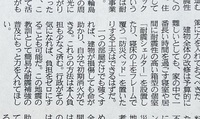『環成経』福岡キックオフの会~グリーンビジネス・ネットワーク
2009年11月13日
『環成経』福岡・キックオフの会~グリーンビジネス・ネットワーク~
ご案内
催し 『環成経』福岡・キックオフの会
日時 2009年11月18日17:00~20:00
場所 福岡ビル9F 5ホール(福岡市中央区天神1丁目11番17号)
参加費 無料
申込先 環成経 事務局
東京都港区西新橋3-23-12第二山内ビル3F ㈱イースクエアー内
Tel03-5777-3261 Fax 03-5777-6735
福岡キックオフ公式サイト
http://www.kanseikei.net/assets/files/info_kickoff/info_kickoff_fukuoka_1118.pdf
<添付資料>
『環成経』~グリーンビジネス・ネットワーク~
(持続可能な社会を目指す企業家ネットワーク)
公式サイト http://www.kanseikei.net/index.php?id=1
■環成経が目指すもの
環成経の活動を通じて、個々の企業・事業主が、グリーンビジネスを切り口に次なる事業機会を発見・発掘する。
さらに、地域内・他地域の仲間と協働し、新たな事業を生み出していくことで、 地域を活性化させ、日本に活力を取り戻す。
環成経の信条一、自然から学ぶビジネスを実践し、自然の法則を守りながら発展する
一、社会を食いものにしない、誠実で健全な事業を営む
一、人任せにせず、一人称で明るい未来社会づくりに挑戦する
3つの特徴環成経に志ある事業主が集まり、共に「学び」、「企画」、「実践」することで、“事業機会の発見・発掘”と“地域社会・経済の発展”を目指していきます。
■環成経が考える“グリーンビジネス”とは?
環成経では、グリーンビジネスを8つの“分野”、“段階”、“手法” の切り口で整理しています。
狭義の意味での環境ビジネス(廃棄物処理や土壌汚染対策など)に留まらず、限りある地球・地域資源を活かし、事業の様々な分野での工夫を行うことで、次なる事業機会の発見・発掘と地域社会・経済の発展を目指しています。
・グリーンビジネス 8分野(添付ファイル、イメージ1)

活用できる環境・地球資源を8つの側面に分類しています。環境負荷を低減させるだけでなく、環境・地域資源を活かし、環境と社会・経済の調和を図ることで、事業機会の発見・発掘を目指します。
・グリーンビジネス 8段階(添付ファイル、イメージ2)
グリーンビジネスの工程を8つに分類しています。 社会に受け入れられ、環境にも良い商品・サービスを生み出すためには、調達、お客様の使用・活用など、自社事業の上流・下流を含めた見直しが必要です。
グリーンビジネス 8手法事業を「グリーン化」する手法を8つに分類しています。「グリーンビジネス8分野」や「グリーンビジネス8段階」において、どのようなグリーンビジネスが考えられるかといった、アイデアを導くための切り口を提示しています。

■代表の思い
・共同代表
NPO法人フューチャー500 理事長 木内 孝
22世紀を迎えた2101年の時点でこの地球上に人類が住んでいる可能性について、大学の先生のお話がありました。
結論は五分五分、92年後にはこの世に我々人間がいない確率が50%だと仰るのです。今の暮らし、自然環境を20年前、30年昔の自分の生活を支えていた周りの状況を思い出して、比べてご覧なさい・・・とも言われました。
自然を師とする“環成経”の活動の出発点を指摘された思いです。
(株)イースクエア 代表取締役社長 ピーター D. ピーダーセン
3年以内に、日本各地域の志ある事業主がつながり合うことにより、次々に新しい事業を生み出し、地域の資源を大いに活用し、この国本来の元気を取り戻し始める。
グリーンビジネスの実践を通じて、「環境で成長・発展する経済」を形にする。これが、"環成経"の近未来の目標であり、ネットワークを結成し成功させたい、想いと行動の源である。
・発起人
1.石川県 会宝産業(株)代表取締役社長 近藤 典彦
「売上が伸びるほど、利益が増えるほど環境の改善につながるビジネス。」
これは夢の話ではありません。時代の後押しもあり、様々な分野で「環境」が単なるコストではなく、ビジネスチャンスになっています。
“環成経”を通じて、ここ金沢に志ある企業が集まり、「環境」からビジネスを生み出し、社会を変える大きな力になることを切に願います。
2.愛知県 イシグログループ代表 石黒 功
「これからの農業は環境を保全する循環型に切り替えるべきだ。」
そんな気付きを与えてくれたのが(株)イースクエア※でした。以来弊社は事業の舵を切るべく様々な試みをしてきました。“環成経”が、地域の企業が抱える課題に応え、志ある企業が新しい気付きと実践を通して環境ビジネスを育んでいく場となれば望外の喜びです。※環成経の運営事務局
3.大阪府 サラヤ(株) 代表取締役社長 更家 悠介
グローバル時代、世界中の人間が物質的豊かさを目指し、地球の収容能力は限界を迎えており、ビジネスのあり方も変化が求められている。ビジネスは、消費者に対し、限られた資源を有効に活用し、地球温暖化を防ぎ、生物多様性を守るといった、持続可能なライフスタイルを提案し、実践すべきである。
このような変化に向けて、環成経では、「環境」をポジティブなものとして捉え、志ある企業と共に明日のビジネスを作っていきたい。
4.地域代表山梨県 (株)ティー・シー・シー 代表取締役 近藤 雅秀
気候変動の影響は世界の主要農産地の半数以上に及んでおり、今後も、各地で大幅な生産減が予測されています。主要先進国の中でも食糧自給率が著しく低い我が国において、「食料確保」は国家的優先課題と言えます。
「食」ビジネスに携わる者として、“環成経”の熱意あふれる方々と自然環境・地域社会・企業利益のバランスのとれた新しいビジネスモデルを創り、持続的な発展を目指したいと思います。
5.福岡県 加藤特許事務所 代表 加藤 久
「環成経」は環境と調和しつつ事業を成長させることを目指す事業主のネットワークです。当地にはグリーンビジネスの基礎となる技術が山ほどありますが、そこからビジネスを生み出すには、なによりも実行力ある強力なネットワークの活用が近道です。
「企業が成長するほど環境が良くなる」という理念を掲げる「環成経」に集い、人類の将来のためのグリーンビジネスを立ち上げましょう。志ある方のご参加をお待ちしております。
6.(南部九州に作りましょう)
熊本・大分・宮崎・鹿児島をネットワークします。
2010年01月23日19:00、熊本市で呼びかけの会を開きます。
★横井小楠生誕200年記念「国際シンポジウム」
日時 2009年11月21日13時~(開場 12時)
会場 熊本市民会館大ホール
~龍馬←海舟←小楠、維新の回天思想は、出会いが演出~
http://blogs.yahoo.co.jp/echq96/archive/2009/11/12
ご案内
催し 『環成経』福岡・キックオフの会
日時 2009年11月18日17:00~20:00
場所 福岡ビル9F 5ホール(福岡市中央区天神1丁目11番17号)
参加費 無料
申込先 環成経 事務局
東京都港区西新橋3-23-12第二山内ビル3F ㈱イースクエアー内
Tel03-5777-3261 Fax 03-5777-6735
福岡キックオフ公式サイト
http://www.kanseikei.net/assets/files/info_kickoff/info_kickoff_fukuoka_1118.pdf
<添付資料>
『環成経』~グリーンビジネス・ネットワーク~
(持続可能な社会を目指す企業家ネットワーク)
公式サイト http://www.kanseikei.net/index.php?id=1
■環成経が目指すもの
環成経の活動を通じて、個々の企業・事業主が、グリーンビジネスを切り口に次なる事業機会を発見・発掘する。
さらに、地域内・他地域の仲間と協働し、新たな事業を生み出していくことで、 地域を活性化させ、日本に活力を取り戻す。
環成経の信条一、自然から学ぶビジネスを実践し、自然の法則を守りながら発展する
一、社会を食いものにしない、誠実で健全な事業を営む
一、人任せにせず、一人称で明るい未来社会づくりに挑戦する
3つの特徴環成経に志ある事業主が集まり、共に「学び」、「企画」、「実践」することで、“事業機会の発見・発掘”と“地域社会・経済の発展”を目指していきます。
■環成経が考える“グリーンビジネス”とは?
環成経では、グリーンビジネスを8つの“分野”、“段階”、“手法” の切り口で整理しています。
狭義の意味での環境ビジネス(廃棄物処理や土壌汚染対策など)に留まらず、限りある地球・地域資源を活かし、事業の様々な分野での工夫を行うことで、次なる事業機会の発見・発掘と地域社会・経済の発展を目指しています。
・グリーンビジネス 8分野(添付ファイル、イメージ1)

活用できる環境・地球資源を8つの側面に分類しています。環境負荷を低減させるだけでなく、環境・地域資源を活かし、環境と社会・経済の調和を図ることで、事業機会の発見・発掘を目指します。
・グリーンビジネス 8段階(添付ファイル、イメージ2)
グリーンビジネスの工程を8つに分類しています。 社会に受け入れられ、環境にも良い商品・サービスを生み出すためには、調達、お客様の使用・活用など、自社事業の上流・下流を含めた見直しが必要です。
グリーンビジネス 8手法事業を「グリーン化」する手法を8つに分類しています。「グリーンビジネス8分野」や「グリーンビジネス8段階」において、どのようなグリーンビジネスが考えられるかといった、アイデアを導くための切り口を提示しています。

■代表の思い
・共同代表
NPO法人フューチャー500 理事長 木内 孝
22世紀を迎えた2101年の時点でこの地球上に人類が住んでいる可能性について、大学の先生のお話がありました。
結論は五分五分、92年後にはこの世に我々人間がいない確率が50%だと仰るのです。今の暮らし、自然環境を20年前、30年昔の自分の生活を支えていた周りの状況を思い出して、比べてご覧なさい・・・とも言われました。
自然を師とする“環成経”の活動の出発点を指摘された思いです。
(株)イースクエア 代表取締役社長 ピーター D. ピーダーセン
3年以内に、日本各地域の志ある事業主がつながり合うことにより、次々に新しい事業を生み出し、地域の資源を大いに活用し、この国本来の元気を取り戻し始める。
グリーンビジネスの実践を通じて、「環境で成長・発展する経済」を形にする。これが、"環成経"の近未来の目標であり、ネットワークを結成し成功させたい、想いと行動の源である。
・発起人
1.石川県 会宝産業(株)代表取締役社長 近藤 典彦
「売上が伸びるほど、利益が増えるほど環境の改善につながるビジネス。」
これは夢の話ではありません。時代の後押しもあり、様々な分野で「環境」が単なるコストではなく、ビジネスチャンスになっています。
“環成経”を通じて、ここ金沢に志ある企業が集まり、「環境」からビジネスを生み出し、社会を変える大きな力になることを切に願います。
2.愛知県 イシグログループ代表 石黒 功
「これからの農業は環境を保全する循環型に切り替えるべきだ。」
そんな気付きを与えてくれたのが(株)イースクエア※でした。以来弊社は事業の舵を切るべく様々な試みをしてきました。“環成経”が、地域の企業が抱える課題に応え、志ある企業が新しい気付きと実践を通して環境ビジネスを育んでいく場となれば望外の喜びです。※環成経の運営事務局
3.大阪府 サラヤ(株) 代表取締役社長 更家 悠介
グローバル時代、世界中の人間が物質的豊かさを目指し、地球の収容能力は限界を迎えており、ビジネスのあり方も変化が求められている。ビジネスは、消費者に対し、限られた資源を有効に活用し、地球温暖化を防ぎ、生物多様性を守るといった、持続可能なライフスタイルを提案し、実践すべきである。
このような変化に向けて、環成経では、「環境」をポジティブなものとして捉え、志ある企業と共に明日のビジネスを作っていきたい。
4.地域代表山梨県 (株)ティー・シー・シー 代表取締役 近藤 雅秀
気候変動の影響は世界の主要農産地の半数以上に及んでおり、今後も、各地で大幅な生産減が予測されています。主要先進国の中でも食糧自給率が著しく低い我が国において、「食料確保」は国家的優先課題と言えます。
「食」ビジネスに携わる者として、“環成経”の熱意あふれる方々と自然環境・地域社会・企業利益のバランスのとれた新しいビジネスモデルを創り、持続的な発展を目指したいと思います。
5.福岡県 加藤特許事務所 代表 加藤 久
「環成経」は環境と調和しつつ事業を成長させることを目指す事業主のネットワークです。当地にはグリーンビジネスの基礎となる技術が山ほどありますが、そこからビジネスを生み出すには、なによりも実行力ある強力なネットワークの活用が近道です。
「企業が成長するほど環境が良くなる」という理念を掲げる「環成経」に集い、人類の将来のためのグリーンビジネスを立ち上げましょう。志ある方のご参加をお待ちしております。
6.(南部九州に作りましょう)
熊本・大分・宮崎・鹿児島をネットワークします。
2010年01月23日19:00、熊本市で呼びかけの会を開きます。
★横井小楠生誕200年記念「国際シンポジウム」
日時 2009年11月21日13時~(開場 12時)
会場 熊本市民会館大ホール
~龍馬←海舟←小楠、維新の回天思想は、出会いが演出~
http://blogs.yahoo.co.jp/echq96/archive/2009/11/12
<第二次世界大戦の検証>一度は行きたかった「大刀洗平和記念館」に行ってきました。
能登半島地震、「倒壊死9割」に愕然となる。何か耐震の工夫が必要。
<熊本城再建>宇土櫓の解体修理に関心を持っています。現場見学会に参加したい。
「耐震シェルター」、「防災ベッド」、一つの部屋だけ強化する。〜福和伸夫名誉教授(名古屋大学)〜
世界のデジタル競争力は、日本は世界32位、しかし韓国は6位だった。日本のデジタル化の取り組みを前へ。
>たとえ100年続いてきた仕組みであったとしても、変えようとする柔軟性を、校長をはじめとする教育関係者は持つべき
能登半島地震、「倒壊死9割」に愕然となる。何か耐震の工夫が必要。
<熊本城再建>宇土櫓の解体修理に関心を持っています。現場見学会に参加したい。
「耐震シェルター」、「防災ベッド」、一つの部屋だけ強化する。〜福和伸夫名誉教授(名古屋大学)〜
世界のデジタル競争力は、日本は世界32位、しかし韓国は6位だった。日本のデジタル化の取り組みを前へ。
>たとえ100年続いてきた仕組みであったとしても、変えようとする柔軟性を、校長をはじめとする教育関係者は持つべき
Posted by ノグチ(noguchi) at 08:22│Comments(0)
│新技術、新潮流