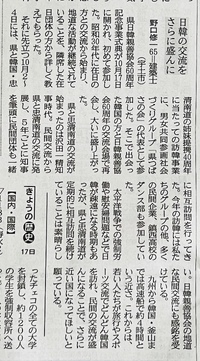[朝読書]質問のこつ、代理業務の姿勢。地域活動に「質問」が必要と思う。
2014年04月18日
[朝読書]質問のこつ、代理業務の姿勢。地域活動に「質問」が必要と思う。
今朝は小雨で、朝ウォーキングはお休みです。日課の5時起床で、朝読書の時間がたっぷりできました。
20年以上前から、色々な知識吸収のために研修会、講演会、シンポジウム等々に参加する中で、「質問時間」に持論を語る人、お礼を述べる人、的外れの話をする人がよく居ます。その話は、だいたい長く、主催者に止められることもしばしばあります。質問とは、難しいものです。
江戸時代にも勉強会はあったようで、儒家の佐藤一斎の『言志四録』の一節に質問について書かれたものがあります。
・質問のこつ
「事を人に問うには、虚懐(きょかい)なるを要し、毫(ごう)も挟(さしはさ)む所有るべから ず。人に替(かわ)りて事を処するには、周匝(しゅうそう)なるを要し、稍(やや)欠くる 所有るべからず。」
【訳】
人に物事を問うときには、公平でわだかまりのない心でなければならず、ほんの少しでも自負するところがあってはいけない。
人に代わって物事を処理するときには、用意周到でなければならず、少しでも落ち度があってはいけない。
(以上、渡邉五郎三郎編著『佐藤一斎 一日一言』)
さすが、佐藤一斎と感じ入ります。講演会後の質問時間で、延々持論を語る年配者を見るとき、発表する場が場がない、あるいは発表する場を作れないのだろうな、と思います。私は、異業種交流会を50回以上主催して来て、講話後の質問時間の司会をする中で、「これが質問」と思う質問者は、なかなか居ないと感じます。
短く参加した意味を語り、講話のどの部分に興味を持ち、だから◯◯◯について詳しく聞きたい。これを、1〜2分程度で語れる人が、なかなか居ない。質問の内容は素晴らしいが、前話が長かったり、質問の後に別の質問も加えたり、他の聴衆者の気持も考えて、質問は一点で短く簡潔に語る。これも訓練が必要と思います。
後半部の「代理業務の姿勢」
昨日の午後は、地域の先輩に同行して、地域回りをしたのですが、会う方々の会話を横で聞く中で、相手に合わせ、同行する他の方の言葉を活かせるような配慮が必要だなと、佐藤一斎の訓示の後半部の「代理で物事を処理することの難しさ」からも再確認しました。
話は飛びますが、今日の午前中は、友人の選挙活動に同行しようと思っています。
選挙は、それまでの活動の結果が票となると思っています。遊説で語る言葉が、過去4年、あるいはそれまでの社会活動に合致しているのか、演説を聞く住民の心の琴線を響かせることができるのか。
地方議員は、「地域の代弁者」と選挙遊説で語ります。
私は、これからの地域活動(=議員活動)には、ボランティア活動も含め、地域変化(人口の増減、経済の浮沈)に合った主旨を持ち、常に先を見て、現在必要な事(処理、準備)を早め早めにすることが重要と思います。また、その活動のきっかけづくりに、地域住民への活動主旨を訴える前に行うことが、地域を回りいろいろ分野の方への「質問」が大事で、これが地域課題の掘り起こしにつながると考えています。
今日は、あっちこっとと主旨の無い話になりましたが、「質問」で地域課題を探し、仲間を募り、活動へつなげる。昨年「聞く力」が話題になりましたが、「質問」は活動をする人に必要な要素と思った、朝読書でした。今日も一日、元気に乗り切りたいと思います。
今朝は小雨で、朝ウォーキングはお休みです。日課の5時起床で、朝読書の時間がたっぷりできました。
20年以上前から、色々な知識吸収のために研修会、講演会、シンポジウム等々に参加する中で、「質問時間」に持論を語る人、お礼を述べる人、的外れの話をする人がよく居ます。その話は、だいたい長く、主催者に止められることもしばしばあります。質問とは、難しいものです。
江戸時代にも勉強会はあったようで、儒家の佐藤一斎の『言志四録』の一節に質問について書かれたものがあります。
・質問のこつ
「事を人に問うには、虚懐(きょかい)なるを要し、毫(ごう)も挟(さしはさ)む所有るべから ず。人に替(かわ)りて事を処するには、周匝(しゅうそう)なるを要し、稍(やや)欠くる 所有るべからず。」
【訳】
人に物事を問うときには、公平でわだかまりのない心でなければならず、ほんの少しでも自負するところがあってはいけない。
人に代わって物事を処理するときには、用意周到でなければならず、少しでも落ち度があってはいけない。
(以上、渡邉五郎三郎編著『佐藤一斎 一日一言』)
さすが、佐藤一斎と感じ入ります。講演会後の質問時間で、延々持論を語る年配者を見るとき、発表する場が場がない、あるいは発表する場を作れないのだろうな、と思います。私は、異業種交流会を50回以上主催して来て、講話後の質問時間の司会をする中で、「これが質問」と思う質問者は、なかなか居ないと感じます。
短く参加した意味を語り、講話のどの部分に興味を持ち、だから◯◯◯について詳しく聞きたい。これを、1〜2分程度で語れる人が、なかなか居ない。質問の内容は素晴らしいが、前話が長かったり、質問の後に別の質問も加えたり、他の聴衆者の気持も考えて、質問は一点で短く簡潔に語る。これも訓練が必要と思います。
後半部の「代理業務の姿勢」
昨日の午後は、地域の先輩に同行して、地域回りをしたのですが、会う方々の会話を横で聞く中で、相手に合わせ、同行する他の方の言葉を活かせるような配慮が必要だなと、佐藤一斎の訓示の後半部の「代理で物事を処理することの難しさ」からも再確認しました。
話は飛びますが、今日の午前中は、友人の選挙活動に同行しようと思っています。
選挙は、それまでの活動の結果が票となると思っています。遊説で語る言葉が、過去4年、あるいはそれまでの社会活動に合致しているのか、演説を聞く住民の心の琴線を響かせることができるのか。
地方議員は、「地域の代弁者」と選挙遊説で語ります。
私は、これからの地域活動(=議員活動)には、ボランティア活動も含め、地域変化(人口の増減、経済の浮沈)に合った主旨を持ち、常に先を見て、現在必要な事(処理、準備)を早め早めにすることが重要と思います。また、その活動のきっかけづくりに、地域住民への活動主旨を訴える前に行うことが、地域を回りいろいろ分野の方への「質問」が大事で、これが地域課題の掘り起こしにつながると考えています。
今日は、あっちこっとと主旨の無い話になりましたが、「質問」で地域課題を探し、仲間を募り、活動へつなげる。昨年「聞く力」が話題になりましたが、「質問」は活動をする人に必要な要素と思った、朝読書でした。今日も一日、元気に乗り切りたいと思います。
人と付き合うとは、違いを許容することから始まる。〜曽野綾子著『人びとの中の私』〜
議長の活動内容について(10月)
信じれば実現する。「独立する。家を建てよ。著書を出せ」と日々イメージする。〜中村天風〜
<地域の文化レベル>数字で見る人口に対する図書館の規模、宇土市の人口は現在36483人のための図書館。
豊かさとは何かを、自分も地域も社会も含めて、考える一年になる気がする。〜令和6年、龍の年〜
令和6年元日、新年あけましておめでとうございます。
議長の活動内容について(10月)
信じれば実現する。「独立する。家を建てよ。著書を出せ」と日々イメージする。〜中村天風〜
<地域の文化レベル>数字で見る人口に対する図書館の規模、宇土市の人口は現在36483人のための図書館。
豊かさとは何かを、自分も地域も社会も含めて、考える一年になる気がする。〜令和6年、龍の年〜
令和6年元日、新年あけましておめでとうございます。
Posted by ノグチ(noguchi) at 06:52│Comments(0)
│私の意見
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。