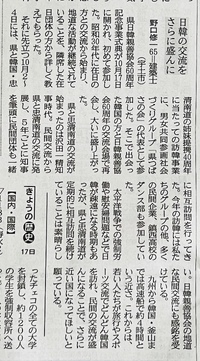「医師不足」危機的状況の地方でのお産
2007年09月03日
「医師不足」危機的状況の地方でのお産
最近新聞紙上で、「地方の医師が減り続けている」、「特に、産科医、小児科医は、危機的状況」と目にします。地元紙に、政府・与党は、国公立医学部に「僻地枠」を設け、卒業後の僻地等で勤務の義務化策を打ち出す方針と出ていました。私の住む熊本市近郊の地域ですら、産科閉院の話を聞くようになりました。また昨年度九州で産科医の新たな認可は、12名とか(?)、本当に危機的状況にあります。
熊本県内の少子高齢化が進んでいる地域から、産科医院(医師)が急速に無くなり、産科と小児科連携の育児、母体ケアが難しくなっています。日本では、妻の実家で出産と聞くのですが、過疎地域では叶わない状況にあります。これは、全国的な医療状況で、ついに国を上げてた取り組みが必要と重い腰が上がった気がします。
また少子化は、産後の母体ケアを、非常に厳しくしています。我が家の長女が生まれた時は、産後7日に退院でした。現在熊本市近郊でも産科医院閉鎖が続き、元々ベッド数が少ないのに患者が集中し、入院期間が減り退院が4日目、3日目とか、産科医の居ない過疎地の人は、産後ケアのため遠距離通院があると言います。
知人が、「母乳で育児」の指導をする助産院をしているのですが、産後のケアと母乳指導のため、産後5日目から自宅→産科→助産院を毎日通う人も居ると聞き、「産後の育児疲労から病気なる」とか聞きますので、少子化が現在の子育て期の母体にも家族にも、負担を余儀なくしています。この状況から、産科医師の増加はもちろんですが、助産婦の増加も必要と考えてます。
代議士の方々は、ほとんどが東京ですから、危機意識が希薄に見え、医療福祉こそが「社会保障の根幹」と思い、国が何処まで本気にかかっています。今回の医療系技術者の地方派遣策が、地方に安心をもたらす改革になればと願っています。
最近新聞紙上で、「地方の医師が減り続けている」、「特に、産科医、小児科医は、危機的状況」と目にします。地元紙に、政府・与党は、国公立医学部に「僻地枠」を設け、卒業後の僻地等で勤務の義務化策を打ち出す方針と出ていました。私の住む熊本市近郊の地域ですら、産科閉院の話を聞くようになりました。また昨年度九州で産科医の新たな認可は、12名とか(?)、本当に危機的状況にあります。
熊本県内の少子高齢化が進んでいる地域から、産科医院(医師)が急速に無くなり、産科と小児科連携の育児、母体ケアが難しくなっています。日本では、妻の実家で出産と聞くのですが、過疎地域では叶わない状況にあります。これは、全国的な医療状況で、ついに国を上げてた取り組みが必要と重い腰が上がった気がします。
また少子化は、産後の母体ケアを、非常に厳しくしています。我が家の長女が生まれた時は、産後7日に退院でした。現在熊本市近郊でも産科医院閉鎖が続き、元々ベッド数が少ないのに患者が集中し、入院期間が減り退院が4日目、3日目とか、産科医の居ない過疎地の人は、産後ケアのため遠距離通院があると言います。
知人が、「母乳で育児」の指導をする助産院をしているのですが、産後のケアと母乳指導のため、産後5日目から自宅→産科→助産院を毎日通う人も居ると聞き、「産後の育児疲労から病気なる」とか聞きますので、少子化が現在の子育て期の母体にも家族にも、負担を余儀なくしています。この状況から、産科医師の増加はもちろんですが、助産婦の増加も必要と考えてます。
代議士の方々は、ほとんどが東京ですから、危機意識が希薄に見え、医療福祉こそが「社会保障の根幹」と思い、国が何処まで本気にかかっています。今回の医療系技術者の地方派遣策が、地方に安心をもたらす改革になればと願っています。
人と付き合うとは、違いを許容することから始まる。〜曽野綾子著『人びとの中の私』〜
議長の活動内容について(10月)
信じれば実現する。「独立する。家を建てよ。著書を出せ」と日々イメージする。〜中村天風〜
<地域の文化レベル>数字で見る人口に対する図書館の規模、宇土市の人口は現在36483人のための図書館。
豊かさとは何かを、自分も地域も社会も含めて、考える一年になる気がする。〜令和6年、龍の年〜
令和6年元日、新年あけましておめでとうございます。
議長の活動内容について(10月)
信じれば実現する。「独立する。家を建てよ。著書を出せ」と日々イメージする。〜中村天風〜
<地域の文化レベル>数字で見る人口に対する図書館の規模、宇土市の人口は現在36483人のための図書館。
豊かさとは何かを、自分も地域も社会も含めて、考える一年になる気がする。〜令和6年、龍の年〜
令和6年元日、新年あけましておめでとうございます。
Posted by ノグチ(noguchi) at 11:06│Comments(0)
│私の意見