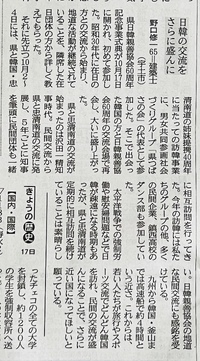(生きるとは)老歌人の智恵、隣人との交流が命を救う
2009年03月12日
(生きるとは)老歌人の智恵、隣人との交流が命を救う
歌人の黛まどかの本「詩っておきたい この一句」で、歌人永田耕衣のことを読み、九十五歳の時、阪神淡路地震を被災したことを知った。
・奇跡は、偶然と智恵を合わせて起る
永田老人は、震災直前の二十秒前、二階のトイレに入った。地震は家を全壊させたが、辛うじて狭いトイレが老人の命を救った。しかし震災直後の状況は、直ぐに老人の生存を気付かない。そこで手元にあった金物で、洗面台の縁をたたき続けた。一向に救助に来る気配がない瓦礫の下で、死と向きあいながら、生へとつながる唯一の音を鳴らし続けたとあった。だいぶ時間が経ってから、音を聞きとめ隣人が気付き救出した。
・日々の交流と心を鍛えておく
永田耕衣が後に詠んだのが「枯草の 大孤独居士 ここに居る」です。青年期には、禅の世界にも没頭したそうですが、九十歳を越えた老人の意志の強さを感じる一句と思います。遠くの身内より近くの隣人と良く聞きますが、老歌人を救ったのは日々顔を合わせる隣人だったことを知り、日ごろから危機のことも頭の隅において「生きる」ことを考える必要があると思った。
・危機回避に、日常、地域と交流が必要
時々都市部での孤独死が報じられて来ます。救助された九十五才の永田老人は、家に籠らずなんらか方法で、隣人、地域と交流を持っていたのだろう。田舎では高齢化が進み、一人暮らしが増えている。永田老人の救出状況を知り、危機回避のためにも、時々は散歩したり、地域の行事に顔を出すとか、高齢になっても地域とのつながりを持つことが大切だと思った。
歌人の黛まどかの本「詩っておきたい この一句」で、歌人永田耕衣のことを読み、九十五歳の時、阪神淡路地震を被災したことを知った。
・奇跡は、偶然と智恵を合わせて起る
永田老人は、震災直前の二十秒前、二階のトイレに入った。地震は家を全壊させたが、辛うじて狭いトイレが老人の命を救った。しかし震災直後の状況は、直ぐに老人の生存を気付かない。そこで手元にあった金物で、洗面台の縁をたたき続けた。一向に救助に来る気配がない瓦礫の下で、死と向きあいながら、生へとつながる唯一の音を鳴らし続けたとあった。だいぶ時間が経ってから、音を聞きとめ隣人が気付き救出した。
・日々の交流と心を鍛えておく
永田耕衣が後に詠んだのが「枯草の 大孤独居士 ここに居る」です。青年期には、禅の世界にも没頭したそうですが、九十歳を越えた老人の意志の強さを感じる一句と思います。遠くの身内より近くの隣人と良く聞きますが、老歌人を救ったのは日々顔を合わせる隣人だったことを知り、日ごろから危機のことも頭の隅において「生きる」ことを考える必要があると思った。
・危機回避に、日常、地域と交流が必要
時々都市部での孤独死が報じられて来ます。救助された九十五才の永田老人は、家に籠らずなんらか方法で、隣人、地域と交流を持っていたのだろう。田舎では高齢化が進み、一人暮らしが増えている。永田老人の救出状況を知り、危機回避のためにも、時々は散歩したり、地域の行事に顔を出すとか、高齢になっても地域とのつながりを持つことが大切だと思った。
人と付き合うとは、違いを許容することから始まる。〜曽野綾子著『人びとの中の私』〜
議長の活動内容について(10月)
信じれば実現する。「独立する。家を建てよ。著書を出せ」と日々イメージする。〜中村天風〜
<地域の文化レベル>数字で見る人口に対する図書館の規模、宇土市の人口は現在36483人のための図書館。
豊かさとは何かを、自分も地域も社会も含めて、考える一年になる気がする。〜令和6年、龍の年〜
令和6年元日、新年あけましておめでとうございます。
議長の活動内容について(10月)
信じれば実現する。「独立する。家を建てよ。著書を出せ」と日々イメージする。〜中村天風〜
<地域の文化レベル>数字で見る人口に対する図書館の規模、宇土市の人口は現在36483人のための図書館。
豊かさとは何かを、自分も地域も社会も含めて、考える一年になる気がする。〜令和6年、龍の年〜
令和6年元日、新年あけましておめでとうございます。
Posted by ノグチ(noguchi) at 07:02│Comments(0)
│私の意見