<学校は何のためにあるのか?>学校がなかったら絶対に世界に平和はやってこない。〜工藤勇一(教育者)〜
2022年12月19日
<学校は何のためにあるのか?>学校がなかったら絶対に世界に平和はやってこない。〜工藤勇一(教育者)〜
(長文です。お時間ある時にお読みください)
私は、学校と地域との連携というテーマに、以前から関わって来ました。小学校のPTA活動が終わった後、役員仲間数人と地元中学校区内の郷土史について聞き取り調査を始めた。きっかけは、土地改良組合の元組合長から、干拓の歴史を聞き取りからでした。
さらに組合長の高齢者仲間から、戦争のことを聞く機会があり、太平洋戦争時代に陸軍に従軍した方から、大陸での戦争の実体を語ってもらう会を開催した。その時に、戦中時期に小学生だった人から、当時の国内の苦しい生活や、空襲、戦闘機から銃撃の話を聞きました。
その時の資料を基に、今小学校で「戦争講話」をやっています。私は、戦争経験者ではありません。しかし、先輩たちから聞き取りをした歴史を伝承することは必要と思っています。
前置きが長くなりました。哲学者・苫野一徳×教育者・工藤勇一の対談録『子どもたちに民主主義を教えよう』の中に、以下の工藤氏の言葉を見つけました。
(以下、本より転載)
「自分のためだけだったら学校っていらないのかもよ。だって勉強なら家でもできるじゃん。僕はね、学校は平和のためにあるとおもうんだ。もし学校がなかったら絶対に世界に平和はやってこないと思うよ」
(以上、『子どもたちに民主主義を教えよう』より)
工藤氏が言われる
>もし学校がなかったら絶対に世界に平和はやってこないと思うよ
学校と平和の関係は、とても新鮮な意見だと思います。
私の母は、戦時下に小学校に通った世代で、「勉強はほとんどやらなかった」と思い出を話していました。子どもたちには「神の国、負けるはずがない」と教え込んで、苦しい生活を強いていたのだと思いました。
工藤氏の意見が、日本の太平洋戦争時代の教育をついてもありました。
(以下、『子どもたちに民主主義を教えよう』から)
「世界には学校教育で戦争を煽る国があるわけですね。残念ながら、かつての日本もそうだったとも言えるわけです。だから学校とはただ存在していれば価値があるわけではなく、そこで何を学ぶかが肝心」
(以上、本より)
工藤氏の指摘に、賛同します。この後、本で展開される対談で、国連が現在取り組む「持続可能な社会」や「1人も取り取り残さない社会づくり」などについても語られています。
世界の人口が80億人を超えたとニュースで聞きました。一つの地球に、人類が住み続けるにはどうするのか?
各地で紛争が頻発する中、その揉め事を起こさない役割(考え方)を果たすのが、学校なのだと、哲学者・苫野氏と教育者・工藤氏の対談録『子どもたちに民主主義を教えよう』での意見に、参考になるヒントがあります。
この2人の「自由の相互承認」の議論の最後にある苫野氏の言葉が印象に残りました。
(以下、本より)
でも学校は、同時に社会のためにもあるんです。それがまさに、民主主義社会を成熟させるための目的ですね。そしてそれはもちろん、最終的には一人ひとりの自由のための実現につながるわけです。
(以上、『子どもたちに民主主義を教えよう』より)
学校で、自由と民主主義を学ぶ、教える、そんな発想を持つ教育者がいることに、感銘を受けます。対談録『子どもたちに民主主義を教えよう』は、これからの学校運営、教室運営に、大きな影響を与えていくように思います。
*参考資料:苫野一徳×工藤勇一の対談録『子どもたちに民主主義を教えよう』
平和の祭典の一つ、サッカーワールドカップの決勝戦を見ながら、お二人の対談録を読んでいました。
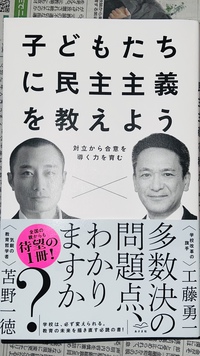
(長文です。お時間ある時にお読みください)
私は、学校と地域との連携というテーマに、以前から関わって来ました。小学校のPTA活動が終わった後、役員仲間数人と地元中学校区内の郷土史について聞き取り調査を始めた。きっかけは、土地改良組合の元組合長から、干拓の歴史を聞き取りからでした。
さらに組合長の高齢者仲間から、戦争のことを聞く機会があり、太平洋戦争時代に陸軍に従軍した方から、大陸での戦争の実体を語ってもらう会を開催した。その時に、戦中時期に小学生だった人から、当時の国内の苦しい生活や、空襲、戦闘機から銃撃の話を聞きました。
その時の資料を基に、今小学校で「戦争講話」をやっています。私は、戦争経験者ではありません。しかし、先輩たちから聞き取りをした歴史を伝承することは必要と思っています。
前置きが長くなりました。哲学者・苫野一徳×教育者・工藤勇一の対談録『子どもたちに民主主義を教えよう』の中に、以下の工藤氏の言葉を見つけました。
(以下、本より転載)
「自分のためだけだったら学校っていらないのかもよ。だって勉強なら家でもできるじゃん。僕はね、学校は平和のためにあるとおもうんだ。もし学校がなかったら絶対に世界に平和はやってこないと思うよ」
(以上、『子どもたちに民主主義を教えよう』より)
工藤氏が言われる
>もし学校がなかったら絶対に世界に平和はやってこないと思うよ
学校と平和の関係は、とても新鮮な意見だと思います。
私の母は、戦時下に小学校に通った世代で、「勉強はほとんどやらなかった」と思い出を話していました。子どもたちには「神の国、負けるはずがない」と教え込んで、苦しい生活を強いていたのだと思いました。
工藤氏の意見が、日本の太平洋戦争時代の教育をついてもありました。
(以下、『子どもたちに民主主義を教えよう』から)
「世界には学校教育で戦争を煽る国があるわけですね。残念ながら、かつての日本もそうだったとも言えるわけです。だから学校とはただ存在していれば価値があるわけではなく、そこで何を学ぶかが肝心」
(以上、本より)
工藤氏の指摘に、賛同します。この後、本で展開される対談で、国連が現在取り組む「持続可能な社会」や「1人も取り取り残さない社会づくり」などについても語られています。
世界の人口が80億人を超えたとニュースで聞きました。一つの地球に、人類が住み続けるにはどうするのか?
各地で紛争が頻発する中、その揉め事を起こさない役割(考え方)を果たすのが、学校なのだと、哲学者・苫野氏と教育者・工藤氏の対談録『子どもたちに民主主義を教えよう』での意見に、参考になるヒントがあります。
この2人の「自由の相互承認」の議論の最後にある苫野氏の言葉が印象に残りました。
(以下、本より)
でも学校は、同時に社会のためにもあるんです。それがまさに、民主主義社会を成熟させるための目的ですね。そしてそれはもちろん、最終的には一人ひとりの自由のための実現につながるわけです。
(以上、『子どもたちに民主主義を教えよう』より)
学校で、自由と民主主義を学ぶ、教える、そんな発想を持つ教育者がいることに、感銘を受けます。対談録『子どもたちに民主主義を教えよう』は、これからの学校運営、教室運営に、大きな影響を与えていくように思います。
*参考資料:苫野一徳×工藤勇一の対談録『子どもたちに民主主義を教えよう』
平和の祭典の一つ、サッカーワールドカップの決勝戦を見ながら、お二人の対談録を読んでいました。
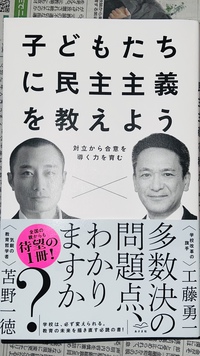
Posted by ノグチ(noguchi) at 03:56│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。



